
「夢見る小学校」きのくに子どもの村教育×「ホンモノの仕事」
共育LIBRARYへようこそおいでくださいました✨
教育、人間、人生など、様々な「知恵」や「情報」が詰まった図書館のような、皆さんがくつろぎ、人生の「気付き」を得たり、知的好奇心を満たしたりできる居場所を目指しています😌
どうぞ、ごゆるりとお過ごしください。
共育LIBRARYりょーやん、元教師です。
N高等学校。
大阪市立大空小学校
ホームスクール。
大阪府立箕面高校。
これまで多種多様な学校や、
教育の在り方を紹介してきました。
今回の記事もその1つ。
和歌山県にある、きのくに子どもの村。
ここでは殊更、
ユニークな教育が行われています。
「学校現場の見直しと改革に小さな一石を投じたい」
そんな思いから出発した、
現状の公立学校とは正反対の主義を貫く学校。
そんな学校に記録を踏まえて、
「ホンモノの仕事とは何か?」
を考えていける記事にしていきたいと思います。
楽しんでもらたら幸いです。
きのくに子どもの村の教育

きのくに子どもの村教育。
ここでは一体、
どんな教育が行われているのか。
その一旦を見てみます。
例えば、
「ジャンボすべり台を建設する」
というプロジェクト。
木材を用意し、
どれだけの枚数がいるのか、
長さや面積はどれぐらいなのかを計算し、
角度や耐久性を考えて、実際に建築をする。
近くにあるきのくに小学校の校庭に、
別荘を建築する。
きのくにファームで野菜を育て、
それらの食材を使って調理をする工程を、
全て自分たちで組み立てる。
基本的に、
大人がルールを決めるのではなく、
自分たちでルールを決めて話し合う。
大人も子どもも皆立場は平等。
それが文字通り、
中身も伴って実現されている。
そんな学校であると言えます。
きのくにの起源はどこにあるのか?

このきのくに子どもの村は、
堀真一郎さんが発起人となってつくられました。
大阪市立大学の教授であった堀さん。
「新しい学校をつくる会」
という団体のメンバーであり、
日本にもサマーヒルのような学校がほしいという思いから、1984年にプロジェクトが動き始めた。
サマーヒルとは、イギリスにある
「世界で1番自由な学校」と言われるところ。
ここでは、
全校集会の中で学校のルールを
自分たちで話し合う。
そのような学校を見学し、
公立学校の正反対とも呼べる様相を目の当たりにした堀さん。
それがきっかけとなり、
日本にも作ろうと動き出したのです。
堀さんの考えを知っていく内に、
根本的なところで思想が同じだと思う言葉があります。
例えば、
宿題は出さない。
教師は1時間の授業の中で勝負しなければならない。
というもの。
宿題とはすなわち教師の仕事不足による、
子どもたちに押し付けた残業です。
筆者は新卒3年目から宿題というものを
ほとんど出したことがありません。
(代わりに自主学習にしていました)
それでも漢字テストや算数のテストは、
平均90点を超えることが多いです。
また、
教師は自分自身が自由でなければ
子どもを自由にすることなど、
できるものではない。
という言葉もそう。
これは内面的な自由さです。
世間の空気、マナー、ルール、
それらを気にし過ぎて凝り固まっていたら、
真に自由な発想など生まれようもないのです。
大事なことは、
自分たちで考えてそれを創り出すこと。
ではここから、
さらに独創性溢れるきのくに村教育の中身を見ていきます。
プロジェクトベースのカリキュラム
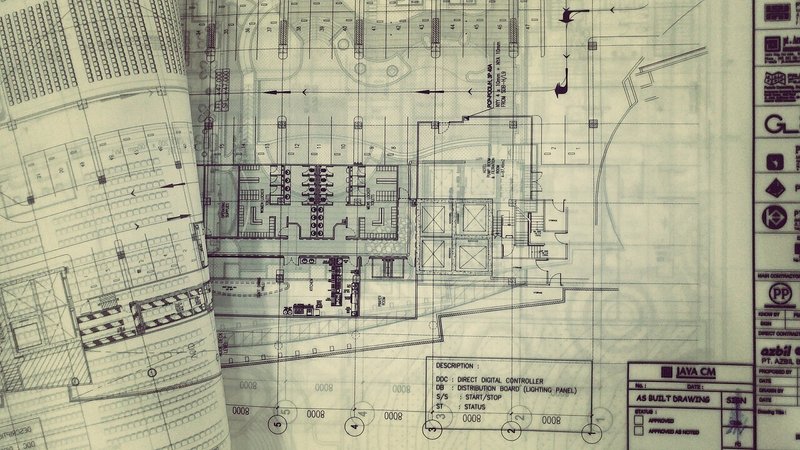
まず、所属するクラスが面白い。
普通は、1年1組といった振り分けになる。
しかし、きのくにでは以下のようになっています。
▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢
【小学校】
・工務店 → 木工、家づくり、花づくり…
・ファーム → コメづくり、野菜づくり、料理…
・劇団きのくに → 劇づくり、阿波踊り、落語…
・おもしろ料理店 → 日本各地の料理、保存食…
・クラフト館 → 木工、焼き物、大型遊具
【中学校】
・動植物研究所 → ビオトープ、里山の管理…
・道具製作所 → 自転車や車整備、道具の歴史…
・電子工作所 → 電子部品の道具やおもちゃ…
・わらじ組 → 担任なしの自主運営クラス…
▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢
これらのプロジェクトチームから、
1年間どこに所属するのかを
自分で選択するのです。
ということは、学年は関係なし。
縦割りになっており、
年齢もごちゃまぜです。
これらのプロジェクトと、
基礎的な学習を結び付ける。
きのくにの言葉を引用します。
子どもの村は体験学習中心の学校だ。
基礎学習といえども
自分たちのプロジェクトの仕事と
密接に結びついていなくてはいけない。
プロジェクトを遂行するためには、
様々な材料を購入したり、
設計図を考えなければならない。
だからこそ計算も必要になる。
他の教科も全てそう。
実際の生活、プロジェクトに生かすために、
それを学ぶということになっているのです。
他にも、
70~80%の子どもが寮生活を送っているのも
大きな特徴。
週末帰宅の子や通学の子もいますが、
本当の意味での共同生活を送っているのです。
さて、このような様子で、
子どもたちはどう変化していくのでしょうか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
