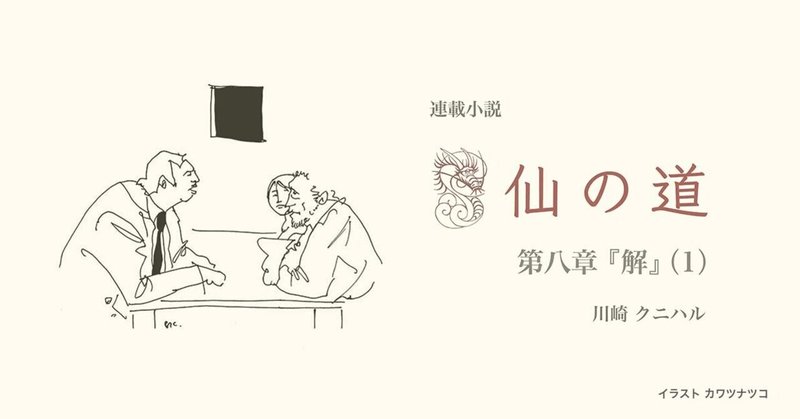
仙の道 17
第八章・解(1)
礼司たちを乗せたパトカーが横浜の警察署に到着したのは正午少し前だった。
署内に連れていかれた2人に再び逮捕状が明示され、手錠と腰繩が着けられようとしたが、もちろん多くの署員の徒労に終わった。
担当の署員たち数人が集まって相談を重ねていた。
「何をやってんだよ?時間の無駄だって言ったろう?」
業を煮やして善蔵が声を掛けた。
「とにかく、留置の手続きだけ先にして貰うから…」
1人の署員が申し入れた。
「お前えら、本当に手続きが好きなんだな?ま、何でもいいや。で、何処に行きゃあいいんだ?」
礼司たちは署員たちに取り囲まれながら、階上の『診断室』と書かれた広い部屋に案内された。
「じゃあ、ポケットのものを全部ここに出して。ズボンのベルトを外して。靴も脱いでここに置きなさい。そこのサンダルに履き替えて」中年の係官がぞんざいな口調で命令した。
「何でだ?」
「そういう規則だからな。いいから言われた通りにすりゃいいんだ」
「嫌だよ。俺達ゃこのまんまでいいからよ」
「そういう訳にはいかないんだよ。おい、お前等、従って貰え」係官は控えていた警官たちに指示した。
「いや…あの…駄目なんですよ。こいつ等、手錠も腰繩も駄目なんですから…」1人がおずおずと答える。
「何言ってんだ?駄目って、どういうことだっ!まあいい、俺がやるから。ほら、二人とも両手を上げてっ!」
礼司と善蔵が言われた通りに両手を上げると、テーブルを回り込んで係官が近付いた。係官は2人に近付き上着のポケットに手を突っ込もうとしたが、どうやっても衣服に触れることすら出来ず、2人の周囲をぐるぐると回るばかりだった。
「おっさん、何やってんだ、犬っころじゃあるめえし…手続きだか規則だか何だか知らねえけど、いい加減にしてくれねえか」
「ね、何だか訳が分かんないんですけど、どうやっても駄目なんですよ」
「でも…これじゃあ…留置は出来ないぞ…参ったなあ。あのお、おたく等、何とか言う通りにして貰えないかなあ…このままだと、こっちも困るんだよなあ…」
「別に俺達がここに連れてきて欲しいって頼んだ訳じゃねえんだぞ。聞きたい事があるから来てくれって言ったのはそっちだろう?そうじゃねえのか?」
「いや、私は、その…留置の管理をしているだけなんで…」
「何言ってやがる…お前え、自分でもの考える頭持ってねえのか?手続きと規則だけでおまんま食ってよ、いい歳して本当にそれでいいと思ってんのか?情けなくて涙が出るぜ。役人がこれじゃあ日本もいよいよおしめえだな。もういいから、さっさと取調べでも何でもやってくれよ」
「…と、取り敢えず、君たち、先にこの2人、取調べの方に連れてった方がいいんじゃないか?」困り果てた係官が警官たちに提案した。
「でも、1日じゃ終わらないですよ…」
「そんなこと俺が知るかっ!第一被疑者にわっぱも掛けねえで連れて来て…お前ら何やってんだっ!上と良く相談してこいっ!」遂に係官は逆上した。
「あのお…僕、お腹空いたんで、何か食べてきていいですかね?」そろそろ空腹を感じていた礼司が口を挟んだ。
「そういやそうだな…何だよ、もう昼過ぎてんじゃねえか。悪いけど、取り調べは飯食ってからにしてくれ。おい、ここは食堂かなんかねえのか?」善蔵が警官たちに尋ねた。
「いやいや、そりゃまずいよ…はは…参ったなあ…」
「お前えの意見なんか聞いてねえよ。ま、いいや適当に探すから。おい礼ちゃん、ちょっと飯食いにいこうぜ」周囲の状況に構わず善蔵は礼司に声を掛けた。
「はい。でも…いいんですか?この人達は…」
「なあに、構わねえよ。じゃな、また後でな」構わず2人は部屋の出口に向った。
「ちょちょちょっと…あんた達拘留中なんだから、勝手に動いちゃ駄目だよ。大体そこは鍵が掛かってるから、出られないよ…」
善蔵が扉に手を掛けると、鋼鉄製の鍵は大きな音を立てて解錠された。
部屋から出て行く2人を、慌てて警官たちが追いかけた。
エレベータホールの前で警官たちは礼司たちに追い付いた。
「駄目だよ勝手に歩き回っちゃ!」
「がたがたうるせえな、全くよ。飯食いに行くだけだよ。大丈夫だ、ちゃあんと金は持ってるからよ」
「いや…はは…そういう問題じゃなくて…」
「大体昼時に連れ出しといてよ、飯の心配もしてねえたあどういう了見だ。礼儀もへったくれもあったもんじゃねえな」
「いや、あんた達がおとなしく留置手続きに応じてくれてりゃ、官弁の後に取り調べっていう予定だったんだよ…」
「何だ?かんべんって…」
「あ、ああ…留置場の食事のことだ」
「いいよもう。勝手に食ってくるからよ。あんな面倒くせえとこで飯なんか食いたかねえよ」
「あの…署内の一般食堂なら…一階ですけど…」若い警察官がそっと呟いた。
「あ、馬鹿っ!お前何言ってんだ!」
「え?…あ、す、すいません…つい…」
「何だよ、知ってんなら早く教えろ。もったいぶりやがって…じゃ、そこに行ってるからよ。そっちの取調べの準備が出来たら、呼びに来い。な」
「いやあ…困ったなあ…じゃあ仕方ない。お前等一緒に付いて行ってこい。俺は何とか上に話してくるから…ほら…」男は胸ポケットから財布を取り出し、若い警官2人に2枚の千円札を渡した。
「確か、あそこの定食500円だったよな。これ4人分な…」
「いいんですか?」
「だって…仕方ないだろ。もう面倒臭いから俺のポケットマネー出しとくよ。お前等も一緒に食ってこい。誰にも言うんじゃないぞ」
「何だ…お前さん、頭の堅え唐変木かと思ったら、いいとこあるじゃねえか。人はよ、そうじゃなきゃいけねえや。じゃ、お言葉に甘えてその定食とやらをごちになるか。おい行こうぜ。案内しろ」
4人は階下に降り、食堂で一緒に昼食を摂った。
若い2人の警察官は善蔵と礼司に興味津々の様子だった。手錠をいとも簡単に破壊し、留置場の鍵を無造作に解錠し、一切の抵抗なしに拘束を寄せ付けない人間が実在したことに興奮していた。一体どうすればそんな能力を身に付けることが出来るのか訊ねられたが、持って生まれた潜在能力であることを正直に告げると、2人とも落胆を隠せない様子だった。
昼食が終わると礼司たちは取調室に案内された。
2人を別々の部屋で取り調べると言われたが、2人は離れていても情報を共有できることを善蔵が説明すると、すんなりと2人一緒の部屋で取調べを行なうこととなった。
「だから、成和会の連中は誰も怪我してねえだろう?」善蔵が取調べの係官に詰め寄った。
「そんな訳はないだろう?50人近くも待機してた場所に数人で乗り込んで手打ちしたなんて、誰が信じると思うんだ?出入りだったんじゃないのか?じゃなきゃ、あの成和会が手を引くなんて考えられないだろう?」取調官が冷静な態度で対峙していた。
「じゃあ、一体、誰が被害を届けたんだよ?」
「それは…言えない。ただ暴力行為があったことは明白なんだよ」
「俺達は何もしねえ。でも、彼奴等は俺達に何も出来ねえ…それが理解できねえってことだな?あんたには…」
「まあ、普通常識で考えりゃ、そういうことだ」
「なるほどな…お前えがトカゲの尻尾の先っぽってことか…じゃよ、こうしたらどうだ?ほら、俺達は何もしてねえぞ」善蔵がそう言うと、取調室にいた4人の署員全員がその場で微動だに出来なくなった。男達は声を発することも指先を動かすことも出来ず、次第に目の中に恐怖を滲ませていった。
「おい、隣の部屋で覗き見してるあんちゃん達よ、どうだい?どうすんだ?このまま放っといていいのかい?」暫く間を置いて、善蔵が壁の鏡に向かって声を掛けた。
暫くすると、隣の部屋のドアが開き誰かが早足で廊下を通り過ぎていった。
「ゼンさん…いいの?このままで…」礼司はマネキン人形のように固まってしまった男達を眺めながら善蔵に訊ねた。
「ちっと可哀相だけどよ、こんな下っ端連中といつまで話してても埒があきゃしねえ。このまま待ってりゃあちったあましな野郎が出てくるぜ。ま、こっちから出向くこともねえだろ」
善蔵の言う通りだった。少し待つと何人かの靴音が近づき、部屋のドアが開いた。先頭に入ってきたのは制服姿の恰幅の良い中年男だった。男は部屋の中のただならない様子を見ると、血相を変え不動の男達に近付いた。
「おいっ!お前ら!何をやってるっ!おいっ!」
「おっと、立ってる奴に下手に触ると倒れちまうぜ。動けねえんだ。怪我あさせることになるぜ」善蔵が男に声を掛けた。
「お、お前たち…な、なにをやったんだ?」
「何もしてねえよ。後のあんちゃんが隣の部屋から見てた通りだ。こいつらがよ、何もしねえでも喧嘩にゃ勝てるって言っても、なかなか信じてくれねえからよ、ちょいと同じことしてやっただけだよ。おい、どうするんだ?このまま放っといていいのかい?それともお前さんにも試してみるかい?」
「い、いや…一体…どうしたらいいんだ?あんた達が何とか出来るのか?」男は狼狽を隠そうともしていなかった。
「お安い御用だ。ほらよ」善蔵の一言で4人の男達は呪縛から解放された。
4人はいずれも自由になった身体をかろうじて両腕で支え、肩を揺らして大きく呼吸を繰り返しながら恐怖で目を見開いていた。
「おい、これが傷害か?俺達ゃ触ってもいねえぞ。分かったかい?」
「…あ、ああ…」取調べの係官はそう返事を返すだけで精一杯だった。
「分かってくれりゃあいいんだよ。しんどい目に合わせて悪かったな。じゃあ、おい、お前え、そこ席空けて、そっちのおっさんと替わってくれよ。こっからはこっちの取調べだ」
「な、なんだ…どういうことだ?」中年の男は壁に後ずさった。
「いいから、そこに座れ。ちょいと聞きたい事があんだよ。おい、礼ちゃん、随分人が集まってきちまったみてえだ。入口塞いどいてくれ。怪我させんなよ」
「あ、はい…」
取調室前の廊下にはもう大勢の警官が完全防備で押し掛けていた。その先頭で何名かが入口越しに中を覗き込んでいる。ドアがゆっくりと閉まっていくと、廊下の警官たちは目に見えない分厚い空間に押し戻され、閉まったドアに近付くことすら出来なくなってしまった。
部屋では係官が逃げるように座席から部屋の隅に退き、中年の男が脅えながらおずおずとその椅子に腰掛けた。
「ところで、お前さんはいってえ誰だ?」
「ここの、副署長の…あ、秋山だ…」
「副署長さんかい…今日の俺達の逮捕、お前さんに指示したのは誰だい?」
「そ、そんなこと…お前らに話せるかっ!」
「こら小僧…偉そうにふんぞり返ってる場合じゃねえんだぞ。何ならお前えの頭ん中入り込んで、脳みそ引っ掻きまわして探したっていいんだぜ。その代わり、気が狂ったって責任取らねえからな…」善蔵が凄みを利かせて睨みつけると、副所長は素直に求めに応じた。
「あの…私は、署長から指示されて…」
「上から言われりゃ、被害者がいなくてもしょっぴくってか?全くヤクザよりたちが悪いな、ここは…じゃあ、お前えはもういいや。その署長ってのを直ぐに連れて来いっ!」
「いや、あの…署長は、いろいろ忙しくて、スケジュールのこともあるし…すぐには…」
「何言ってやがる。本庁と検察と裁判所がグルになってなきゃ、逮捕状なんて取れねえだろう?俺はその辺が誰なのか知りてえんだ。それとも、お前えが全部知ってるのか?」
「いえ、私は何も…」
「じゃあ、直ぐに連れて来いっ!待たせるんじゃねえぞ!」
「あの、ゼンさん?」礼司がやり取りを遮った。
「ん?何だ?」
「僕…ちょっと、トイレ行きたくなっちゃって…すいません。丁度いいから一緒に行って連れて来るよ。そうすりゃこっちで様子も分かるでしょ?」
「そうか…じゃあ、そうして貰おうかな。逃げられても何だしな」
「じゃ、副署長さん、行きましょうか。まずトイレに寄って下さい」
「気を付けろよ。誰も怪我あさせるんじゃねえぞ」
「分かりました…副署長さん、傍にくっついてて下さいね。僕たちには誰も近付けないようにしますから…」
「わ、分かった…」副署庁は緊張の面持ちで礼司に従った。
連載小説『仙の道』では表紙イラストを、毎回一点イラストレーターであり絵本作家でもあるカワツナツコさんに描き下ろして頂いています。
カワツナツコさんの作品・Profileは…
https://www.natsukokawatsu.com
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
