
『0メートルの旅』への旅
『0メートルの旅 -日常を引き剥がす16の物語-』という本を出す。
今しか作れない本になった。
正確に言えば、新型コロナウイルスによって、本のコンセプトを根本的に変更せざるを得なくなったことで、今しか作れない本になってしまった。
企画当初は、『マクドナルドと機関銃』というタイトルだった。そこから『0メートルの旅』までの道のりは、それ自体が旅だった。その旅程を、書き残しておこうと思う。
『0メートルの旅』の著者は岡田悠という。本作が書籍としてのデビュー作になる。noteや、オモコロなどのWebメディアで旅行記を書いていた。ひょんなことでnote社員の方から「おもしろい人がいる」という話を聞き、興味を持ってお会いした。本業は会社員だが、毎年有給休暇を100%消化し、そのすべてを旅行に突っ込む。年に3、4回は海外に行き、訪れた国は70か国、日本は全都道府県を踏破しているらしい。他にもそういう人はいるだろうが、社会人になってから有給を全部旅に突っ込む人は少ない。おもしろい人だなと思った。
わたしにとっての岡田さんの記事の魅力は、「日常の中に非日常を見出す」ところにあった。イランに行こうがインドに行こうが仙台に行こうが、彼なりの楽しみ方をする。彼の記事の読者も、旅先の魅力ではなく、旅先で巻き起こす先の見えない彼の行動や思考の過程に惹かれていると感じた。
わたしの好きな彼の記事に「近所の寿司屋のクーポンを記録し続けて3年が経った」がある。通い詰める回転寿司チェーン店にLINEクーポンがあって、これは毎週送られてくるランダムな寿司ネタが数貫タダで食べられる、というものらしい。
彼は、ある時「来週のクーポンを予想できないか?」と思い立つ。
そこから3年間、クーポンの遍歴を記録し続ける。

(当該記事から引用した狂気の沙汰)
3年間記録し続ける過程で、彼は「ある周期性」を発見し、その周期性を元に「大予想」した結果までの顛末が描かれている。そして、この記事を書き上げた後、その周期性とネタ選定の意図を、当の回転寿司チェーン商品販売企画部まで聞きに行く。
LINEクーポンは、当然使ってもらうためにある。わたしなら、回る皿に手を伸ばし胃に流し込むベルトコンベアーと一体化するような作業の中で、クーポン対象のイカゲソが無料だったことなど、次の軍艦巻きに手を伸ばす頃には忘れているだろう。
岡田さんは違う。ただ消費し続けることを仕向けられる毎日に抵抗する。消費行動の中にひと匙の創造を入れていく。日常の中に非日常を抉り出す。次の駅が見えている予定調和のレールの上に予定不調和の方へ向かう分岐器を自作する。いや、実際は知らんけど、岡田悠という書き手の魅力はそこにあると俺は思った。
だから当初、この本のコンセプトは、「旅の魅力は、どこに行くかではなく、どう楽しむかにある」にした。
旅のエッセイや旅行記や冒険記は星の数ほどあるが、沢木耕太郎でも角幡唯介でも山野井泰史でも開高健でも世界遺産探訪記でもない、岡田悠だけの旅の楽しみ方を書いてもらおうと思った。
しかし、企画を社内で通過させ、執筆過程に入った2020年初旬、旅を取り巻く環境は、これ以上にないレベルで一変した。
増え続ける感染者数と逼迫する医療機関の情報がメディアを侵食するに連れ、人の移動がどんどん制限されていく。街から人が消えていく。
わたしは小平市という埼玉との県境にほど近い東京都民だが、隣町の東村山市が産んだコメディアンの感染症による訃報が届いた頃、近所は戦々恐々としていた。ゴミ捨て場に行くことすら憚られる。家を一歩出るのに命の危険が伴うように感じる。会社になど行けたものではなく、かといって幼子が2人いる家の中でずっと仕事することもできず、わたしの職場は運転席になった。

こんな世界であってほしくないと、何度も思った。
もはや、旅どころではない。
いや、それどころか、正直、本を作っていられるような状況ではなかった。何にも集中できなくなった。作らなきゃ、自分も家族も生活できない。そんなことはわかっている。しかし、なにせ原稿が読めないのだ。人生の最優先事項が生き延びることになってしまったのだ。誰も望まなかった非日常が日常にすり替わった世界で、息を整え、現在地を確認するために、こういう文章を書いたりした。
そして、世界各国で都市がロックダウンし、事実上国境が封鎖され始め、世界から旅行が消えつつあったころ、Twitterでも、体内から漏れ出てくるような「旅への渇望」を多く目にするようになった。
外出すら気軽にできなくなった事により俺の中に眠っていたらしい旅人のDNAが目を覚まして旅行欲が爆発している。国内海外問わず旅に出たくてたまらない。旅の移動時間とか罰ゲームだと思ってたんだけど、移動すらも恋しい。飛行機とか電車とか乗ってただただ移動したい。みんなの旅人DNAも暴れてない?
— Testosterone (@badassceo) April 29, 2020
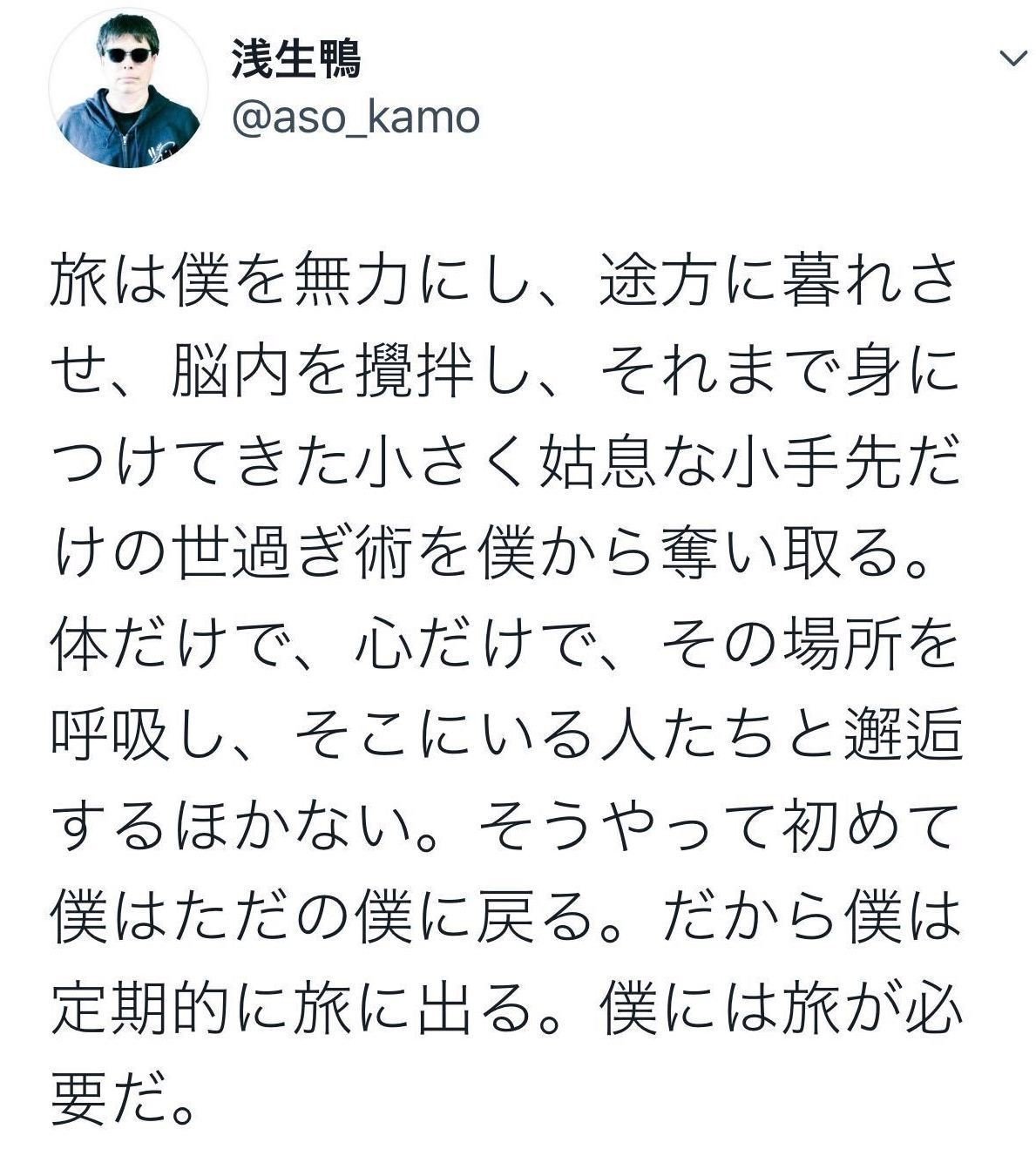
そして、もちろん岡田さんも、同じ空の下で、大きな影響を受けていた。これはわたしが書くことではないけれど、ご本人が書いている。一世一代の結婚式を直前で自粛せざるを得なくなり、そして家の中に閉じ込められて翼をもがれた生粋の旅人は、風呂の中で意識を失い頭を打って病院に運ばれる。
もう、このご時世に旅の本なんて世迷いごとだろ。出したって不謹慎だとか言われんだろ。もう、やめようか。誰も文句は言わないよ。そう思っていい状況だったと思う。でも、不思議とそんなことは一度も思わなかった。
「書く」は、「思い出す」と直結する行為だ。
旅行記とは、基本的に「旅を終えた後」に書かれるものだ。リアルタイムで逐次更新されるものではなくて、この旅はなんだったのか、なぜわたしは旅に出たのか、そこで起きたことを旅を終えた今どう捉えるか、記憶を思い返しながら、反芻しながら書かれるものだ。
それなら、今、できるんじゃないか。
というよりも、世界から旅行が失われた今こそ、「旅とは何か」を問いなおす本を作りたい。
そこから、我々は再起動した。岡田さんは、過去の自分が書いた旅行記を徹底的に読み返しあさり、「自分はなぜ旅をしてきたのか」「自分にとっての旅とは何か」を自問自答する旅に出た。
わたしの方はと言えば、愛する歌い手の宅録を聴くなどして英気を養っていた。
FM802のハンバーガーDJの樋口くんから頂きましたうたつなぎですー☺️まだまだ不安な日々が続くけれど、心折れないよう頑張ろう。みんないつも本当にありがとう🌸🌸🌸 pic.twitter.com/qA5Idvdfs6
— aiko official (@aiko_dochibi) May 13, 2020
その中で、1つ、面白いことが起きた。
岡田さんのあるツイートが、めちゃくちゃ拡散されたのだ。
子どもの通学路についてフィールドワーク研究した学者の本を読んでるんだけど、子どもが全然ちゃんと帰らなくて良い pic.twitter.com/ODxnfntdmm
— 岡田 悠 『0メートルの旅』予約開始 (@YuuuO) July 16, 2020
これは『子どもの道くさ』(水月昭道・著/東信堂)という本を紹介するツイートだ。わたしの邪推だが、岡田さんは、「日常の中に非日常を見つける」という行為に向かわせる自分の中の衝動を、「子どもの頃の道くさ」という概念から捉えようとしていたのではないかと思う。
そして、『子どもの道くさ』は、当時絶版状態になっていたのだが、このツイートが拡散されると、出版社に「読みたい」という声が殺到し、復活再販された。
ひとりの読者が絶版状態になってた本を手に取りその面白さを発見してTweetすると、12.6万のファボ♡がつき、「読みたい」という声が著者へ殺到し、出版社へ繋ぐと再版が約束されてしまったという夢のような出来事が起こった。小さな一声が死にかけた本を復活させ、著者を喜ばせ、出版社を生き返らせた pic.twitter.com/oYXeGr4Xd3
— 水月昭道🌸3刷「子どもの道くさ」東信堂 (@syakusanjiki) July 19, 2020
わたしは10年以上この業界にいるが、寡聞にしてそういう話を聞いたことがなかった。
もしかして、みんな、動けなくなったこの世界で、子どもの頃ランドセルを背負っていつもの通学路を辿る家路を外れて迷い込んだより道を、何があるか何が起きるかわからなかった道くさを、親教師に咎められようが止められなかった衝動を、懐かしく思っているのかもしれない。
やっぱり、この本は、今こそ作るべき本だ。そういう思いを強くする出来事だった。『0メートルの旅』は、大人の道くさの本でもあるからだ。
そして、最終的な目次構成は、こうなった。



この本は、岡田さんの自宅から1600万メートル離れた、地の果て南極から始まる。そして、アフリカ大陸、中東、アジア地域を経て日本に入り、東北と島などを経て岡田さんの自宅周辺に近づき、最後は自宅から0メートルの「部屋の中の旅」で完結する。
旅の魅力は距離に比例しない。遠くに行くことだけが旅ではない。ならば、地球の最南端から次第に距離を縮めていく中で、いったいどこまでが旅と呼べるのか。「部屋の中でする旅」は、果たして旅と呼べるのか。それを検証する本になった。この本自体が、旅とは何かを探す旅だ。開催されなかった岡田さんの結婚式の後日談も、当初のタイトルだった「マクドナルドと機関銃」の場面も、その旅の中にある。
そして、編集者であるわたしにとっては、本作りも、1つの旅である。
本作りは、企画を立て依頼して原稿を書いてもらい編集して本文を完成させデザイナーに依頼しデザインを仕上げてもらう、という最後の時点まで、手触りのない状態で進む。紙に落としこまれるのは、9割以上の工程を終えてからだ。
今回、原稿を読んでくれたデザイナーの吉岡秀典さんと相談し、章ごとに違う本文用紙を使用している。わたしにとって初めての試みだ。なぜそうする必要があったのかは、手にとって感じていただきたい。

そして、カバーデザインに使用した色の出方を確認するために、デザイナーとともに印刷所の印刷現場に立ち会わせてもらった。我々の魂を込めたデータを形にしてくれる職人たちの真剣な眼差しは、惚れ惚れするほど美しかった。

本の中で、岡田さんは開高健の言葉を引用してきた。記者として、兵士として、そして作家として世界中を飛び回った開高もまた、旅の魔力の虜になった者の一人だったはずだ。開高は、辺境に行くほど理解の及ばない文化に出会え、予想もしないトラブルに巻き込まれ、しかしそういう異質な存在との遭遇こそが旅の魅力であるという文脈で、「抵抗感覚の快感」と書いた。『0メートルの旅』は、岡田さんの「抵抗感覚の快感」の集積でもある。
同じ開高健の別の作品に、『玉、砕ける』という傑作短編がある。その中で開高は、海外から日本へと戻る自分の心象をこう表現する。
スーツケースの荷造りを始めると、確実に体の背後か左右のどこかに黴が芽を出すのをおぼえる。
東京に近づけば近づくだけ黴はいよいよくまなく繁殖して、わたしは憂鬱に犯されるままになり、無気力になっていく。
一カ月か二カ月すれば私は青や灰のもわもわとした黴に蔽われて雪だるまのようになってしまう。わかりきっているのだけれど、そこへもどっていくしかない。
黴。カビ。
開高にとって、日本に戻ることは、東京へ還ることは、日常を繰り返すことは、じわじわと自らの身に黴が生えていくような感覚だったのかもしれない。
日常が、悪いものであるはずがない。むしろ今、なんでもない日常を過ごすことの尊さは、戻ってくる場所があることの有り難さは、私自身が、身に沁みて感じている。
しかし、同じような日々が続くことに、生産性や再現性やコスパや因果関係を求められる毎日を過ごすことに、どうしようもなく狭苦しさを感じる時がある。すべてをぶち壊して、すべての予定をペンディングして、頭に身体にまとわりつくすべてを0にして解放されたくなる瞬間がある。
『0メートルの旅』のサブタイトルは「日常を引き剥がす16の物語」とした。開高健が身に巣食う黴を拭い去るように、旅から戻ったわたしの体に残る旅情で桃色になった皮膚を覆い隠されても疼く瘡蓋を再びめくるように、引力の強い日常の膜を、時折引き剥がす。そしてまた、愛すべき日常に戻っていく。今、そういう本があっていい。何よりわたし自身が、そういう本を今、読みたいと思った。

とにかく、岡田悠というひとりの旅人の旅を、『0メートルの旅』という本にして閉じ込めた。この本は、どうしても2020年が終わる前に出したかった。
読み終えた誰かの次の旅につながることを願って、12月15日、この本を世に出す。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
