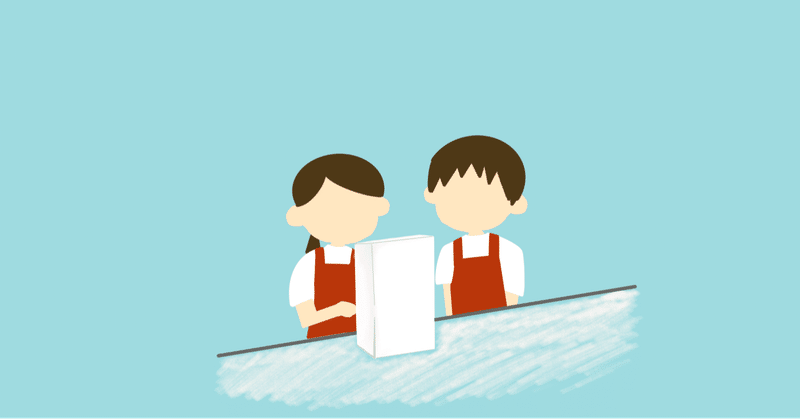
#85 OJTは教える人の劣化コピーしか作れない欠陥システムなのか~私の指導方法の紹介~(2024/05/18)
こんにちは。ITベンチャーエンジニアのこへいです。
先日、木下斉さんのVoicyのコメントでOJTは教える人の劣化コピーしか作れない欠陥システムという指摘を拝見し、ものすごく腹落ちしたので、OJTについて考えてみます。
指摘の主は、いつも広く深い知識と豊富なご経験から学びのあるコメントをされているスパルタキャンプ塾長さん。木下ファミリーのみなさまにはお馴染みの方かと思います。
〇OJTの始まり
OJTについて調べてみると、リンクアンドモチベーションのこちらの記事が詳しかったです。
OJTは第一次世界大戦で、アメリカが軍員を大幅に増やしその軍員をいかに早く指導するかに重きを置いた結果生まれた指導方法です。
その源流は、チャールズ・R・アレンが1917年に提唱した「4段階職業指導法」であり、4つの段階があります。
Show:やってみせる
Tell:教える
Do:やらせてみる
Check:指導する
軍で運用されていた指導法を、管理職の為に企業用に改良したものが日本のOJTの基本になっています。
また、より効果的な人材育成を実現する考え方として、「経験→省察→概念化→実践」という4段階により構成された経験学習型モデルがあり、このモデルをベースに「4段階職業指導法」を実践するのが良いOJTということです。
〇OJTが欠陥システムであることへの納得感
教える人が全員優秀で、業務に関する全てを知っている場合には機能しますが、そんな人いません🤣
結果として、育成される人のスキルレベルに圧倒的なバラつきが発生。
というのが塾長さんのご指摘で、まさにその通りだと思いました。
OJTが向いているのは、ルールが確立されている業務やパターン化出来る業務とされています。メンター側はすでにルールやパターンがわかるので「業務を全て知ってる状態」が確保出来るからです。
一方で、イレギュラーが発生しやすい業務や属人性の高い業務はOJTには向きません。メンター側がイレギュラーに適切に対応できその対応を言語化しメンティーに「やってみせ」を実践させる能力が必要で、メンティー側は言語化された内容を咀嚼しアクションに移す能力が必要だからです。
そんな指導が成立するケースはほとんどないというのは納得です。
それなのに、とりあえずメンター役を付けるだけであとは現場に丸投げすると、育成される人の能力次第で仕事が出来る・出来ないのバラつきが出来てしまいます。
〇私なりのOJTの紹介
弊社の新人研修
弊社は新卒採用・新人教育に力を入れており、私も10年ほど前に教育チームの立ち上げに参画しました。
その際に、弊社が顧客の要望を受けその要望を実現するまでの一通りの仕事を体験する研修を用意しました。新人一人一人に顧客役とメンター役が付き顧客役と新人のやり取りをメンター役がフォローします。
一定のパターン化された業務をクリア出来ると、次のステージでは顧客役が無理難題を要求するといった少しのイレギュラーを発生させます。
コントロールされたイレギュラーを発生させることで、メンター側がリスクを負わずにメンティーに経験学習をする機会を設けることで、研修終了時の新人たちのボトム側のバラつきをかなり小さく出来た実感があります。
チームに迎え入れたメンバーへのOJT
実戦の業務では研修とは比べ物にならないくらいの複雑さがありイレギュラーの連発です。
そんな状況で、チームに迎えたメンバーに対して私は、「地図渡して後ろを歩く」というスタンスで指導しています。
地図を渡す:
メンバーに関わってもらっているプロジェクトについて、背景や目的、どうやってゴールにたどり着こうとしているか、今どこを進んでいるか、何が課題かなどの全体像をお伝えします。
いきなり日本地図を渡してもすぐには咀嚼できないので、まずは日本地図と今歩いているエリアの詳細な地図をセットで渡します。
進みながら少しずつ広域の地図を渡し日本地図との関連を伝えていきます。
後ろを歩く:
地図を渡したらタスクもセットで渡します。その際に、詳細な地図と直近の目的地を伝えて、どういうルートで行くかを尋ねます。そのルートで行くと途中で落とし穴に落ちるとか遠回り過ぎてタイムオーバーになりそうに感じた時は、その旨を伝えて違うルートを考えてもらいます。
何ターンかやりとりし、ある程度妥当なルートを描けたら歩き始めてもらいます。
歩いている最中、私は後ろから見ているだけです。振り返ったらいるので都度お困りごとの相談には乗りますが、先頭を歩くのはメンティーです。
ご自身の力でゴールに辿り着いたらレビューしフィードバックをさせていただきます。
この繰り返しで、ゴール設定を少しずつ遠くにしていき、渡す地図も大きくしていくことで後ろを歩かなくてよくなります。
前提として、新人の方々は私なんかよりよっぽど優秀です。なのであれこれを指示を出して劣化コピーを作るようなことはしません。
地図を渡して後ろを歩くやり方は、教わる側が優秀であることが前提の経験学習モデルの実践であり、OJTがうまくいく前提と合致していればメンティーはどんどん勝手に活躍してくれるようになります。
ということで、今回はOJTが始まった背景や目的、指導方法としてのメリット・デメリットなどを調べ、自分がチームを運営する中で模索して見つけ出した指導方法をふんわりと共有させていただきました。
みなさんはどのような指導をされているのでしょうか?
最後までお読みいただきありがとうございます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
