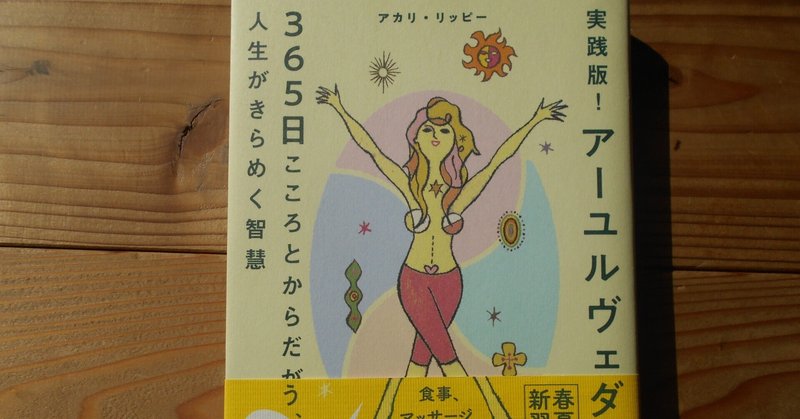
薬の使用は生き方の問題~薬を見直すことは、自分軸で生きること
先週から、久しぶりに風邪をひきました。
以前の記事にも書きましたが、症状で、風邪のひきはじめなのか、ピークなのか、あるいは、治りかけなのかを見通せます。
ざっくりいうと、
ひきはじめ:何となくだるい、寒気を感じる
ピーク:のどの痛みが出て、発熱が起こる時
峠を越えると:たんや鼻水が出る。黄緑色や黄色になる。
治りかけ:咳が出る。鼻水が少なくなる、止まる。
です。
いつもは、のどの痛みが出た段階で、めちゃくちゃ体を温めてすぐに寝るのが定番の風邪の経過方法でした。熱が出るのは、感染したウィルスなどの働きを鈍くする、体の免疫反応だからです。そして、その中で、体の免疫がウィルスを抑え込んでいくからです。なので、あえて熱いお風呂に入ることもありますし(私の場合です、普通は入浴禁止だろうと思います)、重ね着をして、湯たんぽを布団に入れたりなどします。
汗がしっかり出るぐらい熱い状態で1日過ぎると、すぐにのどの痛みがひき、体のだるさのピークが下がって行きます。
しかし、今回の風邪では、あまりにのどが痛かったので、ロキソニン(痛み止め)を飲んでしまいました。
おかげで、のどの痛みは和らぎました。しかし、同時に熱も下がりました。
「しかし」と書いたのは、薬の力で「熱を下げた」からです。本来は、発熱によって、体が免疫反応、自己治癒力を高めていくのに、その逆の方向にしてしまったからです。
案の定?のどの痛みが和らいで、さあ、「風邪の治りかけ段階」に突入・・・と思っていたら、何と、再び熱が出て、体の重さ、だるさを感じるようになりました。起き上がるのがきついくらいでした。
ここでピンと来たのが、熱を薬で下げてしまったために、しっかりとウィルスを抑え込めず(免疫力が上がらず)、中途半端になって、こじらせた…と言うことでした。
風邪の辛い症状を和らげ薬は多々あります。
鼻水をおさえたり、痰を出しやすくしたり、咳止めだったり、痛みを和らげたり。
しかし、「風邪」そのものを治す薬はないそうです。ウィルスを完全にやっつけてくれる薬はないため、自分の体に備わった免疫力や自己治癒力をあげることが重要になります。だから、水分や栄養をしっかりとって、安静にして、ぐっすり眠ることが推奨されます。むしろ、風邪はそうやって治すしかないようです。
「ただの風邪」と言う言い方もありますが、「こじらせる」と厄介です。
「風邪は万病の元」と言われるくらいですので、治しきることが最優先です。
このように、身近な病気である、風邪であっても、すぐに薬に頼ったり、間違った使い方をしたりしてしまいます。
他の病気については、さもありなん。
では、薬との付き合い方について、どう考えればいいのでしょうか?
いくつか紹介します。よかったら、お付き合いください。
1 病院で「薬やめる科」が誕生している!!
熊本県で松田医院和漢堂を開業されている、松田史彦医院長先生。
日本で初めて、「薬やめる科」をつくられた
おもしろい?・・・すごい先生です。
あちこちの不調の為、何十種類もの薬を手話放せない(飲む)状態になっている人が結構います。しかし、
・何年も飲んでいるのに、体調が悪い。
・薬なしでは、そして、量を増やさないと眠れなくなっている。睡眠薬中毒かも。
・血圧の薬を飲み続けていたら、元気が無くなってきた。
・・・
などの声も聞かれます。
そこで、松田先生は、少しずつ薬を減らしていくことで、その体調不良を減らしていく、体調不良をなくしていくことに尽力されています。
ズバリと表現しているのが、「薬の9割はやめられる」です。
そして、
次のような「養生十訓」を紹介しています。
1 薬は毒と心得よ。
2 薬(=毒)が必要なこともある。上手に使うべし。
3 薬が病気をつくる事もある。恐れずやめてみるべし。
4 薬に使われるな。薬をうまく使え。
5 医者は単なる助言者である。患者は自らも考えるべし。
6 ネット、マスコミ、医者から与えられた情報を鵜呑みにせぬこと。
7 心と体の毒を出し、自らの治癒力を信じるべし。
8 心の毒は、自らの心の言葉でつくられる。
9 健康は体の栄養と心の栄養でつくられる。
10 「病は気から」を肝に銘じるべし。
ドラッグストアも増えてきて、気軽に「薬」を手に入れられるようになってきました。しかし、その分、
薬を安易に使う傾向も強まりました。しかし、使い方を間違えれば、むしろバランスを崩す、別の部分を痛め
きつい言い方ですが、「薬は毒でもある」と言う言葉は、いつでも覚えておきたいです。
2 薬を飲むか飲まないかは生き方の問題でもある
松田先生の本のタイトルは「薬の9割はやめられる」なので、逆に言えば、1割は必要。その薬によって命が助かったり、症状や病態がかなり改善すしたりるともいえます。
ただ、「前文」でも書いたように、体には自然治癒力があります。
自分で体を守ったり、バランスをとったりする力もあります。
薬に頼らず、そのまま自然に(自分の体の力に任せて)生きることもできます。
実際、ヨーロッパの高齢者は薬をほとんど飲まないそうです。
そして、平均寿命は、日本と比べても「2歳」くらいしか違わないそうです。
もちろん、平均寿命なので、個人差もありますし、文化や習慣、気候など様々な違いが影響しているとは思いますが、薬を飲まないで、「自然に」生きたとしても、大きな差がないことは言えます。
不自然なほど薬を飲んで(薬漬けになって)、長生きした方がいいのか。
自然のまま、薬を減らして生きた方がいいのか。
この辺りは生き方の問題ですが、
本来の健康は「楽に生きること」であって、血圧やら〇〇値など、基準値という数字に合わせることが健康ではないはずです
「正常値」に戻そうと「我慢」「窮屈」な生き方を続ければ、それこそ、ストレスで心身をおかしくしてしまします。
また、たくさんの薬を使い続けることで、別の体の不調を呼び寄せてしまします。
今一度、薬との付き合い方を考えてみてもよさそうです。
3 「健康」に生きることは、「自分軸」で生きること
科学が発達してきたとは言いますが、全ての事が分かっているわけではありません。ほんの一部であり、私たちの体についても医学ですべて解明されているわけでもありません。なので、すべてのことを鵜呑みにするのも違っている気がします。
実際、いろんな体にいいとされる研究結果が出たと宣伝されていますが、あくまでそれは「平均」の話です。100人が100人、全員にいい効果があったわけではなく、ある程度の人に効果があったということになります。なので、ひょっとしたら、100人中10人には効果がなかった、逆に副作用があったとして、その10人に自分が入っているかもしれません。
また、「正常値」「基準値」が出されていますが、様々な値が「悪い」のに、元気で健康に生きている人もいます。
ここで、正常値にするために無理やり薬を飲んで、かえって健康を害する、元気を失う人だっています。
本来は、自分の体の事は自分が一番よく分かっています。
自分の体質に合わせた生活が一番、自分の健康につながると思います。そして、そうやって工夫を重ねることは「自分軸で生きる」ことにもつながります。
その一番のスタートは、「薬との関係を見直す」ことかもしれません。
ここまで読んでいただき、ありがとうございます
皆様の心にのこる一言・学びがあれば幸いです
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
