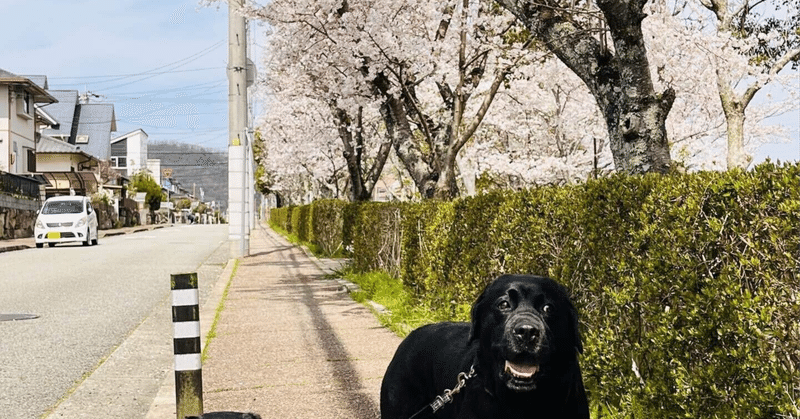
保阪正康氏著「近代日本の地下水脈」(2)を読んで
第4章 戦争が「営利事業」だった日本型資本主義
軍事が先導する日本型の資本主義は国家社会主義に近い性質のものであり、その地下水脈は現代の日本経済にも流れている。
日本企業の終身雇用、年功序列は多分に藩による武士の禄を食むという風潮を継承したものと思われる。
しかし、明治期の新政府は全国の武士を召し抱える金銭的余裕はなく、不満をなだめながら、リストラをし、一時金にて雇用関係を清算した。
一時金はすぐに生活費に消えてしまったが、それを元手に商売を始める者が出現した。その大半は代々の商人に及ばなかったが、五代友厚のような卓越した「政商」になった者もいた。
政商の筆頭は岩崎弥太郎で1870年三菱の前身となる海運会社を創設した。
政商としての三井は1871年からの公債の発行業務を独占的に受注し莫大な利益を得た。
幕末以来、日本の金融制度は大混乱にあった。江戸時代の貨幣や藩札、外国貨幣のほか、明治政府が財政難のために出した大政官札や民部省札などの不換紙幣も入り乱れて流通していた。
1872年国立銀行条例を公布した。第一国立銀行に出資したのは三井組と小野組だった。
日本は金に比べて銀が高いので
、外国人は日本に銀を売って金を買ってその利ざやで儲けていた。⇒日本からの金の流出⇒国立銀行が金を準備できない。
第一国立銀行の頭取になったのが渋沢栄一で、岩崎弥太郎とは対立ししばしば論争した。
(中略): 体調不良によりメモを取ること能わず。ごめんなさい。
軍国主義と資本主義の激動の数十年間。
軍先導型の資本主義は、つまるところ「戦争に勝って賠償金を取る」という最終目標が達せられない限り回らない。⇒兵士の命よりも勝利が至上命題となる。
恐慌と戦争
第5章 なぜ日本に民主主義が根付かなかったのか
日本型民主主義とは何か
著者は、日本の民主主義は独自のもので「それは五箇条の御誓文に現れている」と述べ、昭和天皇もそう述べたと書いてある。そこに日本の民主主義の特徴があるとすると、日本の民主主義は天皇から与えられたものだということになる。
私は、天皇に与えられた民主主義は本当の民主主義ではないと思う。だから、日本は民主主義が根付かなかったのだ。けれども、私たちはGHQに「戦後民主主義」を与えられ、天皇にも「五箇条の御誓文」を与えられたような民主主義ではなく、本当の民主主義を探さなければ、BRICSの非民主主義国に呑み込まれるのではないかという危機感を感じる。
因みに五箇条の御誓文は下記の通りである。
五箇条の御誓文
一 広ク会議ヲ興シ万機公論ニ決スヘシ
一 上下心ヲ一ニシテ盛ニ経綸ヲ行フヘシ
一 官武一途庶民ニ至ル迄各其志ヲ遂ケ人心ヲシテ倦マサラシメンコトヲ要ス
一 旧来ノ陋習ヲ破リ天地ノ公道ニ基クヘシ
一 智識ヲ世界ニ求メ大ニ皇基ヲ振起スヘシ
確かにこの精神性は日本人のメンタルの底流に流れていると思われるが、本当の民主主義ではなく(民主ではなく、やはり君主なのだと思うので)日本人は覚醒したほうが良いと思うが、いずれBRICSの非民主主義国に呑まれるなら、君主制の方が親和性が高いのでこのままでいいのかしら?とも思う。
ただ君主にアメリカを据えて戦うことになれば(その確率はかつてなく高まっている)、太平洋戦争の焼け跡を再び体験するかも知れないと思う。
ご参考:https://youtu.be/pdVlNEJe_Vg?si=xgM7NMDVvNmmroOH
一番重要なのは、五箇条の御誓文そのものではなく、(明治)維新の先達たちの、歴史に向き合う姿勢である。
そして終わりに、思想家の鶴見俊輔さんの言葉を引用して締めくくっている。「デモクラシーの後を必ずファシズムが歩いてくる。デモクラシーが疲弊するといつでも取って代われるように準備している」(了)
感想) 当然のことであるが、人間には多面性がある。状況によりそのときどきで異なる面を見せる。天皇にしても、近衛総理大臣にしても。そのことを描き分けた著書で、軍事と資本主義の濃密な関係も描き出している。途中体調不良もあり私にはまだ消化不良であるが、ご興味を持たれた方にはぜひ手に取って戴きたいと思います。
読んでいくうちに、現在の日本を憂える気持ちになります。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
