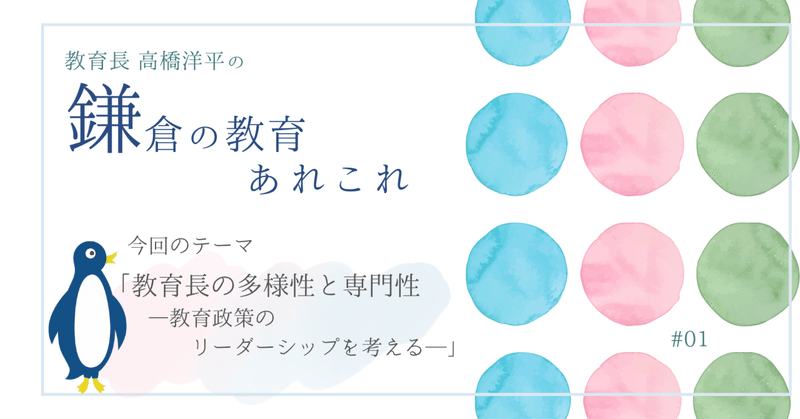
教育長の多様性と専門性 -教育政策のリーダーシップを考える-
教育長の高橋洋平です。
令和6年度に入り、いくつかの教育関連誌で連載をスタートさせています。
それらの記事をはじめ、教育長の仕事をする上での視点や日々の気付きなどについて、新たに「鎌倉の教育 あれこれ」と題して、鎌倉市教育委員会noteで発信していきたいと考えています。
どうぞよろしくお願いいたします。
経験すべて生かす
私は大学卒業後、文部科学省に入りました。福島県や米国大学への出向などを経て、文科省を退職後、コンサルティング会社に勤め、昨年鎌倉市の教育長に就任しました。
『LIFE SHIFT』(リンダ・グラットン著、東洋経済新報社、2016年)では、人生100年時代にあって、子どもたちは「学ぶ」と「働く」を往還するマルチステージ型の人生を生きていくとしていますが、私自身公教育という軸はぶれさせずに、さまざまな立場や切り口でキャリアを歩んできました。
教育長の職に就いて半年を過ぎ、これまでの経験すべてを生かせる仕事だなあと感じています。
教育長は「教育行政に関し識見を有するもの」のうちから、「地方公共団体の長が、議会の同意を得て、任命する」(地方教育行政の組織及び運営に関する法律4条1項)こととされています。
教育行政の識見とは何とも抽象的ですが、教育長という職の資質能力を巡って教育行政学の論文等をレビューするに、それは
教育的な指導力
行政的なマネジメント力
政治的な調整力
の大きく三つかと思われます。
文科省で法令や大臣答弁など大量の文書を読み書きするとともに、さまざまな関係者に説明・調整してきた日々、福島県では知事と教育長それぞれにそば付きの課長としてお仕えしリーダーとしての立ち居振る舞いを学ぶと共に、現場主義を掲げて学校と共に復興の歩みを進めた経験、外資コンサルティング会社での多様な同僚とプロジェクトを起こし、マネジメントする経験など、上記三つの資質能力という観点では何一つ無駄でなかったなと思われます。
市町村の教育長のうち女性は約5%、50歳未満は約0.3%(文科省2021年度「教育行政調査」)となっており、多様性が乏しい状況です。
退職校長出身の教育長が悪いとするものではありませんし、経験が必要な職であるのは確かです。その上で私の願いは、教育長という職がより多様でより専門性が高く、もっと存在感があり、公教育を通じて社会全体をリードしていけるような輝ける専門職集団にしていきたいのです。
そういった思いもあり、このたび、同僚である現職教育長などと共に一般社団法人LEAP(Leadership for Educational Administration for diverse Professional)という団体を設立し、4月21日(日)に設立シンポジウムでもある「教育政策リーダーフォーラム」を行いました。
元文科副大臣で東京大学公共政策大学院の鈴木寛教授や、教育行政トップリーダーで修士号を持つ兵庫教育大学の加治佐哲也学長、教育改革を進めている青森県の宮下宗一郎知事、文化庁の合田哲雄次長、認定NPO法人カタリバの今村久美代表などにご登壇いただき、大阪府の水野達朗教育長や石川県加賀市の島谷千春教育長ら現職教育長とのパネルディスカッションを行いました。
これからの教育政策のリーダーシップを考える上で、重要な示唆が得られたと思いますし、私自身、資質を磨いていかなければと思いを新たにしました。
(2024年4月19日『内外教育』掲載文 加筆)

