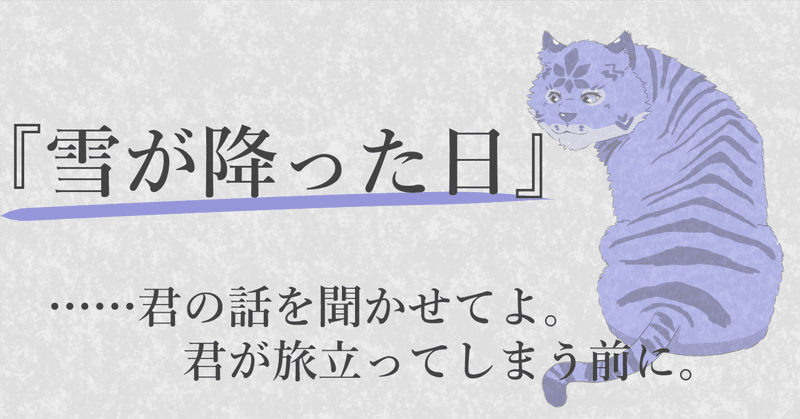
小説『雪が降った日』
1,作品概要
小説『雪が降った日』とは、小説創作系獣VTuber(2023年8月3日現在、準備中)の氷野峰アトラ(作者)が自己紹介のために書き下ろした短編小説作品です。Twitter(X)で日々呟いておりますので、気になった方は是非フォローください。
2,あらすじ
異世界ゼーバルの北方グラシエール。その酷寒の大地に一匹の仔氷虎がいた。寒さに強く、氷の魔力を操ることができる仔氷虎は、厳冬、人間の遭難者を助けることもある。
春になり寒さは幾分穏やかになったが、グラシエールの山間では見慣れない生き物が増えている様子。仔氷虎は避暑に来た少年魔導士マルコと友達になりアトラという名前をもらう。
しかし、氷虎の群れから失踪するものが出てきて……
________________
仔氷虎アトラが異世界の氷原を駆け抜ける。
友達とは、親子とは、そして「僕が僕であるために」できることとは。
新人のバーチャル物書き、氷野峰アトラの前日譚です……
3,本文
その日は雪の降る日だった。一日中、水が溶ける気温になることはなく、とにかく寒い日でもあった。辺りを見回しても白しかなく、歩き続けてようやく、あれは針葉樹かな、などと見てとることができるようになるという過酷な日。
きっと氷のエーテルが落ち着かない日なんだ。エーテルに感情なんか無いよって友達は言うけど、僕はきっとあると思っている。だって、自然が人間の表情みたいにころころと移り変わっていくんだから、それを後押ししているエーテルにだって気分はあるはずなんだ。
そして、エーテルだけじゃなく、運なんかにも気分はあって。多分今日は、誰も彼もが落ち着かない日なんだろうと思う。
雪は降っているけれど風は強くなく、退屈をしていた僕は洞穴から誘われるように飛び出して、人間の住む村の方へサクサクと足跡をつけながら駆けて行った。辺りが見えなくても方向はなんとなく分かる。それはきっと北にそびえるとても高い山、巨龍の角の不思議な力のおかげだと思う。
雪原は寒いけれど、僕は氷虎だから気にならない。むしろ寒い方が元気になることもある。魚だって美味しくなるし、人間の子供が遊んでくれることも多くなる気がする。
僕は人間が好きだった。家族や友達はあまり近寄らない方がいいよって言うんだけど、人間の楽しそうな顔を見ていると、何だか僕まで嬉しくなってくる。人間の使う火も僕は怖くなくて、温かいスープの匂いはお腹が空いてくるほどだった。それに、人間は甘い果物をくれる。赤くて中身は白くて、食べるとサクサクする丸い果物!
今日も、その赤い果物がもらえないかなと甘い味を想像しつつ、ピョンピョンと人里へと向かっていると、白い風景の中に黒い影が見えた。
仔熊かな? 一瞬そう思ったけれど、微かに聞こえてきたうめき声が、熊ではなく人間のものであることに気がついた。
(大丈夫かな、助けたいけど、でも僕にできることなんてあるだろうか)
恐る恐るうずくまる人間に近づくと、その人間は意外なほど軽装で雪に埋もれかけているのが分かった。僕は、魚を獲る要領で雪を掘り、どけていく。でも、雪の積もる速さは想像以上に速くて掘っても掘っても人間は出てこない。
それでも掘っていると、人間は助けようとする僕に気づいたらしく、体をよじって雪から出てこようとした。
そして、ようやく人間は積もる雪から立ち上がった。
「ふう、助かった。 ありがとう、見知らぬ人!」
僕は意外に元気のある、その遭難者に思わず後退りして首を傾げる。
遭難者も首を傾げ周りを確認すると、ようやく足元にいる僕の存在に気がついた。
「なんと、氷虎の子供か! いやはや、確かにこんな人間の通らなそうな道で助けがあるわけもないか。私はなんて幸運なのだろう」
遭難者は、ふむ、と思案顔になり白い手袋をした手をこちらへと伸ばすと、えいっ、と一声上げた。すると、僕は喉に微妙な違和感が現れたことに気がついた。
「ん、んー」
「お、成功したようだな」
満足気に頷く遭難者。
「あれ、もしかして僕の言葉が聞こえてる?」
「うむ、そのように魔術をかけたからな」
「へええ、お兄さん魔法使いなんだ!」
魔法使いの遭難者は自らをゲルンと名乗り、僕に人里までの道を聞いた。僕はどの方向に村があるのかは分かっていたけれど、そこまで行くために通るのは、氷虎の通りやすい道であって人間の通りやすい道じゃない。説明の仕方を考えるのも難しいことのように思えたし、何より魔法使いに会うのは初めてだったから、僕は好奇心も手伝って、人里まで一緒に行ってあげることにした。
ゲルンがこの雪国、人間の言葉でいうグラシエールに来たのは、単純に観光だったらしい。世界の中でも北限に位置しているグラシエールは生態系の限界として興味深い生き物に溢れているようだった。氷虎もその一つだ、というゲルンの笑顔はどこか影を感じて怖かった。多分、魔法使い特有の笑い方なんだろう。
また、魔法使いとしてのゲルンはあまり出来が良くなかったらしく、かなりの苦労をして今の力を得たみたい。僕は氷虎の力で物を凍らせることはできるけど、小難しいことはできない。魔法が使えるだなんてそれだけでカッコいいと思う。でもゲルンは苦労した割にそれをくどくどと話すことはなかった。研究や魔術そのものに対する熱意が勝っているのかもしれない。
降る雪も落ち着いてきた頃に、人間の村へと辿り着いた。僕は小さいけれど一応氷虎なので、人間の大人に出会うと警戒させてしまう。だから、果物を探し終わったら早々に村を出ることにした。
「ありがとう、小さな勇者」
「え、それって僕のこと?」
「そうだよ。これからも好奇心を大事にね。僕はその心に救われたんだから」
「えへへ、わかったー」
僕は口をにやつかせながらゲルンにさよならを言い、洞穴まで戻った。洞穴に戻った後、喉の調子はもういつも通りだったし、家族や友達にも変に思われなかった。ゲルンのことは明日魚を獲りに行くときにでも友達に話そうと思う。雪は夜になったら止んだ。
1
空気が澄んでいる。北にある巨龍の角も、朧げな影としての山ではなく青白い切り立った岩山として見渡すことができる。最近は吹雪くこともそうなくなってきたので、ようやく春を迎えたのだなあ、と嬉しくなって鼻がむずむずしてもくる。
「へくち!」
くしゃみが出てしまった。大人たちが軽く振り向いて笑う。少しだけ年上の友達は呆れ顔でからかってくる。
「お前、かわいいくしゃみするなあ。そんなんじゃ大人の男は遠いな」
「そうかなあ、くしゃみも男らしい方がいい?」
「そりゃそうだよ。例えば、こう……」
友達は顔を歪めて男らしいくしゃみをしようとするが、くしゃみをわざと出すのは難しいことだ。僕は散々友達の変な顔を見て、しばらく後、友達は諦めたのか何事もなかったように湖へと歩き続けた。友達は多分変な顔を僕に見せつけたかったんだと思う。
一応、狩りに向かうところなので、あまり騒ぎすぎることのないようにし、大人たちの顔色を伺いながら湖へとやってきた。
冬場は分厚い氷に覆われている湖だったが、春になり表面の氷が溶けているようだった。風なのか泳いでいる魚なのか、揺らぐ湖は陽の光の反射をきらきらと湛えている。湖に注ぎ込む雪解け水もとびきり透明で、音まで透き通っているかのよう。
僕らはここで食べられるだけの魚を獲る。魚の泳いでいる場所は水の中でも何となく分かるので、そこの水を魚ごと凍らせて獲るんだ。
陽が傾いてきたので狩りを終わり洞穴に帰るまでの休憩時間、僕らはシャリシャリの魚を食べながら雑談する。この時間は多少騒がしくしても問題ない。
僕は少し疲れてしまったので、大人に混ざって穏やかな話を聞いていた。遠くで友達らが雪の上を駆け回っている様子も見える。
「そういえば、北の山の話聞いたかい?」
「いんや。何かあったんかね」
新しい話題が出てきた。
僕も雪から首を持ち上げて耳を傾ける。
「なんでも見慣れない生き物が次々に出ているらしくってさ。ちょっと気にかけておいた方がいいかもしれない」
「へえ、新種ってことかねえ」
「そうなんだろうけど、数が多いみたいで、今年は異常だって」
「大変だなあ。いかにオイラたちが氷虎だって言っても、新しい生き物がどんなやつがわっかんねえからな。気ぃ引き締めねばならんよ」
「全くだ」
新しい生き物。それもたくさん。それがどういったものなのかは解らないけれど、ちょっと見てみたい気もする。仲良くなれるだろうか。もしかしたら危ないかもしれない。でも、きっといいヤツもいるはずだ。
見たことのない生き物の姿を空想している間に休憩時間は終わり、洞穴へと戻った。
魚を持ちかえると待っていた母親たちは喜び、僕の母さんは微笑みながら毛繕いをしてくれた。友達は、そんな子供っぽいこと、と言って断っていたけれど、今日の僕は疲れていて、毛繕いをしてもらいながら、いつの間にか眠りについていた。
2
人里は針葉樹の林の中にある。その濃い緑色の林はそれなりの広さがあり、僕の足では一日でも一回りできない。村の広さはそれほどでもないから、木が生えているだけの土地が大部分なのだけれど、今日僕はこの林の中にいた。
大人の氷虎はこの辺りに来ることがない。なぜなら、この林は人間の土地であり、入り込めば弓で射られる可能性もあるからだ。人間は強い。道具と魔法の力を使えばあらゆる生き物に打ち勝てるんじゃないかと思う。
僕はまだ小さいから人間もあまり怖がらない。なので、今、人間の子供と一緒に遊んでいる。僕の毛は、自慢になってしまうけど、とてもふわふわしている! そのふわふわを求めて人間の子供は僕に抱きついたり、触ってみたりする。
人間の大人は滅多に現れないけど、木陰から子供達を見守っているんだ。だから、子供も安心して僕と遊べる。大人たちは僕がひとりきりで遊びに来たことを知っているから、それほど警戒はしていない。
かけっこをしているときだった。村の子供の中で一番大きな男の子が急に足を止めた。元気な子だから体調が悪くなったわけではなさそうだ。
よく見てみるとその子の前に知らない子が立っていた。肩まである金色の髪に緑色の帽子を乗せて、服も緑色だったけれど村の子供達のものと比べるとだいぶ上質なものらしかった。よく見ると右手の人差し指に銀色の指輪もつけている。
立ち止まった男の子が声をかけた。歳は多分同じくらい。
「見かけない子だね。どこから来たの?」
男の子の声は落ち着いていて、できる限りの優しさに満ちていたけれど、緑の服の子はその声に驚いたのか、林の中に走っていってしまった。
村の子供達はしばらくその方向を見ていたけれど、やがてまた自由に遊び始めた。
でも、僕はどうしてもその緑の服の子が気になってしまったので、こっそり広場を抜け出して後を追うことにした。
足跡を追っている途中、気づいたことなのだけれど、あの緑の服の子はどうやって広場に近づいたのだろう。広場の周りは大人たちが見張っていて、よそ者が簡単に近づけるわけじゃない。誰かに入れてもらったのだろうか?
しばらく走ると、木がぎっしりしていない、林の隙間のような場所があった。足跡の間隔が狭くなり、そして緑の服の子が木に寄りかかっているのが見えた。
美しい光景だった。きらきらした白い雪と緑色の針葉樹。そしてさらりとした金色の髪を持つ子供。僕がもし絵描きだったら絵にしたくなっただろう。
「こっち来なよ」
声は男の子のものだった。美しかったから性別も分からなかった。僕はいつの間にか止まっていた足を動かし、男の子が寄りかかっている木の根元まで近づいた。
「君は人語を喋るのかい?」
僕は喋れないと言うかわりに、まだ少し高めの音のガオ、を返した。
「なるほど。わかるけど喋れはしないんだね」
納得したように頷き、男の子は右手を僕に向かって突き出した。人差し指の銀指輪が不思議な色に光る。
そのとき理解した。この子は魔法使いなんだと。
魔法使いなら、村の大人に気づかれず広場に近づけたのも納得がいく。気配を消すことなど簡単なことに違いない。
「あ、あー」
「喉の調子はどうだい?」
「うん、いい感じ」
「あんまり驚かないんだね」
「前にも似たようなことがあったから」
魔法使いの男の子は緑の帽子を持ち上げると、金色の髪の毛をかきあげながら興味深そうに青色の瞳を光らせた。
「僕はマルコ。君の話を聞かせてよ。僕が家族のところへ帰る前に。大丈夫、時間はまだあるよ」
広場の子供達は気になったけど、僕は子供の魔法使いに好奇心が抑えられなくて、最近起きたことや家族のことをマルコに話した。
マルコは座ることなく、木に寄りかかったまま話を聞いた。ときどき静かに頷いたり、涼しく響く声で相槌を打ったりする。
遭難した魔法使いを人里まで案内した話。
春になって湖の氷が溶け出した話。
そして、見知らぬ生き物が増えてきた話。
特にマルコは見たことのない生き物について詳しく聞きたがった。
「急に増えたってことだね。その新しい生き物たちが」
「そうなの。僕が見たのは大きな雪ウサギだった。かわいいウサギでも大きくなるとちょっと怖いね。跳ぶときも人間の背の高さくらい跳ぶんだもの」「ふーん、興味深いね」
思案顔になったマルコは緑色の上着についているポケットから銀色の小石を取り出して、雪の上に置いた。それから左手を伸ばすと白い指先で綺麗な図形を描いていく。その図は小石を中心に散りばめられているようだった。
「少し光るから」
そう言うと、マルコは小石に向かって右手を突き出した。すると、描いた図形が輝きだす。
光っているところをずっと見ていたかったけれど、あまりの眩しさに、一瞬目を閉じてしまった。もう一度開いた時には小石は無く、かわりに三本の線が一点で交差するような銀色の図形が形取られた小さな装飾具になっていた。
「イヤリングだよ。これを付けているとまた僕に会える」
「これ、くれるの?」
「そうだよ、また会えるように」
マルコは僕の左耳に銀のイヤリングを止めて外れないようにした。装飾具なんて初めてだったから、嬉しくて思わず飛び跳ねてしまう。
「今日のところは帰るよ。家族も心配しているだろうし」
「帰っちゃうの?」
「名残惜しいけどね」
マルコは背にしていた木から離れて僕のところまで来る。屈んで撫でてくれた左手は温かかった。
「見知らぬ生き物のことは僕も調べてみるよ。またね」
「うん、ありがとう!」
林の中に去っていく緑色の影。僕も洞穴に戻ろうと体の向きを変えたとき、微かにマルコの声が聞こえたような気がした。
何も起きなければいいけれど。
3
洞穴に帰ったとき、家族や友達にはイヤリングのことについて詳しく聞かれたけど、人間にもらったと言うだけで納得はしてもらえた。ただ、大人の中には呆れ顔もあった。人間に良い感情を持たない大人もいるので仕方ないことだと思う。
それ以降、僕はマルコと時々会うようになった。
「君、名前は無いのかい?」
「名前、人間が呼び合うときに使うやつだよね。氷虎の中では必要ないから無いよ」
「うーん、じゃあ、好奇心が強い君にアトラという名前をプレゼントしよう」
「名前をくれるの? ありがとう!」
「嬉しそうでなによりだ」
「ちなみになんだけど、アトラってどういう意味?」
「幻の古代都市の名前だよ。西方の海にあったらしい。海は知ってる?」「うん! 海の街の名前かあ……いいね!」
アトラという名前が嬉しくて、僕は母さんや友達に名前をもらったことを話した。そのことが好ましく受け取られたのかは分からないけど、僕は仲間の中でアトラと呼ばれるようになった。
マルコは雪国グラシエールに旅行で来ているらしい。両親とも北国の生まれだったようなのだけど、マルコが生まれるとき暑い地域へ引っ越しをした。この時期にもなるとすでにだいぶ気温が高いということで、避暑のために旅行しに来たらしい。
彼自身は人間の子供が通う学校というものに行っておらず、魔法の研究機関ですでに働いている。しかし、親の強い意向で無理やりグラシエールに連れてこられ、内心退屈していたという。
「確かに暑いのは苦手なんだけどさ。かといって寒けりゃ良いってものでもないだろう」
僕は寒いことが嫌になったことはないし、暑さがどんなものかきちんと体験したこともないから、曖昧な返事を返すことしかできなかった。
見知らぬ生き物たちが現れることについては、マルコと岩山に入ったり、林を探したりして調査を続けている。でも、僕ができることといったらマルコの話し相手になることと、道の案内くらいであまり役に立っている気がしない。
マルコと一緒にいると僕も賢くなった気がして楽しい。それで良いのかもしれない。
ただ、仕方がないことなのだけど、氷虎の友達と遊ぶ機会が少なくなってしまった。元々はかけっこをしたり湖を覗きにいったり、毎日変わらないようでいてやることは色々あったのだけど、それをすっぽかしてしまっている状態だ。いつも約束をして、そういったことをしていたわけではない。でも、付き合い悪くしているような気分になって申し訳ない気持ちになることも増えた。
マルコとの調査が進んで、謎の生き物たちはどうやら北の山岳地帯から来ているらしいことが分かった。エーテルの流れがわかるマルコによると、山岳地帯の中には、なんでもエーテル溜まりのようなものがあって、その影響からか新しい生き物が生まれている、と推測が立てられるようだ。
僕にはセンモンテキなことを理解する力はないけれど、北がおかしいということは分かった。昔から氷虎にとっても人間にとっても、北の地は聖なる土地とされていて、中でも一際大きい山、巨龍の角は誰も入ることができない禁足地になっている。
もしかしたら、その巨龍の角には何か大きな秘密があるのかもしれない。そう考えると胸がどきどきした。
その日もマルコが帰るというので、暗くなる前に解散になった。僕は洞穴に一人で戻る。
少し赤味を帯びた光が洞穴の中に伸びる日暮前。暗がりでは家族や友達が集まって、なにか話をしている最中だった。
「どうしたの?」
友達に後ろから声をかけると、体を飛び上がらせて驚き、それから怒りだした。
「びっくりさせるなよ!」
「ごめんごめん」
「でもアトラが帰ってきてよかった」
「え?」
珍しいことを言うもんだ。僕は少し友達をからかってやろうと思って口を開きかけたのだけど、周りを見ると皆んなが心配そうな表情で僕の方を見ていたから、僕は口を閉じて神妙な顔つきになるよう努力した。
母さんが近づいてきた。
「本当、無事で良かった……」
「どうしたの、母さん、何があったの?」
「あのね、おじいさんがいなくなってしまったの」
話を詳しく聞くと、仲間の中でも高齢な氷虎が知らないうちにいなくなってしまったそうだ。高齢とはいえ、まだ元気なおじいさんで、足腰も強く、どこかで動けなくなっている可能性は低い。
くわえて、おじいさんは今日、北の湖に仲間と魚を獲りに行っていて、その狩りの最中に、ふっ、といなくなってしまったらしい。
「北の……湖」
北といえば謎の生き物たちがやってくるのも北だった。心が落ち着かない。
「どうしたの、アトラ。なにか知って……」
母さんが僕に尋ねようとしたとき、
「帰ったぞ!」と洞穴の入り口から声がした。
声を出したのは仲間の中でも活発で、体力のある男衆の一人。入り口から皆んなの元にやってくると、おじいさんを探した結果について説明しはじめた。
「結論から言うと、爺さんは見つからなかった」
誰からともなく溜息がもれる。
「でも、関わりのありそうな奴なら見かけた」
「え?」
「魔法使いだ。人間の大人。男のようで白い手袋を使って魔法を扱う」
僕の鼓動が何倍にも膨れ上がった。大人の魔法使い、それってもしかして……。
友達が僕の方を怪訝な目で見る。
「それ、アトラが前に会ってたヤツじゃあ……」
僕に全部の視線が集まる。代表してお爺さんを探しにいっていたお兄さんが僕に質問する。
「アトラ。心当たりがあるのか?」
「う、あるかもしれない……」
不安な気持ちを抑えられない僕の頭を母さんが優しく撫でる。僕は勇気を出して皆んなに説明した。
「冬の終わりに、多分、その魔法使いを人間の村に案内したの。この辺りじゃ魔法使いは珍しいし、大人の男で白い手袋と言ったらその人ぐらいしか……」
「案内した後のことは解るか」
「ううん、それからは会ってない。ねえ、髪の毛はどうだった? 黒髪で波打っていたと思うんだけど」
お兄さんたちは息を呑み、顔を見合わせてから僕に向かって頷いた。
「やっぱり……」
確か名前はゲルン。そう伝えると、お兄さんは仲間皆んなにゲルンらしい男には近づかないように注意をした。
話は長くなってしまって、皆んなも疲れているようだったので、お兄さんの言葉で解散することになった。
でも、そこまでずっと黙っていた友達が、僕に向かって悪態をついた。
「アトラがその悪人を案内なんてしなけりゃ爺さんは無事だったんだ」
「やめろ、そんなこと言うんじゃない」
お兄さんがかばってくれた。でも、本当に友達の言う通りかもしれない。僕が人間に興味を持ちすぎたせいでお爺さんは……。
下を向いている僕に友達は追い打ちをかける。
「最近じゃ他の魔法使いと友達になって、浮かれてるみたいじゃないか」
洞穴の地面をつかむ手に力がこもる。
「いっそのこと群れから出ていって人間と暮らしたらどうだ」
「そんな……!」
「おい、お前、言い過ぎだぞ!」
僕は皆んなの横をすり抜けて走り出していた。洞穴の外は夕焼けも終わりかけで、そろそろ夜の領域に入る。僕はとにかく遠くまで行きたかった。恥ずかしくて、申し訳なくて。本当はイヤリングも投げ捨てようとしたのだけど、うまく外すことはできなかった。
どれだけ走っただろう。後ろから声がする。
「アトラ、アトラ、待って!」
母さんの声だ。
僕は走り疲れたのもあって、速さを緩め、やがて止まり、それから後ろを振り向いた。
すぐ後ろに母さんがいた。母さんはやっぱり大人の氷虎だから、子供の僕になんかすぐ追いついてしまう。僕って情けない。
「アトラは何も悪くないわ。ゲルンとかいう男のことも、悪人だなんて分からなかったのでしょう?」
「うん……」
「もちろん、ゲルンが悪いかどうかすら分からない。でもお友達が不安な気持ちになって、あんなこと言ってしまったことも、分かるかしら。うん、あなたなら分かるわよね」
「分かる」
「母さんは、というか群れの皆、あなたたちが仲良く暮らしていけるのを望んでるわ」
「でも、僕、どうしたらいいかな。こんなに悲しくなったのは初めてなんだ」
そうねえ、と母さんは少し首を傾げた。それから周りを見て、何かを探す。
母さんは視線で僕に伝えたいことがあるようだ。
「私ね、昔、幻の湖を見つけたことがあるの」
「え、マボロシ?」
「そう、噂にはなっていたのだけど。どこかの山に七色の水を湛えた湖があるって」
「ほんとう? 本当にそんな綺麗な湖があるの?」
「そう、とても綺麗で、幻想的で……」
懐かしそうな母さんの瞳に七色の光が映ったように見えた。
「お友達を誘って、探しに行ってみたらどうかな?」
「うん、きっと喜ぶよ!」
良い子ね、と母さんに頭を撫でられ、元気よく洞穴に戻ろうと思ったのだけれど、すぐに足が止まってしまう。
「でも、僕、なんて言って誘ったら良いんだろう。結局、友達に言われたこと、何も解決できない」
「んー、多分ね、友達も不安だったからああいうふうに言ってしまっただけだと思うの。最近アトラが遊んでくれないから寂しかったんじゃないかしら」
「そうかなあ」
「もし、それでも不安なら、こういうのはどう?」
母さんは僕に耳打ちする。
4
切り立った峰に緩んだ雪の組み合わせは、とても足を滑らせやすくなってしまう。僕は注意深く進んでいたのだけれど。
「あっ!」
よく見えない後ろ足が硬い氷をつかみそこね、体のバランスを崩す。ずるりと崖下へ飲み込まれそうになる。
僕は必死に前足を伸ばした。
「危ねえ!」
伸ばした前足は思いの外しっかりとした別の前足に掴まれる。
「リンゴ!」
「待ってろ、今引き上げる……っと!」
僕は峰に引き上げられ、深呼吸をしてから友達に声をかける。
「ありがとう、リンゴ、助かったよ……」
「まったく、気をつけろよ! 肝が冷えたぜ」
「ごめん」
「いいよ、名前も貰ったしな」
リンゴは白い牙を見せて、にかっと笑う。友達に名前を贈るのは母さんの提案だった。名前を考えるにあたって、マルコにも意見を聞こうと思ったのだけど、イヤリングを使った心での会話は通じなくて、僕は一人でああでもないこうでもないと考え続けた。
リンゴという名前を友達に話すと、友達は一応喜んでくれた。
(でも、なんでリンゴなんだ?)と、友達は言った。
僕が、(一番大好きだからだよ!)と言うと、友達は照れて、(じゃあ、リンゴでいい)そう言って、そっぽ向いてしまった。
次の日、僕らは仲直りして幻の湖を探す約束をした。
そして、今日。僕らは雪の峰を歩いている。
朝早く洞穴を出発して、延々と探しまわり、もうすぐ陽が傾いてくる。
「まだ見つからないのかよー、どこにあるんだ、幻の湖」
「まあまあ、幻って言うくらいだからさ。きっと珍しいんだよ」
「でも、湖なんだから勝手に動いたりしないだろ?」
「そうだねえ、もしそうならなんで幻なんだろう」
「また考え事しながら歩いて、滑り落ちないようにな!」
湖が幻である理由。湖自体は生き物じゃないから動くことはないはず。しかし、それでも見つけにくいということは、単純に視界に入らない場所にある?
「もしかして、もしかしたらなんだけど」
「ん?」
「幻の湖は見えないところにある、とか」
「見えないところって……」
「例えば、洞窟の中」
「でも、七色に輝くんだろう? 光はあるんじゃないのか」
「うーん……」
僕らは周りを見渡す。遠く西方に陽が傾き、白い地平が広がっている。北を見れば山々はまだ高いが、谷の一つ一つは逆にそれほど深くない。なんとか歩いて降りていけそうな場所が多い。
「見ろよ」
僕はリンゴの声に視線を巡らした。リンゴが見ている方向。そこには岩盤にいくつもの穴が開く岩山があった。ちょうど下の方には歩いて入れそうな大穴がある。
「あそこなら光も入りそうじゃないか?」
「行ってみよう!」
「あ、おい、待て!」
僕とリンゴは足元に気をつけながら峰を降り、穴あきの岩山へと入っていった。
洞窟の中は洞窟の中であるにもかかわらず陽の光で溢れていた。しかし、それでも外より気温は低く、僕は短く身震いをする。
内側の壁面にはヒカリゴケも生えていて、夕方の光を吸収しながら淡く黄金に光っている。
僕らは洞窟に入ってから、一言も話さなかった。並んで歩いていたから尻尾が触れ合うことはあったけど、静かで澄んだ空気に言葉は必要無い気がした。リンゴも同じ気持ちだったんだと思う。
洞窟の中には小高くなっている場所があった。水の匂いが漂っていて、上を見ると洞窟の天井、氷柱の隙間に輝き揺らぐ紋様が浮かび上がっていた。やっぱりここに幻の湖があったんだ。
高い場所に上がるにはつるりとした壁をよじ登らなければならなそうだったが、その壁は上にある湖をぐるりと取り囲んでいるようだった。
難儀なことに思えたが、周りをよく見てみると段差を使って上に登れそうだ。不思議なことに段差は一定の間隔で作られていて、よくよく考えてみるとつるりとした壁も、自然にできたというには表面に凹凸が無い。
もしかすると、ここは自然な洞窟というよりも、人間の遺した遺跡なのかもしれない。
僕らは段差を上がりきり、目の前に広がる湖に息を呑んだ。
それは確かに七色の湖だった。洞窟にあるものとしてはあまりにも巨大で、水の中には氷が張り付いている。その氷に光が反射し、なんとも言えない色合いを生み出しているようだった。
普通、氷は水に浮かぶものだと思うけれど、湖の中にはたくさんの氷が沈んでいる。内壁に張り付いているんだ。その幻想的な風景はまさに幻と表現してもいいものだと感じる。
僕らは何も言わず、ただ時間を過ごした。僕とリンゴは男同士だったけど、恥ずかしさも起きることなく、寄り添って二人座っていた。
長い時間。長い時間だったように思う。でも七色の光が消えていくまでの時間、つまり陽が落ちるまでの時間だったから、実際には短かったんだと思う。
「綺麗だな」
リンゴの言葉に僕は頷いた。七色が消えてしまってからでも綺麗だと言える心の中の景色に、気持ちはずっと震えていた。
洞窟の中は薄暗かったが、ヒカリゴケの明かりに加え、今日は月も出ている。洞穴に帰るには困らなそうだった。
僕はリンゴに声をかけ、皆んなの場所へと帰ろうとした。でもそこで、洞窟内に音が響いた。
コツン、コツン
はじめ何の音かわからず、音がはっきりしてきてようやく人間の足音だということに気がついた。
リンゴも気がついたようで、反響する音に惑わされながらも辺りを警戒している。
でも、僕はその足音が誰のものだか気がついた。リンゴに、安心して、と警戒を解くように言った。
「マルコ」
名前を呼ぶと、その人物の手元に光が灯った。魔法の光だ。マルコは軽く手を上げる。
「どうしてここに?」
「ちょっと調査がね。一緒にいるのは仲間かな」
僕は、うん、と答え、リンゴを紹介した。リンゴは少し緊張しているようだったが、僕が親しく話している様子を見て、少しずつマルコに慣れていった。
「調査ってのは、聞いた感じゲルンについてか?」
「そうだね、後をつけて何をしているのか探っていたんだ」
「何かわかったの?」
「詳しくはわからないが、何か生き物についての研究をしているようだ」
マルコは七色を失ってなお輝きを湛えている湖を眺めながら、ゲルンについて話した。
「僕の所属している魔法研究機関を介して、ゲルンについて照会したところ、ゲルンの主な研究は世界の果てについてのようだった」
「世界の果て?」
「そう、この世界ゼーバルについては、実のところまだまだわかっていないことが多い。世界がどんな形をしているかすら、まだ解明されていない」「ふーん、人間は小難しいこと考えるんだな」
「疑問に疑問を重ねることこそが人間の本質でもあるからね」
マルコの話によると、北の世界の果ては霊峰、巨龍の角の向こう側にあるらしい。でも、巨龍の角はあらゆる生き物を退けるため、調査に向かうことができない。ゲルンはその調査を可能にするため、研究に明け暮れていたようだ。
「もともとゲルンは才能に溢れた方ではなかったらしい。それこそ、魔術だけでは研究も行き詰まったので機械の力も借りていたようだ。機械自体は魔法に関わるものの禁忌というわけではないが、機械の力は絶大で魅了されてしまう者も多い」
思案顔になるマルコ。
そのとき、僕とリンゴの耳が動いた。
「聞こえたか?」
「うん……マルコ、洞窟の外に出よう」
僕らは足早に洞窟を出口に向かって駆けていく。マルコも魔法の力を借りているのか、速やかについてくる。
「何かあったのかい、二人とも」
マルコの言葉に答えるのは僕の仕事だと言うように、リンゴは視線を投げてきた。
僕は洞窟の出口一点を見つめて、駆けながらマルコに言った。
「助けを呼ぶ声が聞こえたんだ。母さんの」
5
幻の湖から一直線に駆け岩山から出た僕らはそのままの勢いで雪の積もる坂を降り、声の聞こえる方向へ足を止めなかった。母さんは一定の間隔で助けを呼んでいる。僕はその声に答えなければならなかった。
月明かりの夜。春になったとはいえ、厳しい寒さの雪山は足元にも注意して進む必要がある。幸い、真っ暗というわけじゃない。僕らはしばらく無言で声の出どころを探した。
そして、北の岩山、巨龍の角もいよいよ近い場所に、研究所はあった。
人工的な明かりに飲まれるように岩山の中へと入っていくと、自然の洞窟を利用した研究所が作られていた。機械が群れをなす様子は、まさに生物研究所と言った様相で、ゼーバルで人間の子供が読むおとぎ話に出てきそうな、悪い研究者の根城といって申し分ないものだった。
洞窟の壁を埋め尽くすように並ぶ円筒形の容れ物。その間を三人は警戒しながら進む。天井からぶら下がる明かりも機械から漏れ出す光も、その淡さが故に研究所内の黒い闇を拭いきれない。
リンゴが足を止めた。透明な容れ物の中に何か浮かんでいるのが見えたからだ。
それは、力なく液体に浮く氷虎の姿だった。
「爺さん……!」
容れ物に歩みよったリンゴは機械を眺め、どうにかおじいさんを外に出すことができないか考えているようだった。
それを見て足を止めた僕に、リンゴは小さく、しかし鋭く言った。
「先に行け」
「リンゴはどうするの?」
「俺は助けられないかやってみる。群れの皆んなも呼んでくるよ。だから、早く!」
僕は頷き、マルコと一緒に奥へと駆けた。リンゴのことは振り返らなかったけど、心の中で、ありがとうを呟いた。
立ち並ぶ容れ物には、次第に中身が入るようになった。洞窟の出口に近いものには、今までよく見ていたような生き物が入っていたが、研究所の奥へと進むにしたがって、見慣れない生き物が増えていく。
熊のようなウサギ。鷹のような雪ヒョウ。部分的に体が肥大化したような生き物もいるし、中にはどんな生き物とも違うような全く見たことのないものもいた。
それらは全て透明な液体の中で浮遊し、眠っているようだった。
しばらく薄暗い中を駆けていると、ついに辿り着いた部屋は洞窟の行き止まりのようだった。ただ、とても広い。
「まるで、劇場だな」
マルコがぽつりと言った。
大小様々な機械と容れ物。今までと異なるのは、容器の中に液体は入っておらず、生き物たちはただ眠りに落ちているということ。そして、人間たちが劇に使うような舞台の上に、一際大きい容器が置かれていることだった。その容器は他の容器とは異なり、格子状金属に覆われているらしく頑丈に作られているが、反面、中に生き物はいなかった。
僕は辺りを見回した。暗がりの中よく見てみると、やはり氷虎の姿が見える。
「母さん!」
母さんは容れ物の中でぐったりと横たわっている。呼吸はしているようだけれど、ちょっとやそっとじゃあ起きそうもない。僕は試しに体当たりしてみたけれど、機械はとても頑丈でどうすることもできなかった。
それでも僕は、僕自身の気持ちを止めることができなくて、何度も、何度も、機械を壊すために体当たりをした。マルコはドン、ドン、と響く音の中、僕に視線を投げかけてくれていたと思う。
不意に不機嫌そうな声が響いた。
「ウルサイな。やめてくれるか?」
声の主を広い空間の中探すと、コツン、コツン、と足音も聞こえてきた。
舞台の上だ。
「せっかく私の最高傑作が、そろそろ誕生するというのに。そんな騒音で邪魔されるのは興醒めだ」
僕ら二人と舞台の上とはある程度の距離がある。それでも、射抜くように的確な視線が僕の目をぴったりと掴んで離さない。
「君はいつぞやの氷虎だね。好奇心は大切にしろと言ったが、他人の楽しみを邪魔していいとは言っていないなあ」
「ゲルン。子供から母親を奪っておいて、なんて言い草だ」
マルコは軽蔑するように言う。
「これはこれは、マルコといったか」
「なぜ僕の名を知っている」
「君は有名人だからね。魔術に携わる者で知らない者はいない」
ゲルンはマルコに頭を下げる。それこそ舞台上での挨拶として。
「その歳、わずか五つで魔法研究機関に所属し、人に役立つ魔術をいくつも考案してきた。まあ、大人でも習得するのに困難なものが多いことは玉に瑕らしいがね」
「お前の知ったことじゃない」
マルコは厳しく返答するけれど、ゲルンは意に介さない。
「私は君のように才能で評価される人間が嫌いでね。他人の好むものをたまたま作れるだけで、こうも贔屓されていいものかと虫唾が走るんだ」
口調こそ朗らかなものの、その表情、声の中に含まれる毒のような嫌悪感は、心が蝕まれるくらいに感じられる。
「だいたい人間ってやつはクソなんだ。皆平等、誰も差別されないなどと言っておいて、そのじつ、能力によって嫌らしく差をつけられる。それも高い能力を持つものを高く評価するだけじゃなく、低い能力のものを蔑視しだすんだからね!」
マルコはゲルンをじっと見つめている。少し歯噛みをしたようにも見えた。
「だからね、私は人間とはオサラバするんだよ。世界の果てから向こう側へ行く」
「どうやって行くというんだ。どうせ巨龍の角は越えられない」
「いいや、越えられるさ」
マルコの言葉を否定し、満面の笑みのゲルン。
「そもそも、巨龍の角にどんな生き物も入れないのは何故か。答えは簡単。土地に適合していないからだ。もともと彼の地は絶滅した龍族の棲家だった。であれば、龍族なら巨龍の角に入ることができる」
「でも、お前が言ったように龍は既に……」
マルコは言いながら、何かに気づいたように口をつぐんでしまう。
そして再び口を開くと、その声を苦々しさに満ちていた。
「ゲルン、お前は龍になるつもりか」
「ハハハハハハハハハハハハハハハ!」
壊れた機械のように笑うゲルン。僕は恐ろしくなったけれど、背後には眠った母さんがいることを思い出して、後退りはしなかった。
「そう、ご名答! いやあ、流石に察しがいいな! そういうところは好きだよ、うん!」
「絶滅した生物を蘇らせるのは、新しく生命を生み出すのと同種の禁忌だ。あまつさえ、その生物になろうというのか……」
「人間なんかでいるよりずっと良いよ! 龍は強い、強い生き物は子供の憧れだろう? ま、この素敵な機会を共有してやろうとは思わんがね!」
ゲルンはグフグフくぐもった笑いを漏らす。
「既に素材は整っている! 龍の生態情報、内骨格、多様な生物、そして君のお母さんだ」
嫌らしい笑み。
「なんで、なんで僕の母さんなんだ!」
「君のお母さんは氷虎の中でも類い稀なるエーテル親和性体質なんだ。エーテルの扱いにも卓越したものがあるはず。龍は人間以上に複雑な魔術を扱っていたようだからね。君のお母さんは素材にうってつけな訳さ。ありがたく使わせてもらうよ」
マルコの視線が数段鋭くなった。
「下衆が」
一瞬、マルコがどこに行ったのか見えなくなった。視線が追いついた時には既に空中でゲルンへと魔術を打ち込もうとしていた。
青白い光がマルコの指先に集まる。
「おっと」
ゲルンの立っていた場所に氷塊が落ちる。しかし、ゲルン自身には当たっていない。よく見ると、ゲルンの背中から何やら奇妙なものが生えている。
「翼、か」
それは巨大な白いコウモリの翼だった。グラシエールのコウモリは氷のエーテルに干渉され、白く大きいのが特徴だ。しかし、ゲルンの背中に生えている白い翼は自然のコウモリと比べてもあまりにも大きい。僕は研究所の通路に眠らされていた、部分的に肥大した体の生物を思い出した。
「さあて、そろそろ龍の再誕だ。生まれてすぐ私に体を乗っ取られてしまうんだから、少し、可哀想だがね」
そう言って、ゲルンは舞台上の装置についたバーを下ろした。すると、部屋の中全ての装置が明るく輝き始める。
「さて、私は時間稼ぎをしよう。龍が生まれるまで、のんびり命のやり取りだ」
ゲルンは言葉を終えると、白い翼で羽ばたき、勢いよく飛翔した。
6
白衣に白い翼を生やしたゲルンは狂気の笑みを浮かべながら空中に浮かぶマルコに飛びかかっていく。コウモリ特有の不規則な飛行軌道に、マルコの放つ氷の槍はなかなか命中しない。
「くっ……」
ゲルンの繰り出した飛びながらの回し蹴りを紙一重でかわすマルコ。氷の塊をそのまま当てるのは困難だと判断したのか、距離をとり別の魔術を唱え始める。
「おやおや、悠長に詠唱だなんて。させると思うかい?」
呆れたような物言いをしながら、ゲルンは指揮をするかのように手袋をはめた手をマルコの下へとかざす。すると、その場所にあった透明な容器の上部が開き、中から異形のワニが勢いよく飛び出した。その巨大な顎がマルコを噛み砕こうとしている。
そして、マルコが消えた。
「マルコ!」
僕は息を呑んだ。確かにマルコはワニの中へと消えた。信じたくない。子供とはいえマルコは強い魔法使いなんだ。負けるはずがない。どうか、何かの間違いであってほしい。
そのとき、部屋の天井付近が輝いた。それも一部ではなく、ほぼ全面と言っていい。
「凍りつけ!」
それは無数の氷のつぶてだった。まるで雹のような、魔術で引き起こす天気の変化。ここが屋外であると間違ってしまいそうな広い範囲の魔術にゲルンは驚きを隠せない。
可能な限り素早く翼を翻し、部屋の入り口へ逃げようとするゲルン。さながら宙を飛ぶ猪の突進のように見えたが、氷は数個、ゲルンの翼を傷つけ凍らせた。
安定した飛翔が困難になったゲルンは飛んできた速さをそのままに、床に転がり込んだ。
痛そうな声が聞こえる。
「クソ、確かにワニが喰らいついたはず……」
マルコは遠く、舞台の上からゲルンを見下ろす。
「広範囲の魔術には詠唱がつきものだ。けれど、詠唱時間を稼ぐために無詠唱の幻影魔術を組み合わせることは可能。発想があればどうとでもなる」
相手の言葉を聞き、不気味な笑い声を響かせるゲルン。
「発想? 発想ねえ……ならば私は発想の転換。勝利条件の変更を行おう」
ゲルンは何もできないでいた僕の方へと手を伸ばす。
気がついたマルコは咄嗟に魔術で僕を守ろうとしたのだろう、指輪をはめた手を伸ばし詠唱をした。
しかし、ゲルンの魔術はどうやら使い慣れたものだったらしい。即座に奇妙な色のエーテルの塊が僕の体を包み込んだ。
「アトラに何をしたんだ!」
「教えて欲しいか? いいだろう」
ゲルンは、くつくつと笑った。
「今かけた魔術は変質の魔術。周囲に存在するエーテルが徐々に体組織を組み換え、生き物を別の存在に変える。くわえて、私の手駒として使えるように調整もしておいた」
「なんてことを……」
「これで私は君を倒す必要がなくなった。その仔氷虎が異形になってしまえば、母親を助ける意義も薄いだろうし。時間は少しかかるが私は逃げ続ければ勝利することになる」
僕を包んだエーテルの塊はすぐに消えたけれど、体の中に奇妙な熱がある。それは悪い風邪のように熱く、寒かった。
「お前を絶対に許さない。必ず裁きを受けろ」
マルコは空中を飛び、ゲルンの元へと向かった。その静かな怒りは僕も恐ろしく思うほどだったけれど、それが心強くもあった。
ゲルンとマルコが戦う最中、魔術の音とは別にバチバチという音が聞こえてきた。僕はその音が気になって、重い体をどうにか動かして辺りを調べることにした。
音の出所はすぐに見つかった。装置の一つが故障していたんだ。とても頑丈な機械のはずなのに、なぜか煙を出し、容器の上部は口を開いている。
よく見ると、機械に接した部分の氷が溶け出して、水に濡れている。これは……。
(アトラ、大丈夫か?)
マルコから心を通じた言葉が届いた。イヤリングの効果だ。
(うん、平気だよ。それより、機械を壊す方法がわかったかもしれない)(本当か)
(機械はとても水に弱いみたいなんだ。魔法で水を作れないかな?)
(水か……。魔術でどうにかするのは難しい。この場にはほぼ氷のエーテルしかなくてね。水も氷を溶かすための炎も生み出すことができないんだ)
目の前で壊れている機械は床にめり込むように設置されているため、水が入り込んで壊れたようだ。でも、他の機械はほとんどが背の高い作りをしている。少しくらいの水ではどうにもならない。
(だが待てよ……そうか。僕に案がある)
僕はマルコから、その案を聞いた。
(わかった、やってみよう!)
マルコはゲルンから距離を取り、僕のそばへと飛んできた。発光する指輪をはめた指先で僕のイヤリングに触れる。
「なんだ、解呪でもするつもりか? 残念だが、それは呪いの類ではない。そいつは氷虎をやめるしかないんだよ!」
マルコは鼻で笑った。
「誰が解呪だと言った」
魔術は完成し、僕は足に力を込めた。立てる。そして、いつもより何倍も、いいや、何万倍もの力に満ちている。
元気の出た僕の代わりに、マルコが片膝をつく。僕は少し心配になったけれど、ここで僕が立ち止まってしまっては意味が無い。
僕は駆け出した。洞窟の出口へ。
二人の姿はすぐに見えなくなった。去り際、ゲルンが僕を嘲る声と、マルコの僕を信じる言葉が聞こえた気がする。
僕は風であり、音であり、光だった。速さだけでなく、耳も目も鋭くなっている。目的地まで、それほど距離はなかったけど、心も鋭くなっているのか色んな想いが堰を切ったように溢れてきた。
母さんは無事に助けられるだろうか。マルコは怪我をしていないだろうか。ゲルンに勝てたとして、僕は僕のままでいられるんだろうか。
もしかしたら、この戦いを境に、僕の生き方が変わってしまうかもしれない。今まで、日々氷に閉ざされた野山を駆け回り、魚や林檎を食べてきた、そういう当たり前の日々が。
恐ろしい。恐ろしい。けど、それでも、僕は母さんを助けなきゃいけない。
母さんだけじゃない。マルコも大事な友達だ。それに、龍が復活したらこの辺りの生態系だって変わってしまうかもしれない。そうしたら、氷虎の群れもただじゃ済まない。
僕が僕であること。それが当たり前だと思っていたけれど、もう当たり前とは言えなくなる。
それがなんだというんだろう。
僕は僕だ。
脚はしなやかに体を前へと運び、駆ける速さはどんどん上がっていく。僕は坂道を上り、目的の洞窟を見つけると速さを落とさないようにして暗がりに駆け込んだ。
内部はほのかに光っているけれど、どうせ一本道だと解っている。
そして辿り着く大空洞。
月明かり差し込む空間にある、幻の湖。その水を湛えた壁面に、僕はそのままの速さで激突した。
強化された僕の体と猛烈な勢いによって、願っていた通り、壁にひびが入った。僕はすかさず跳躍して月の見える岩山に開いた穴のへりに飛び上がった。
ズズズ……
幻の湖の壁は砂糖菓子のように崩れ、澄んだ水が洞窟の入り口の方へと殺到する。水はやがて氷と雪を含んだ急流となって、僕が駆け上がった坂を駆け下り、あまりにも速やかに、ゲルンの研究所へと飲み込まれていった。
そのとき、研究所のある岩山の一部が崩れ、穴が空いた。僕はそれを合図に、跳躍し、研究所へと引き返した。
僕が研究所へと戻ると、マルコがゲルンを捕らえていた。宙に浮かぶ水玉の檻だ。
「やあ、うまくいったね。水のエーテルも供給されて捕縛できたよ。凍らせてもらえる?」
「もちろん!」
僕はにんまり笑ってから氷の吐息を吐き、ゲルンを氷結させた。狩りの時も凍らせた魚は死なないので、多分ゲルンも大丈夫だろう。
視界に入っている無数の透明な容器には眠ったままの生き物たちが入っており、母さんも眠ったままだった。機械は既に全て故障して、上部の蓋は空いているけれど、容器自体が縦に長い円筒形をしているので、水に沈んではいなかった。
そのあと、水は流入の反動で流れ去り、床は濡れているものの行動するのに不便は無くなった。
驚いた顔で凍りついたゲルンと眠っている生き物たちは、マルコが通信道具で声掛けした人間たちが回収するらしい。
僕は母さんを起こして、リンゴが呼んできた群れの仲間と一緒に、岩山の洞穴へと帰ることにした。おじいさんも無事だった。
マルコには一度お別れを言い、お互いに今日は休もうということになった。
またね、と言った僕にマルコは笑いかけた。その笑顔はどこか曇っていて、僕がゲルンにかけられた魔法は、まだ僕の中に残っていることを再認識した。
7
グラシエールに珍しく暖気が入ってきているらしい。南からの風が強く、雪がとけ、みぞれが降ることもしばしばあった。
僕は母さんやリンゴ、群れの皆んなと最後の日々を過ごしていた。マルコによると、ゲルンのかけた魔法は本人が遠く隔離されてしまったため弱まっているものの、エーテルのある環境に居続けると、その影響を受け、徐々に体が変質してしまう状態にあるらしい。
実際、風邪のような寒さは続いていて、体がむず痒くなることも増えてきた。僕の体は、そう遠くないうちに異形になってしまう。
いっそのこと、遠い山の中に一人で暮らすことも考えた。でも、マルコは解決方法を提示してくれた。
その解決方法は、異世界に旅立つこと。
この世界ゼーバルには、どこへ行こうとエーテルが満ち溢れている。安心して暮らすにはエーテルの無い世界へ行くしかない。
異世界に関する研究はマルコの先輩がかなり確立しているらしい。マルコ自身も転送の魔術を使うことができるようだ。
しかし、それなりに大きな代償が伴う。転送の魔術には、転送先の世界に関する情報が必要で、それを手に入れるには莫大なお金を必要とする。貴重な情報だ、無理もない。でも、当たり前なことだけれど、僕はお金を持っていない。少しもない。
だから、今日はマルコと二人きりで朝焼けを見る約束をした。貯めていたお金の大半を使って、僕を助けようとしてくれるマルコ。そのマルコが言ったんだ。最後に僕と、朝焼けが見たいって。
まだ、日の出ていない暗闇の崖。東に向かい宙に足を投げ出して、マルコは僕のことを待っていた。
マルコは歌を歌っていた。それは、意味の分かる言葉ではなかったけれど、どこか懐かしく、爽やかな切なさに満ちた歌だった。
「それって、なんの歌?」
僕はマルコの隣に座った。ふわりと僕の頭は撫でられた。
「異世界の歌だよ。今回転送の魔術に使うやつだ」
「わあ、高い歌なんだね」
「ふふふ、そうだよ」
マルコは笑い終わると、まだ静かに歌い始めた。僕も真似して歌ってみたけど、あまり上手くはなかった。きっとマルコには歌の才能があるんだ。
しばらくして陽が昇った。とびきり綺麗な光が地平線からゆっくりと顔をのぞかせて、輝く線が放射状にいくつも見えた気がした。
僕らはその様子を黙って眺めていた。マルコの瞳は光を湛えていたから、僕の目もきっと煌めいていたんだと思う。
陽が昇りきると、マルコは言った。
「僕の旅行もそろそろ終わりだ。だから最後に、君の話を聞かせてよ。君が旅立ってしまう前に。昼までは少し、時間がある」
僕を転送するために自分のお金を使う。その代わり、夜明けを見ながら話が聞きたい。マルコは僕にそう言った。きっと、お金の代わりはなんでもよかったんだと思う。ただ、僕が心苦しくなく旅立てて、友達として対等な関係でいられる方法を探した結果なのだろう。
僕はグラシエールで経験した全ての思い出を、マルコに話した。僕だけじゃない。マルコも、自分のことを話してくれた。
僕らは十分に話して、話し合った。そして、辺りの雪が真白に輝く昼の時間までに、僕らは穏やかな沈黙に包まれていた。
「アトラ」
後ろから声がかかる。母さんだ。リンゴや群れの皆んなもいる。
「迎えに来たわ。旅立つあなたを祝福する宴をしましょう」
僕は頷いて崖から離れた。今日はマルコも一緒だ。
宴では皆んな楽しそうにしていたけど、お別れの時間が近づいてくると、やっぱり悲しさが辺りに漂い始めた。
僕はとにかく林檎を食べて、悲しさを紛らわせていた。でも、その様子を見て悲しくなるものもいたようだった。
母さんは僕を送り出すために、少し長めの話をした。実を言うと内容はそれほどあったわけじゃない。僕の旅の健康と幸福、そして楽しさを願ってくれた話であり、愛に満ちた言葉を詰め込んだ話だった。
「いい? 絶対に幸せで暮らすのよ。あなたが正しいと思ったことをするの」
「うん、わかった」
何度も聞いた言葉。それが重なって温かさになる。
僕は皆んなに挨拶し、マルコの用意してくれた舞台の上に上がる。周りには雪の上にいくつもの模様が描かれていて、これが全て、僕を送り出してくれる力になるんだ。
「もういいのかい?」
僕が頷こうとすると、リンゴが、達者でな、と大きな声を上げる。僕は笑って手を振った。
「転送先ではなるべく友好的に振る舞うんだ。決して争おうとしてはいけないよ」
「うん」
「じゃあ、いくよ」
「マルコ」
「なんだい?」
「ありがとう」
優しい笑みのあと、ついに、マルコが詠唱を始めた。長い、長い詠唱。音がいくつも交差し、掛け合わされ、いつしか、あの歌が聞こえ始める。
光る模様と図形、それが空中にも干渉し、やがて僕の体を包み込んだ。
天空に渦状の雲が現れ、大気が逆巻き、僕の体が持ち上がる。
そして、瞬間。消えた。
____________________
「行っちゃったな……」
リンゴの声が寂しそうに漂う。
ポツリ、ポツリ
アトラが消えていった天空の雲から、水滴が落ちてきた。
雨だ。
春の雨は他の地域では珍しくもないが、グラシエールでは百年に一度あるかないかの珍しい現象に違いなかった。
氷虎の群れも、マルコも、突然の雨だったが、その雨の優しさゆえに逃げることはなかった。
しばらく雨は降り続き、半刻ほどで止んだ。
雲はいつのまにか消えてしまい、元通りの陽の光が雪原に降り注いだ。
マルコが空を見ていると、不思議な色彩の虹がかかっていた。その虹はしばらく残り続けた。まるで、旅立ったアトラの代わりであるかのように。
____________________
雪が降った日
関東で雪がこんなにも降ることは珍しい。一月の終わり。道路や公園の積雪は一メートルを優に超えていて、注意しないと子供がどこに行ったが分からなくなる程度のものだった。
私は、こっそりとわくわくしていた。大人になっても、それこそおばさんと呼ばれる年齢になっても、雪が降ると故郷の北国を思い出して、家を飛び出したくなるのだ。
北国の思い出にはもちろん苦しかったと思うものもある。雪に苦しめられた記憶も、多分にある。
でも、雪は原初的な童心を掘り起こす性質を持っているらしい。私は手早く防寒着に身を包んで、家人が眠る家を飛び出した。
雪にはしゃぐおばさんを見て、警察はどう感じるだろうか。家人に連絡でもするだろうか。雪の日の散歩などで騒ぎになってしまっては敵わない。私は常人だ。少なくともそう見えるように振舞おう。
最寄駅には暖かい紅茶を出す店もある。雪の積もった今日、その店がやっているかはわからないけれど、少なくとも営業開始時間は早かったはず。
駅までの道の途中には広い公園もある。除雪はされていないだろうけれど、むしろ新雪の広がる景色を見たい。
そう思って公園に来たのだが。
周りに誰もいない公園。その入り口近くの雪の中に青い何かが埋まっているのが見えた。美しく鮮やかな青色。
なんだろう。やけにふわふわとしているが……。
少し様子を伺って気がついた。子供の形をしている。
私は慌ててその子供を抱き起こした。ひやりと冷たいが、芯に体温を感じる気がする。冷たい耳を近づけると、確かに呼吸をしているようだ。
迷う、警察に連れていくか病院に連れていくか。
とりあえず、顔を確認するために、青いふわふわしたフードを脱がせてみよう。そう思ったのだが、はた、と気がついた。これはフードではない。
額に六つの菱形、頬に模様、鼻は動物のように突き出している。これは、いわゆる獣人の子供なのだろうか。
初めて見た、なんて日なのだろう。雪が降り、白く染まった街の中で、青い獣人の子供を拾った。
何はともあれ生命だ。助けなければならない。
私は自宅へと走った。家人を説得して、なんとか、この命を救うんだ。
・・・・・・・・・・
アトラはすぐに体調を取り戻した。人間の幼児の服も尻尾穴を開けてやるだけで着られるので、とりあえずの生活に問題はなかった。
調べてみると獣人は世の中に、少ないながら存在しているようで、学校へ通う例もあるらしい。
ただ、その場合日本では苗字が必要になる。
アトラは先程から心配そうに私を見つめている。幼稚園へ提出する書類にアトラの名前を書かなければならないからだ。今までは戸籍上、私の苗字を仮に与えていたが、これからはアトラの人生。自分の苗字がないと不便だろう。
「アトラ、どんな名前がいい?」
「うーん、わからないよ。かっこいいやつ?」
「そうかあ……」
アトラが話したゼーバルという世界の風景。氷に閉ざされた、それでいて美しい野山の景色……。
「氷の野と峰。氷野峰というのはどうだろう」
「ヒノミネ? かっこいいかも」
「じゃあ今日から君は氷野峰くんだね」
「うん!」
アトラという名前も亜と虎で獣人としてはぴったりな名前に思える。どちらかというとアトラは「亜」の次点というイメージよりも「阿」のおもねるイメージの方が強いが……。
いずれにしても、この子の未来が絶対に幸福で満ちていますように。
4,あとがき
いかがだったでしょうか。私小説のような話ではありましたが、作者がどんな人物か、なぜ現在に至るのか、少しお分かりいただけたかと思います。
今後もnoteで小説作品を投稿していこうと思っていますので、見かけた際は文章を開き、世界に飛び込んでいただけたら嬉しいです。
それでは、また。氷野峰アトラでした!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
