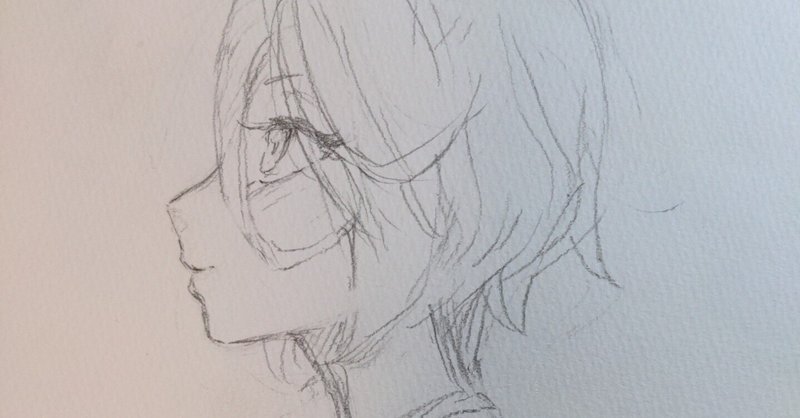
絵の個性と流行り
漫画家を目指していたときの完成しなかった原稿を見ていました。
当時の俺は「うひょ〜かわいい〜」と思って描いていた顔が、今見ると「ぶっさ…」となってしまう出来でした。
なぜこうなるのか?そして、どうやって克服していったのか。つらつら語っていてます。
まず、一次創作の場合、程度の差はあれど私は大体独りよがりで、客観性のないキャラクタデザインをしてしまいます。「これがかわいいんじゃ!」と今の基準からだと目の小さいキャラを作ってしまったり、妙にリアルな等身の絵柄にしたり、今思うと痛え〜っす。
時が経ち、二次創作をしてよかったーと思ったことは、「大衆から受け入れられるカワイイ遺伝子」を自然に絵に取り込むことができたことです。
まず描く上で「癖」を出すと「似ない」です。もちろん絵柄の程度はありますが、同一人物に見えない、という問題が発生します。そこで、要らない線を削る。(例えば鼻の穴を、描かない。余計な線を減らす。顎を削る。など…)
↑こうして考えると、うまくなる過程は自分が良いと思ってた(思い込んでいた)特徴を消していくものでした。
自分は絵を料理に例えるのが好きなのですが、この過程は臭み消しだなぁ〜と思いました。「見る人を選ぶ表現」は「ある種のゲテモノ」と言えます。(ゲテモノを好む方もいるので、ブランディング次第だと思いまス)
美大で熟成発酵した私の表現欲は、人様に見せる前に臭み消しが必要だったんですね〜という悲しみ。ですが、二次創作でそれに気づくことができて良かったです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
