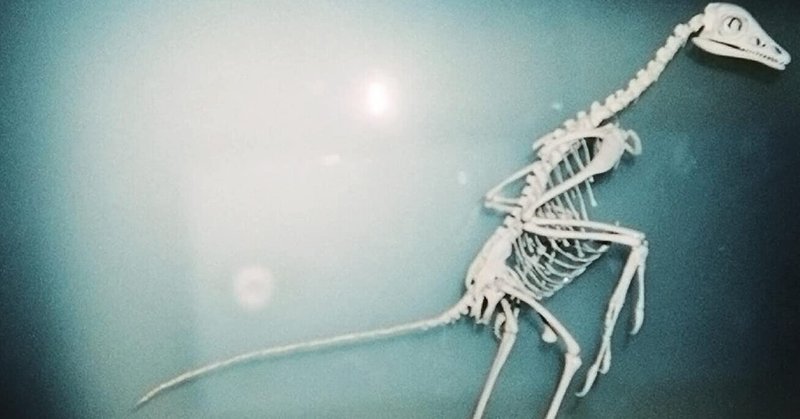
【告知】「擬人化する人間」連載6回目
久々の投稿が告知文ですが、雑誌「小説トリッパー 2021年冬号」にて「擬人化する人間 脱人間主義的文学プログラム」第6回目が掲載されました。
内容は前回に引き続き平野啓一郎論です。
平野文学が書いてきた分人主義の本質とは何かを論じていきました。
多分、この連載の意図がよくわかられていないと思うので、ここで書くと、僕がこの連載で書こうと思っているのは、この先の人間のゆくえと可能性としての文学です。
そもそも僕が最初に寄稿した論文は限界研という現代文化を研究する会が出した『ポスト・ヒューマニティーズ 伊藤計劃以後のSF』という論集で書いた「円城塔論」でした。
本書はゼロ年代以降を象徴する作家「伊藤計劃」の死後、日本SFはどのようなものを描いてきたのか、という主題のもと「日本的ポストヒューマン」(=水平的・キャラクター的なポストヒューマン像)という概念を打ち出したものでした。まだ日本にポストヒューマン論が広まる前に、SFという文学からそれを考えていった画期的な論集だったと思います。
(当時はその言葉は広まらず、それよりも「伊藤計劃以後」と括ったことが炎上していたのが懐かしい思い出です。)
そんな伊藤計劃以後のSF作家として「円城塔」を取り上げて、その特徴を述べたものになっていました。正直十年ぐらい前のものなので、稚拙で読み返すのも恥ずかしいのですが。
ただ稚拙でも僕が円城塔を論じた理由は、彼の文学が自分の実存と繋がっていると思ったからです。
僕はすでに幼いころからテクノロジーに囲まれて過ごした世代で、小学生の頃には携帯を、また中学の頃にはPCに触れて文章を書いたり、ネットで動画を見たりしていました。(YouTubeがまだ英語ばかりの時です。)
そんな中、「機械的なもの」がある種の自分自身のアナロジーとして感じることが多く、自分と機械が同じようになってしまったような感覚がありました。だからこそ、自分の「自我」のようなものがあまり感じられず、世界はすべて分析されるべき対象であり、いわばデカルト二元論を「方法として使う」のではなく、「生きている」という感覚があったのです。
そんな実存感覚と等式に「記述する機械としての『私』」を描いていたのが円城塔であり、そこに自分自身を見ていたのでしょう。だからこそ、この『ポストヒューマニティーズ』では円城塔という作家を論じたのでした。
しかしそんな実存感覚は現在多くの人が感じるところになっているのではないか。そんな問題を現在感じました。
テクノロジーやネットは今や僕たちの生活に欠かすことのできないものになっています。しかし、それらは「個人」というものを解体し始めているのではないか、と思うのです。
非常に卑近で分かりやすい例でいうならば、今はスマホで撮った写真画像編集は手軽にできます。自撮りをしても加工をする、また自動的に加工される。それを保存したりネット上でアップしたりするわけですが、それは果たして誰なのか。化粧と同じと言われればそれまでですが、それ以上に自分自身の容姿を一転させることなど簡単です。テクノロジーは「私」という存在を可塑的にしていく。
またネットでの書き込みもそうでしょう。匿名性が高くなったことも、自己と言葉が離れる要因でもあり、また実名であってもそれを加工する意識は強くなる。
そもそも書くこと自体が自己を分裂させる行為と言えます。例えば安藤宏は『「私」をつくるーー近代小説の試み』という本では、近代以降の小説を分析しているのですが、小説の一人称は「演じられた私」であり、そもそも描く私とはイコールにならないと述べています。つまり、近代小説で書かれる「私」自分自身を加工しているということです。
書き言葉全盛期の今日、そんな自己解体は日常茶飯事に行われていて、それが意識的にせよ無意識的にせよ、人々を混乱に陥れている可能性があります。
他にも「近代的主体」の幻想を破壊するような言説は学術界でも頻繁に出されており、そもそも「人間」という枠組みをもう一度考えなければいけなくなっているのではないか、というのが本連載「擬人化する人間」の連載意図になります。
「擬人化する人間」の擬人化は人間以外のものを人間として扱うことです。それを人間に扱うこと。この語義矛盾性こそ、現代で起こっていることなのではないかと思っています。
だからこそ、僕が行っていることはかつて文学や哲学が長いこと考えてきた「私とは何か」という問題を考えることと同義なのですが、そこで扱う「私」は「解体された『私』」=「『私』がない『私』」であるため、いささか厄介なものなのですが。
今回、平野啓一郎という作家を扱ったのは、そんな「個人」の解体感覚を小説内で扱っていると思ったからです。具体的な内容は是非論考を読んでほしいのですが(作品を通して、緻密に考察しています)、「分人主義」も、その後の作品で書かれる救済としての物語も、この「解体」というのがキーワードになっています。
そして次号以降はそんな「解体された自己」=「『私』のない『私』」をどうすればいいのか、を考えていきたいと思っています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
