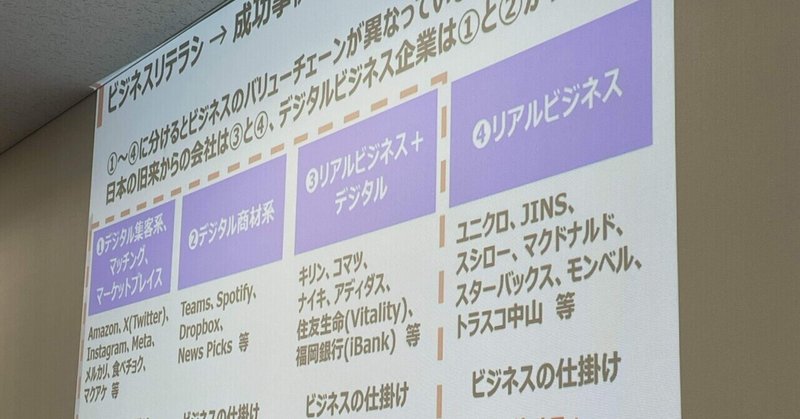
デジタルの世界では「プロダクトアウト」は辛く、「まずコンテンツで興味ある人を集め、複数のプロダクトやサービスを投入する方が有利」な件
はじめに
筆者は生命保険会社のCDOとして、社内のデジタル戦略や執行支援をする傍ら、顧問先やパートナー企業のDX支援、自治体向けのビジネス発想支援や官公庁のDX推進委員を務めており、日本全体のDX推進や人材育成のあり方を考える活動に携わっている。
その関係でJTC(日本の伝統的大企業)のデジタルビジネスに不慣れな新規事業部門の人たちから相談を受けるが、彼らは「自分で作れそうなもの」をデジタルで販売しようとする。しかしそれではマーケティングコストばかりかかる割には売れないし、コスト負けして辛い状態になることが多い。これでは新規事業部門は閉じられてしまう懸念がある。
先日、デジタルプラットフォームでプロダクトやコンサルティングを大量に販売し日本のデジタルコンテンツビジネスに貢献している著名なYouTuberのA氏とご飯を食べる機会があった。A氏もコンテンツビジネスについて同じことを言っていたので今回はこれをテーマにしたい。
プロダクトアウトの特性
プロダクトアウトはよっぽど旬で誰でも欲しいと思うプロダクトやサービスでないとダメだ。例えば今のデジタルの世界でいえば
「個人事業主向けに生成AIやその便利ツールを使ったマーケティングやコスト削減」
の文脈が良い。個人事業主は常に人手不足で手が回らない。またいろいろ外部委託コストがかかって困っている人が多いので、個人事業主層はこの文脈だと欲しがる。だからAIツールは売れる。これは旬だからプロダクトアウトでも良いケースだ。
一般にプロダクトアウトは買い手が多くプロダクトが少ない場合は有効だ。日本の家電製品、インターネット幕開け時代のPC、MicrosoftのOSなど昔はそうだった。しかし今はプロダクトが溢れている上に消費者の好みが多様化しているのでプロダクトアウトは難しい。
さらに、プロダクトアウト型のビジネスモデルでは、市場調査や製品開発に多額の資金が必要となる。失敗のリスクも高く、一旦失敗すると立て直しが困難だ。特にデジタル領域では、技術の進歩が速く、市場の変化も激しいため、プロダクトアウトでは対応が遅れがちになる。だからクラウドファンディング(試験販売ができる)が人気になる。
デジタル時代の有効なアプローチ
ではどうするべきか。これは先に消費者を集めてグループを作り、コンテンツやセミナーなどでニーズを把握しそこに合うプロダクトやサービスを作って投入する方が有利だ。プロダクトやサービスを内製できないなら外から持ってくるのでも良いしホワイトレーベルでも良い。要はデジタルの世界ではプロダクト→客ではなく、コンテンツ→客→プロダクトの順番だ。
このアプローチの優れた点は、顧客との関係構築に重点を置いていることだ。コンテンツを通じて顧客とのコミュニケーションを深め、信頼関係を築いていく。そうすることで、顧客のニーズや悩みを深く理解することができ、それに合ったプロダクトやサービスを提供しやすくなる。
コンテンツは自社の専門性やノウハウを示す格好の手段でもある。消費者や顧客が何を望むのかの調査にも使える。高品質なコンテンツを発信することで、自社の強みをアピールし、ブランディングにも役立てることができる。顧客にとって有益な情報を提供し続けることで、自社が頼れるパートナーとしての存在感を高めていくことが可能だ。
JTCの課題
JTCの新規ビジネス担当はこれが分かっていない人が多い。先にCVC(企業ファンド)を立ち上げてプロダクトやサービススタートアップに出資するからその使い道に困る。まずコンテンツで客を掴む。これにはsnsやnoteなどのデジタルプラットフォームが有効だ。だからJTCの社員は自分でコンテンツを作れるようにする必要がある。
JTCがデジタル時代に適応するためには、社員のスキルセットを変革していく必要がある。特にコンテンツ作成力は重要だ。自社の強みや専門性を活かしたコンテンツを発信し、顧客との接点を増やしていくことが求められる。
多くのJTCでは、こうしたスキルを持つ人材が不足している。デジタルネイティブ世代の採用や、既存社員のリスキリングが急務だ。社内でのコンテンツ作成を推進するための体制づくりや、インセンティブ設計なども必要になるだろう。
経営層がデジタル時代のビジネスモデルを理解し、コンテンツファーストへの転換を主導していくことも重要だ。短期的な売上を追うのではなく、顧客との長期的な関係構築を目指す姿勢が求められる。
コンテンツ→客→プロダクトの実践
これを実践する上では、まず、対象とする顧客層を明確にし、そのニーズや関心事を深く理解することが重要だ。単なる自社の宣伝にならないよう、顧客にとって価値のあるコンテンツを提供し続けることが求められる。
コンテンツの質を高めるために、専門性やオリジナリティを追求することも大切だ。他社との差別化を図り、顧客から選ばれるコンテンツを目指す。コンテンツの発信だけでなく、顧客とのコミュニケーションにも力を入れる必要がある。コメントやメッセージに丁寧に対応し、顧客の声に耳を傾ける姿勢が求められる。
まとめ
デジタル時代においては、プロダクトアウト型のビジネスモデルは非常に厳しい状況にある。消費者の嗜好が多様化し、プロダクトが溢れている現在、まずはコンテンツを通じて興味ある人々を集め、そこから得られるニーズに合わせてプロダクトやサービスを投入するアプローチが有効だ。
JTCは、この点を理解せずに、プロダクトファーストの発想で新規ビジネスに取り組もうとするため、苦戦を強いられているケースが多い。今後は、社員自らがコンテンツを作れるようになり、デジタルプラットフォームを活用して顧客とのつながりを強化することが重要になってくるだろう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
