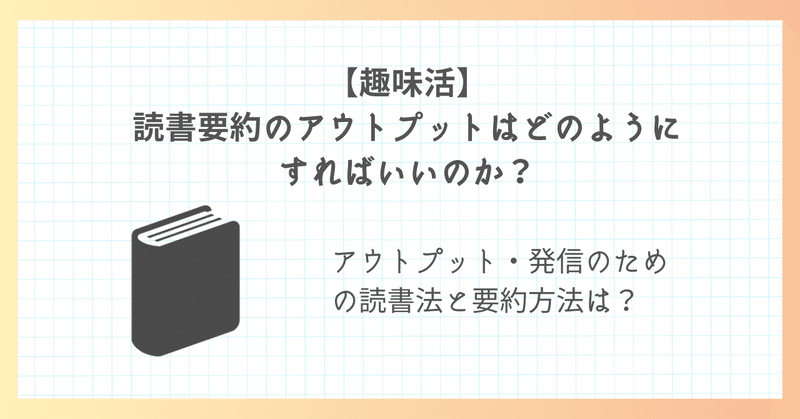
【趣味活】読書要約のアウトプットはどのようにすればいいのか?
こんにちは、けいごです。
以前、あんぱんだ | 視える化推進エンジニアさんのnoteページにてアウトプットの方法がわかりやすく書かれていたので、参考に記事を書いていきます。
本記事では、「読書要約の仕方がわからない」、「何に焦点を置いて読書をして、記事にしているのか知りたい」という方に向けて書いています。
アウトプットのやり方
個人的に実践している読書要約のやり方には以下があります。
・「書きたい」を好きなように書く
・読みながらアウトプットしてしまう
「書きたい」を好きなように書く
アンパンダさんが紹介されていたアウトプット方法は、まず「書きたい」ことを書くことで、「書けない」という壁を壊す方法が紹介されていました。
私もよく「書けない」という状況が発生するので、共感できる内容です。読書要約が目的なら、「まずは書きたいように書いてしまう」ということを意識します。
読みながらアウトプットしてしまう
荒技ですが、慣れてくると本によっては、これができるようになります。因みに私は最近はずっとこれです笑
本を開くと同時に、noteに直接書いてしまいます。本に書いている文をそのまま使う時もありますし、噛み砕いて変換することもあります。
読む時のコツを掴み、繰り返し実践していれば要点だけを抽出しながら読み進め、まとめるかことができます。
要約のための読書のコツ
今でこそ、スラスラと要約できるようになってきました。しかし、こうなるまでは本の読み方もよくわからないし、当然まとめ方なんて更にわからないわけです。
これについては、地道な蓄積によって、スラスラと出来るようになっていっただけだと考えます。※今もまだまだですが、過去の記事を見ると酷いと感じます笑
安心してください、向いていないことでも「誰でも継続すれば人並み以上」にはなります。問題は、継続してやってるかやってないかです、、、とか偉そうなことを言っている私ですが、統計学とか数学の本は難しくて読めません笑 要約しきれなかった統計学の本は、そのうち投稿します。
しかしながら皆様には近道をしていただくために、私が現在どのような思考回路で読書をしているのかをまとめていきます。ビジネス書やサイエンス、テクノロジー系など、小説以外の本の読み方になりますが、小説でも工夫すれば出来ます。
①幹を固める
②枝を確認する
③葉を集める
イメージとしては、本を「一本の木」と考えると良いです。
①幹を固める
まず、本を読むときに前書きと後書きから読みます。前書きと後書きには「軸」がまとまっているからです。そのため、これらを先に読んでおくことで、「後にどのように情報を集めれば良いか」が明確になっていきます。
イメージとしては、「木の幹の部分」です。幹がしっかり固まっていれば、枝も明確になります。
中には、軸がわかりやすくまとまってる本もあります。しかし、それがない本がたまにあります。では、そういった本の「軸」はどのように見つけるかというと、以下にまとめます。
・繰り返される単語を見つける
・繰り返される単語を辿って「断言」を見つける
本の前書きと後書きの中に、繰り返される単語があったりします。それは、その本のキーワードです。そのキーワードを辿っていくと、断言しているところが見つかると思います。それは、その本の「軸」です。断言が複数ある場合は、「それらを掛け合わせて要点をまとめる」か、「より重要そうなものを抽出する」か、「前書きと後書きで共通しているものだけ抽出」します。
②枝を確認する
前書きと後書きからその本の「軸」が見えたら、本の中からその軸にそった情報を集めていきます。これは、「木の枝」の部分です。
ここで大事なのは、「目次」です。目次を読んで、繋がりそうなポイントを抽出します。しかしわかります、、、繋がりそうなポイントがわからないんですよね笑
これは、繰り返すしかないというか、感覚的な部分が大きく影響します。そのため、最初は色んな本を読んで感覚を磨いていく必要はあります。
しかし、それでは記事を書く意味がなくなってしまうため、現状で言語化出来るコツを紹介します。
【2W1H】
・「軸」に対しての「なぜ?(Why)」が解明できる目次
・論じているテーマが「何なのか?(What)」がわかる目次
・論じている問題に対して「どうする?(How)」がわかる目次
【その他ポイント】
・本のタイトルと同じ単語(又は類似した単語)が書いてある目次
・本の帯に入っている文章や単語が書いてある目次
【更に深掘りするなら】
・状況がわかる目次(When、Who、Where)
まず、①で定めた「軸」の証拠を探します。
例えば、もし仮に「歴史を知ることで、今後自分の身の回りにある問題を解決することが出来るようになる」という「軸」の本があったとしたら、「それは何故なのか?」を知らなければ、説得力がありません。
そのため、その証拠をどこかから探します。証拠を見つけたら、「何をどう解決するのか?」を明確にしていきます。
そして更に深掘りしたいなら、「状況がわかる目次」を探していきます。それは、物事が解決されるための条件を知るために役立ちます。
③葉を集める
目次で枝を見たら、今度はその中身を探っていきます。これは、枝についている「葉」を集める作業になります。
ここで、やっと本格的に本の中身に入ることになります。ここからは、具体的な深掘りが可能になります。
文書を集める際に意識することは、以下です。
・本のタイトルや、目次と同じ単語(又は類似した単語)が書いてある文章を探す
・繰り返されている単語を探す
・「軸」と繋がる文章を探す
関連する文章を探すには、タイトルや目次と同じ単語や文章を探していくことが効率的です。また、タイトルや目次に含まれていなくても、一つの目次内や本全体で、「繰り返されている単語なども探っていくこと」が、本を読むコツになります。
また「軸」と繋がる文書を探すと、読みやすくなります。
木の模様はそれぞれ違いながらも、その種類ごとの一定の規則に従って表面に表れています。繰り返された単語は木の模様のようなもので、幹である「軸」に繋がっていきます。
他のアウトプットに応用する
この読書要約方法ですが、他のアウトプットに応用が出来ます。
例えば、映画要約です。一本の映画をこの読書要約と同じ流れで進めていくと、映画のあらすじなどをまとめられるようになります。しかしながら読書と違い、自分のペースで物語を進められない点や、結論が最後までわからないため、その点を考慮してみる必要があります。
とはいっても、「敵を倒すための物語」とか「時間を解決する物語」とか、「自分の生き方を見つける物語」とか、「物語の軸」は序盤の方に把握できます。そのため、軸を把握できれば、物語の進行から情報を集めていくだけなので、本と同じなのかもしれません。
この記事の軸は?
因みにもうお気づきの方もいると思いますが、この記事の軸は一体何でしょうか? 結構わかりやすく書いたつもりです、、、わかりにくかったらご遠慮なくコメント欄にて教えてください!
是非本記事を練習台に使っていただいて、コメント欄などに2〜3文程度で投稿してみてください! 楽しみにお待ちしています!
また、読書要約をされている方で、「これ以外にもコツがあるよ〜」という方も是非コメント欄で教えてください!
Keigo.log サイトマップ
この記事を気に入った読者様、是非フォローと拡散宜しくお願い致します!
ご一読有難う御座いました! もし「ここがわかりやすい」「ここがわかりにくい」などありましたら、ご遠慮なくコメント欄にご投稿ください!
