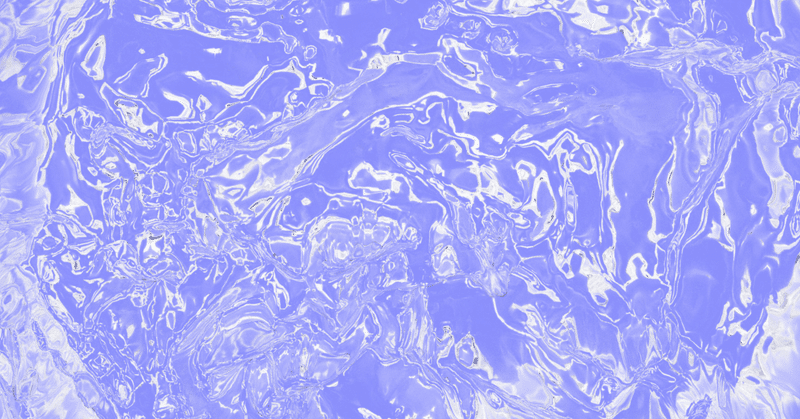
「海のたね」(短いお話)
生まれた場所は、それは小さな島だった。
自然は豊かで、花や蝶の彩は、鳥や魚にも写し込み、そこへ差し込む光さえ様々に様子を変える。うつくしい島。わたしの故郷。
そこにわたしが居られなくなったのは突然だった。
ある夕暮、これからを誓い合ったひとと浜辺を歩いていた。
可愛らしい子供たちが笑いながら手を振った。振り返すわたしに、そのひとは静かにこれからのことを話していたのだった。
子供が群れて家路に走り出す時だった。
わたしの身体は突如大きくなりはじめ、それは目の前のひとの瞳に黒く恐怖として映し出されていた。ずん、と体重が増す。着ていた衣服は散り散りに空を舞っていき、すぐに夕暮に染まった。あっというまに島を傾けるほどに大きくなったわたしに、村の人間たちも森を飛びだしてきた。さっきまで笑顔で手を振ってくれていた子供たちも、化け物を見る目でわたしをみあげている。いや、かれらの眼ではわたしの表情を判別することなど出来なかっただろう。それほどわたしは大きくなっていた。
涙は自然と零れ、下のほうでやいのやいの騒いでいるひとたちの上に、または森の樹々の上へと落ちていった。
ああ、ここにはいられないのだ。
ただそれだけは私の脳裏にしっかりと刻印された。
夕陽を背にしたときの陰ほども深く、黒く、焼かれた文字だった。
わたしは思わず故郷の浜辺を思い切り蹴散らし、出来る限り遠くへとこの体を沈めることしかできなかった。
そこから私は泳いだ。時折、少しばかりの砂浜を見つけては腕を預け、浅瀬に頬を埋めて休んだ。夜は暗闇ではなく、幾億の星たちのお祭りだった。毎日のように、運命を狂わせている祭りのようだった。
私は昼の間はできる限り泳いだ。まわりの島に大きく波が立たない様に、そうっとそうっと泳いだ。息継ぎに空を見上げる一瞬、わたしはあのひとのことを想った。あれから数日しか経っていないように思うのに、どうしてなのか、人々の顔は朧に溶けていっていた。わたしを見上げて恐怖に足を震わせていたあのひとの、黒い瞳。これだけを覚えていられたらと思うけれど、恐らくそうはいかないのだろうと、わたしは分かっていた。
長く泳いだ。島々は時折現われ、わたしに休息を与えた。いくつかの大きな島には体を上げることもしてみた。しかし、腰を浅瀬に座らせるだけで、足はどうしても海の深い色に溶けこみ持ち上げることはできなかった。
やがて、そのときは来た。
私は泳ぐのを止め、そっと上を向いた。明るい太陽は沈み始めていて、黄色味と白が不思議な味わいに混ざり合っていた。空は青く、遠くのどこかをわたしに降り注ぐようだった。
ああ、これがわたしの旅の終りだ。
そう感じた瞬間、わたしの長かった髪の毛は背中や尻を支えるように硬化し、または穴をもつ石に姿を変じた。わたしの両腕は砂浜へ。今まで海を泳いだ分細わやな砂が流れた。ひとつ、そっと息を吐きだすと、その凹みにいは真水が湧いた。ゆっくりと苔のようなものが腹のあたりを覆いだし、剥き出しの乳房を様々な虫や鳥が食べにやってきた。それは少しも痛みのない、まるで愛くるしいいきものを抱きしめているような感覚だった。それらが置いて行ってくれた種が、その内植物を私へ繁らせ始めるのだろう。目は、ゆっくりと眼孔を落ちていき、留まったところでくるりくるりと回った。剥きだしになった眼孔に、夕暮れと宵の闇が垂れて落ちてくる。わたしの唇は僅かに開いたまま、時折通り過ぎる風が歯をすぎる時に音を立てた。
足は、暗い海の色に染まり切り、ぼろりと落ちていった。深海に生きるものの糧の一つとなるのだろう。
わたしの抉れた胸は虫や植物の種のお陰でよい土に変わり、臍には小さな沼が出来た。もう顔の役目の果たされない顔も、小さな生き物たちの力ですべてを良き方へと整えられていくのが分かった。
ああ、わたしは島になったのだ。まだ若い、そしてわりと大きな。
そしてここには、いろんな生物が生き、そして歌声を奏で、樹々はその特性を香らせるだろう。
わたしはどこまでも満足していた。この島をこれからどうされていっても、構わないと思った。わたしの命は隅々まで、この島を作り上げた生物と、そして浮かべる海に、見守る空と月と太陽に、天体に、感謝をささげていた。
いつか、ああ、あのひとの子孫が、この地を踏みにくればいいのに。
そう思って、私の意識は静かになった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

