
選択の間を気にすべき場面【麻雀】★★★
今、選択の間に関する原稿を書いている。
その中から少し。
麻雀は総合力といつしか書いた。
牌効率や押し引きを含め、あらゆる要素をマルチタスクでこなしていく必要がある。
間の大切さは時として牌効率や押し引きを超える
その中でも「打牌選択の間」はそこそこの比重になる。
この記事(無料です)に、宣言牌に長考したリーチに対し、松本プロがガン攻めしてトップを取りきった局面を取り上げた。
もちろん、間があった(長考した)からといって、愚形待ちとは限らない。
役アリ好形・高打点で迷ったのかもしれないし、どちらの好形で待つかを考えていたのかもしれない。
難しい局面はしっかり考えるべきだ。
ただ松本プロの例のように、押すかどうか微妙な局面(損益分岐点前後の場面)で「間があった」ことを理由に押し切られてしまうことは往々にしてある。
その場面の「間」の重要性は牌効率や押し引きを超える。
なんとも人間同士の駆け引きゲームっぽくて、泥臭いではないか。
今日は「相手の「間」を読み切って押し切ろう!」という話ではなく、「こういう時こそ「間」に気を遣って、情報漏えいを防ごう!」という主旨で書いていく。
======================
イーシャンテンでの準備
牌図①

こういうイーシャンテンのとき、あらかじめツモを想定し、なるべく間を作らないようにする。
カン7mが入ったら誰もがリーチを打つ。
だから、リャンメンをツモったときから考えていくのがいい。
ツモ2mはリーチか。
手変わりが少なく、そのどれも打点上昇に乏しい。
ではツモ5mはどうする?

こうなると少し話は変わってくる。
4巡目なら打8mという選択も有力だ。
ツモ245m68sでリャンメンになり、裏目のツモ7mでもフリテン3面張リーチが打てる。
ツモ8pでノベタン、ツモ36mのシャボやツモ1mのカン2mも、カン7mよりはマシだろう。
選択の優劣ではなく、考えておくことが大事なのだ。
すると「迷った上でカン7mリーチを打つ」「迷った上で1巡回してカン7mリーチを打つ」という最悪ルートを避けられる。
また、考えておくことはその瞬間だけでなく、長期的な雀力向上にも役に立つ。
ツモってから考えている人は、1つの場面で1つのツモからしかインプット・アウトプットできない。
しかし、常にあらゆるツモを想定している人は、1つの場面で何倍もの成長を遂げる。
余裕がある人は「ドラが◯だったら?」「もう3巡遅かったら?」と場面をずらして考える。
ツモってから考える人とあらかじめ準備している人で、成長に差がつくのは当たり前といえる。
絶好のツモにも注意
ではツモ7mときたらどうか。

どうかも何も意気揚々とリーチするよりない。
ここで気をつけてほしいのは、必要以上にノータイムでリーチを打たないことだ。
特に普段うんうん悩む人ほど気をつけるべきである。
寿人プロなんかは常にノータイムなのでこれもノータイムで構わない。
ようは、愚形のときも好形のときも、打牌の間を揃えることが大事。
「迷いは傷にならないけど、ノータイムは傷になる」
と言う人もいるくらい。
(誰が言っていたか忘れた)
(ノータイムということは好形の可能性が高い…ということは筋が通る!)
という方向で利用されてしまうのだ。
宣言牌周りの待ちは準備しておく
この記事で
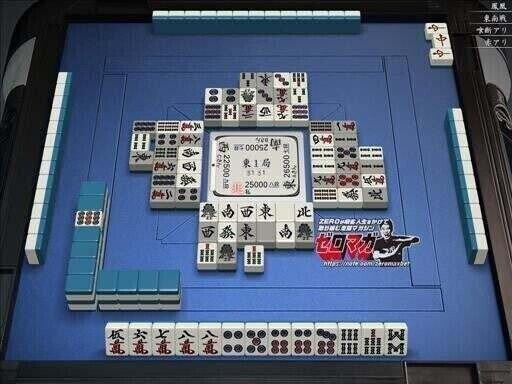
ゆうせーさんのモロヒリーチに飛び込んだことを語った。
これ、宣言牌の4sがあまりにノータイムだったことが7sは通りそうだなと思った決まり手になった。
7sは2枚切れているのに、そっちで受けるなんて、あらかじめ考えておかないとできない。
うんうん迷ってのリーチだと、宣言牌周りの待ちが警戒され、当然7sもその警戒の域に入るだろう。
フーロ時も大事
牌図②

タンヤオ1000点のテンパイ。
こんな仕掛けしねーよ、という人も一応考えておいてほしい。
トイトイに受けるのが基本だけど、3900にしかならないんだよなー。
しかも4と4のシャボなんて最悪やんかー。
よし、ここは4pを切ろう。
あれ、手出しとツモ切りどっちがいいのだろう。
…と、迷うのは分かる。
でも、3副露しているほとんどの場面において「迷うことが悪手」なのだ。
3pを切っても4pを切っても手出しでもツモ切りでもなんでもいい。
とにかく、先に考えておこう。
3フーロした時の有効牌なんて限られている。
牌図②なら34pの縦と4m暗刻の3種類を考えておくだけだ。
フーロ時のテンパイは「25pが出たらロンという」という自動プログラムを頭に走らせた上で、他に変化がないか考えよう。
フーロ時はテンパってからが勝負!
フーロ時はテンパイタイミングが全て
相手がフーロした時、まずはおぼろげながらに打点と速度を考える。
そして打点が高そうなとき(ホンイツっぽい仕掛けなど)もしくは高打点が確定しているとき(ドラポンなど)は、テンパイタイミングがいつなのかに全神経を集中させる。
ノーテンが分かれば、好き放題牌を切れる。
「イマノウチ!」と危険牌を先に処理することもできるだろう。
逆にテンパイが分かれば、リーチと同じように対応できる。
だからこそ、フーロ時はテンパイタイミングを漏らさないことが大事になってくる。
牌図③

安全牌の西を残して7sを切るか、それとも西を切るか。
場況や巡目にもよるだろう。
そういう意味ではどっちでもいい。
しかし最悪なのは「迷って西をきること」だ。
鈴木優さんの本にも「迷って字牌を切ったらノーテンの可能性が高い」と書かれている。
こんな喰いタンの手でノーテンを晒すのは危険極まりない。
イマノウチ!と下家と対面に中張牌を連打されてしまう。
だから
牌図④

こういう染め手でも、白と発の枚数をあらかじめ数えておき、どちらを切るか、それとも9mを切るのかを決めておこう。
迷って字牌は地獄行き!
国士テンパイ時
国士もテンパイタイミングが全ての手役である。
イーシャンテンまではロンと言われることが絶対ないからだ。
こないだの配信より。

わたくし、国士をテンパイしました。
テンパイ時の打1s。
そしてこの7mツモ切り。

そして下家のリーチを受けての1m手出し。
全て同じ「間」で打った。
ここらへんはどういう「間」で打っても、さほど影響がないものの

この6mプッシュはノータイムで切ってはいけない。
絶対切るし、全く迷わないんだけど、それでも今までと同じリズムを心がける。
6mはどう切ったところで強い牌なんだけど、それでもノータイムだとテンパイっぽいと思われる。その点少し間があるとイーシャンテンかも、と警戒の枠が広がる。
テンパイのときはノーテンにみせ
ノーテンのときはテンパイにみせるべし
これも誰かが言ってた。
ただ必要以上に考えると、いわゆる「三味線扱い」されるので、相手を騙すわけではなく、情報漏えい防止の意味で、なるべく一定のリズムで打つことを心がける。
他にも待ち変え、食い延ばし、ケーテン取りの鳴きなんかも「間」でバレやすいと言えるので、あらかじめ考える癖をつけよう。
まとめ
麻雀は総合力。
今日の記事「間」は、他の能力が一定以上あるという前提で、大事なことなので★★★とした。
時として「間」の重要性は牌効率や押し引きを超える
まずは迷うツモ(リャンメンが入ったら…など)から考えよう
絶好のツモは逆にノータイムにならないように ノータイムも傷になる
宣言牌周りの待ちになる時は決めておく
フーロ時も間に気を遣う
フーロ時はテンパイしてからが勝負
佐々木寿人選手が示してくれている。
一定のリズムで打つことの隙のなさを。
最後までお読み頂きありがとうございました! ↓スキすると毎回違うメッセージが表示されます!
