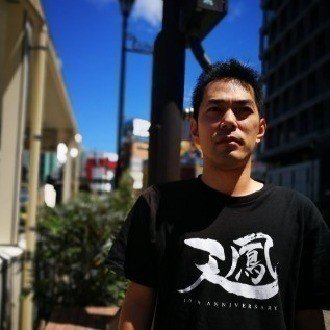ネット麻雀の特性、ラグ読みの基本【麻雀】★★★
昨日超久しぶりに配信をした。
配信も久しぶりだし、人と話すのも久しぶり。
それに配信全盛のこの時代、あらゆる配信者を見た後だと、自分の話の下手さに辟易としてしまう。それでも楽しかった。
その話はおいといて、配信中に語った「ラグ読みの基本」についてまとめていく。
ラグ→対戦者の鳴く・鳴かないのコマンドが出る間、切られた牌が止まること
ラグ読み→それによって持っている牌を推察し、選択に活かしていくこと
===================
先日、RMUが公式タイトル戦をネット麻雀「雀魂」で行うことを表明した。
リアル麻雀とネット麻雀、それぞれにメリット・デメリットがあり、賛否を巻き起こした。
私としては、この先鋭的な決断に「さすが多井プロは既存のプロとは違うな」と感じた。
ネット麻雀のデメリットの1つとして「本来ないはずのラグ読み」ができることがある。
とはいえリアル麻雀も表情や視線、落牌だったりコシだったり、競技としての欠陥と言えるものはいくらだって挙げられる。
だからどっちがいい・悪いとかではなく、ルールの違い・システムの違いでしかないと私は思っている。
A店とB店でルールが違うように、ネットとリアルでもルールが違うだけなのだ。
そこで今回は、いずれは注目されるであろうラグ読みの基本を抑えておく。
基本と言ってもこれまであまり語っていなかったことだし、読んですぐ使える内容である。
有料にするが、無料で知りたい方は昨日の動画を見てみて。
これまでの私はどちらかというと、ラグ読みは軽視してきた。
あくまでも不確定要素であるし、麻雀は他にも見るべき部分が多い。
先日、麻雀は「牌効率」か「押し引き」どちらが大切か、というようなことが話題になっていた。(定期的にあがる話題ではある)
わかりやすくていいレビューだけど対象段位は適当すぎじゃないか?w雀聖ですらウイング系知らないのたくさんいるだろうし。あと優先度って押し引き>牌効率じゃないのか麻雀で一番大事な技術って押し引きだよね? https://t.co/ePHZjNDNw7
— プロプー@proryu2 (@suzumetamashi) January 25, 2021
しかし、残念ながら麻雀で1番大切なのは押し引きでも牌効率でもない。
総合力である。
何ツモったらどれを切るか、どれか鳴く牌はあるか、点数状況は?親はどう打つ?下家の仕掛けは?全員の重要手出しを漏らさず見るべし…など、瞬間的に考えるべき項目が無数にある。
牌効率や押し引きはそれらの項目の1つにすぎず、麻雀のごく一部分でしかない。
これらの項目を1人の人間がある程度の優先順位を付けてこなしていかないといけない。
麻雀はマルチタスクである。
そして総合力は実戦でしか培えない。
これは昔から変わらない私の信念だ。
その証拠の1つとして、Mリーガーの平均年齢が40を超えていることがあげられる。(平均40.1333歳。中央値は38.5歳。なお黒沢さんは39歳計算)
実績(各種タイトル)を積むためにはある程度の年月を必要とする現在の構造が、一流選手の高年齢化を助長している側面は大いにある。
しかし、これだけ麻雀の戦術が体系的に語られ、強者の思考が、動画・サイト・書籍などの媒体によりいくらでも手に入る時代で、藤井聡太二冠(現在)のように若くてめっちゃ強い人が現れないことが「麻雀が経験のゲーム」であることの証左ではないだろうか。
あらゆる項目がある中で、1つの項目だけを机上で学んでも絶対に強くならない。
そういう意味でもラグ読みだけを覚えるのは危険だ。
他の項目が人並みにこなせるようになって初めて手出しを見るようになり、鳴き読みやラグ読みによって選択の精度を高めていく。
ということを踏まえた上で、ラグ読みを解説しよう。
なお雀魂はラグがわかりにくいという話を聞くし、天鳳限定の読みもあるので、そこらへんはご留意いただきたい。
ラグを確定させる
まずは「ラグ」を確定させることが大事だ。
天鳳にも雀魂にも「ニセラグ」が存在し、ラグっただけでは「本ラグ」とは言い切れない。
しかし「本ラグ」とわかるケースが3パターンある。
① 早すぎるラグ・遅すぎるラグ
一瞬でラグが解除されたり、逆に3秒以上止まったらラグである可能性が非常に高い。(回線が重いと遅くなることがあるため「非常に高い」とした)
最後までお読み頂きありがとうございました! ↓スキすると毎回違うメッセージが表示されます!