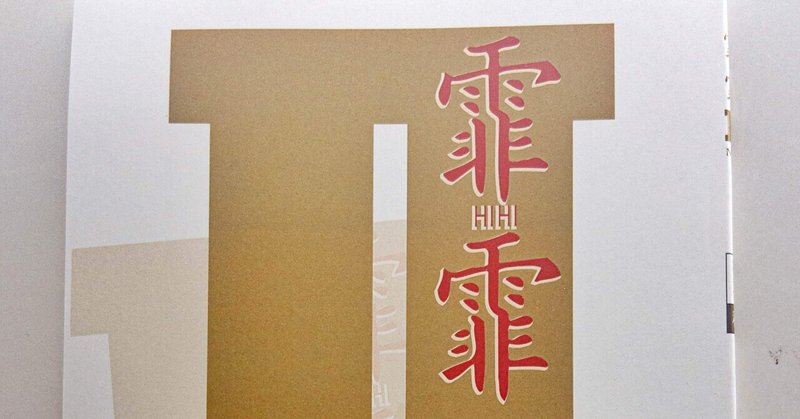
なゐの夜(『霏霏Ⅱnext』第4号(秋号)を読む)
令和3年10月7日22時41分、千葉県北西部を震源とするマグニチュード6.1の地震が襲った。仕事で疲れ果て寝ていたぼくは浅い眠りから飛び起きたが、長い周期の揺れに「震災」の二文字が明滅した。幸いぼくの周辺に実害は無かったが、東日本大震災の記憶がフラッシュバックしてしばらく寝付けず数日前に届いた『霏霏Ⅱnext第4号(秋号)』を手に取ったのだ。そこには震災を過ぎ、コロナ禍にあってなお句を発し研鑽し続ける熊本の俳人たちの揺るぎない姿を見つけ心強く思った次第である。
細麺をゆで月影と暮らす家 中山宙虫
停電。それは現代人の根源的恐怖の最たるものではないか。太い闇は高度に発達した利便を奪い取り、霊長を嘯くぼくらを赤子同然に戻してしまう。震災ともなればぼくらに出来ることなんて呆然とすることしかできない。しかしそんな時こそ俳人宙虫は泰然とカセットコンロを取り出し、棒ラーメンを茹で始めるのだ。恐怖に固まる胃の腑は温い麺にほぐされ、ふと月影が畳に映っている事に気づくのだ。山頭火よろしく草庵めく暮らしもよしか。と呟いてみせる。俳と諧を旨とする俳人の面目躍如たる一句である。
世をすねて冬の掌にのる少年忌 星永文夫
文学忌に無い「少年忌」のやけどするようなヒリヒリとした三文字にドキリとする。「少年」は作者とは限らない。大人として社会人として、親として生きる為の代償として裏切り傷付けて来てしまった純真無垢なる内なる存在を意味するのではないか?
ぼくらはその都度「少年」に謝りながら言い訳をしてごまかし、強がりながら年齢を重ねいつしか老いてゆく。作者は「少年忌」とすることで内なる少年への譚歌を奏でたかったのではないか?そっと触れてもたちまち壊れてしまうようなフラジャイルな「少年」は居場所を探しあぐねた挙げ句、繁華なネオンの明滅する暗流のような「冬の掌」へと身を任すのだ。目に曠野を宿した少年はいつまでもぼくらを責めるような表情で見つめ続けている。
まんじゅしゃげ千本咲けば千の飢餓 西口裕美子
もうこの国で飢餓は遠い話となった。しかしそれは本当だろうか?ぼくらは飽食しながら飢えてはいまいか?スマートフォンはすべての欲望を叶えてくれるように見え、反面焦がれるような餓えに身を灼いてはいまいか?ぼくらは生きながらにして無限の餓鬼道を彷徨っているのかもしれないと思うことがある。コロナ禍の日々は寥々たる曠野に居るような心象風景を作者にもたらしている。そこに咲く曼珠沙華はぼくたちひとりひとりの孤独な墓標だ。
午睡してエンケラドスに立っている 上杉波
昭和史の影だけ太る半夏生 矢嶋道子
蜘蛛の糸余白へ延ばす生命線 志賀孝子
いつの日か廃墟にカンナだけ咲くか 姫野章子
まっすぐにきて秋ほたる二つ三つ 山田昭子
ガラス器に万緑盛って雨の宿 井上望月
撫子の束を土産の草泊り 片山貴恵子
秋の風コトンと喪中葉書くる 山田節子
「災害列島」と呼ばれる我が国で地震に無縁な場所は無い。5年前の熊本地震でも多くの犠牲者と損壊した熊本城の酷い姿が記憶に新しい。以前から熊本発のネットラジオのリスナーであるぼくは震災当日から次々アップされる報道とは全く異なるリアルな惨状、遅々として進まぬ復興に疲弊し、人々が為政者に絶望してゆくプロセスを目の当たりにしてきた。中山宙虫氏が熊本在住である事から、大いに気を揉んだ事を昨日のように覚えている。東日本大震災の後、多くの表現者はナーバスにその作風を変えた。傷付き怯え、尖り切った社会詠、時事詠、政治詠を含むいわゆる震災詠が飽和した後、ある者は筆を折り、ある者は為政者批判に酔うまま詠が歪み、ある者は年月を掛け平静を取り戻していった。そのプロセスは人の弱さそのものであり、人間の業を肯定すべきぼくら文芸人がその行為を否定してはならないが、あの混乱を知っているからこそ『霏霏Ⅱnext』第4号を開いた地震の夜、この丁度良い大きさの俳誌の着実な歩みこそが俳人の、俳句そのものの底力なのだと喜ばしく、発行するにあたり労苦を惜しまぬ主宰、編集発行者に対し深い共感を覚えた次第である。
中山宙虫さん、西口さん、ご恵贈くださり、ありがとうございました。
里俳句会・塵風・屍派 叶裕

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
