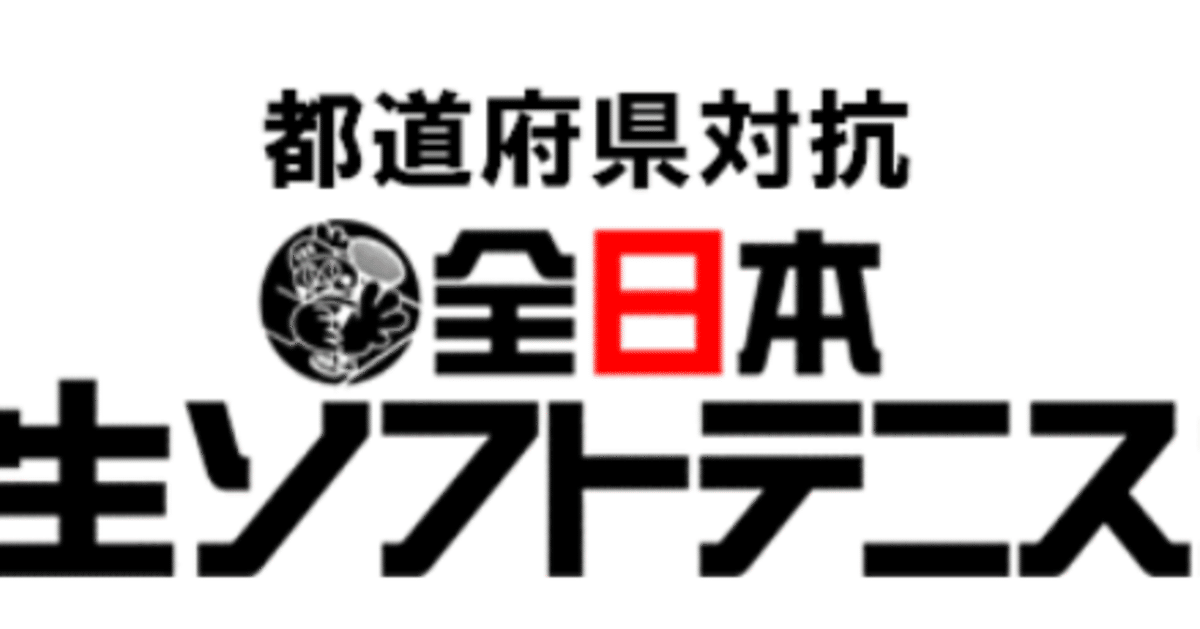
都道府県対抗全日本中学生ソフトテニス大会 中止に思うこと
先日、三重県伊勢市で令和3年3月26日より開催される予定だった、都道府県対抗全日本中学生ソフトテニス大会を中止にしたと伊勢市教育委員会から発表された。多くのプロスポーツやアマチュアスポーツが、観戦や参加数の拡大などを徐々に緩和しているさなかでのこの発表に大きな衝撃を受けた。この大会は昨年度も中止になっており、これで二年連続の中止となる。ソフトテニスをしている中学生は、この大会には中学1年時と中学2年時しか参加資格がないため、現在の中学2年生にとっては、この大会への参加が一度も認められないまま中学生活を終えることが確定したことになる。
ソフトテニスは日本発祥のスポーツであるが、非常にマイナーなスポーツと言っても良い。日本、韓国、台湾、中国などで取り組まれているスポーツであり、韓国では早々にプロ化されてもいる。日本では最近になってようやくプロ選手が現れた。といっても、日本のソフトテニス界において【プロ】とは、そう宣言した者がプロ選手となる。いわばプロ野球界とは全く異なる『プロの世界』だ。どちらかというと陸上界と似ているのかな?したがって、令和2年10月21日時点において日本ソフトテニス界のプロ選手は4人しかいない。自分はプロのソフトテニスプレーヤーであると宣言したのが4人、ということだ。
そんなマイナーなスポーツであるソフトテニスであるが、実は、日本の中学生が取り組む部活動において、その登録者数が一番多いのもこのソフトテニスなのである。学校で取り組んでいる部活というものの種類は多岐にわたるが、野球やサッカー、バスケットボールなどを抑えて、堂々の1位なのである。したがって、ソフトテニスに真剣に取り組んでいる中学生たちにとっての“ソフトテニス界”はけっこう熱いのである。
そんな中学生たちにとって憧れの場所でもあるこの大会。しかし、早々と中止の決定である。中学生の選手たちの落ち込みよう。特に、この大会に挑戦することさえ叶わなかった中学2年生たちの落胆ぶりは見ていられないものだ。モチベーションを保てず、練習に取り組めない子どもが現実的にいる。保護者もコーチたちも同様だ。今年こそはと意気込んでいただろうし、昨今の経済界やスポーツ界、GoToキャンペーンの推進具合などを見ても、中止にされるなんてことは思ってもみなかったに違いない。
主催者側にもやむを得ない事情はあるのだろうが、全てをかけてきた人間たちの落胆するこの光景を目の前にして、ちゃんと説明責任を果たしてあげほしいと思う。伊勢市教育委員会のホームページに記載したこんな文章だけではなくて、中学生の目を見てきちんと説いてほしいと思う。

コロナは多くのものを奪い去っていった。しかし、本当にコロナのせいだけなのであろうか。コロナの前では、さも人間は無力であるかのようにバッサバッサと切り捨てていくが、どこかコロナが免罪符のようになってはいないだろうか。
やりたくないものをコロナのせいにして捨てればまかり通る。そんな世の中になりつつないか。
今、コロナは試金石になっている。人間の本気さを試されている。
もちろん命より大切なものはない。コロナで命を落とすことが可能性としてある以上このウィルスを軽んじてはいけない。
だが、この数ヶ月で人間はこの未知なウィルスの未知な部分を少しずつ解明してきたではないか。
数年かかると言われたこのウィルスへの対抗措置。だが、この数ヶ月でどうすれば最小限に押さえ込めるか構築してきたではないか。
あとは、人の本気、である。
判断をした大人は、本気の鋭意努力をし本気の議論をし本気の決断をしたと信じたい。しかし、当該の中学生たちはその大人たちよりも、もっともっと本気だったと感じられてしまう。それは、あまりに早すぎる判断であり、そこにもっと努力できる道があったように思えてならないからだ。
都道府県対抗全日本中学生ソフトテニス大会は二年連続の中止。その判断に至る過程で、選手であり、感染予防対策をしながら毎日練習に励んでいる中学生の本気の想いはどれほど反映されたのだろう。大人の判断は本気の判断だったのだろうか。もしかして、子どもはおきざりにされてやいないだろうか。
「インターハイや国体が中止になり、彼らの目指す場所をいかに作ってあげるかが責務だと思っていた中で、最後のウインターカップだけは何としても開催したかった」
これは、日本バスケットボール協会会長の三屋裕子会長(令和2年10月20日)の言葉である。今年度の高校生の全国大会である【ウィンターカップ】の開催を決めたときの記者会見。ご存じの方も多いだろうが、三屋会長は元バレーボールの日本代表である。選手としてものすごい実績があり、中学生や高校生の気持ちが心底理解できるのであろう。自身が通ってきた道は、決して平坦なものではなかっただろうが、そのすばらしさを身をもって感じており、その機会を奪ってはいけないと中心より感じているのだろう。だからこそ、今年度のウィンターカップの開催を決めたのだろう。
また、日本バスケットボール協会会長は三屋会長の前は川淵会長。この方はサッカー界の人。Jリーグを立ち上げた人物である。混迷していたバスケットボール協会をひとつに統一し、Bリーグを立ち上げた。バスケ界初の1億円プレーヤーも誕生するなど、川淵元会長のバスケットボール界への功績も計り知れない。以前、日本のバスケ界には二つのリーグが混在し、双方が対立関係にあったようだ。それを国際バスケットボール連盟が問題視し、国際大会への参加を認めなかった。己の利権を主張して相まみえない二つのリーグ。それではこの競技の未来がないと、バスケとは畑が違うサッカー界から川淵元会長を招聘した。英断である。
双方のリーグの代表者たちを集め一つのリーグにまとめる会議の中で発した言葉。
「さっきから聞いてりゃできないできないばかりじゃねえか。できない理由を聞いてんじゃねえ。できる理由を聞いてんだよ!やらなきゃいけねえんだよ!」
江戸っ子のようなべらんめえ口調だが、競技の発展の未来を見据えた説得力のある言葉だ。この言葉がなくては、今のBリーグの存在もないのだろう。
ああソフトテニス界。
推進力が違いすぎる。川淵元会長や三屋会長。これは今のソフトテニス界にはないものだろう。
もしかしたら、日本ソフトテニス連盟にも外部からの強い風が必要なのかもしれない。オリンピック種目になることを本気で目指すなら。
ちなみに、中学生のバスケットボール大会も開催する方向なのだそう。これだけトップがしっかりしている協会である。子どもたちとその競技の未来を見据え、しっかりと対策をして開催するのであろう。
かたやソフトテニス界。10月の初めに日本のトップ選手が招待されミズノ主催でようやく無観客の試合が行われたのみ。
各地方の都・道・府・県レベルの大会やその下部の地方大会は中止にされたまま。いわゆる新人戦は行われていないまま。このままでは、ソフトテニスに打ち込んできた中学生が、あまりにも不憫でならない。
未来を見据えるとはどういう意味なのか。
コロナに勝つ?
逃げてるだけのソフトテニス界に未来はあるのか。
よろしければサポートをお願いいたします。いただいたサポートは、今後の治療費に使わせていただきます(^_^;)
