デッキレシピ【銀河零域】

こんにちはこんばんはおはようございます、大久保ユイです。
久々のnote投稿。備忘録の意味を含めたデッキ紹介記事第3回になります。
早速始めます。
◆前置き
皆さんは、好きなカードの種類って何がありますでしょうか?
効果モンスター、シンクロモンスター、速攻魔法、装備魔法、通常罠、カウンター罠。
一言に言っても、それらのカードにはそれぞれ役割が存在し、それらを中心にした戦い方も様々です。
そんな中でも僕個人としては、「永続魔法」「永続罠」を好んでいます。「見えている罠」として昨日することがある彼らは、遊戯王OCGにおける「伏せカード」とは異なった戦い方が楽しめます。
そんな中でも特に僕は「永続魔法」が好きです。
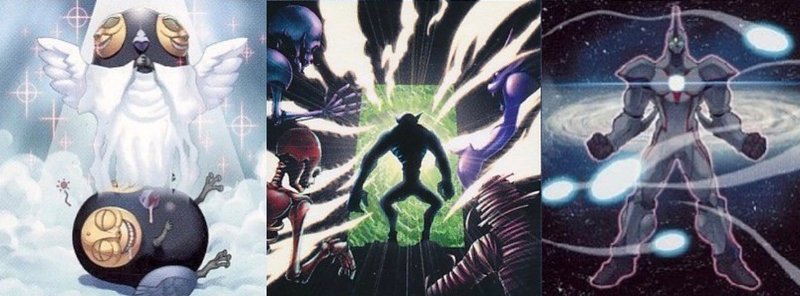
(一部の好きな永続魔法群。左から「昇華する魂、暗黒の扉、魂の共有ーコモンソウル)
そして今回は、僕が長いこと付き合い続けている一枚である、
『ゼロゼロック』
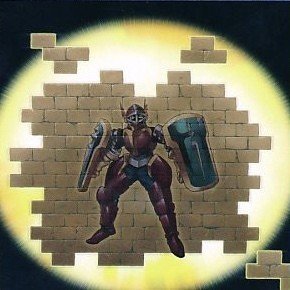
のデッキになります。
◆デッキレシピ

◆コンセプト
まず、ゼロゼロックの効果から確認したいと思います。
永続魔法
このカードがフィールド上に存在する限り、
相手は表側攻撃表示で存在する攻撃力0のモンスターを攻撃対象に選択できない。
攻撃力0のモンスターが攻撃表示の時に攻撃対象にされない。それ以上でも、それ以下でもないカードです。
端的に見ても、合わせるとするならば、
・攻撃力0のモンスター
・攻撃力0になるモンスター
・攻撃力を0にするカード
辺りになるでしょう。
その中で、このデッキは特に一番下の項にある『攻撃力を0にするカード』との組み合わせが中心となっています。
まずは、この1枚。

『天球の聖刻印』の一番の弱点は、個人的に「適当なモンスターで特攻し、効果を『使わせる』」ところにあると考えています。
EXモンスターゾーンにいる時には限るのですが、ここにゼロゼロックを組み合わせることで「攻撃されない妨害札」として機能してきます。
また、仮に自身をリリースしたとしても、「手札・デッキからドラゴン族を攻撃力0にして特殊召喚」という効果を有するため、後続のドラゴンもゼロゼロックと組み合わせる上で無駄がないです。
このデッキなら、リリース後の展開要因としては『レッドアイズ・ダークネスメタル・ドラゴン』、火力&フィニッシャーの一種として『クリアー・バイス・ドラゴン』を採用しています。
次に、

『転生炎獣ベイルリンクス』から楽々サーチが可能なフィールド魔法。
勿論ですが、本デッキでは②の効果がメインです。②の効果を使用することで、戦闘を介する必要はありますが、リンクモンスター全ての攻撃力を0にすることが可能となります。
と、ここまでの2枚を合わせて用意していくルートですが、以下の通りに展開していきます。
1. 『フォーマット・スキッパー』を通常召喚し、『転生炎獣ベイルリンクス』をリンク召喚。『パラレルエクシード』と『転生炎獣の聖域』をサーチ。
2. 『転生炎獣の聖域』の効果で『転生炎獣ベイルリンクス』を転生リンク召喚。手札の『パラレルエクシード』を特殊召喚し、デッキからももう1体特殊召喚。
3. 『パラレルエクシード』2体で『御影志士』をエクシーズ召喚。『魔救の探索者』をサーチし、自身の効果で特殊召喚。
4. 『転生炎獣ベイルリンクス』と『魔救の探索者』で『水晶機巧-ハリファイバー』をリンク召喚し、『太古の白石』を特殊召喚。
5. 『太古の白石』で『リンクリボー』をリンク召喚。エンドフェイズに、『太古の白石』で『青眼の白龍』を特殊召喚。
(↓次の相手ターンへ↓)
6. 『水晶機巧-ハリファイバー』の効果で『シューティング・ライザー・ドラゴン』をシンクロ召喚し、効果で『九尾の狐』を墓地に送りレベル7→1に。
7. 『シューティング・ライザー・ドラゴン』と『青眼の白龍』で『蒼眼の銀龍』をシンクロ召喚。ドラゴン族に効果破壊耐性・対象耐性を付与。
(↓次自分ターンへ↓)
8. スタンバイフェイズに『蒼眼の銀龍』の効果で『青眼の白龍』を蘇生し、2体で『天球の聖刻印』をリンク召喚。
と、『効果破壊耐性+リンクリボー』の耐性が地味に良く、意外と想定より耐えた後に展開出来ることが多いです。突破されたら死にます。
次に、いざ『転生炎獣の聖域』と組み合わせるリンクモンスターとして。


色々リンクモンスターは採用していますが、展開や勝ち筋のギミックに採用しているのはこの2枚。
①銀河衛竜の場合
銀河衛竜の場合は、コンセプト欄で紹介した最終地点:『天球の聖刻印』の着地後、
『九尾の狐』の効果でリリースし『レッドアイズ・ダークネスメタル・ドラゴン』をリクルート→『天球の聖刻印』を蘇生
でドラゴン族×2が揃うため出力は楽です。
このモンスターとゼロゼロックを組み合わせることによる最大の強みは、攻撃対象にされないことで②の効果を狙えること。
②:相手エンドフェイズに発動できる。
デッキからカード1枚を選んでデッキの一番上に置く。
デッキの一番上に持ってくるカードの種類は限られていないため、それこそゼロゼロックを持ってきたり(『和睦の使者』がフル採用されているのは1ターン確実に耐えてゼロゼロックを持ってきたいからだったりする)、
『アフターグロー』と組み合わせてフィニッシャーにする、なんて動きも可能です。
②パワーコード・トーカーの場合
召喚条件が「モンスター×3体」のため、多少の出しにくさはありますが種別を問わず出せるのはいいのかなと。
さておき、このモンスターも活かすポイントは②との組み合わせになります。
②:1ターンに1度、このカードが相手モンスターと戦闘を行うダメージ計算時に、
このカードのリンク先の自分のモンスター1体をリリースして発動できる。
このカードの攻撃力はそのダメージ計算時のみ、元々の攻撃力の倍になる。
これで注目したいのは最後の、「元々の攻撃力の倍になる」という点。
ゼロゼロックと組み合わせると微妙かな? と思う時もなくはないのですが、状況に応じて、
1. 『転生炎獣の聖域』で攻撃力0にして戦闘対象にされなくする
2. 攻撃力が0になっていたとしても、②の効果を使用し攻撃力4600まで底上げして火力を作れる
ことが強みになるのかなと思います。
『リコーデッド・アライブ』やその他のサイバース族サポートの恩恵を受けやすい(ものすごく抽象的)ため、使い勝手も悪くはない… はず。
ただ、ここまでデッキ内容を列挙してきましたが、
・そもそも効果除去に弱い
→『ゼロゼロック』や『転生炎獣の聖域』のサポートとして『警衛バリケイドブルグ』を採用しており、「魔法カードが相手の効果で破壊されない」という効果はありますが、そもそも『銀河衛竜』や『パワーコード・トーカー』が除去されちゃ意味ねえよなって感じる時は少なくないです。
・エクストラデッキがかなり逼迫している
→展開の多くにかなりのエクストラデッキを消費するため、もう少し簡略化したいなあと思う時は少なくないです。
・ゼロゼロックが引けない
専用サーチカードくれ。
以下、解説していない周辺カードについて軽く触れます。
・サイバース族関連
正直全て『フォーマット・スキッパー』を呼び込むためにと言っても過言ではないです。
ただ、『プロフィビット・スネーク』『アクセスコード・トーカー』『サイバネット・コンフリクト』は、採用が難しくない除去カードとして採用しており、『サイバネット・リカバー』はリンクモンスターが処理された後に『蒼眼の銀龍』を出して壁にしたり。
あと、『警衛バリケイドブルグ』と『サイバネット・リカバー』の組み合わせが地味に推し。
・ロケットハンド
正直枚数増やしてもいいのかなあと思います。ダメージステップに僅差の戦闘で活躍する+除去+攻撃力0に出来る汎用。
マジで軽くしか触れられなくてびっくりしました(小学生並の感想)。
◆終わりに
久々に記事を書いたので、言いたいことあんまり言えてない+めちゃくちゃ読みにくい気がします。ここまでお付き合い頂きながら申し訳ない。
かれこれこのカード、もう考え出して5年程度経つのですがやはり難しさが強いですね… 改めてギミック見ても「そりゃそうやろ」程度の内容にしかならなかったので、今後も対戦の中で練っていきたいと思います。
また、何かデッキがまとまったら書きたいと思います。
ではでは。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
