
高校卒業・大学入学・新会社設立について
こんにちは!無事に聖学院高校を卒業し、4月からは大分県別府にある立命館アジア太平洋大学サステナビリティ観光学部に進学しています。中高時代に立ち上げた一般社団法人Sustainable Game(SG)は川村賢人が代表理事となり、今月から私が理事として参画しました。今後、さらに未成年へと継承を続けていく中で、継承者側の責任やリスクの分散等々を目的に、より一層、共にSGが目指す世界づくりに貢献していきます。そして、SGの「愛を持って社会に突っ込め」という理念を引き継ぎながら、7月10日より株式会社Emunitasを創業しました。私が代表取締役、SGの卒業生である増渕を取締役に、世界各国の新たな同志と「Empower Everyone's Potential」というミッションを果たすべく事業を始めます。ご一緒していただける個人・企業様を絶賛募集しています。
受験よりも自分らしさを大事にしよう
【170日前:共通テスト2日目】
緊張している。僕は勇気を振り絞って隣にいる少年に声をかけた。
「このお菓子、良かったら食べますか?次の数学もお互い頑張りましょ」
あくまで話し始めてからが僕の得意分野だ。しかし正直なところ、いきなり誰かに話しかけることが苦手で、100回以上行ったピッチも直前まで異常に緊張している。何かを始めるとき、体も足も重く感じる。しかし、僕は如何ともし難く、いつも何かを始めている。
その理由の1つは、おそらく相手への興味関心であろう。その好奇心が抑えきれなくなると、緊張を乗り越えて話しかけてしまう。隣席の青年もそうであった。彼が試験直前に取り出していた使い古したノートは、彼のユニークネスで溢れていた。それを見た瞬間、僕の手はすでに彼の前にあった。その上、偶然か否か、六花亭(函館の銘菓)を渡すと、彼は北海道出身だったらしく、懐かしみながら東京の高校に進学するために上京してきた生い立ちを話してくれた。彼の高校は、有名な大学附属校だったが、国立大学を目指して努力を続けているとの話に尊敬の念を覚えた。行動するって、面白い。
話を少し巻き戻そう。12月24日、私は初めてコロナに感染した。隔離期間は1月3日まで。正直、部屋に篭っているのは変わらないので、勉強も続けられると楽観していたが、40度の熱は止まらない。もはや僕の体は、勉強は否や本さえも開くことを許してくれない。そんな時、無意識から「なんで大学に行くのだろうか?」という問いをベットの上で繰り返し、自分自身に問いかけることになった。共通テストが迫るこんな時期に、あるべきでない考えが頭をよぎる。それに東大からの落選という無情な現実が、答えを探そうとする自分の脳内で冷たく反響していた。
天井を見ながら思った。「僕はなんでこの大学に執着してるんだろうか。」脳裏に過ぎったのは、模試会場の休憩時間に筆箱を落とした人を目の前にして、散乱する文房具を跨いで小走りに通り過ぎていくライバルたちだった。その姿をみて、僕は慌てて消しゴムを拾ってあげたが、このまま消しゴムを拾ってあげられない人間になってしまうんじゃないかという違和感を天井に投影するかの如く思い出していた。そして同時にK弁護士から頂いた「活動の中で学ぶのは当たり前です。それ以外の座学を含めた学問を必ず、活動をしない学生よりもやらなければいけない。」という言葉をボソボソと復唱していた。
結局、考えるのをやめた。自分らしくいよう。
共通テストも、一般受験も必死にやってみよう。でも、自分らしく。
例えば、英語は模試や共通テストの過去問をタイムアタックで解いた後、欠かさずDMM英会話で単語を使ってみる訓練をした。そして、毎日のBBCニュースを聞いてみる。ご褒美にNetflixの「ウ・ヨンウ弁護士は天才肌」という韓ドラを英語吹き替え/字幕で視聴した。正直、これが一番英語力が伸びた勉強法だったかもしれない。現代文は過去問を解いてみる。これは色々なトピックに触れられて結構楽しい。興味がさらに沸いたら好奇心を止めずに、メルカリで本を買ったり、論文を読んだりもしてみた。漢文ドリルと古文単語は毎日やっていたので習慣で続けていた。全ページを終わらせた時の感動は今でも忘れてない。生物基礎や地学基礎は、NHKやnetflixで壮大なドキュメンタリーを30分ぐらい見て、ひたすら番組に出てくる知識をメモして、家にくる友人や母に説明した。それぐらい感動し、その勢いで基礎知識を蓄え、そこから今でも微生物や土壌再生は興味が終わらない。地理や世界史はもともと好きだったので、教科書や参考書を何回も見ながら一人ニヤニヤしていた。最後に、数学である。授業で数学をまともに勉強していなかった(そして、数2Bは授業でほぼ学べていなかった)ので、夏休みから「面白いほどわかる数学」という小学生でも理解できる参考書を片手に、K先生に大変お世話になりながら模試の過去問を頭を抱えながら解き続けていた。おかげさまで点数は伸び悩んだが、数学を学ぶ大切さや楽しさを少し感じられた。(本当に感謝してます。)そして、高校の図書館、駒込図書館、家の近所の図書館を渡り歩いた日々は今では忘れられない思い出である。夏休みが始まる後輩へ、自分らしさを忘れずに勉強頑張ってね!

高校卒業〜大学入学までの約2週間


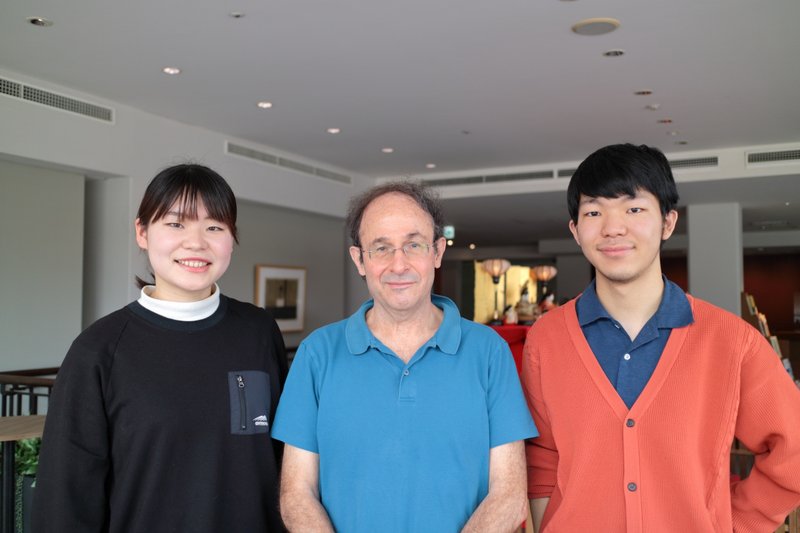




いつの間にか別府にいた
3月末、千葉でキャンプをした翌朝。飛行機に乗ると、そこは大分だった。到着するや否やInstagramのDMに「見たよ」と連絡が入る。すると今度は「バスに先に乗ってるね」とTwitterのDMから。慌てて、バスのチケットを買おうとすると券売機前のおじさんが行き先を訪ねてくれた。「APUで..」声を遮るかのように「これね」と言われる。そう、僕は今からAPUという大学に行くのだ。DMでは、なぜか僕をすでに認識している同級生から連絡が届いていたらしい。(彼ら/彼女らとは結果的にとても仲良くなるのだが..)

APUとは、正式名称を立命館アジア太平洋大学という。この大学との出会いは意外にも中学2年生に遡る。私がSustainable Gameを立ち上げた初期の頃、「課題発見DAY」を開催するための会場提供先を探し、APUの東京キャンパスを訪ねていたのである。結果的に会場は貸してくださらなかったが、その際にIさんから伺った「日本にはAPUっていう大学があってね。カフェテリアでは、アジアの色々な国の人が、スマホを見ないで、アジアの政治や国際情勢について語り合ってるんだよ」という話が脳裏に刻まれていた。加えて、高1の時には、出口学長がtwitterで「ぜひキャンパスに遊びにいらしてください」というリプライと共にフォローをしてくださったエピソードもある。(それから最初のキャンパス訪問が入学と同時とは想像もしていませんでしたが..)そのような幾つかの点と点が繋がり、加えて母が僕が普通に捨てようとしていたAPU のパンフレットをどこかに隠していたこともあり、青々とした表紙に書かれた「サステナビリティ観光学部」という新学部に興味を抱いた。ここなら当時の住民参加型の政策立案を研究してみたいという自身の好奇心を思う存分発散できるかもしれないと思ったのだ。あいにく、東大の選択肢が薄れ、様々な事情で奨学金がないと大学入学を考え直そうと考えていた中、APUから奨学金をいただくこともでき、無事に4月から入学するチャンスを掴むことが出来た。この機会を頂けたことは本当に感謝している。人間万事塞翁が馬という言葉のとおり、一見、不運に思えたことが幸運につながったり、その逆だったりする。まったく、幸運か不運かは容易に判断しがたい。

さあ、Emunitasをはじめよう!
改めまして、7月10日に株式会社Emunitasを登記します。これまで、そして、これから大変お世話になる多くの皆様、よろしくお願い申し上げます。

この3ヶ月間、年齢、国籍、宗教、みんなバラバラの10人が本当に不思議な出会いの中で集い、株式会社Emunitas(エミュニタス)は設立された。具体的には、日本、ベトナム、インド、インドネシア、バングラディシュ、メキシコ、韓国、アメリカにルーツを持つ。
会社名Emunitasとは、ラテン語で"特定の制限からの解放"を意味する言葉である。そして、私たちが大切にしている"Empathy(相手の状況を理解しようとする努力と能力)"と"Unity(失敗を気にせず、皆で一緒に挑戦すること)"の2つの言葉の音をかけ合わせた。
今ある私たちの強みは、世界中のローカルに対して"Empathy"を持てる次世代であるということ、そして圧倒的な"Unity"だ。"Empower Everyone's Potential"というミッションと共に前に突き進む。
最初の拠点は、別府、インドネシアのジャカルタ、そして南インドのチェンナイである。まずは、日本にいる留学生のワンストップ就活サポートを主軸とした事業に取り組んでいく。弊社の就活サポートには、日本企業との有給インターンシップ(バイト)で日本の労働環境を知っていただく機会の提供や日本で働きながら暮らす上での知恵の影響、企業への紹介、就活フェアの開催(予定)、日本語とVISA申請のサポート等が含まれる。加えて、起業したい外国人留学生がスタートアップビザなどの枠を使って挑戦を続けられる仕組みも作っていきたい。
2023年9/11追記:何をやるべきか少しピボットしたので、アップデートを近々新しいnoteとWEBサイトでまとめます。
株式会社Emunitas代表取締役山口由人:
yamaguchi-y@emunitas.com
なぜEmunitasを立ち上げたのか
去年の6月、僕はSustainable Gameを継承した後、SGを卒業した社会をより良くしたいという想いを持つOBOGと再び何か挑戦してみたいと考えていた。同時に、これから先は様々なスキルやノウハウを身につけたOBOGに再び声をかけつつ、未成年が主体のSustainable Gameという組織をより持続可能に続けていける体制を築いていきたいと考えていた。一方で、現実として、生活費を自身で稼ぐ必要がある大学生や社会人の場合、無償で活動に参加してもらうことは難しい。そうした背景から「社会をより良くしたいと志した同世代が、その想いを継続させることができる仕組みを作れないだろうか」という問いを抱き、別府の温泉で出会ったベトナム出身のルアンと語り合い始めた。すると、新たに見えてきたのは、国際生(留学生)が別府でスキルアップに繋がる有給の仕事を得ることが困難であるという課題だった。とりわけ、地方になると自身の可能性を活かすことができる英語を使える仕事はほとんど存在しない。加えて、28時間/週しか働けないという労働基準法、そして、労働時間の算出が「客観的」でないといけないという点から仮に都会にある英語が使えるスタートアップがあっても、国際生がリモートワークで別府から働いてしまうと、雇用した企業側の労務リスクになりかねないのである。私たちはまず、この課題を解決することに取り掛かろうとした。すると、高校や高校卒業後に母国にある深刻な社会課題に立ち向かい、課題解決を実践していた様々な国際生と次々に出会ったのである。彼らとは出会った途端に打ち解け、仲間になってもらった。彼らが今の創業メンバーだ。

僕は当時、インターンシップでの仕事などを通じて、あるいは今まで接してこなかった未知と日々遭遇する中で、自身が何をしたいのかを見失ってしまっていた。ただ、それと同時に沸々と湧き起こるのは、さらなる世界へ好奇心と「何をするのかよりも、誰とするか」を大事にしていきたいという想いであった。出会った最高の国際生と何かしたい。これまで出会った最高の方々と何かしたい。きっと楽しくて、社会を喜ばせられるに決まってる。
思い返せば、Sustainable Gameの時も、入管の収容所に通っていた高校時代も、目の前の人の課題を解決したいから行動していたわけではなくて、目の前の人と「一緒に生きたい。一緒に世界を創りたい。」のに、それが出来なかったから課題を解決しようとしたのだった。この価値観と想いを持てれば、正直、どんなにハードワークでも成し遂げるために動き続けられる。そう思った瞬間、再び、しっかりと行動力のスイッチが押された。
その後、投資家やメンバーと話を重ね、光栄なことに出資していただくことを検討いただいている素敵な方々とも出会うことが出来た。そして、同時にに留学生に特化するのではなく、よりマーケットとしても広いアジアをターゲットに捉え直した。また、その中でも一緒に世界を創りたくても、気軽に一緒に活動をすることが難しい方々をエンパワーできる、そして、同時にアジアに投げた種が実となり、日本の未来に還元されていく仕組みをつくることに決めた。
未来はどうなるか分からない。でも「皆で生きる世界は皆で創りたい」という19年間の信念は、これからもずっと続くだろう。そうして、僕は覚悟を決めた。生まれた時からのご祝議、18年間のお年玉、すべてを資本金として投資して、後ろへは立ち返らない。2社目も大好きなメンバーと共に前に進み続けます!
Empathy and Unity: Diving into Society (会社のバリュー)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
