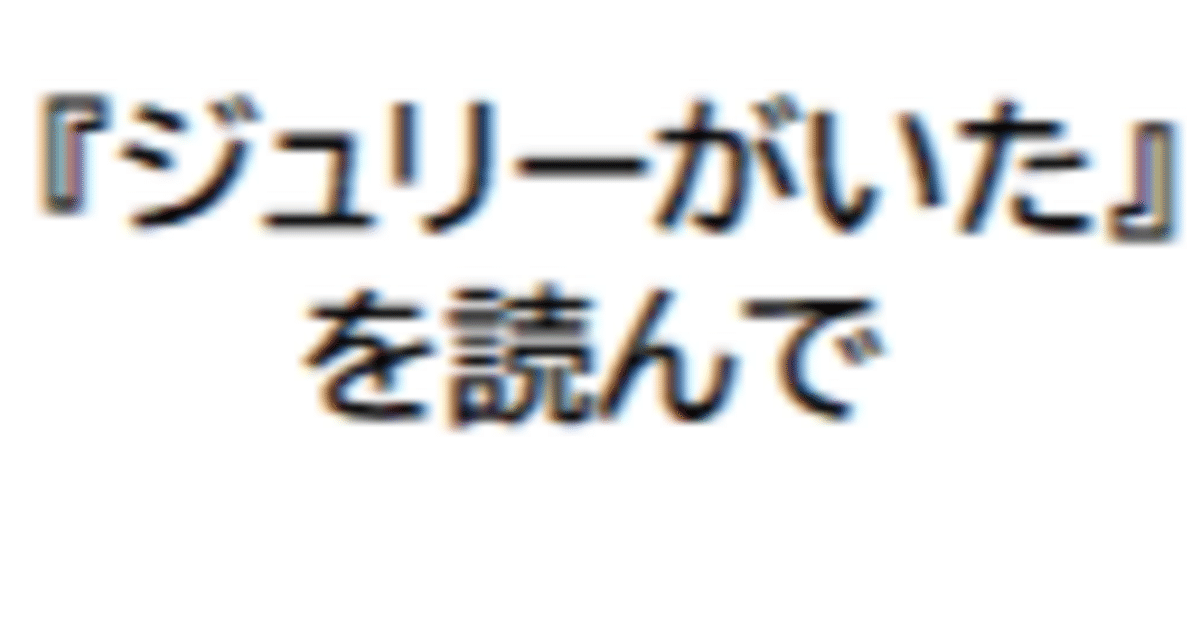
番外【島﨑今日子『ジュリーがいた』を読んで】
ジュリーこと沢田研二さんの経歴やあれやこれやを徒然なるままにつらつらと綴って参ります。細々とやっていきます。
Xで連載(?)しているネタのまとめです。
よろしくどうぞ。
※普段は上記のように沢田研二さんのあれこれを綴る
「まだまだ沢田研二」のまとめをやっておりますが、今回は番外編です。
#沢田研二 #まだまだ沢田研二
島﨑今日子『ジュリーがいた』
とりあえず、ジュリー本人がこの本に否定的だから、と言うのではないです。ただ、読んでて「???」となる箇所が多すぎ。それも、ごく基本的な事柄に関して。
別に「どこかに間違いはないか?」と目を皿のようにしたわけではないですが、それでこれだけ気になりました。
1.BLについて

冒頭からBL論、それは別に良い。ただ「おっさんずラブ」がブームの契機とはどういう意味でしょう? 私は別にBL愛好家でも研究者でもありませんが、そんな人間でもBLはこのドラマの2016年以前からかなり人口に膾炙していたことくらいは分かります。
著者自身、ここから延々とBL文化史を綴っていながら、この記述に疑問を持たなかったのでしょうか。それとも2016年までBLがアングラだったと思っているのでしょうか。
アングラ好きだから数あるジュリー舞台の中で『唐版 滝の白糸』ばかり延々と語ってるんでしょうか。
まぁこれについては「ブーム」という言葉の定義次第なので「間違い」とまで言うつもりはないですが。ただ少なくとも「『おっさんずラブ』がブームの契機」という記述には疑問を禁じえないです。
2.コンセプトアルバムについて

『サージェント……』は「世界初のコンセプトアルバム」ではありません。確かにブームを作った作品ではありますが、これ自体がマザーズ・オブ・インヴェンションの『フリーク・アウト!』に影響を受けています。
確かに『SPLHCB』を世界初のコンセプトアルバムと語る向きはあるようです。しかし異論もある。ここはせめて「世界初とも言われる」「世界初とされる」とすべきでしょう。
3.レッド・ツェッペリンについて

この件は意味不明。「スーパーバンド」は1970年前後に流行した、「既にキャリアを有するメンバーによって結成された豪華バンド」の事。エイジアやBB&A、EL&Pのように。
しかしZEPはペイジ以外は世界的に無名なメンバーで結成されたバンドです。
そしてZEPの音楽性は「ブリティッシュロックの集大成」ではなく「1970年代の新しいロックを切り開いたバンドの1つ」です。HR/HMの源流にも位置付けられる(異論あり)バンドですから、過去の集積より新時代を開いた功績の方が圧倒的に大きい。
おそらくZEPが始動した時期とスーパーバンドが流行した時期が同じで、ペイジは既にヤードバーズで知られていたことが混同してこんな記述になったんでしょうが。
4.村八分と裸のラリーズ、頭脳警察について

ここの「村八分の母体となった裸のラリーズ」という記述は限りなく誤りに近い説明不足です。
村八分:柴田和志(チャー坊)と山口冨士夫が中心となり1969年に結成。
裸のラリーズ:水谷孝を中心に1967年結成のバンド。
裸のラリーズは水谷以外のメンバーが非常に流動的なバンドでした。
そしてザ・ダイナマイツ解散後の1970年頃、京都に戻った山口冨士夫は柴田和志と意気投合。柴田はそれ以前から水谷と知り合いでした。
水谷、冨士夫、柴田らがこの時期の「裸のラリーズ」となりました。
しかし間もなく水谷とそれ以外に分裂、2つの「裸のラリーズ」が並立する事態を経て、冨士夫らはバンド名を「村八分」と改め、水谷は東京へ行き「東京ラリーズ」から「裸のラリーズ」を継承。後々までこの名前を名乗ります。
しかし冨士夫らが「裸のラリーズ」を名乗った時期は極めて短く、また「裸のラリーズ」自体は「水谷孝のバンド」です。冨士夫らの在籍時前後も水谷はこのバンド名で活動し、散発的に1997年まで続きました。
何より、水谷は村八分に加入したことはありません。
つまり何の説明もなしに「村八分の母体となった裸のラリーズ」と書けば「ラリーズは水谷孝が作って村八分より後まで続いたバンドなのに何言ってんだ」となります。
冨士夫は1980年にもラリーズに参加しますが、普通「ラリーズの山口冨士夫」と言えばこの時期を指します。
恐らくロックと新左翼の関係を書きたいが為にラリーズの名前を出したのでしょう。
ラリーズにいたよど号メンバーとは若林盛亮のことですが、彼が参加したのは最初期。著者も記すように村八分メンバーとは関係がありません。そしてラリーズとジュリーに活動を共にしたような接点はありません。
村八分、頭脳警察、沢田研二。
これらを結び付けたいのであれば、何故にPANTAとジュリー・内田裕也の関わりや上原裕が元村八分であることに触れられていないのでしょう。
冨士夫は鮎川誠や忌野清志郎とも組んだことがあり、いずれもジュリーとも関りがあります。
そして頭脳警察を「新左翼のアイドル」と。確かにこの呼び名はありましたが。
少しでも頭脳警察を知る人には、これが蔑称であることは言う迄もありません。著者はzkをディスりたいのかと思いましたが、この文脈でそれは唐突すぎます。
晩年のPANTAのインタビューから。
「“左翼のアイドル”から抜けられなくなって」……PANTAが明かす“頭脳警察を一度解散した理由”
https://bunshun.jp/articles/-/38905
5.赤軍派について

連合赤軍へとつながる赤軍派の集会は1月24日ではありません。翌1月25日です。ここが事実誤認では象徴も何もあったもんじゃないです。
場所も九段会館ではなく千代田公会堂です。日本遺族会が管理していた九段会館が極左の集会に使われるハズがない、と何故気付かないのでしょうか。
当時のロックが反体制で新左翼と近しかったことを書くのは重要だろうと思います。が、スペースの問題もありましょうが筆を尽くさず端的に書こうとして粗雑(そして不正確)な記述になったのでは、著者の力量を疑わざるを得ません。
6.ヨウジヤマモトについて
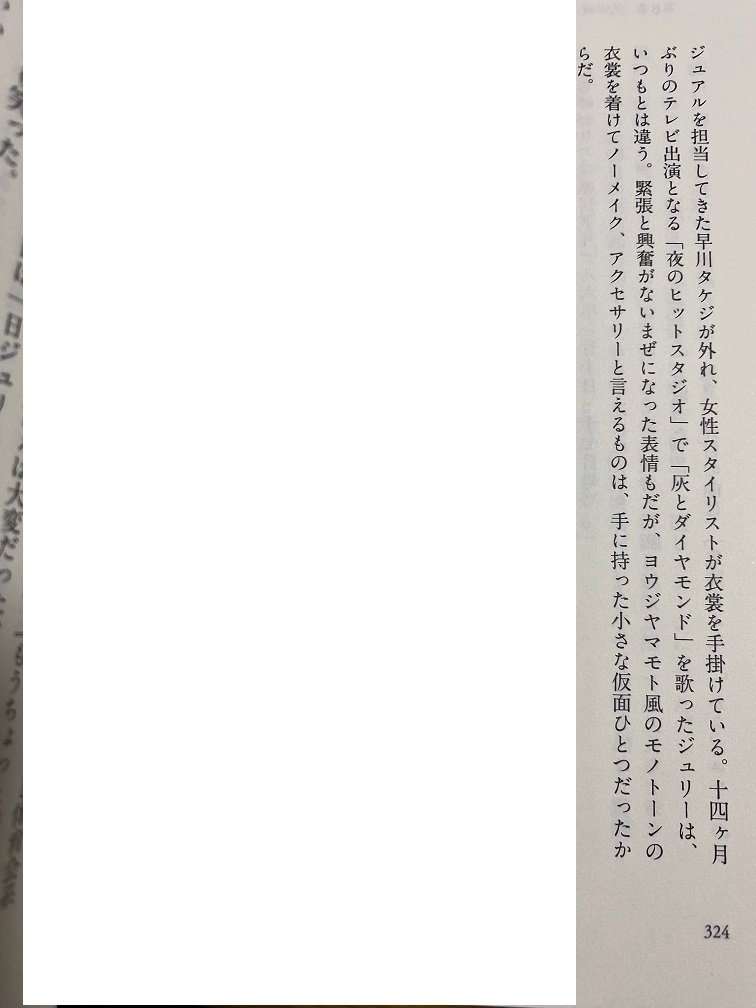
ここは半分難癖に近しいことを自覚した上であえて書きますが。
「夜のヒットスタジオ」に『灰とダイヤモンド』で初めて出た時のジュリーの衣装は「黒のベスト、白のシャツ、黒のパンツ」で、これを著者は「ヨウジヤマモト風」と書きます。
確かに「黒」はヨウジの代名詞ですが。
「黒のベスト」「白のシャツ」「黒のパンツ」といった組み合わせは「ヨウジ風」でしょうか? ヨウジもブランドとして長い歴史がありますから、これらのようなアイテム自体はあったでしょうが。
しかし一般的なヨウジヤマモトのイメージは。
・黒一色(模様としての他の色)
・オーバーサイズ
・大胆なカッティング
といったものではないでしょうか。
少なくとも「黒のベスト、白のシャツ、黒のパンツ」という上下の衣装を見て「まるでヨウジヤマモト」と思う人は相当少数派ではないでしょうか。
しかもベストは途中で脱ぐ為、後半は「白シャツと黒パンツ」です。
これは「シック」とか「オーソドックス」と言える出で立ちで、「黒の衝撃」と呼ばれた「ヨウジ風」とは真逆だと思います。スタイリストの狙いは革命的なファッションではなく、そこ=シックなジュリーを魅せる、にあるとしか思えません。
※全て書き終えてから気付きましたが
「十四ヶ月ぶりのテレビ出演」も誤りです。
この出演回は1985年7月24日放送です。そしてこの前の「夜のヒットスタジオ」への出演は1984年5月14日。
しかしこの間もジュリーは紅白歌合戦等のテレビ番組に出演しています。
正確には「十四ヶ月ぶりの『夜のヒットスタジオ』への出演」です。
7.岸部修三(現・一徳)について



「岸部修三(現・一徳)」の注釈が何回も出て来る。
これは元が雑誌連載だったからでしょうが、こういうのは普通、初出時に「岸部修三(現・一徳、以下同)」とするべきでしょう。ま、これについては編集者が仕事しろよって話ですが。
8.大澤誉志幸について



大澤誉志幸は歌手に先んじた作曲家デビューから1999年の一時引退まで「大沢」名義です。「大澤」表記になるのは2002年の再開から。にも関わらずこの本では全て「大澤」です。著者は『A WONDERFUL TIME』の歌詞カードを見た事がないのでしょうか?
「岸部修三(現:一徳)」を何回も書くのであれば「大沢(現:大澤)誉志幸」でないと整合性が取れません。
9.『永遠に』について

アルバム『第六感』の『永遠に』とシングル『永遠に』は全く別バージョンです。アルバムはエレキの多重奏、シングルはアコギ1本という別音源なので「シングルカット」ではないです。厳密に言えば先行シングルだし(先行の場合もシングルカットと言うことはありますが)。
10.「初のカバー曲」について

「ジュリーが自分のために作られた曲以外でシングルを歌う」のは『渡り鳥 はぐれ鳥』が最初ではありません。この本の中で一文字も触れられていない『魅せられた夜』はカバー曲です。
11.ザ・ピーナッツについて

これ、読んだ時物凄く混乱しました。
「ザ・ピーナッツの姉」とは伊藤エミさん、つまりジュリーの当時の奥さんです。彼女がジュリーより前に松下治夫と子供をもうけていたのでしょうか????
松下はピーナッツのマネージャーでもありましたが……。
と思ったら「赤ちゃんだった従弟」という記述。これはジュリーとエミさんの一人息子のことと思われます。ということは松下と子供をもうけたのは「ザ・ピーナッツの『その上の長姉』」と思われます。エミさんは三女ですので、姉妹の上にさらにお姉さんがいます。
そして一般の方ですから、名前が出ないのも分かります。
しかし他に伊藤家の家族構成について何の説明もなく、いきなり「ザ・ピーナッツの姉」と書かれて「伊藤エミさん?」と誤解することは不自然でしょうか?
松下が伊藤家の長女と結婚して子供をもうけていることは、そこまで広く知られていることでしょうか? こんなデリケートな話を書くのに説明もなければ「姉」を誤読させるような記述は配慮が欠けていると思います。
12.『君をのせて』について

この本の中で一番許せないと思ったのがこの件。
ジュリーが当初『君をのせて』に否定的でやがて肯定的になったことは事実です。
そして再婚後のジュリーが「私が歌う『君』は妻のことです」と語っているのも事実です。
ですが、それとこれを結び付けて良いのでしょうか?
『君をのせて』を好きになったのは田中裕子さんに出会ったからですか?
もちろんジュリー自身がそうだと断言しているのであれば構いません。
しかし「だろう」と書いている通り、これは著者の推測でしょう。
そして、特定の個人への愛情を勝手に推測するくらい、下世話なことはありません。これはジュリーにも2人の妻にも『君をのせて』を書いた人にも全てに失礼な書き方だと思います。
13.ショーケンについて

そして著者が長々と熱弁を振るうショーケンについても。
ショーケンとジュリーとの交流を描いた章の結末に近い部分に、このような記述があります。
この事自体は、決して嘘ではありません。
ショーケンが自ら記した著書はそう多くありませんが、『ショーケン』『ショーケン 最終章』の2冊は自叙伝としての性格を有する貴重な資料です。
そして、書名で一目瞭然ですが後者が後に書かれ、本人の没後に刊行された公的な遺言に近い書籍です。
しかし著者は『ショーケン 最終章』について全く触れません。巻末の参考資料にも掲げられていません。『ショーケン』の中にジュリーを批判するような記述があったことは事実ですが、『ショーケン 最終章』ではジュリーをどう描いているのでしょうか。
『ショーケン 最終章』では
「たとえば沢田研二は抜群の歌唱力だ」
「ジュリーのすごいところは、プロデューサーの意向をパーフェクトに実行し、開花させる誠実さにある」
等と触れられています。
そしてこの節には以下の表題が付いています。
「ジュリーはすごい」
確かに批判はあった。ですが、その後にショーケンが語った言葉がこれなのです。
人間ですから、長い人生の中で意見が変わることは間々あります。ましてショーケンはとても複雑でセンシティブな心理の持ち主でした。
ですから彼がジュリーに批判的な意見を吐いた、そんな時期もあった、それは事実。
ですが人生の最終局面で「やっぱ凄い奴だ」と思ったこともまた、事実です。
著者が刊行から日が浅く現在も容易に入手できる『ショーケン 最終章』に全く触れない理由は分かりません。
もし「知らなかった」とでも言うなら、不勉強にもほどがあります。
歴史を検証する際、同時代の当事者、関係者による資料を「一次資料」と呼びます。もちろんこれらの資料が「事実か否か」の検証は別途必要ですが、「読んでもいない」のでは話になりません。ショーケンの事を書くのにショーケンが書いた本を読まない、は問題外でしょう。
或いは。
『ショーケンがジュリーを批判した」ことだけを記し、その後のショーケンの意見は知っていても触れていないのであれば。
それはもう、救い難く許し難い過失です。
つまり「あえてスキャンダラスに書いてやろう」という意図があることになるからです。
それはゴシップであり、そうした記述が1行でも存在したならば、書籍全体の性格がそれで「ノンフィクション」から転落します。
14.助動詞と「いた」について

「確定・発見の助動詞」という文法用語は聞いたことがないんですが。
助動詞「た」は広辞苑によると「過去・完了・存続」という風に書かれております。
確定ではなく「確認」「断定」の助動詞なら聞いたことありますが「発見」の助動詞って何ですか?
これもそもそも論ですが。
助動詞は読んで字の如く「動詞を助ける」、つまり動詞に意味や機能を付加する品詞です。
「発見」は既にそれ自体が一つの動作だと思うのですが、確定や発見の意味を持たせたいのであれば「ジュリーがいる」(11人いる!的に)でしょう。

そして著者自身、その意味にたじろいでいるくらいですから。
明確に、この書名に込めた意味は「過去」「完了」なんでしょう。本当に「現在までもが含まれている」なら「いた」という表題にしないでしょうから。
著者の旧著である『安井かずみがいた時代』はより明確に「過去」「完了」の意でしょう。同一著者が類似の表題に揃えることはよくありますが、それで「前の本は過去・完了で今回は現在まで含まれています」は通らないでしょう。
私自身がそうですが「ジュリーがいた」と聞いて「過去」「完了」以外の意味を感じ取れる人は少ないと思います。「まだ現役なのに勝手に過去形にすんな」と思われても文句は言えないと思います。本当に「現在までもが」ならやはり説明が足りないです。
15.結論
……といったところです。
繰り返しますが、別に間違いを見つけようとして読んでいた訳ではありません。だから私が気付いていない(知らない)誤りがもっとあるかもしれません。
総じて、この著者に対しては「無神経だ」という思いを禁じ得ません。
情報の誤り、不正確、説明不足、不用意な表現、そして拡大解釈。
だからこそ、私は思いました。この本はノンフィクションでも評伝でもないと。
もちろん、功績も多々あることは分かります。大野克夫さんや吉田建さん、そして木﨑賢治さんや大輪茂男さんのインタビューは貴重です。
大野さんが語る井上バンド離脱の背景には、深く得心するものがありました。
また早川タケジさんインタビューを始めビジュアル面の掘り下げ、そしてBL談義には、ページを大いに割いているだけあって著者の関心の強さと熱の入りようを大いに感じました。
この本をあえてジャンル分けするならエッセイでしょう。エッセイならいきなりBLを延々と語ろうとザ・タイガースよりPYGの、ショーケンの話が長かろうと自由です。「56年の光芒」とか言っときながら独立後は思い切り駆け足なのも自由です。
BLやショーケンで同じ話が何度も出て来るのも自由です。編年体でまとめず時間軸を行ったり来たりするのも自由です。YouTubeに上っている非公式の動画を延々と語るのも自由です。エッセイであるならば。
そしてジュリーを過去・完了の「いた」で語るのも自由です。少なくとも今現在も現役で自身の意志に基づいて活動を続けている人物の「評伝」ではありません。
更に。安井かずみの本を読んだ時も思いましたが、この著者は音楽に興味が無いのでしょう。前著でもZUZUと加藤和彦のセレブ生活を延々と滔々と描き続けていました。
今回もジュリーのビジュアル、BL的表現を延々と滔々と書き続け、一方で名前すら出て来ない音楽作品がどれだけあるか。
海外での展開も、下山淳・吉田建・村上"ポンタ"秀一が同時期にサポートしていた泉谷しげるのことも、20世紀の集大成としての『耒タルベキ素敵』のことも一切触れられていないのは、私には理解が出来ません。
そして著者は映画にも興味がないようです。
『カポネ大いに泣く』はショーケンと共演したことだけ何度も書きながら『炎の肖像』も『パリの哀愁』も『リボルバー』も『ヒルコ』も『カタクリ家の幸福』も全く出てきません。
舞台の話も『唐版 滝の白糸』はしつこく、ACTシリーズは多少触れてますが。
一方で久世光彦、マキノノゾミ作品が全く取り上げられない。
藤山直美さんとの共演もない。
ACTシリーズに触れながらCobaさんがジュリーに熱いリスペクトを捧げ続けていることも、全くノータッチ。
もちろん人間ですから得手不得手、既知未見はあります。しかし「ノンフィクション」を謳うならば知らないこと、興味のないことも能う限り掘り下げて、そして正確を期して書くべきではないでしょうか。
あれだけBLを情熱的に書くのであればなおの事。
好きな事、知っている事だけを深く掘り下げ、知識も興味もない分野には軽率な事実誤認が頻発するのでは「ノンフィクション」や「評伝」とは言えません。
『BLの源流 ジュリー伝説』とでも銘打ったエッセイ集にしとけば良かったんじゃないでしょうか。
この本にも名前が出て来る阿野冠『君だけに愛を』も1960年代のザ・タイガースファンの話なのに『色つきの女でいてくれよ』が出て来ました。「ジュリー以外の4人が同級生」とも。
ジュリーを「鳥取生まれの他国者」とも書いてました。それならばトッポも「大阪生まれの他国者」でしょうに。
何でその程度の事を調べてから書かないんでしょうか。
その程度の事が正確に書けていなければ、他も全てこんな程度かと思われるでしょうに。
少なくとも「自分に興味のある方面は熱心に書くが、興味がなければ杜撰な記述か全く触れない」というスタンスの書き手は「ノンフィクションライター」ではないと、私は思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
