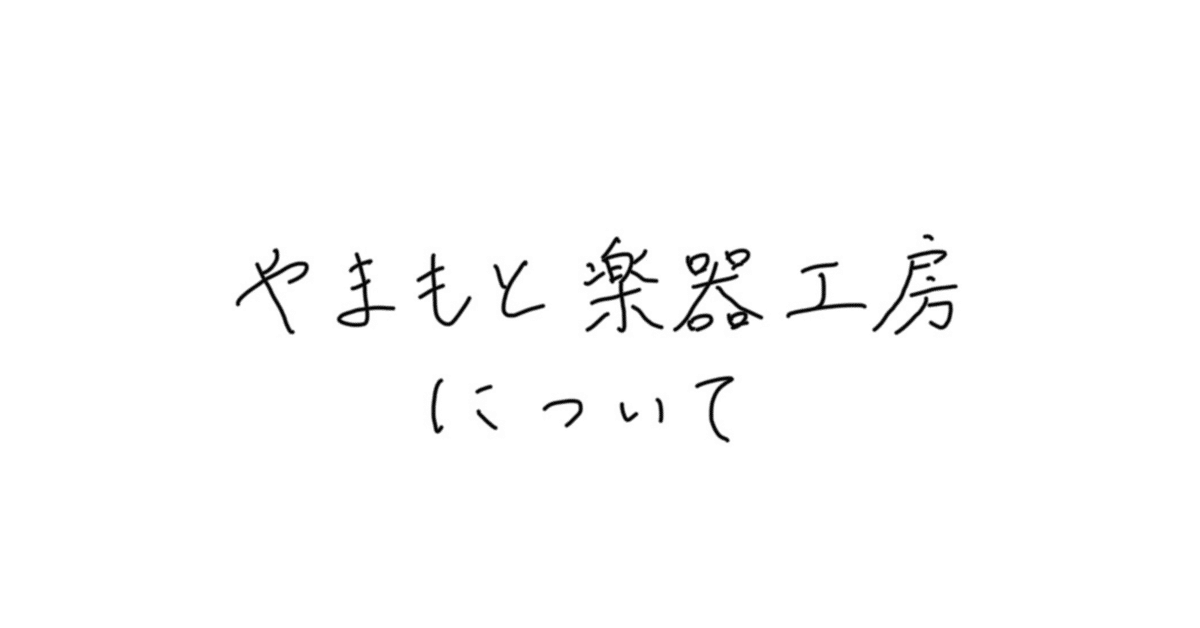
なぜ、やまもと楽器工房を立ち上げたのか。
こんにちは。
この記事では、やまもと楽器工房を立ち上げるきっかけと、活動内容について、ご説明させていただきます。
マレットとの出会い
小さいときから音楽と触れ合ってきたんですが、中学生になって吹奏楽部に入部し、その時初めて、「マレット」というものと真剣に向き合いました。
「叩くバチが変わるとこんなに音色が変わるのか」と、かなりの衝撃を受けたんです。
もちろん、小学生のときから木琴、鉄琴を叩くことはあって、そのバチの存在は知っていました。
ただ、吹奏楽部に入って、より日常的に音楽と、特に打楽器と深く向き合うことになって、マレットの種類の大切さを認識したことが、ブランド立ち上げの最初のきっかけだったと思います。
使うマレットで音が変わるということは、もちろん、同じ楽器でもメーカーやコンディションで劇的に音が変わるということです。
中には素晴らしい楽器を持っている学校もありますが、僕の入っていた吹奏楽部は、良い楽器もあれば、イマイチの楽器もある部でした。
良い楽器が無いと良い音は出せない、良い楽器とはいかずとも、最低限の状態が保たれた楽器じゃないと、良い演奏をしても音が伴わない、そういうジレンマを感じていました。
自分の演奏の実力が無いことを棚に上げて、そんなことを考えていた、ちょうどその頃に、打楽器の「師匠」と出会いました(別の機会に詳しくご紹介させてください)。
今もですが、本当にたくさんのことを師匠から教わりましたが、その中でも、
「楽器は自分で作れる」ということ、
これがやまもと楽器工房のものづくりの基礎となっています。
楽器は作れる。
当たり前のことなのですが、中学生・高校生の頃は、バチ類を含め、楽器は買わないといけないものと思っていました。
初めて、マレットを作ったときと、錆びまみれのシンバルを磨くと音が蘇ったときの感動は、今でも忘れられない経験です。
楽器を自分で作ることができるということは、目から鱗のような感覚で、この感動が、これから始める活動の基盤となってくれています。
シンバルの例を出しましたが、シンバルに限らず、どんな楽器も定期的なメンテナンスは必要ですよね。
どんな楽器でもちゃんと手入れをすれば、良い音は鳴るんです。
ティンパニや大太鼓を一回解体して、ヘッドを正しく張りなおすだけでも、音は格段に良くなるんです。
楽器を触る(メンテナンスという意味で)のが怖い人に、その楽器のあるべき状態、鳴るべき音をメンテナンスを通じて伝えていきたいと思います。
やまもと楽器工房は何をするのか?
やまもと楽器工房は、打楽器関連品の製作をメインの活動としますが、まずは打楽器のメンテナンスと、バチ・マレットのオーダーメイドと修理から始めていきます。
楽器を自分で作ることができるという感動をきっかけに、高校生の時から、バチやマレットを作るようになったのですが、ある時、兄が通っていた音大の打楽器科の先生に、僕の作ったマレットを何本か、試していただける機会がありました。
二人の有名な先生かつ素晴らしいプロのプレイヤーの方に実際に触って演奏していただいて、一人からはとても良い評価を、もう一人からは「もう少しこういう方が良い」という評価をいただきました。
一流のプレイヤーの方でも、同じマレットに対する意見が違ってくる。
この経験は本当に貴重で、演奏する上で、その人に合った楽器であることの大切さに気付きました。
それと同時に、自分の作ったマレットに対する自信も芽生え、「マレットのオーダーメイド」という可能性と必要性にも気付きました。
音楽に必要な音を出すためには、その音を出すための環境が必要だと考えています。
というのも、例えば、
ピアニッシモかつスタッカートでティンパニを叩くときは、ソフトマレットは多分使わないと思うんです。
極端に言えば、「〇〇の交響曲の○楽章の、この音」を叩くためだけのマレットがあっても良いのではないか、と考えています。
プロアマ関係なく、演奏する人に合ったマレット、特定の音を出すためのマレットなど、マレットに対する要望をできる限り叶えることが、やまもと楽器工房の最初の活動となります。
マレットの修理に関して、
部活でも個人の奏者さんでも、先が使えなくなったマレット、バケツとかに溜まっていませんか?
よく使うマレットほど、すぐにダメになってしまいますよね。
でもマレットも安くない、経済的な悩みの種です。
マレットも楽器で、消耗品ではありません。
楽器と同じで、手入れをすれば長い期間使えます。
巻かれているフェルトや糸がダメになったらまた巻き直せば良いんです。
もちろん、元のマレットとは別の用途にリメイクすることも可能です。
新しくマレットを買うのではなく、手に馴染んでマレットを修理して何回も使い続けてほしい。
たとえ値段が高いマレットじゃなかったとしても、叩き続けて手に馴染んだマレットは、愛着も安心感も与えてくれると思うんです。
マレットのオーダーメイドと修理。
これを通じて、皆さまのより良い音楽のためのお手伝いをさせてください。
音楽をするためには、お金がかかります。
しかも少額ではない金額です。
全部が全部ではないですが、やっぱり音楽は、お金に余裕がある人のものというイメージを持たれているように感じます。
金銭的な理由で演奏することを楽しめない、諦めないといけない人がいるなら、本来それはあってはならないことです。
部活であれば、マレットに使うお金を、他の楽器を買う資金に回してほしいですし、
個人の奏者さんには、少しでも経済的な負担を減らすことができたらと思っています。
料金も含めて、お金のことは別の記事にまとめますが、基本的に、やまもと楽器工房は、利益の最大化を目的としません。
活動目的は、音楽への貢献のみです。
なので、ほぼ材料費しかいただきません。
1人でも多くの人が音楽を楽しむことができるための環境や設備を整えること。
それが、やまもと楽器工房の使命だと考えています。
長くなってしまいましたが、やまもと楽器工房を立ち上げる決意をした理由は、
音楽への貢献をしたくて、多くの人に音楽を楽しんでほしいと思ったからです。
繰り返しになりますが、活動内容は、将来的には色んなことをしていけたらと計画しています。そして、まずは、
打楽器を演奏するための環境整備、特にマレットのオーダーメイドと修理から始めます。
近々、実際にどんなオーダーメイドと修理をして、ご依頼をいただくか、についてもご説明させていただきます。
皆さまの音楽に対する思いも、お聞かせください。
それでは、良いお年を!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
