
洋上風力の発電事業者の体制図において社名の有無が意味すること
「洋上風力ラウンド2の結果から見えてきた入札ルール変更の問題点」の記事に、興味深いご質問をいただきました。
ご質問:(発電事業者グループが経済産業省・国土交通省の審議会に提出した資料の中で、体制図にゼネコン名が入っていない理由として、)実は決まっているけど諸々の事情であえて書けなかった、という可能性は考えられませんか?
つまり、「入札資料にはゼネコン名を載せられても、公開資料だから載せられないだけでは?」という疑問ですね。この疑問にお答えしようとすると、さらなる疑問が湧きます。
4海域のうち、2海域のグループは、審議会に提出した資料にゼネコン名を載せていて、他の2海域のグループは載せていません。さらなる疑問とは、「ゼネコン名を載せられるグループと載せられないグループの差は何か?」ということです。
この2つの疑問にお答えすることで、洋上風力発電の業界構造を知っていただくことになるので、今回は、その回答を記事にさせていただきます。
洋上風力発電の業界構造
まずは洋上風力の調達体制を見てみましょう。下図は、洋上風力の調達・建設の体制図の例です。

例と書いたのは、必ずしもこの通りになるというわけではなく、発電事業者によって変わるためです。発電事業者の調達能力や信用力が高ければ、直接発注先(上図の2階層目)が増え、調達能力や信用力が低ければゼネコン丸投げに近くなり、サブコン(上図の3階層目)が増えます。
いずれにせよ、発電事業者から見て、直接的・間接的にも、これだけの発注先が要るということになります。
その一方で、プレイヤーの数は、発電事業者が多く、風車メーカー、ゼネコン、海底ケーブルメーカーなどは、ほんの数社しかありません。つまり、プレイヤーの数の分布は、上図に反して逆三角形になります。
そうなると何が起きるか?
このような業界構造において、洋上風力の公募締め切りまでに何が起きるでしょうか。風車メーカーやゼネコンには、同じ海域の複数の事業者グループから検討依頼が舞い込みます。しかし、風車メーカーやゼネコンのほうが数は少ないのですから、全ての検討依頼に付き合いきれません。
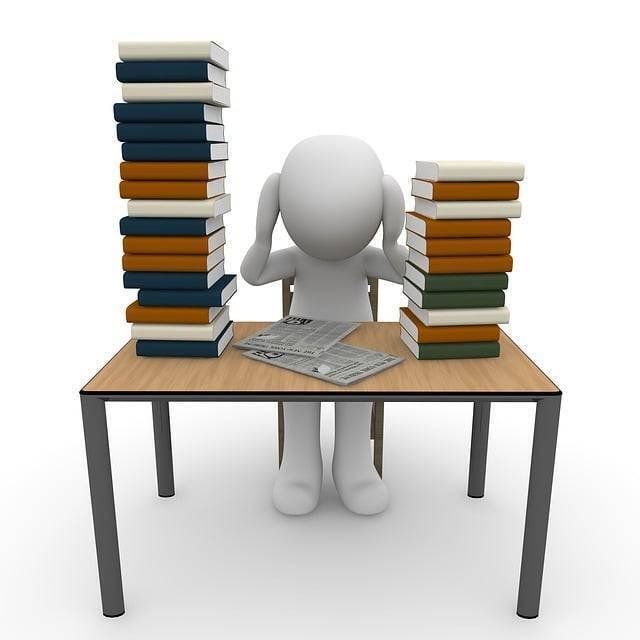
陸上風力では、開発がほぼ確定した頃に、発電事業者は風車メーカーやゼネコンと、設計や建設検討のための先行作業契約(Early Works Agreement)を結びます。先行作業契約は、設計や建設計画などのソフト業務です。しかし、風車メーカーは製造・販売、ゼネコンは建設というハード業務で儲けるビジネスです。彼らのビジネスは、ソフト業務で儲ける体制になっていないので、ソフト業務はできるだけ受けたくないはずです。
その一方、洋上風力(一般海域)には、公募があります。公募前の発電事業者は、風車メーカーやゼネコンにとって、大半が客ではなく見込み客です。公募に勝ってハード業務を下さるのが風車メーカーやゼネコンの本当のお客様であって、公募前のソフト検討だけのお付き合いに終わる大半の発電事業者は見込み客でしかありません。
ここに、風車メーカーやゼネコンのジレンマがあります。
本当のお客様とだけ先行作業契約を結びたい=大半が負けるとわかっている見込み客のすべてと先行作業契約する余裕はない
本当のお客様がだれになるのか、公募の結果が出るまでわからない

こういった状況で、風車メーカーやゼネコンは、どのように発言事業者と付き合うことになるのでしょうか。ここからは、風力業界の中の人の個人的な見解をお示しします。
風力業界の中の人の見解
もし風力業界の中の人が風車メーカーやゼネコンの中の人だったら、「確度の高い発電事業者グループとしか先行作業契約を結ばない」と思います。そのためには、風車メーカーにせよ、ゼネコンにせよ、発電事業者グループとの打ち合わせを通じて、各グループの実力を見定めているはずです。

実力の低いグループから先行作業契約を依頼されても、「公募の結果が出てから」と逃げ続け、無償のお付き合いレベルの対応しかしないでしょう。
風力業界の中の人から見れば、発電事業者グループの実力には、大学生レベルから小学生レベルぐらいまでの差があります。小学生グループと先行作業契約をしてしまったら、確実にひらがな・カタカナ・足し算・引き算から教える羽目になります。

いくら「岩盤だからジャケット基礎ではなくモノパイル基礎で」と先生が言っていても、「フランスで使えるんだから日本でも使うのー」とダダをこねる小学生がいます。「フランスか日本かではなく、どういう地盤なのか調査するのが先でしょ?」とか、「フランスに地震はないけど、日本には地震があるでしょ?日本では地震に耐えられるように設計しなきゃいけないの?わかるかな?」と諭しているうちに、学級崩壊しかねません。
そういう小学生グループと先行作業契約をしたい風車メーカーやゼネコンがいるでしょうか。
風力業界の中の人には、「ゼネコン名を載せられるグループと載せられないグループの差」は「そのグループがゼネコンからどう見られているか」を暗示しているように見えるのです。
ここで、ようやく元のご質問にお答えすることができます。(発電事業者グループが経済産業省・国土交通省の審議会に提出した資料の中で、体制図にゼネコン名が入っていない理由として、)実は決まっているけど諸々の事情であえて書けなかった、という可能性はあります。
その背景として、風力業界の中の人が考えられることは、「その事業者グループが公募前からこのゼネコンにしたいと思っていても、ゼネコンにとってはそうではなかった」、つまり「事業者グループからゼネコンへの片想いだった」ということです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
