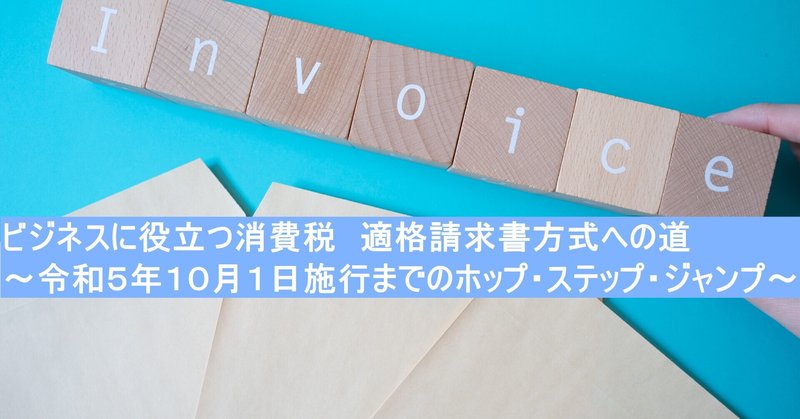
令和3年4月1日から総額表示に~その1~
令和3年3月31日,消費税の総額表示の時限措置が失効しました。
総額表示は,今から遡ること約19年前の平成14年6月の税制調査会の「あるべき税制の構築に向けた基本方針」の中で,今後の改革の方向として,消費税の「信頼性,透明性の向上に向けた改革」の1つとして,消費者に対する価格表示のあり方について「消費者の便宜を図る観点から積極的に検討されるべきである。ヨーロッパ諸国と同様,今後,消費者保護行政等の中で早急に具体化が図られるよう,関係機関において適切に対応していく必要がある。」とされ,その後の中間整理,答申を経て,平成15年度税制改正において,次のように規定されました。現行法は63条です。
(価格の表示)
第63条の2 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等(第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同じ。)を行う場合(専ら他の事業者に課税資産の譲渡等を行う場合を除く。)において、あらかじめ課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の価格を表示するときは、当該資産又は役務に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければならない。
要するに,不特定多数の者に価格表示をするときは,消費税等相当額を含めた総額表示にしなさいということです。
通常,税法の年度改正は3月中に改正法案が国会審議をへて可決・成立すると,附則で同年の4月1日から施行となるのですが,一部の規定については附則で施行日が別途規定される場合があります。上記63条の2についても,施行日は平成16年4月1日とされ(平成15年3月31日附則1条8号ニ),同日から一旦,総額表示がされるようになりました。
そもそも「消費者の便宜」ってどういうことなのでしょうか。
消費税法の施行以来,消費者が商品やサービスを購入する場合には,その商品やサービス本体の価格に加え,消費税を支払う必要があります。こんなことは幼稚園児でも知っています。
ただ,その商品やサービスを購入する際,レジで請求されるまで最終的にいくらお店に支払えばいいのか分かりにくいとか,A店では税抜価格表示なのに,B店では税込価格表示だと消費者が価格の比較をしづらいといった状況が問題視されました。
この状況を解消するために,消費者が値札やポップ広告をみただけで,消費税相当額を含む支払総額が一目で分かるように「総額表示」を義務付けようと考えたのです(財務省「消費税における「総額表示方式」の概要とその特例」参照)。
私から言わせると,総額表示方式になると,今後税率が上がっても,価格が上がったのか,税率が上がったのか,消費者(消費税負担者)が判断しづらくさせようとか,消費者がいくら消費税を支払っているのかわからないようにしてしまおうという課税・徴税側の魂胆としか考えられないのですが,まぁ,理由は何とでもつけられるものです。
これについては,以下で述べるように,税率引上げの前後は純額表示も認められていたという反論もありそうですが,「納税者の便宜」というより,「事業者の便宜」からの事情と思われます。
さて,さきほど「一旦,総額表示」と書きました。
施行当時の消費税率は5%でした。
その後,しばらく総額表示がされていたのですが,消費税が平成26年4月1日から8%,平成27年10月1日から10%(一部は8%)に段階的に引き上げられることになりました(「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改悪を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」(平成24年法律第68号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改悪を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する等の法律」(平成24年法律第69号))。
この過程で,事業者の事務負担等に配慮する観点から,「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(消費税転嫁対策特別措置法)で,特例措置として,「事業者は・・・消費税の円滑かつ適正な転嫁のため必要があるときは,現に表示する価格が税込価格(略)であると誤認されないための措置を講じているときに限り・・・税込価格を表示することを要しない」とされたのです。この特例は,消費税率引上げ前後の期間(当初は平成25年10月1日から平成29年3月31日まで)限りの時限措置として設けられました。
その後,皆様もご存知のとおり,消費税率10%への引上げが平成29年4月1日まで1年半延長され,さらに,同引上げが平成31年10月1日まで2年半再延長されました。これに伴い,総額表示に係る特別措置の失効期限も平成30年9月30日まで延長,平成33年(令和3年)3月31日まで再延長されていました。
このように重ねての延長の経緯があったものですから,事業者の中には,総額表示だけはまた延長されるのではないかという淡い期待もあったようですが,延長されることなく令和3年4月1日から施行されました。
もし,まだ,対応されていないという事業者の方がいらっしゃいましたら,違法ですから,至急対応してくださいね。
ただし,対象となる表示は限定されています。これについては次回,条文を詳細に検討していきますので,気になる方は続きもご高覧くださいませ。
なお,実は,「税込価格」「税抜価格」,あるいは「内税方式」「外税方式」は,消費税の計算に大きく影響するのですが,この話はいずれしますので,今回は,とりあえず,平成15年度税制改正により一定の課税資産の譲渡等について総額表示が義務付けられ,税率引上げに伴い,時限措置により純額表示が認められていた期間もありますが,令和3年4月1日から再度総額表示となったことを確認しておきます。
コンテンツをご覧いただき、誠にありがとうございます。頂いたサポートを励みに、有益な情報発信に努めてまいります。今後とも宜しくお願い申し上げます。
