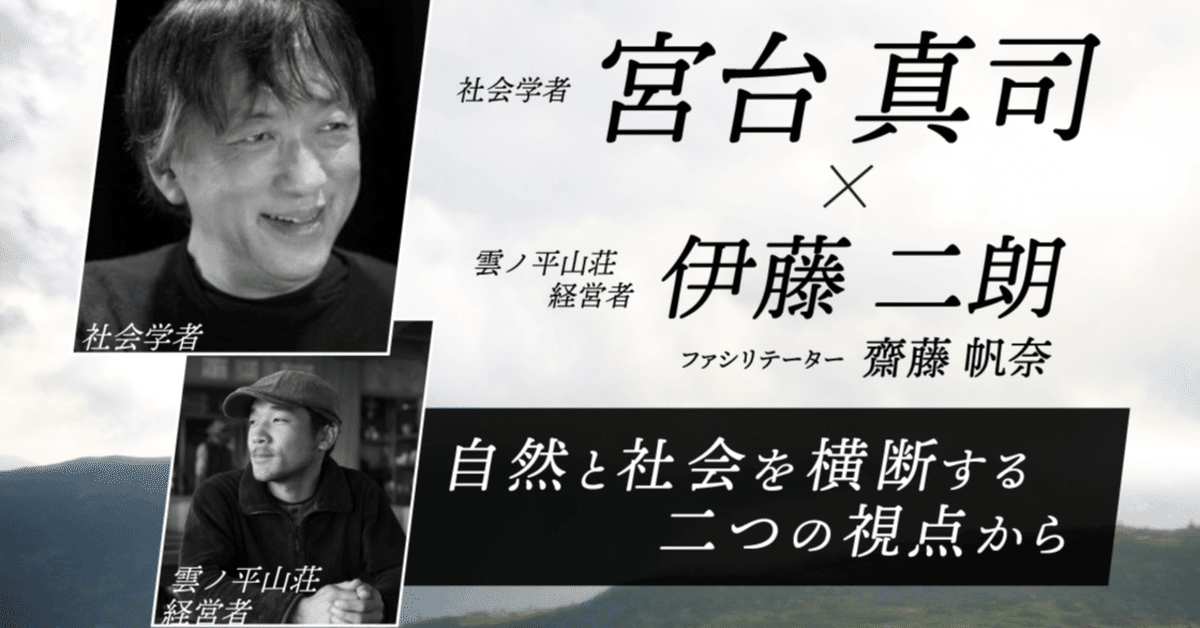
備忘録 宮台真司「〈社会〉を貫徹する〈世界〉について」
宮台真司×伊藤二朗 -自然と社会を横断する二つの視点から-(2022年4月24日)より要点を抜粋。

※以下の文章は宮台真司による解説の必要箇所を抜き出して要点としてまとめたもので、宮台真司の語りをそのまま書き起こしたものではありません。
ピュシスとノモス
産業革命以降の「自然」の概念は、人類史上、非常に特殊なもので、歴史的に言えばデタラメである。ギリシャ哲学のもともとの概念「ピュシス」は「自然」と訳されているが、これは間違いで、本来ピュシスは「万物」という意味であり、フィジックスは自然学ではなく「万物学」なのである。
僕(宮台真司)の書籍には〈世界〉と〈社会〉という概念装置がよく使われているが、〈世界〉とは「ありとあらゆる全体」の意味で、これがピュシスなのである。それに対して〈社会〉というのは「コミュニケーション可能なものの全体」で、ギリシャでいえば「ノモス」にあたる。ギリシャの発想では〈世界〉のなかに〈社会〉がある。つまりピュシスの中にノモスがあって、ノモスも、実はピュシスなのである。ここが大事なポイント。
ところが産業革命とほぼ平行して19世紀ちょっと前ぐらいから散発的に広がっていくロマン主義の動きがあり、ドイツが民族的なロマン主義、フランスが性愛的なロマン主義の本場となる。このロマン主義はギリシャと違って〈社会〉の外を〈世界〉と呼ぶ。つまり、我々は社会に閉ざされているから、その外にある峻厳な山々や疾風怒涛の海原に直面することで〈閉ざされ〉の外に〈開かれ〉るのだ、と。これがロマン主義的な発想なのだが、ギリシャ時代から見ると実はこれは頽落、つまり一段階レベルが下がって劣化deteriorateしているのである。
どこが劣化しているかと言えば、ギリシャ悲劇を見て判るように、ギリシャの場合、〈社会〉を〈世界〉が貫徹している。〈世界〉というのは実は「未規定な全体」で、我々から見るとカオスに見える。それに対してノモス、これには「法」という訳があるように、我々に規定可能なものだと思えるものなのだが、実はソポクレスの『アンティゴネ』や『オイディプス王』の劇のように、〈社会〉も〈世界〉と同等にデタラメで、不吉な予言を避けようとして却って予言が実現してしまうことが典型的なのだが、〈社会〉も〈世界〉であり、ノモスもピュシスなのである。
たとえばフィジカルphysicalを物理的あるいは身体的と訳すことがあるが、これもピュシス的なのであり、「万物的」の意味である。つまり我々の身体も「万物的」なのであり、それは他の動物、植物、菌類などと同じように遺伝子の複製によって個体も種も維持してきている。要するに社会の外に自然があるとする発想はごく最近のもので、人間の感受性の働きとしては劣化したものであり、社会の中に閉ざされることが当たり前になった人たちの感受性だということになる。
テレオノミーとランナウェイ
僕(宮台)の師匠の一人、故見田宗介の重要な概念を紹介する。見田の著作『自我の起源(1993)』は、自我、エゴ、これは「自己現象」の意だが、この自我の起源、自己現象の起源は何だろうかというもので、そのキーワードに「テレオノミー」と「ランナウェイ」の2つがある。
テレオノミーはテレオロジー(目的論、つまり人の営み)とは異なり、自然現象に見られる、一見すると目的論にも見えるものだが、しかし、徹底的な因果性のことを言っているのである。
「セントラル・ドグマ」という概念がある。リチャード・ドーキンス(進化生物学者1941~)による今や誰一人反対する人のいない遺伝子中心主義の概念である。遺伝子の乗り物としての原核細胞生物、の乗り物としての真核細胞生物、の乗り物としての多細胞生物(個体)、の乗り物としての個体集団があり、より性能の良い乗り物に乗った遺伝子が生き残る。第三者的にはあたかも遺伝子が生き残るための目的論が存在するようにも見えるのだが、実際にはたまたま良い乗り物に乗ったものが生き残るという条件プログラムしかないので、目的論は存在しない。これが我々生きとし生けるもの、自己複製的な万物のすべてが持っている性質なのである。
次に「ランナウェイ」であるが、マンモスが滅びたのは牙が大き過ぎたからで、同様に孔雀の飾り羽根も大き過ぎて保護しなければ死滅してしまう。なぜこのようなことが起きたのかと言えば、大きな飾り羽根を持っているオスはその分栄養が行き渡っていて、個体、つまり乗り物としての性質が高いので、メスはより飾り羽根の大きく美しいオスを選ぶという性選択を行う。斑紋が一個多いだけでメスはそのオスを選ぶという。その結果、何が起きたかと言えば、この性選択が「暴走(ランナウェイ)」して、最終的には自然選択に逆らうような方向性を持つに至るのである。
(※ランナウェイには「駆け落ち」の意もある)
自己現象としての「自我」もこれと同じなのだというのが見田宗介が提起している問題である。我々の身体には自己現象が宿る。自己現象が宿った方がおそらく遺伝子の生存確率が高くなったからで、乗り物としての性質がより高くなったから自己現象が宿る身体が残ったのである。しかし、その自己現象がランナウェイし、その一環として個体集団における暴走も起きる。例えば人類を死滅させる核ボタンを押せるような事態が起きているのがそれである。
自己現象を「裂開」することの享楽
さて、見田宗介が『自我の起源』の最後、辛うじて希望を託せる部分として述べていたものがある。自己現象はある種の〈閉ざされ〉によって暴走するのだが、この自己現象を「裂開」、つまり切り裂くような、あるいはdiffuse(開放)するような様々な契機、モメントというものがあり、その典型的なものが「性愛」であると彼は言うのだ。
花に吸い寄せられるミツバチは能動的なのだろうか。そうではなく、おそらく花の美しさの享楽に惹かれて蜜を吸いにいく。性愛においても同様なことが生じる。自己現象は「選ぶ・選ばれる、する・される」といった能動・受動のことなのだが、性愛はその自己現象を裂開して、気がついたら吸引されている。そのことによって巨大な「享楽」を感じることがあるのである。
性愛のみならず先述の万物的なもの、本来そうであり得たかも知れないもの、未規定なもののすべてに〈開かれ〉ることは、我々の身体にとって享楽となるのである。このことは「同じ世界に入る」ことの享楽であると言ってもよい。同じフローに乗ることで一つのアメーバになる。生態心理学の概念を使えば、周辺の事物や身体に同じようにアフォードされる経験である。
アフォーダンス affordanceとは、知覚心理学者ジェームズ・ジェローム・ギブソン(1904~1979)によって提起された有名な概念で、例えば山道を歩いていたら疲れてきたので岩に座るという、自己現象を中心に記述する出来事が、実際に起きているのはそうではなく、他の動物たちにも起こることと同じであるが、ある心身の状態にあると岩が「座れ」とコールしてくる。それに自動的、オートマティックにレスポンスすることで、気が付くと座っているのである。そこには選択も能動もない。
気が付いたら誘ってしまっている、気が付いたらそれに応じて身体が動いてしまっている、このような自動的、あるいは中道的なcall&responseが人間に最大の享楽を与えるのである。自己現象の内側で、あれよりもこれが良いという選択の背後にあるのは「快楽」であり、それに対して、気が付いたらこうしているという中で生じる快楽が「享楽」である。
自我という自己現象を「裂開」するような契機は、文明化あるいは産業化して以降も本当は我々の周囲に溢れかえっていた。それはお祭りであったり、恋愛であったり、子供時代の外遊びであったり、いろいろな経験があったのだが、この30~40年、突然、中国を含めて全世界的にそれが〈閉ざされ〉てきた。自己現象、すなわち能動と受動しかなくなり、自動あるいは中道がなくなった。
パッション、受苦としての情熱愛
我々が言う愛(ラブ)とは、もともとラブ・アズ・パッション、つまり「受苦としての情熱愛」であり、パッションとは「受苦」、苦しみを負うという意味である。パッションフルーツは情熱フルーツではなく、果実の付け根が十字架の模様に見えるからで、十字架は受難である。パッションはギリシャ語のパトスに由来し、「上から降ってくるもの」である。天変地異も降ってくる。運命的も降ってくる。感情、欲望、情熱も降ってくる。この降ってくるものに自動的にレスポンスすることが、万物としての人間の心身の大きな特徴なのである。だから、パッションは、従って「受苦としての情熱愛」と僕(宮台)は訳す。
この受苦が享楽なのである。自然の中で脅かされたり、自然によって「裂開」されることが人間にとっては享楽である。たとえ死ぬかも知れないとしても享楽なのである。ところが、この悦びを知らないまま、自然は危険であるとか、恋愛の被害者になることを心配するとか、自然によって脅かされるかも知れないと危ぶむとか、悦びを知らない、そのような経験をしたことのない者たちに、危険や不安を教えるだけであれば、今日のように感情が劣化してくるのも当然である。
このような劣化した感情の状態を放置して動かさないままでいては、何をやっても無駄である。僕はさまざまなワークショップを通して経験的にそれを知っているのだが、この基本的なベースが変わらない人間が、知的に何をどう理解しようとも、それに悦びを感じることがなければ、また、いかなるモデル学習の経験を通じても、それが悦びであることを知らない人間に対しては、何を言っても、100%、無駄である。
生きものとしての「場」
「人間中心主義の非人間性」VS.「脱人間中心主義の人間性」の問題がある。人間中心主義がなぜ非人間的なのかと言えば、人間は安心・安全・便利・快適を求める。単純に言えば、快・得を求める。そうすると人は尊厳なき入替可能な存在になり下がるのである。逆に先に述べたパッション、〈世界〉から侵入され、「裂開」され、それゆえ快・不快であるなら不快、当座の幸・不幸であるならば不幸、そうしたものを経験することによってのみ尊厳を回復、あるいは醸成できる。これは人間のもともと持っているゲノム的な性能だと思われる。
※パッションはパッシブ(受動的)、と同じ語源である。
「人間中心主義の非人間性」と「脱人間中心主義の人間性」は、概念としてはもともとのギリシャのピュシスにもあるとも言えるし、人文学の歴史からいえば70年代に「空間ではなく場所、スペースではなくプレイスが大事」と言った中国系アメリカ人の地理学者、イーフー・トゥワン(1930~)、そして80年代から90年代にかけて日本の京都学派、特に西田幾多郎と田辺元の影響を強く受けた環境倫理学者ベアード・キャリコット(1941~)がいる。キャリコットは僕(宮台)にとって町づくりに関わる際の理論的バックボーンとさえなっている。
「場」から切り離されれば人間は尊厳を失う。「場」とは、我々がそれを「場」と呼ぶ時のふんわりとした全体性のことを言うのだが、キャリコットは「場」全体を一つの生き物とみなす。人は、動植物や岩石や河川と同じく、「場」という生き物の単なる部品なのである。この生き物としての「場」は人間の人生、人間のライフスパンよりずっと尺度が長い。従って人間の快・不快、つまり人間中心主義的なものさしで「場」をいじると、生き物としての「場」の全体性はズタズタになって、その結果、「場」によって保たれる人間の尊厳は自動的に破壊される。これが「人間中心主義」が人間の尊厳を破壊するという理論的なバックボーンである。この考えは町づくりにも援用され得るし、括弧付きではあるが自然保護にも援用可能である。
※注:ベアード・キャリコットの「場」についての説明は、宮台真司が新国立競技場について寄稿した東京新聞の記事(2013)を参考に加筆しました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
