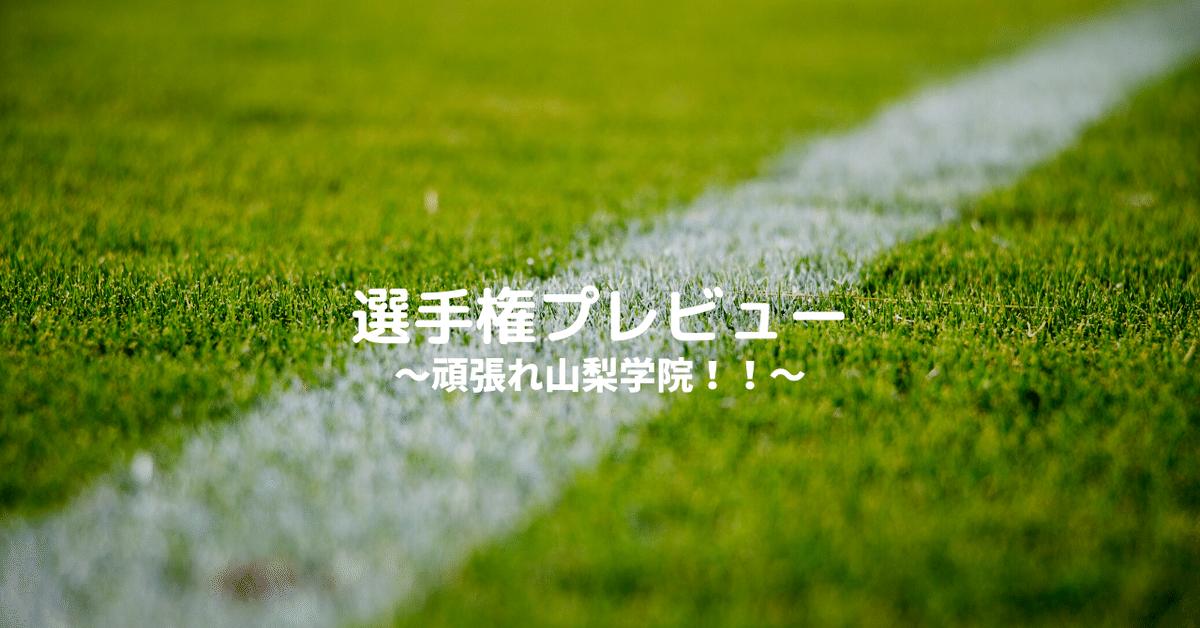
選手権プレビュー
第100回大会となる今年度の高校サッカー選手権大会。
山梨県の代表、山梨学院高校の初戦について書いてみた。
1.学校紹介
山梨学院
山梨県甲府市にある私立の中高一貫校。
創立は1956年、生徒数は1049人の学校となる。
サッカー部の創部は1969年、現在は129人の部員を抱えている。
☆全国大会成績
・全国高校サッカー選手権出場8回
最高成績 優勝(88回大会、99回大会)
・インターハイ出場5回
最高成績 優勝(2018年度)
☆主なOB
岡西宏祐(ヴァンフォーレ甲府)
白崎凌兵(サガン鳥栖)
渡辺剛(FC東京)
前田大然(横浜F・マリノス)
宮崎純真(ヴァンフォーレ甲府)*平成30年度全国高校総体優勝
佐賀東
佐賀県佐賀市にある公立の高等学校。
創立は1963年、生徒数は556人の学校となる。
サッカー部の創部は1963年、現在は114人の部員を抱えている。
☆全国大会成績
・全国高校サッカー選手権出場12回
最高成績 ベスト16(95回大会)
・インターハイ出場15回
最高成績 ベスト4(2008年度、2009年度)
☆主なOB
中原秀人(鹿児島ユナイテッドFC)
赤崎秀平(ベガルタ仙台)
中野嘉大(サガン鳥栖)
平秀斗(福島ユナイテッドFC)
平河悠(山梨学院大学)*FC町田ゼルビア内定
2.今季成績
山梨学院
・県下高校サッカー新人大会 優勝
・県高校総体サッカー大会 優勝
・関東高校サッカー大会Aグループ 1回戦敗退
・全国高校総体サッカー競技大会県予選 ベスト8
・プリンスリーグ関東 10位
佐賀東
・県下高校サッカー新人大会 ベスト4(途中中断?)
・九州高校サッカー新人大会 準優勝
・全国高校総体サッカー競技大会県予選 優勝
・全国高校総体サッカー競技大会(インターハイ) 1回戦敗退
・県リーグ1部 優勝
3.勝ち上がり
山梨学院

3回戦から登場した山梨学院。
初戦の笛吹高校を5−0と快勝を収めるとここから山梨のサッカー界を牽引してきたチームとの対戦が続く。
まずは準々決勝で10度の選手権出場を誇る帝京第三を迎える。
共にスコアは動かず、PK戦に突入するが勝ちきり準優勝へと進む。
次の相手は3大会前にベスト8に進出した日本航空。
3−0と快勝を収め、2大会連続の決勝進出を決める。
決勝の相手は県内最多の34度選手権に出場している名門韮崎。
13大会ぶりの選手権出場が掛かる韮崎との一戦はスコアが動かず延長へ。
延長後半に韮崎が先制し、万事休すかに思われたが同点に追いつきPK戦の末に優勝を決めた。
佐賀東

2回戦から登場した佐賀東。
初戦の相手となった佐賀工業に6−0の快勝を収める。
3回戦は鳥栖工業には9−1と2試合続けて攻撃陣の爆発で準々決勝へと進出する。
準々決勝は9回の選手権出場を誇る佐賀学園との一戦。
こちらも攻撃陣の活躍もあり、12−0の大勝を収める。
準決勝は龍谷に1−0と接戦を物にして決勝進出を決める。
決勝の相手は県内最多13度選手権に出場している佐賀商業との名門対決。
立ち上がりに先手を取られた佐賀東が追いかける展開となる。
主導権を握る時間は多くあるが、決めきれず敗戦もちらつき始めた後半終了間際に追いつき延長戦へ突入する。
延長に入るとすぐに逆転に成功し、この1点を守りきり2年連続の優勝を決めた。
4.基本布陣

山梨学院
県大会決勝のメンバーからボランチに石川選手、前線に大島選手と怪我を抱えていた選手の復帰の可能性もある。
佐賀東
県大会決勝で後半から右SBの牧瀬選手に代えて坂本選手を投入して流れを変えただけにスタートから変更してくる可能性もあるのではないか。
5.注目選手
山梨学院
5.柴田元
圧倒的な空中戦の強さを誇るCB。
地上戦でも自慢のフィジカルを活かし、ゴール前の壁として君臨する。
足元の器用さも併せ持っており、ビルドアップにも貢献できる選手である。
セットプレー時には得点源ともなれるだけに攻守共に目が離せない。
昨年の一瀬太寿、板倉健太のように選手権で活躍し、大学サッカーで一年生ながら活躍しているような軌跡を辿れるか注目だ。
将来的にはOBの渡辺剛のように日本を代表するCBになる可能性を秘めた選手ではないか。
6.谷口航大
昨年の優勝メンバーは今年キャプテンとしてチームを牽引。
中盤でハードワークをこなしながら相手の攻撃の芽を潰し、前線に駆け上がり得点にも絡める万能型のボランチとなる。
前回大会の決勝、今大会の県予選決勝で優勝を決めるPKを決めたようにメンタルも強い選手。
守備的な役回りでは全国トップクラスの力は持っているだけに攻撃面で違いが作れる選手となれれば大学サッカーでも活躍し、将来的なプロ入りも期待できる。
9.茂木秀人イファイン
前回大会優勝した山梨学院において唯一悔しい思いをした選手。
青森山田との決勝戦で外した決定機は今でも悔いが残っているのではないか。
フィジカルを活かした力強い突破が持ち味となる。
夏には先輩の広澤灯喜も所属しているポルティモネンセに練習参加。
昨年同様に決定力には課題を残しているが、きっかけ一つで大きく飛躍するポテンシャルを秘めている。
前回大会の悔しさは同じ舞台でしか晴らせない。
決勝戦に置いてきた忘れ物を取りに戻りたい。
佐賀東
3.宝納拓斗
左利きのCBでフィードが得意なタイプ。
佐賀東のポゼッションサッカーの起点となる選手。
安定した足元の技術だけでなく、守備者としても落ち着いた対応を見せるクレバーさを兼ね備えている。
2年生ということもあり、今大会の活躍次第では来年の注目株に一気に躍り出る可能性を秘めている。
直接Jリーグ入りも期待できる逸材だ。
10.吉田陣平
アルビレックス新潟内定の選手。
昨年は2年生ながら高校選抜入りを勝ち取り、今年の注目選手でもあった。
ボランチを中心に中盤ならどこでもこなせる器用さを持った選手だが、最大の特徴はドリブルにある。
安定した技術力を備え、ドリブルだけでなくパスやシュートの質も高い。
来シーズン新潟で試合に絡んでいてもおかしくない実力者であるだけに名前を覚えていて損は無いだろう。
15.小嶋悠央
フィジカルの強さを活かし、前線で起点となるポストプレイヤー。
チームのために身体を張り、味方を活かすプレーだけでなく守備の献身性も備えている。
その上で県予選では5試合で8ゴールと決定力もあるストライカーとなる。
佐賀東のサッカーでは前線の選手は小柄なテクニシャンが活きやすいが、小嶋選手の強さは良いアクセントとなっている。
前回王者相手に得点を決めるようだと注目度は高まるだろう。
6.注目ポイント
佐賀東は足元のテクニックに長けた選手が多く、ボールを大事に繋ぐチームである。
DFラインから丁寧にビルドアップしながら前進を試みていくが、前線の小嶋選手の高さという逃げ道があることも特徴となる。
相手にハイプレスを掛けられ、繋げない状況となっても小嶋選手をシンプルに使うことで前線にボールを運んでいくことが可能となる。
ポゼッション時に中心となるのは宝納選手と吉田選手。
宝納選手の左足からは正確なロングボールが配球され、DFラインの背後やサイドチェンジから局面を大きく動かすことができる。
また、ビルドアップ時にも正確に縦パスを通してくるため宝納選手が自由にボールを持てるようだと佐賀東はチャンスを作っていくだろう。
山梨学院としては前線の選手の献身的な守備は必要不可欠となる。
昨年の決勝で青森山田の藤原優大にマンツーマンを付けたような対応を見せる可能性はある。
だが、宝納選手を警戒しすぎて吉田選手を空けてしまうことは避けなくてはいけない。
吉田選手は前線にラストパスを配球できるだけでなく、中央からドリブルで前進できる選手である。
それだけに遅れて対応に行かざるを得ない状況となると止めるのは容易ではない。
中盤での谷口選手との攻防はこの試合のキーポイントとなるだろう。
前線にボールを運ぶとサイドからの崩しを狙う。
左右で崩しの形に違いが見られる。
右サイドでは森田選手とSBの選手によるコンビネーションからの崩しを狙う。
森田選手はインサイドでも外に張ってもドリブルでの仕掛けやパスからチャンスを演出できる選手なだけに右サイドのコンビネーションは警戒が必要となる。
一方で左サイドでは中山選手の単独での突破が武器となる。
シンプルに一対一で剥がせる選手なだけに簡単に突破は許したくない。
両サイド共にSBは高い位置を取るため、厚みのある攻撃を仕掛けていく。
ボールを失った佐賀東はすぐに奪い返しに圧力を掛けていく。
ボール付近に密集を作り、高い位置で奪い返し再びゴールに迫っていくことを狙うため、安易に繋ごうとすると奪われピンチを招きかねない。
ボール保持時の佐賀東は2CBを残し、敵陣に人数を掛けて厚みのある攻めを見せるため奪い返しに行く際も人数を掛けてボールに圧力を掛けられる一方で、背後には広大なスペースが用意されている。
そのため、奪ったボールをシンプルに蹴り込み前線の選手を走らせスペースで起点を作ることは有効となる。
特に県大会の決勝で多く見られたのが右SBの裏を突かれる場面。
前半は牧瀬選手、後半は坂本選手が右SBを務めていたがいずれの選手も背後を突かれる場面が見られた。
これは左サイドに比べて右サイドは攻撃時にコンビネーションでの崩しを狙うことも関係している。
茂木選手を佐賀東の右SBの背後へ走らせ、CBの石橋選手と一対一の形を多く作りたい。
また、ボールを相手に持たれる時間を佐賀東は少なくしたいため、引いて構える時間は多くはない。
そのため、基本的には背後を突けるかがポイントとなる。
茂木選手の裏抜けと小島選手の高さを活かしたポストプレーで前線に起点を作り、佐賀東陣内でプレーする時間を多くしたい。
山梨学院は昨年の大会でも見られたが、セットプレーに強みを持つチームでもある。
ロングスローは今年も健在であり、県大会でもチャンスを作っていた。
佐賀東は全体的に高さのある選手が少ないだけにセットプレーは狙い目となるだろう。
佐賀東のセットプレーの守備はマンツーマン。
180cm越えの選手の数は佐賀東の方が県大会決勝のメンバーでは多いが、175cm以上となると山梨学院の方が多いためミスマッチが生じる箇所は生まれてくる。
また、控えにも190cm近い小林士恩選手も入ってくることが予想されるため、得点が欲しい局面で高さを活かしていくことも多くなるだろう。
DFラインの背後と高さを徹底的に突くことで山梨学院としては優位に立ちたい。
一方の佐賀東は山梨学院の強度の高い守備を掻い潜って持ち前のテクニックを発揮できるか。
お互いの持ち味を最大限に発揮できた方が勝利に近づくだろう。
7.あとがき
前回大会優勝チームとして100回大会を迎える山梨学院。
初戦の佐賀東に始まり、同じブロックには東福岡や大津、前橋育英といった名門校も名を連ねる厳しいブロックに入った。
佐賀東とは3月にサニックス杯で対戦し、1−3で敗れている。
今年1年、なかなか勝てない時期も続き厳しい1年だったと思うが最後に花を咲かせて欲しい。
佐賀東は県大会決勝1試合のみ配信で観戦したが、非常に魅力的なチームである。
チームとしてのスタイルから選手個々にまで見る価値がある。
高校選抜の監督を務めるだけの監督であるなと感じた。
先日観戦したインカレでの鹿屋体育大学のように九州には魅力的なチームはたくさんあるのだなと感じている。
山梨を飛び出していろいろな地に観戦に訪れたいと実感させられた。
100回の記念大会ということもあり、観戦を楽しみにしていたがまたも新たな変異株の出現もあり今回も観戦を控えることに決めた。
このウイルスに振り回されて2年あまり。
来年こそは自由に、以前までのような生活に戻れることを願っている。
引き続き、新戦力紹介は続けて行こうと思いますがこの記事が本格的に書くものとしては今年最後になる予定です。
年末年始も皆様の健康を願っています。
1年間お世話になりました。
来年もよろしくお願いします。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
