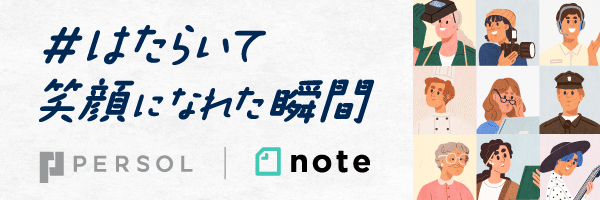餃子からはじまる物語
ひき肉は、粘りが出るまでよく揉むこと。肉に調味料をしっかり吸わせて、その後に野菜を入れること。最小限の水をつけて包むこと。餃子一つ作るだけでもそこには厳しいルールがある。そして私はそれが大好きだ。
高校で留年が決まった年、なんとなく家に居づらかった私は、名古屋の中華料理屋で餃子を包むアルバイトを始めた。早朝に行って、餃子の中身を作り、あとは10時間ひたすら包む。800個包めたらおしまい。頭がおかしくなる、と言ってすぐにやめていく人もいた。店長は「嫌になったらすぐ言ってね。訴えられると困る」と言う。しかし、それが違った。毎日行けないのが悔しかった。この仕事は、後にも先にも私の天職になった。
この仕事のなにが好きだったのか。
たぶん、できた餃子が面白いほどスポンスポンと人の口に運ばれていくこと、そしてその口からは必ず「おいしい」という言葉がでる。それを考えるだけでニンマリせずにはいられなかった。働きながら、なにニヤニヤしてるの、とよく言われた。
私はこれといって得意なことがない生徒だったと思う。英語が話せたり、スポーツで入賞したり、文化祭でエレキギターを弾いたりしている同級生が羨ましかった。羨ましいまま、3年間が過ぎた。勉強しても赤点になり、単位を落とし、留年と言われた時にはもう周りは大学生になっていた。
そんなどうしようもない私でも、絵を描くことだけは好きだった。友達に「不気味」と言われてからというもの、誰にも見せず仕舞い込んだ絵を、餃子屋の店長は見たがった。
持ってきてよ
誰もいない時にこっそりと見せた。店長は、俺はこれでも絵が好きで、あちこち観にいったりするんだ、と前置きして
「不気味なのに、リビングに飾りたいと思った絵はこれが初めて」
と言った。私はその時はじめて、人に自分の絵を褒めてもらう喜びを知った。
いつかデビューしたらさ、
と店長は言う。
必ず連絡してくれ。作品、言い値で買ってやるよ。
その店が好きだった。餃子も、仲間も、店長も。今日も楽しく働いた!と満足し、シフトがない日は元気がなかった。気づけば1年が過ぎ、私もついに高校を卒業した。
ある日、仕込みが終わってみんなとコーヒーを飲みながら、私はふとこんなことを漏らした。ああ、この店でずっと働きたい、ずっと餃子を包んでいたい。店長も喜んでくれると思っていた。ぜひ、そうしてくれ、なんて言ってくれると。しかし、店長は突然、神妙な顔つきになってこう言った。
「いつまでもここで餃子を包んでるわけにはいかないよ、微熱。君には君にしか作れないものを作るんだ。」
それを仕事にしなさい、と。いつもは冗談ばかりの店長がそんなことを言うのは信じられなかった。
「働くということは君が思うより、もっとずっと楽しくて神秘的なことなんだ。君が君の役割を果たしさえすれば。」
翌月、私は、店長の勧めでその店を辞めた。
その日から私の夢は「自分にしか作れないものを作って、売る」というものになった。しかしそれは、口で言うほど簡単ではなかった。私は、これを機に、世の中に何も送り出せない自分と対峙することになる。
◇
さて、何から始めようか。今から新しい旅が始まるみたいでワクワクした。
はじめに思いついたのが文具だった。昔からポストカードやレターセット、シールが大好きだった私は、文具のデザインコンテストにイラストを送った。しかし、いつまでたっても音沙汰がない。門戸を狭くしていてはダメだ、と様々なデザインコンペ、イラストコンペに応募した。絵本も描いた。知らない街のマスコットキャラクターも考えた。しかし届くのは不採用の通知ばかり。
地元のハンドメイドの祭典にも出店した。しかし、ポストカード1枚すら売れなかった。目の前で通り過ぎていく人を見て、消えてしまいたかった。終わればまた家にこもってコンペ用の作品を描き始めた。
そんな生活を2年続けた。どうなったか。自信は底をつき、自分の描きたいものが分からなくなった。筆はだんだん迷い始め、ついにはピタリと止まった。今考えれば当然の末路だった。
馬鹿馬鹿しくなった。ふざけた旅はもう終わりだ。私はやけになり、画材を全部捨てた。店長に見せたあの絵も。
きっぱり諦めよう、思った。ブランド・ニュー・スタート。話題のバーでアルバイトを始めた。お客さんと話しながら、決められた分量の酒を決められた順にシェークしてサーブする。色とりどりのカクテルはバーカウンターに並べられたそばから、お客さんの喉にするすると消えていく。
楽しかった。
こういう生活もいいと思った。
そういえば、カクテルを作るのは餃子を作るのと似ているなと思ったのは、店長の言葉を思い出した時だった。「君にしか作れないものを」。辛かった。思い出したくなかった。まだ諦めきれていない自分がそこにいたから。
その後も様々な仕事を点々とした。ウエイター、引っ越し業者、佐官、雑貨の仕入れ。確かにどんな仕事でも個性は生かせる。クリエイティブさは発揮できる。でも、どこで働いてもそこは自分の居場所ではない気がした。そのたびに、店長が私を店から離した理由を思い出しては、苦いものが喉からせり上がってくるのを感じた。飲み込んで、忘れようとした。目の前の仕事に勤しんだ。しかし、絵から離れれば離れるほど、私の顔から笑みは消えていた。しまいには、同僚に「なんで泣きそうな顔して働いてるの」と言われる始末だった。
そうして3年の月日が流れた。いつからだろうか、私は絵のことをすっかり忘れた。店長の言葉を思い出すこともなくなった。「自分にしか作れない」なんて傲慢でインチキくさいとすら思った。
◇
張り詰めていた糸はある時プツリと途切れるものだ。私は仕事を辞めた。転職はしなかった。長い旅が今度こそ終わったのだ。無気力のまま実家に戻り、ただ毎日、寝て、食べて、風呂に入ってを繰り返していた。こんなに時間があって自由なのに、心はぐったり疲れ、頭の中にはいつも湿った雲が立ち上っていた。
そんな生活が5年も続いた。信じられない。でも確かに5年もそうしていた。
ある日、母と地元の文具店にいった。よれよれのスウェットを着た自分の姿がショーウインドーに映る。みっともないな、なんて思っていたら、入り口に「ポストカードフェア」の文字があった。私はなんとなく近づき、数多く並べられた中から、猫のデザインが施されたポストカードを一枚取った。
それは、色とりどりの猫が気ままに散歩しているイラストだった。隣には、その黒猫バージョンがあった。可愛かった。欲しいと思った。本当に久しぶりに、はっきりとワクワクした。
その帰り道、車の中で、言いようのない不安に襲われる。何かとても大切なことを忘れているような気がしたのだ。いてもたってもいられなくなった私に、母がバックミラー越しにいう。「ポストカードが原因でしょ。また描いてみたら?」とんでもない、また絵を?
かけないよ、もう遅すぎる。
10年も前のはなしだ。
ここまで何もせずに来てしまった。
もう時間が経ってしまった。
しかし、口ではそう言いながらも、頭の中は別の言葉で埋め尽くされていく。
「家に帰って、スケッチから始めてみよう、微熱。今からでも遅くない」
その日、家にある適当な鉛筆で、猫の絵を描いた。手持ちのものを売って、絵を描くためのパソコンを買った。部屋の壁に、こう書いて貼った。「私にしか作れないものを作って売る」。
それからは早かった。モデルはいくらでもいた。ぽかぽかと暖かい日は、近所の猫がうちの庭を横切る。そこでは、「私が一番」といわんばかりに各々ポーズをとってくれるのだ。私は、それを見ながらスケッチを起こした。描いて、また描き直して、気づけば6枚のポストカードが出来上がっていた。すぐにハンドメイド通販サイトに登録をし、写真を撮り、商品説明欄を埋めた。あっという間に自分の店が出来上がった。
しかしやっぱり甘くない。10日経っても何も起こらなかった。でも、今回は手放したりしない。そう決めた。深呼吸をして、庭の猫を描き続けた。ちょうど、猫を18匹描いた頃、ピロリンと携帯が鳴った。そこには、
「販売中の商品が購入されました。発送手続きを行ってください。」
とあった。購入?発送?
そう。記念すべき最初のお客さんが現れたのだった。
慌てて梱包し、郵便局へ急ぐ。発送したその帰り道、なんとも言えない春のさわやかな風が私の顔を撫でた。そして気づいた。餃子から始まった私の物語は、今、この瞬間につながっていたのだと。
2日後、また携帯が音を立てる。購入者からのメッセージだった。
「写真で見るよりもずっと素敵で可愛らしいカードでした。大切にします」
私は心から嬉しい時、はしゃいだりしない。泣くこともない。小さい頃からの癖だ。映画の悪役がそうするみたいに、ニンマリ、とする。そしてそれは止まらない。
なにニヤニヤしてるの、と家族に散々冷やかされた。
また、画材を買う。鉛筆を研いで、紙をピンと張る。
春になった。ちょうどいいタイミングだ。
また、新しい旅が始まる。
先日開いたショップ。よろしければ覗いてみてください↓
この話にはエピローグがある。せっかくなので、紹介して終わろうと思う。
販売を始めたら、どうしてもしておきたいことがあった。カードを一枚取り出し、書く。宛先は名古屋。失礼な話、店はコロナの影響で潰れてないか不安で、何日か躊躇した。でも、思い切って調べたら、ちゃんとあった。頑張ってるんだ。そりゃそうだよな。
カードには、どう書こうか相当悩んだ。(店長は文字を読むのも書くのも苦手だから。)考えた末、「遅くなったけど、ようやく始めたよ」と書いた。
すぐに、返事が届いた。そこにはあの頃と同じ、決して上手とは言えない字でこう書いてあった。
「ずっと応援するよ!!」
文字の周りには、星みたいなものが書き加えられていた。ついでに近況とか書かないところが店長らしいな、と思った。
それを、部屋の壁に貼った。深呼吸する。目を閉じて、また開く。
描こう、どんどん描こう。
描いて、仕事しよう。
きっと、もっと楽しくなるだろう。
なににも代えられない私だけの居場所になるだろう。
この記事が受賞したコンテスト
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?