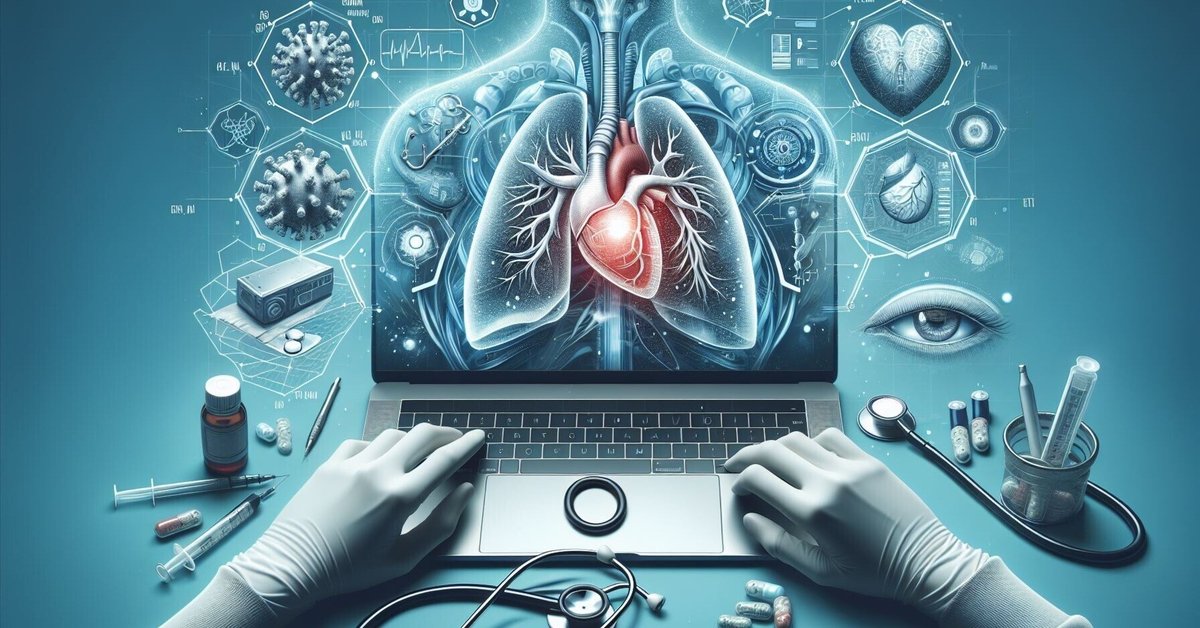
J-OSLER-呼吸器について
今回はJ-OSLER-呼吸器についてまとめていきたいと思います。個人的な見解を含んでおりますので、最終的な症例選択は自己責任でお願いします。また提示した方法を絶対的に推奨する訳ではないので、あくまで参考程度にしてください。
J-OSLER-呼吸器の概略
以下は日本呼吸器学会の病歴要約 作成と評価の手引きからの抜粋です。

内科J-OSLERと同じように、経験症例を作成し、その中から病歴要約を作成していきます。内科J-OSLERと違う点としては、
・経験症例200例、病歴要約25例
・経験症例のうち50例は必須技術の登録(気管支鏡検査30例、胸腔穿刺15例、胸腔ドレナージ5例)が必要
・年度内の登録数の制限がある(症例登録は約60例/年度以下、病歴要約は約10例/年度以下)
・登録できる症例は連動研修開始の専攻医2年目(研修医含めると4年目)から
・内科J-OSLERの症例をJ-OSLER-呼吸器へ移管できる
などが挙げられます。
内科J-OSLERの症例が使い回しできるとはいえ、これだけの症例数は正直しんどかったです(もう二度とやりたくないです)。が、やればいつかは終わるもので、コツコツとやっていくのがよいと思います(私は2-3ヶ月で徹夜もして終わらせました、非推奨です)。
注意点は年度内の登録数に制限があることです。約●例/年度以下と「約」がついており厳格ではない可能性はあります。どこまで詳細にチェックされているか不明であり、超えた場合差し戻しがあるのか、などはわかりません。なるべく毎年分散して症例登録していくことをお勧めします。
病歴要約について
病歴要約についてですが、内科J-OSLERと同様、疾患群からいくつ作成が必要と決まっています。外科紹介症例も2例(症例登録は4例)必要です。私は大学病院や総合病院の勤務がメインだったのでそれほど症例集めに苦労はしませんでしたが、病院によってはこちらもハードルになってくると思います。特に3年目の大学で経験した良い症例が結構あって、それを使えないと知った時は絶望しました。早めにどのような疾患群が必要なのか確認しておくと良いと思います。また内科J-OSLERの使い回しができることを考えて、4年目以降の内科J-OSLERを呼吸器疾患多めで作成するといった戦略も有効と考えます。
以下に病歴要約に必要な疾患群を貼っておきます。ちょっとわかりにくいですが、⑥*が2つある場合にはその疾患群の中から⑥として3例作ってね、という意味です。



具体的に疾患群をみていきます。
前提として、基本的には同一の症例は避けていろいろな症例で病歴要約を作成した方がよいと思います。ただCOPDなど疾患群によっては重複せざるを得ないものもありますので、その場合には考察内容を変えるなどの工夫が必要です。
10個の疾患群で病歴要約を書くうえで、①感染症、②COPD、④アレルギー性疾患、⑦肺癌、⑨胸膜疾患で困ることは少ないと思います。
一方で、③気管支の疾患、⑤特発性間質性肺炎、⑥肺障害や肺循環障害、⑧呼吸調節障害・呼吸不全、⑩外科紹介例 あたりが勤務先の病院によっては苦労するところでしょうか。
③は気管支拡張症やDPBで書ければそれで良いですが、難しい場合には「無気肺」で書くという選択肢もあるかなと思います。私の場合は肺癌による無気肺で1例提出しましたが、特に問題なくacceptされました。ただ絶対に通ると保証するものでもないのでその点はご了承ください。
⑤の特発性間質性肺炎は、IPF以外のIPは気管支鏡検査やVATSでの病理所見がないと書きにくいと考えます。IPF(の急性増悪)や、割と経験し考察も述べやすいCOPあたりが書きやすいかなと思います。
⑥は肺血栓塞栓症のほか、放射線肺炎や膠原病に伴う肺病変、サルコイドーシスなどが書きやすいでしょうか。稀な疾患を経験していればぜひ採用したほうが良いと思います。
⑧の呼吸調節障害・呼吸不全ですが、SASなどの呼吸調節障害についてはよほど良い症例がない限り書かなくてもいいと考えます。私は急性呼吸不全および慢性呼吸不全で合計3例作成し、問題なく通りました。
⑩の外科紹介症例は、内科で診断をつけて外科に手術を依頼した症例でないといけません。複雑な症例である必要はなく、肺癌や気胸、膿胸、IPでVATSを依頼した症例などで十分だと思います。
全体を通して大学病院でみるような稀な疾患は病歴要約にしやすいと考えますので、そういった症例は必ず記憶・メモしておきましょう。
評価について
症例登録・病歴要約をしていくうえで、一番大事なことは指導医・個別評価の先生への評価の依頼の仕方だと思います。内科J-OSLERでもそうでしたが、私の周りでは症例登録にもすべて引用文献が必要と言われ、修正や差し戻しも多くいっこうに病歴要約に辿りつけない人がいて本当に可哀想でした。正直、症例登録については指導医のみのチェックですので、その旨を伝えてみてもいいかもしれません。一方で病歴要約については二次評価で外部の確認が入りますので、しっかりチェックしてもらってください。
二次評価についてですが、私は個別評価でかなりしっかりみてもらっていたこともあり、修正なしですべてAcceptでした(運が良かっただけかも)。先輩や同期をみていると、修正や差し戻しもあったようです。ちなみに呼吸器学会で公表されている一期生の情報だと、全てAcceptが17.5%、要修正ありが70%、差し替えありが12.5%とのことでした。最近はどうか不明ですが、結構厳しいですね。ある程度評価者によるユルイ、厳しいなどの運ゲー要素はありますが、できる限り質の良い要約を提出するに越したことはないかなと思います。誤字・脱字は評価を下げるので注意しましょう。提出後はただ祈るだけです。
まとめ
ただでさえ普段の診療が忙しい中でのJ-OSLERは本当にしんどいと思います。少しでも参考にしていただければありがたいです。
私は来年呼吸器専門医試験を受験予定で、気管支鏡専門医試験もそのうち受験する予定です。また再現問題も作成したいと思ってますので、チェックしてみてください。
すべて無料で公開予定ですが、note作成のモチベーションアップにつながるので、参考になった方は少額寄付いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。
ここから先は
¥ 500
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
