
水本ゆかりと《情熱の赤》
最近、[純粋奏者]水本ゆかりに声がついたり、SSR[ビターエレガンス]東郷あいが登場したりといったことが続いたので、ゆかりとあいさんの関係について私個人がとりとめもなく考えていたことなどを、整理しなおしています。
それで、ゆかりとあいさんの関係の出発点になっているのは、[純粋奏者]なわけですけれども。
ゆかりは結構、有言実行の人というか……誰とユニットを組みたいか、どんな仕事をしたいかをはっきりPに伝える性分なんですね。そしてPは基本的に、それを実現させる方向性でやってきているように見えます。

その代表的な実例が「演奏会ユニット」です。2013年のツアーinイギリスでたった一度だけ実現した、まあマイナーといえばマイナーな、しかし知る人ぞ知る名ユニットであると紹介してもよいでしょう。

この仕事でゆかりは、当時の自分のフルスペックをものすごく楽しんでいた――少なくとも私は、そのように感じました。
しかしその一方で、あいさんや音葉さんがこのユニットをどう感じてくれたかは、以後4年ほどわからないままだったとも言えます。
そこのところがはっきりしてきたのは、意外と最近のことなのです。
たとえば音葉さんがゆかりのことをどう思っているかは、ここ2年の総選挙中にアイドル紹介のコーナーが設けられるようになって、ようやくわかってきたようなものだったりします(ちなみに左が2017年、右が2018年)。

こんなに風に思っていただけるなんて、ゆかりは幸せものですね……ありがとう……(ゆかりP目線)。

そしてあいさんがゆかりについてどう考えていたのか、初めて私に伝わってきたのは、2017年8月末――すなわち夏島アイプロ直前に登場したユニット「夏音の紡ぎ手」を介してのことでした。

ゆかりが演奏会ユニットの時と同じ[清純令嬢]+の衣装であいさんと共演しているだけでなにやら涙腺に来ますが、あえてひとつだけ疑問を呈することを許されるなら「夏音という造語には、いったいどういう内容が含まれているのだろう?」というようなことも気にならなくはありません。
おそらく夏音を「カノン」と読ませて、かの音楽形式と掛けているのでは…という想像はつくのですが、そこから「セミなど夏の虫が、短い一生を完全燃焼するために鳴いて、それが輪唱のように聴こえるってことかな」というところまで発想を飛躍させてしまってもよいものなのでしょうか。もう少し詳しく、台詞などを見ていきたいと思います。
――――――――――――――――――――――――――――――――
「夏音の紡ぎ手」の台詞の中で、強く私の印象に残っているものといえば、DRAW時のこの台詞を真っ先に挙げずにはおれません。

やはり必ずしも晴れやかな曲ばかりではなく、夏を表現するものとして哀しい音色の曲なども演奏したことがわかりますが、私にしてみれば、そこからさらに気になるところが出てくるのです。
「キミたちの細やかな美には及ばない。少し、色を知っているだけさ」
この台詞は、あいさんが共演者の長所を認めた上でなお、自分の個性と実力を鑑みて冷静に述べたものでしょう。ただ、そこからは称賛を受けた者の浴するべき栄誉が、慎重すぎるほどの手つきで切り離されている気配も感じ取れなくはありません。これもあるいは、哀しみのかけらでしょうか。
実をいうとこのユニットは、あいさんが正真正銘の挑戦者であった時のことを思い出させる組み合わせでもあります。かつてあいさんは令嬢アイチャレで、薫ちゃんや池袋ちゃんと一緒に、この「細やかな美」に挑みました。そして琴歌さんの指導のもと、見る者を唸らせる成果を挙げたのです。

したがってあいさんはおそらくこの「細やかな美」を、色に比べればつまらないもの、些細なものという風には見ていないでしょう。もっとはっきり言ってしまえば、細やかな美とはつまり「形」に対する評価であり、それは「色」と相互言及的な概念だという主張が隠れている可能性すらあります。
形とは、もののなかでただひとつ、つねに色に随伴しているところのものである。 ――プラトン『メノン』
――――――――――――――――――――――――――――――――
唐突なようですが、あいさんがCo属性である理由はおそらく、単に「自分の美学を持っている」からではありません。それだけで済む話なら、たとえばCu属性のレナさんもまた、実践に裏打ちされた美学を持っているからです。

スリルに身を投じるだけではCoではない、美学を貫くだけではCoではない。ならばなにが東郷あいをCo属性たらしめているのでしょうか。その答えはPそれぞれといえば確かにそうなのですが、それならばPのうちのひとりであるところの私自身が持つ答えはなんなのか? ――臆さずに述べるならば、私はCoの本質を《精神はただ精神のみでは存在できず、現象(たとえば色)を伴わなければならない》という発想にあると仮定しています。
それは彼女たちが《誰にでも魂はある》という無根拠(あるいは信仰)を、一度は捨てているということです。たとえば、この曲のように。
存在証明を、この悲鳴を、或いは歌を / 叫び続ける ボクは此処にいる――『共鳴世界の存在論』

この曲・この衣装は二宮飛鳥の全てではありません。あくまでも《キミのパルス》に応えた二宮飛鳥の周波数のひとつです。しかしそれは、単にPから一方的に二宮飛鳥に与えられた世界観ではなく、響いて引き合うものであったともいえます。

このように、彼女たちCoアイドルのうち、ある者は自分に魂があることを証しだてるために自己表現してきました。…そしてまた、ある者は魂など自分には(そして誰にも)必要ないことを証しだてようとあがいたりもしますが、あいさんの場合は前者に近いといってよいでしょう。それらはいずれも魂の実証主義と言い換えることができるかもしれません。
人間は万物の尺度である。あるものについてはあるということの、あらぬものについてはあらぬということの。 ――プロタゴラス
アイドルデビュー前には得意なことだけで賞賛を得てきた――というのが、あいさんが自分を振り返って述べた言葉です。たしかに人を魅了してはいたものの、その魅力は今現在と比べるとやや一面的なものだったといいます。この時点ではまだ「少し、色を知っている」とはいえない状態なのです。

あいさんはPと出会い、このような自分を鍛え直すにあたって、根本的なところから再出発したと思われます。つまり《私には、魂があるだろうか?》という問いにまで遡ったのではないか――と。
「魂」という私の言葉選び(一応最後までお読みいただければ、シンデレラガールズのどこから引用してきたかは伝わるはずです)がうさん臭く感じられる方には、才能なり、カリスマ性なり、資格なり、読み替えていただければと思いますが――東郷あいは「私の周囲で魂を備えた人たちをみるかぎり、彼らには色がある」「そしてその色は時に移り変わる」というような研究を独自に続けてきたに違いありません。だからこそ現在の彼女は「少し、色を知っている」のです。その努力の成果は目覚ましく、かつての知人をして「どのような魔法を使ったのだろう」と驚かせるほどだったのでした。

それはあいさんにとってのアイドルの始まり――レッドバラード結成がいかに重要なものであったかということを、暗に物語っています。そしてあいさんからゆかりに初めて伝わった色もまた、赤だったのでした。

――――――――――――――――――――――――――――――――
水本ゆかりは西園寺琴歌と同じく「一喜一憂しない」ことをよしとして育てられ、そのうえで東郷あいの演奏によって表現された「色」に惚れこんでいる人物です。仮にバラエティ番組であいさん大好きアイドルが集まってトークを繰り広げるとすれば、その中には必ずゆかりの姿があるでしょう。

しかしゆかりは、《己の色によってその魂の実在を証明する》というような発想をしません。むしろ全く正反対の出発点から進んで、同じ地点に辿りつきます。つまり彼女は《己の魂の実在によって、世界を照らしだす》ことに憧れているのです。

たとえ今は未熟であるとしても、魂はもうここにある。波風はそれを研磨してくれるに違いない。そして、磨かれた魂によって本物の歌が奏でられたならば、世界は癒され彩られるはず――水本ゆかりの精進はそういう基礎理論の上に築かれてきたのではないかと、私は考えています。クラシカルハーモニーで発せられた「かわいい癒し」という言葉も、もとはといえばこのような見解に端を発するものなのでしょう。
このようなスタンスは、彼女がCoとは根底から異なる別の世界観――すなわちCuの本質を備えた人物であることに由来していそうです。

ゆかりは「アイドルも、きっとフルートと同じ…焦らず、着実に練習を積み重ねていけば、いつかきっと…」と、自分の未来を信じています。そう、Cuの本質はおそらく「きっと」の中にあるのです。たとえばレナさんの場合、「これはきっと人生を賭けるに値する勝負になる」という確信と高揚感こそが、彼女をCuアイドルたらしめているのではないかと私は考えます。

SR[クラシカルハーモニー]のコミュで、ゆかりは「自分の演奏には、一流の奏者がもっているような自分だけの世界がない」と自己分析しています。ですが、そこで折れたりせず、いつかきっとそれを表現できると信じて「ずーっと目指している」わけです。
私が思うに、ゆかりは自分に「色」がついていないことを知りつつ、己の魂の存在を疑わない不思議な人物として、東郷あいの前に現れました。ゆかりは琴歌さんや星花さんに比べると年下で未熟なところもあって、あいさんと並べるとかなり対照的です。
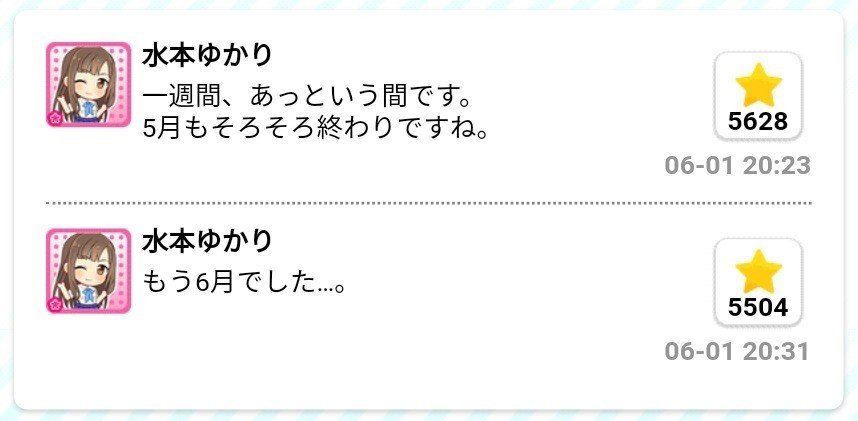
しかしあいさんは「色」について考え続けてきた人なわけですから、「色がついていないので見えないかもしれませんけれど、そこにはきっとなにかが(=確かに私が)存在していますよ」というような話を放置しておくことができません。
あなたの説によると、形とは、つねに色に随伴しているものであるというようなことでした。――結構でしょう。しかしですね、もし誰かが、自分は色というものを知らないと主張したら、そして、形についてとまったく同様の疑問を色について持っているとしたら、あなたの答は、いったいどれだけの意味があると思いますか? ――プラトン『メノン』
あいさんはゆかりと出会うことで、まさにこの引用に類似するようなシチュエーションに直面したといっても、過言ではないでしょう。
ゆかりが主張する内容の真偽を確かめ、互いの成長に結びつけるにはどうすればよいのか。演奏会ユニットから令嬢アイチャレを経て、その後もさまざまな経験を積んだあいさんは、然るべき方法論を確立した上で、再びゆかりの前に立ちました。
そう、色のないものの形が知りたければ、試しに自分が認識できる色を吹きつけてみればよいのです。そこになにもなければ、色が空間を染め上げることはありません。しかし、もしもそこになにかがあるのならば――東郷あいの選んだ色をまとって、そこに水本ゆかりという魂の形が浮かび上がるはずです。「夏音の紡ぎ手」というユニットのライブで繰り広げられた光景は、私から見ればそのようなものでもありました。
――――――――――――――――――――――――――――――――
一見根拠がない主張に対して、その真偽を悟らしめる試練を与えるというのは、なかなか難しいことではないかと思います。

先入観を棄てられないせいで、時には相手に対して辛辣な評価をくだすことだけが目的になってしまうことだって、あるかもしれません。もしもそのような人物が、アドバイスに相応しくないタイミングでゆかりの前に立ったならば、彼がゆかりに素晴らしい色を選ぶことはなかったでしょう。

しかしあいさんは、魂の輝きを音楽にこめて世に問おうという人物を、無碍に扱うことができませんでした。もともと彼女は誰かと移動するにあたって車道側を歩くタイプの人でしたが、それ以上の共感があったものと思われます。だからこそあいさんが選んだ色は、魔法のように自由自在で、時に哀しく時に艶やかな、そんな音色だったのです。
星花さんも昔から、ゆかりのそのような音楽に対する取り組みを「素直な心」と評価してくれています。ゆかりが理解あるふたりと出会って生まれた「夏音の紡ぎ手」は、とんでもなく優しい世界です。しかしそれだけではなく、哀しさや艶やかさといった繊細な「色」に満ちた世界でもありました。それはまるで夢のような、と形容しても差し支えはないでしょう。

もうひとつ、星花さんにとってこのライブがなんであったのかを物語る材料を、私は「水彩のハルモニア」の中に見ました。このユニットについても改めて書きたいことがいろいろある(というか、同時進行で書いている)のですが、今回はとにかく肇ちゃんのこの台詞に注目してみたいと思います。

「いい色」「いい形」――このような評価軸が、西洋・東洋の文化の違いを越えて、比較的初期の肇ちゃん(2014年春)の中に見受けられるのは驚くべきことです。これを踏まえると星花さんにとって「夏音の紡ぎ手」は、かつての「水彩のハルモニア」を発展させる鍵にもなりうる表現だったと思われます。それらは形のない「雲(=ハーモニック・クラウド)」や「空(=スカイコンダクターおよびトークバトル共演メンバー)」とはまた異なる、いわば星々のきらめきのひとつとして星花さんの表現世界の広がりを示すことになるでしょう。
さて、このようなライブに成長のヒントを得たのがゆかりだけではなく、そのPも同じだったとすれば、Pはあいさんからアイドルに試練を与える者としての在り方に関するヒントを得たことになるでしょうか(あるいは、このような相互作用が起こりうると想定した上で「夏音の紡ぎ手」というユニットを実現させたのだという説も成り立たないわけではありませんが)。
いずれにせよ私の解釈によると、夏島アイプロでPがゆかりに託した情熱の「赤」は、単に意外性を求めたり、ゆかりが乗り越えるべきハードルとして用意されただけのものではなかった可能性があります。魂の「形」を浮かび上がらせないもの、心意気の感じられないものは「色」と呼べません。その心意気にあたるもののひとつが、かつての観客や共演者たちへの感謝であったかもしれないと、私はそのように推測するわけです。

あいさんは「夏音の紡ぎ手」でゆかりに彩色を施して、その魂の形を見抜き、それを「細やかな美」と評価しました。この抽象的な表現は、その直後に開催された夏島アイプロにおいて、美しくカットされたコランダムという具体的な比喩を得ることになります。そこにはやはり表現の継承および発展があるように思われます。
――――――――――――――――――――――――――――――――
あいさんから色の概念についてのヒントを得たゆかり(とP)は、この経験をその場限りのものにしません。ついには情熱の赤を自分のものとして、夏島アイプロを成功させます。

かの黒川千秋をして、このような感想を抱かせたゆかりの「赤」は、あいさんが黒川さんとともにレッドバラードで培った情熱の赤にも通じている――というのが、今回の考察における私の主張のひとつになります。
しかし、夏島アイプロにおける水本ゆかりの成果は、ゆかり個人が赤というイメージカラーを演じきったことだけではありません。自分と共演者で纏う色が異なる場合、どのように共存させるかというテーマにも挑んで、進歩がみられます。その秘訣はどうも光の三原色にあったもののようです。このことは初期登場メンバーのゆかり・由愛ちゃん・冴島さんの衣装の取り合わせが赤・青・緑であることからおおよそ看ては取れるのですが、もうひとつ個人的に「これは…」と思われる台詞がみつかったので、そちらもご紹介したいと思います。

これらの台詞をみると、黒川さんがゆかりと由愛ちゃんのパフォーマンスを「赤と青の、頼もしいコントラスト」と評価している一方で、由愛ちゃんは「赤と青を合わせて新しい色を作る」とも言っていることに気付きます。
ふたつの色はコントラストとしてステージ上にあったのか、それとも溶け合っていたのか――私も一瞬「ん?」とわからなくなったのですが、これらは矛盾した発言ではないうえに、いずれも偽りのない言葉であったものと思われます。それが水彩絵具に喩えられる表現であるならば、一度混ぜたものを分離するのは困難でしょう。しかし光の色で喩えられるものであったからには、いずれの表現もステージ上の状況によって自在に使い分けることができた可能性が高いわけです。
実際、このイベントの主役であるかな子自身「(時間経過によって変わる)空の色も考えて、セトリが組まれてるんですよね」と、その難易度を意識した描写があります。とはいえ彼女たちは、みんなで共有できる楽しみを設定することによってこの緊張も乗り越え、課題を無事クリアできたのでした。

――――――――――――――――――――――――――――――――
シンデレラガールズにはスクリーンショットを撮り逃してしまえば二度とみることができない台詞がたくさんあります。したがって「ユニット」であるとか「イベント固有の台詞」であるとかは全て一夜の夢なのだと捉えることも、間違ってはいないのでしょう――いや、むしろある意味では、それこそがもっとも正しい把握認識の仕方なのかもしれません。
しかしその一方で私は、これらの表現に対して夢と夢とをつなぐ不思議な連続性を見出すことも不可能ではないはずだと考えてしまう傾向にあります。
夏島アイプロの中で、ゆかりは「夏が奏でる音色を、めいっぱい楽しみ」ました。それはもはや哀しみや艶やかさに留まらない夏音の数々であったといえます。ゆかりが耳を傾ける波の音は、三村かな子のほっとする感じを投影されている(かな子から見たゆかりの姿にしても、波の音に聴きいる妖精のような少女として、昼とはなく夜とはなく繰り返し現れます)ように思われますし、賑やかにはしゃぐ楽しげな少女たちの声は、期間中ずっと冴島清美の献身によって見守られていたものです。ゆかりばかりでなく彼女もまた、注意の黄信号に加えてオールグリーンをも司る超☆楽園の守護者として、「形から入った」風紀委員への憧れに、色の概念を導入するような成長を果たしたものと受け取ってよいでしょう。

自分も仲間も成長して輝きを増している――そのような日々がいよいよ終わりを告げようというとき、ゆかりの中でついに目覚めたのが、夏の夜空に浮かんだ星辰のきらめきを、音色として紡ぎとる感性でした。

「私の心と一緒」であるところの「星たちの音」――それを魂の歌と言い換えてパープル・ロンドの表現を仄めかすことさえ、今の私から見るとさほど無理筋ではないような気がするのです。

この新ユニットが成立しえた理由を考えるにつけても、あいさんから学んだこと(=情熱の赤/色をもって相手の形を浮かび上がらせること)、夏島アイプロから学んだこと(=赤と青の融和/コントラスト)の双方が活かされているように感じられます。
――――――――――――――――――――――――――――――――
ゆかりが感得した「夏音」はいずれも、絶対音感や共感覚ではなく後天的に磨かれた感性や経験に由来するものです。しかしそれでもやはり、ゆかりが音葉さんの見ている世界に一歩近づいたことを示すものではあるでしょう。
客観的にはそれぞれが遠く離れてバラバラに輝いている星々も、人間の視点から眺めて線で繋げれば、ひとつの星座になります。
この時ゆかりが夜空に感じたのは、「共演の最中ではなくても、かつての仲間たちときっと繋がっている」という感覚だったに違いありません。ゆかりはそれを素直な心のままに「確かな絆」と呼ぶのでした。

このような進歩を遂げたゆかりが、もう一度あいさん・音葉さんとステージ上で出会ったならば、どのような言葉と音楽が響くでしょう。そしてその時そこには、星花さんもいてくださるでしょうか。

はっきり約束されていることなど、なにひとつありません。それでも私は、そういう未来を、きっといつか見てみたいのです。(了)
