
シェアアトリエOPENから1ヶ月-「場」を通じて何を稼ぐのか-
十日町に拠点を移してから「asto」っていうシェアアトリエをオープンしました。この記事でどんな場所と人なのかザックリ書いてるので見てね。
10月1日にゆったりとスタートし、10月12日にオープニングパーティーを催しました。その時のプレゼン内容をここにまとめたいなって感じです。割とふざけたこと書いてないので「いきなりどうした」って感じですが、淡々と説明していきまっす。
asto / アストってどんな場所?

本題の前に、この場(asto)をザクっと説明します。飛ばしても大丈夫。
まず「シェアアトリエ / ラウンジ」と呼んでおりますが「会員制のシェアスペース」を運営しています。
コワーキングスペースやシェアオフィスと同じ方式ですが、ドロップイン(一時利用)は基本やっておりません。(お試し初回利用は無料で出来ます。)
ドロップインをやっていない理由は、十日町市内には「電源とWiFiがあって、作業や勉強を出来る空間」が結構あるからです。しかも無料の場所が多いのですよね。なので初回のみ無料で利用していただいて、2回目以降はasto会員になって使ってもらうという方式で運営しています。

もう一つが「アート関連事業」です。「アートプランニング」「アーティスト支援」と呼んでいます。

アーティストさんに制作していただいた作品を展示して、展示会を毎週土・日曜日にやっています。
展示会以外にもastoの「アートグッズの販売」もしています。まだまだ作品は少ないですが、今後少しずつ増やしていく計画でございます。ゆくゆくは「作品のレンタル」も出来たらいいなと思います。
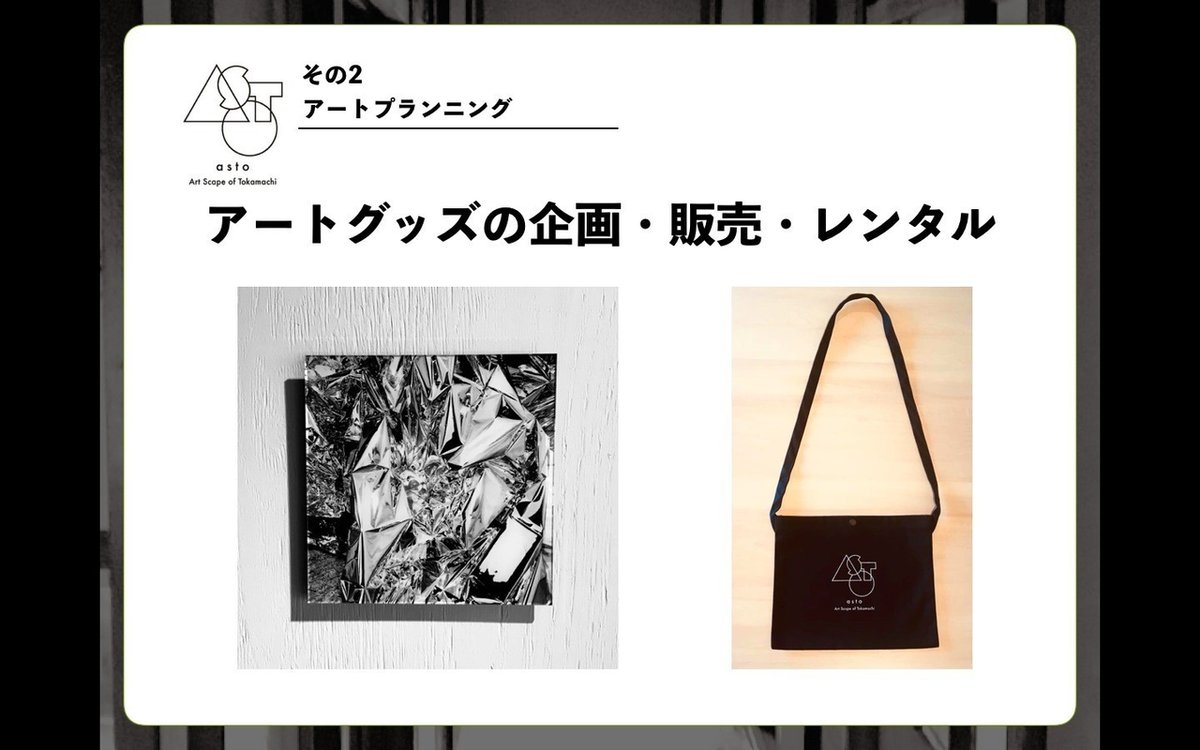
他にも大地の芸術祭に関連して、夏の間は作品管理と運営もしていました。

十日町駅東口公園の中に新しく出来た作品「10th day market」はざっくり言えば「ハンカチ屋さん」。ここで今のasto会員の方にもアルバイトをしてもらって、助けられました。ありがたい。
ひびのこづえさんがデザインしたハンカチやアクセサリーを販売したのですが、このお店に関してはまた別の記事で書きますね。
こんな感じで「単なるシェアスペース」ではなくて、「ART SCAPE」の言葉の通りアートな空間・景色を生み出すだけではなく「SCAPE」が持つ意味「茎」として十日町のカルチャーやクリエイティブ、産業や人を支えていけたらと思っています。
「新しい働き方」ってなんだ。
ここから本題です。
プレゼン資料の中で出てきた「新しい働き方」という言葉。よく使われているので安直かなとも思いつつ「どう定義されているのか」を考えてみます。

書籍やWEB記事の中で言及されている「新しい働き方」を参考にすると、こんな感じでまとまるでしょうかね。出勤せずとも働ける企業やテレワークを活用した働き方、業務委託という形で毎月一定額を得られる働き方も増えていますが、実は十日町でも実践してる人は少なからずいますよね。言うほどマイノリティじゃないと思います。多分。
今後スタンダードになってくるこの働き方をしている人達が心地よく、使いやすく、集まれる場所。それが十日町にあることで、「新しい働き方」を標榜する人達が集まって欲しいなと思うのです。
まだ1ヶ月ですが、asto会員の数だけではなく、問い合わせや要望も増えてきて手ごたえを感じています。
asto会員になってくれた人に僕らが出来ること
asto会員は毎月の会費を払ってastoに関わってくれる人々です。
ラウンジ会員は3000円(24時間利用なら4000円)、ブース会員は16000円〜となっていて、電源・WiFi・キッチン・共用備品は使い放題で内容的にはかなりお得!なのではないかと思います。
がしかし、単なる作業場・ワークスペース・勉強場所として使うとなると、前述の通り市内には無料で利用できる場所が多いので会費を払うことに抵抗感があるかもしれないですね。レンタルスペースとして利用するのも同様です。
だから、この場所を支えてくれるasto会員の人達に僕らは何が出来るだろうかって考える訳です。
その中の一つに「astoという場を通じて稼ぐためのサポートをする」ということがありまして、この記事のタイトルにもしました。astoが何を稼いでいるのか、astoに関わる人は何を稼ぐか、両方の意味があります。
めっちゃ偉そうなのですけど、単純に場所を貸して対価として会費をいただくというよりも「最低でも『場』に払うための会費分くらいは一緒に稼いでいきたい」と僕は考えています。(もちろん、そっとしておいて...って人はそのままにしますけどね。距離感も大事。そして、astoに関わる人々の想いも個々に少しずつ違うので僕個人の考えです。)
ここで言う「稼ぐ」という言葉はもちろん売上やお金な訳ですが、ただもう少し深掘りして、稼ぐこととは何なのかを考えてみたいと思います。
なにを稼ぐのか、稼げるのか

去年あたりに国外のメディアでも取り上げられた「IKIGAI」を構成するものたちの簡略図でございます。
図の説明は省略するのですが「生きがい」や「ナリワイ」を見つける時のキーワードの一つになるのが「稼ぐ」という言葉。国外のメディアでは、ここでも「稼ぐ」=「お金」という意味で言及されていますが、ローカルシフト(地方に住んでるだけ)した僕なりの解釈を若干加えたいなと思います。

「稼げる」=お金?と疑問を投げかけていますが、そもそもお金はどういう仕組みで稼がれているのか。
アルバイトだと時給〇〇円だから「時間とお金」の交換は分かりやすいですけど、労力、知識、経験、技術、モノ、人、精神衛生、肉体と時間以外にもお金と交換する方法はありますよね。(何、当たり前のこと言ってんだ。)
もっと言えば、全ての物事がお金に交換される訳でもなくて「対価」の言葉の通り「価値の交換」を僕らは常に行っている訳です。地方は価値の巡りが見えやすくて、貨幣経済と同列の別の経済が回っているのがよく分かります。「豊かさの正体」みたいなものかもしれません。
だから「稼ぐこと」には様々あって、どんな価値を稼げるのかに着目したいのです。

※知識や経験が持つ価値は消費されずに蓄積され続けていくので、若いうちから積極的に積んでいくと何やかんやコスパいいっすよね※
価値を何に変換するのかを考えた時の選択肢にお金があるみたいなイメージを持つと「稼ぎ方」に対する捉え方も変わってくるのではないでしょうか。
asto会員が稼ぐためのサポートをするというのは、その人にとっての「価値」を稼ぐサポートをしていきたいというのが本意である訳です。
「自分が何を価値として、何を稼ぎたいのか」明確に決めた上で「その価値の一部をお金に変換するまでのプロセス」を設定し、評価するのは少し難しい。だから前述の「最低でも『場』に払うための会費分くらいは(分かりやっすい価値だから)一緒に稼いでいきたい」となるのです。
事業主の方やフリーランスの方は価値をお金に変換するプロセスがある程度設計されているから、astoという場をどう使うかがイメージしやすいかもしれませんが、それがまだ設計しきれていない人は「場」とどう関われば良いか分からないと感じてしまうかもしれないですよね。
場との関わり方が分からない、そんな人へ
この悩みは自分の身近に「場」がある人に共通するかもしれません。
astoという「場」をどう使ったら良いのか分からない。フリーランスでも作家でも事業主でもないし自分には関係ない。と思っている人も「何を稼ぐのか」を考えることが出来れば、自分の可能性を広げるヒントになるはずです。
astoを運営している僕らも十人十色の「あなたにとって価値のあること」を知りたいですし、その価値を稼ぐサポートをしていきたいと思っています。
逆に場を運営する僕たちにも、astoを地域の核となるコミュニティの一つへと育てていくために、自分と地域の可能性を育てていく心を持った人を必要としています。

シェアアトリエ、コワーキングスペース、シェアオフィス、レンタルスペースと言うと単なる座標で区切られた場所や空間として、不動産的な考え方で価値を見られがち(要は家賃や固定費に近い)ですが「場が稼ぐ価値」「場を通して得られる価値」を多面的に考えると上の図みたいな広がりが出てくる気がしませんでしょうか。
学びや繋がりや考えるキッカケでもいい。このastoという場を通じて、何か自分にとっての「価値」を見つけるための足がかりをつくってもらいたいなと思っています。
まとめられたのか分からんですが、今後も何かと所感を書き連ねていきますので、また覗きに来てくださいね。最後まで読んでくださってありがとうございました。
地域PRをしている会社を経営しながら、個人でライターやファシリテーターもしています。日本文学が好き。
