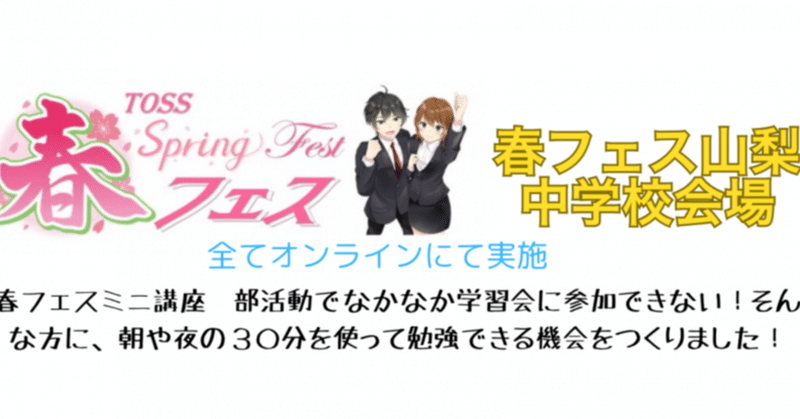
4月20日 (土)夜20:00〜20:30春フェス山梨 道徳授業の基本形 導入・展開・終末〜終末でどんな授業を行うか〜
道徳の授業は、「導入」「展開」「終末」の流れで組み立てると、骨格がしっかりしたシンプルな授業にすることにできます。
では具体的にどのように授業をするのか、中学1年生「席を譲ったけれど」の教材をもとに、参加者の先生方に考えていただきました。
1 導入・展開・終末の授業例の紹介
2 導入・展開・終末の組み立てで授業を作ることでどんな効果があるのか
3 「席を譲ったけれど」での授業づくり
4 発表
5 講師の授業の紹介
という流れで30分の講座を進めました。
あっという間に今回も時間が経ってしまったなという感じでした。
参加者の方からは次の感想をいただきました。
★
春フェスで道徳の授業作りついて、学びました。忙しい中、授業作り大変てんす。導入 展開 終末のパターンで、生徒の実態にあわせて作って見ることが大事ですね。それに。新しい情報が入るといいと思いました。また、一つの教材でみんなで、考えてみたいです。
□私の返信
◯◯先生ご参加ありがとうございました。みなさんでいろいろ導入・展開・終末の例を出すことで、授業づくりのイメージが膨らみましたね!!私も勉強になりました!
★
道徳の授業の構成を学びました。
できるだけシンプルに、そして子どもたちに考えさせて意見を言わせることが大切なんですね。発問をしすぎて迷走することが多かったのですが、来週からはうまくいきそうな気がします
□私の返信
◯◯先生ありがとうございます。大枠を決めることで、骨組みがしっかりしますね!今日はまさにそうでした。
導入・展開・終末の中で、展開の中の中心発問をまず最初に決めると、はじめと終わりがまた作りやすくなります!
★
道徳の授業作りについて、導入、展開、週末の作る時の観点を教われて大変勉強になりました!
私も考えすぎて質問が細かくなってしまいます。まず大枠を作ることでスッキリし終末までブレずに考えられるなと感じました!とても楽しい時間でした!!
□私の返信
◯◯先生ありがとうございます!細かくすればするほど、子どもたちの主体性が消えてしまうことがありますよね。教師がいないと学習できないような、教師の話を全部聞いていないとできないような、難しい授業になってしまいます。でも、発問を少なくして、子どもたち同士の活動を多くすることで、授業がシンプリになり、全員がついてこれやすい、活発な授業になりますね!
https://peatix.com/event/3897330/view
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
