
一筆入魂【0231〜0240】
0231/1000「星という字は日が生まれると書きます。」

辛い時は星を見上げよう。
きっと、明日が生まれます。
その明日はきっと
眩しく明るい日に違いありません。
0232/1000「体が疲れたら一息つくよね。息抜きが必要だから「体」から「一」息抜いて「休」むんだよね。」

【愉快に働く10か条】
1、仕事を必ず自分のものにせよ
2、仕事を自分の学問にせよ
3、仕事を自分の趣味にせよ
4、卒業証書は無きものと思え
5、月給の額を忘れよ
6、仕事に使われても人には使われるな
7、ときどき必ず大息を抜け
8、先輩の言行を学べ
9、新しい発明発見に努めよ
10、仕事の報酬は仕事である
BY王子製紙初代社長、政治家、慶応大学工学部設立者 藤原銀次郎
0233/1000「まず思え」
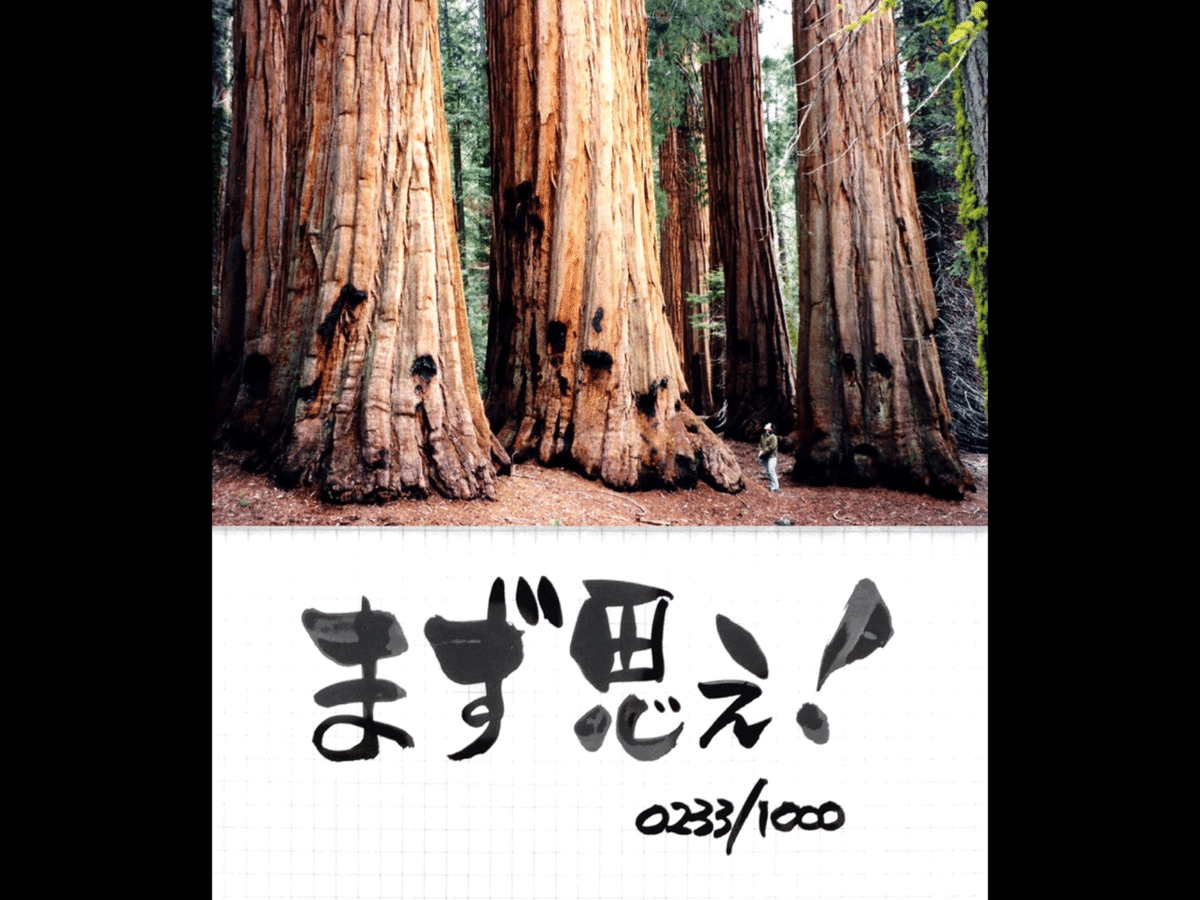
松下幸之助氏の「ダム式経営」というものがあります。
ダムを創って常に一定の水量があって、必要な場合にいつでも放出できるような、余裕のある経営をやるべきだというものです。
京セラ創業者の稲盛和夫氏は、この松下の「ダム式経営」の講演を聞きに行かれました。
講演が終わるなり質問に入った時です。
ある中小企業の経営者が
「私もダム式経営に感銘を受ける。
しかし、今、余裕がないのをどうすればいいか、教えて欲しい」
と聞いたのです。
松下は一息おいて
「そんな方法私も知りませんのや。
知りませんけれど余裕がなけりゃいかんと、
思わないといけませんな」
と答えました。
会場からは「全然答えになっていない」と失笑がもれたようです。
ところが稲盛氏は、この「思わないけませんな」の一言に強烈な啓示を受けて、感動したというのです。
松下は
「まず思わなかったら、どうして何ができようか」
ということを言ったのでした。
理想に対して「そう思うが、現実には難しい」と否定する気持ちがあると物事は成就しません。
強烈な願望を描き、心からその実現を信じることが、理想を引き寄せるのです。
BY「座右の銘」前坂俊之著
0234/1000「若者よ。君たちが生きる『今日』という日は、死んだ戦友たちが生きたかった『未来』だ。」BY戦艦大和語り部 八杉康夫氏

6月23日は「沖縄慰霊の日」です。
日本人にとって忘れてはならない特別な一日であります。
今から74年前の1945年3月下旬から米国沖縄に上陸し、約3ヶ月に及ぶ激しい地上戦が繰り広げられ、一般住民を巻き込み、20万あまりの尊い命、沖縄の文化財、自然がことごとく奪われた沖縄戦であります。沖縄県民の4人に1人が犠牲になったと言われています。
日本軍の組織的戦闘が終結した日が6月23日であります。この日を沖縄慰霊の日として制定されました。
先日、沖縄戦に関わる記事を拝見し、目頭が熱くなったので紹介させていただきます。
ひすいこたろうさんの著書「明日死ぬかもよ」という死生観を考えさせられる内容であります。
1945 年(昭和 20 年)3月末、アメリカ軍はいよいよ沖縄まで迫ってきていました。
アメリカ軍が沖縄海域に集めた戦艦は1500隻以上、兵力はのべ54万8千人。
一方、日本軍の守備隊は8万6千人。大きな差がありました。
もし沖縄が落ちれば、「本土」九州は目と鼻の先。
「沖縄が落ちれば、次は本土決戦だ」と言われていました。
「沖縄はなんとしてでも死守したい、万が一、沖縄が落ちたとしても、本土決戦の準備を進める時間を稼ぐため長引かせたい」。
そこで編み出された戦法が「特攻」でした。
「特攻」は、爆弾と片道分の燃料を積んだ飛行機に乗って、そのまま敵の戦艦に体当たりして沈める自爆攻撃です。
飛行機1機の犠牲で、相手の戦艦を沈められますが、乗組員は「死ぬのが当たり前」「生きて帰ることは望めない」という非人道的な作戦でした。
特攻隊の多くは、まだ未婚の14歳~20歳前後の青年でした。つまり「妻や子どもなど、養う家族のいないもの」が優先されたのです。
上官が「特攻隊員に志願せよ」と言うと、その場で全員が志願されたそうです。
その中から毎回 10名くらいが指名され、宿舎を出発していき、もう二度と帰ってきませんでした。残っ た人はまた志願して、指名されるのを待ちます。
特攻の志願兵をまとめる教官の一人に藤井一中尉と言う方がおられました。
藤井中尉は少年飛行兵の教官でした。教え子たちが次々に特攻隊として死んでいく。
しかし、自分は安全な場所にいる。
「日本が本当に大変なときに、おれは教えるだけで本当にいいのか。」
と、藤井中尉の自問自答と苦しみが始まります。
少年兵と違い、藤井中尉には妻も子どももいました。
自ら志願すれば、妻や子どもとは永遠にさよならです。
妻は特攻に行くのは大反対で、夫の志願を来る日も来る日も思いとどまらせようと懸命でした。
しかし、藤井中尉が悩んだ末に出した答えは、 教え子に対して「お前たちだけを、死なせはしない」という特攻への道でした。
しかし、面倒を見なければいけない家族が多い将校は、特攻には採用されないのが 原則でした。
志願は却下されました。
それでも藤井中尉の決意は変わらず、嘆願書(たんがんしょ)を再提出するのです。
夫の固い決意を知った妻の福子さんは、
「私たちがいたのでは後顧の憂い(自分が死んだあとの心配事)となり、
思う存分の活躍ができないでしょうから、
一足先に逝って(死んで)待っています」
という内容の遺書を残して、当時3歳間近の長女と、生後4か月の次女に晴着を着せて、知覧基地近くの極寒の荒川へ身を投げたのです。
妻子の死を知り、藤井中尉(当時 29 歳)は、今度は指を切って、血ぞめの嘆願書(たんがんしょ)を提出し、ついに特攻志願が受理されます。
藤井中尉の亡きわが子への遺書が残されています(字は原文のまま)。
「12月になり冷たい風が吹き荒れる日、
荒川の河原の露と消えた命。
母とともに血の燃える父の意志にそって
一足先に父に殉じた、哀れにも悲しい、
しかも笑っているように喜んで母と消え去った幼い命がいとうしい。
父も近くおまえ達の後を追って逝けることだろう。
必ず今度は父の温かい胸で抱っこしてねんねしようね。
それまでは泣かずに待っていてね。
千恵子ちゃんが泣いたらよくお守りしなさい。
では しばらく、さよなら。」
そんな思いを残して藤井中尉は特攻隊の一人として飛びたち帰らぬ人となった。
という内容であります。
藤井中尉は、特攻に行かなくてもいい地位にいたのに。 藤井中尉はなんのために、その命を投げ出したのでしょうか。
藤井中尉だけではありません。
すべての特攻隊員は、なんのために、その命を投げ出したのでしょうか。
あなたは、特攻隊員の死や生き方をどう思いますか。
あなただったら、どう生きるでしょうか。
そして、あなたは今その命をどう使って、どう生きていきますか。
このようなことを自らの心に問われているような気になりました。
私たちがこうして毎日、しあわせに生きてられるのは、後世の日本人のために命をかけて日本という国を守って下さった人たちがおられたからだと思います。
0235/1000「発見の旅とは、 新しい景色を探すことではない。新しい目を持つことなのだ。BYマルセル・プルースト(仏作家)」
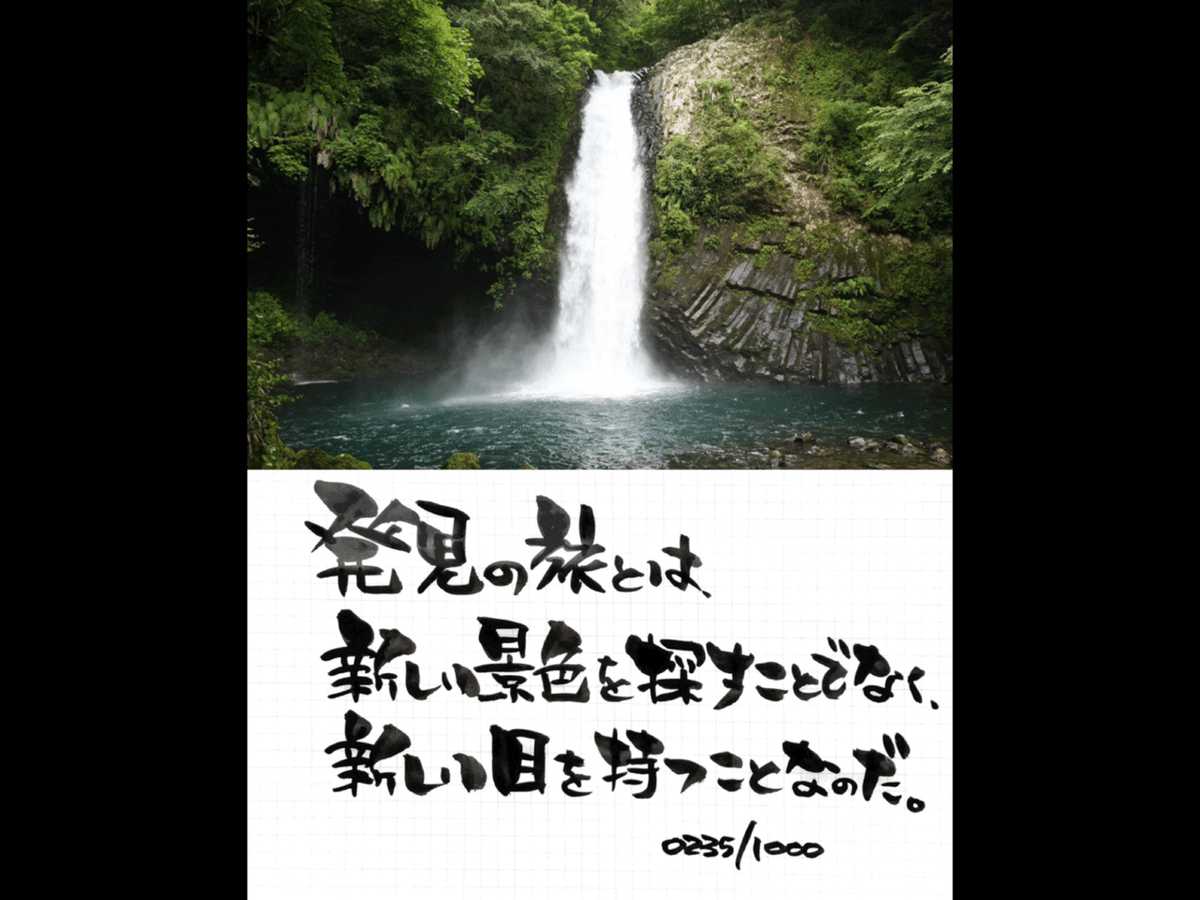
人生はたくさんの見方をできるようになることが大事です。
同じ風景でも、違って見え、同じ仕事でも、異なるように見ることができます。
これができるようになると
人生の幅も
仕事の幅も
人間力の幅が広がりまります。
「上善は水の如し」善き人生は水のようです。
水は飲むだけのもではないんですね。
最上の生き方は、水のようなものです。
水は自ら低い方へと流れていき、他と競争することがありません。
自ら低いところへ身を置こうとする謙虚さと、どんな形にも変化する柔軟さを、水に学ぶ視点も大事ですね。
0236/1000「大人が輝けば、子どもが輝き、子どもが夢や希望をもつ。大人のあきらめない姿が、子どもに夢や勇気を与える。」

福島正伸先生のエピソードより。
小学1年生に夢を描いてもらったときに、ある男の子が意外な夢を書いていた。
「将来の夢、駅でティッシュを配ってるお兄ちゃんになりたい。」
なんで??
「お兄ちゃんが、すごく楽しそうだった。」
子どもは、職業の名前で、夢を見つけるのではなく、僕たちの働いてる姿を見て、夢を描くのです。
楽しそうに仕事をしている姿。
イキイキと輝いてる姿。
誇りを持って本気で仕事している姿。
そんな、僕たちの元気な大人の姿に、子どもは、夢や希望を描いていくのです。
子どもたちのためにも、夢に挑んでいる背中を魅せていきたい。
0237/1000「『今』と『ここ』を充実することが、人生を輝くものにできる唯一の方法」
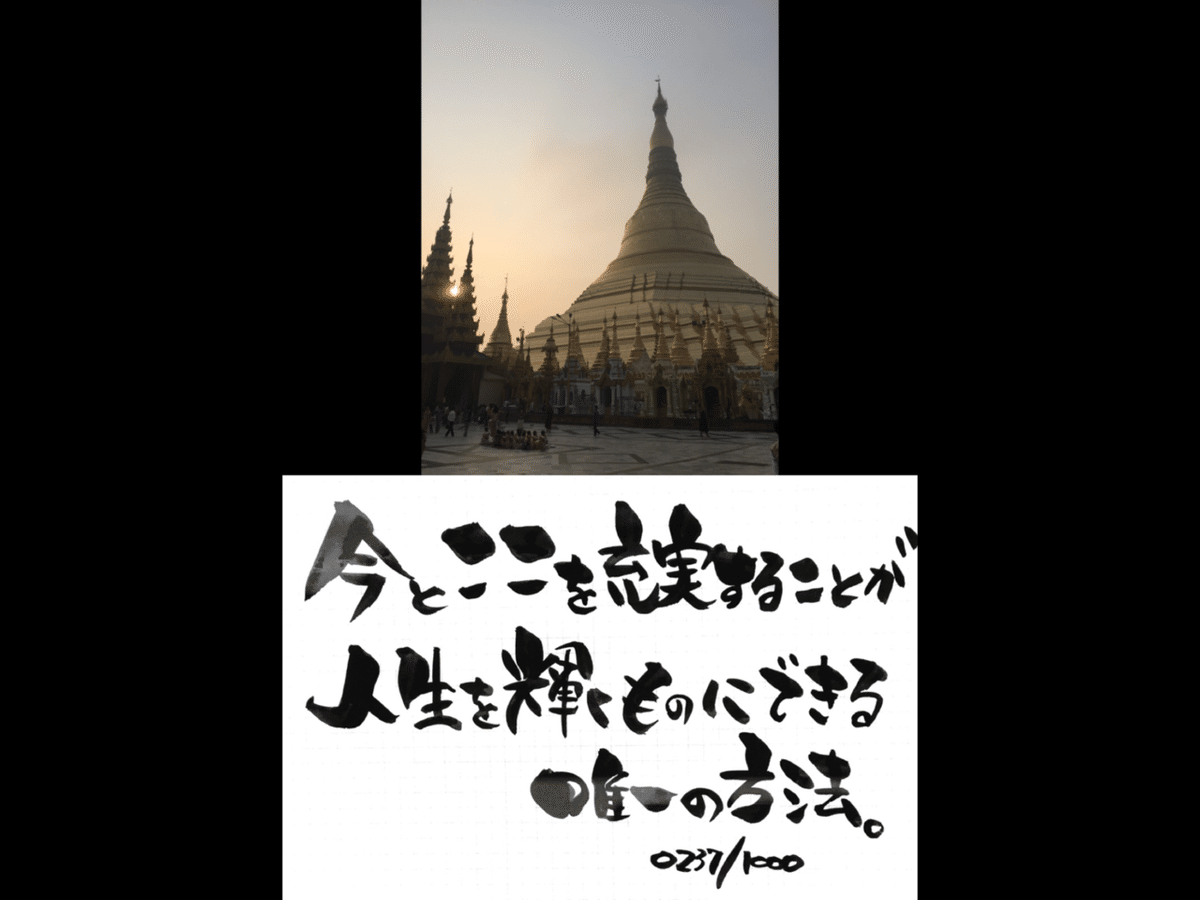
私たちの悩みの多くは、過去を後悔しているか、
未来に不安に思っているかのどちらかです。
過去も未来も手放して「今」に生きたら悩みはなくなるのです。
でも、今に生きてるけど悩んでいる人もいます。
時間軸が今にあっても、
視点が「ここ」に定まっていないからです。
周囲に焦点がいっていると悩むものです。
時間軸を「今」に合わせて、視点を「ここ」に置くことです。
今とここを充実することが、人生を輝くものにできる唯一の方法なのだと思うのです。
0238/1000「大きくジャンプするときは大きくしゃがむ。今、苦しんでいるのは、大きく飛躍するための準備期間。」

苦しいという字は、90度右回転させると「叶」うという字になります。
今の苦しみは、自らの手で夢を叶えるための助走期間なのです。
0239/1000「弱い者ほど相手を許すことができない。許すということは強さの証だ。BYマハトマ・ガンジー」

山が素敵に見えるのは、
谷があるからだね。
晴れがうれしいのは、
雨が降るからだね。
ご飯がおいしいのは、
空腹な時間があったからだね。
幸せを感じることができるのは、
幸せを感じない時間が、
いっぱいあったからだね。
許せない人がいるのは、
いつの日か
許す体験をするための
前準備だったんだね。
0240/1000「辛い気持ちは心の筋肉痛なのだ。」

メンタルも筋肉も強くなるメカニズムは同じです。
負荷もかけないのに心が強くなることはありません。
心が折れるほどの辛さを味わい、そこから超回復するときにはじめて心は強くなるのです。
辛い経験は心を強くするために欠かせないものです。
辛い思いは「心の筋肉痛」なのです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
