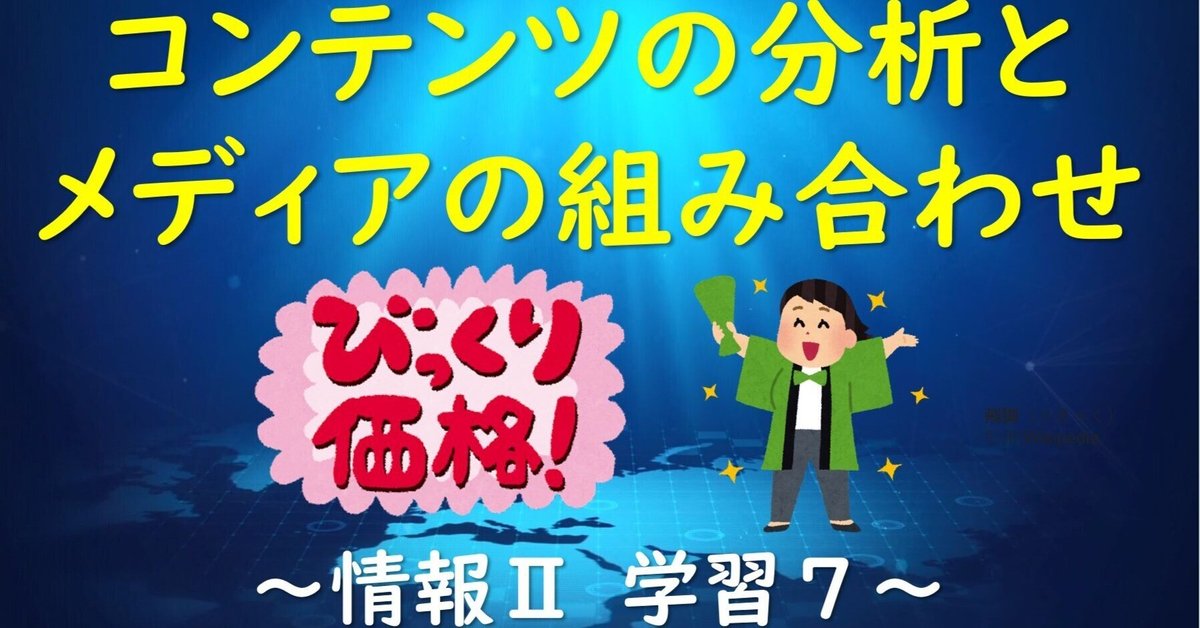
【情報Ⅱ】コンテンツの分析とメディアの組み合わせ(学習7)キーワード:プロトタイプ(試作品)、ラッピング広告 、デジタルサイネージ、メディアプランニング、インフルエンサー、クロスメディア、メディアミックス
コンテンツの分析とメディアの組み合わせ(学習7)
情報Ⅱ動画教科書
資料ダウンロード
文字おこし
今回は、広告などのコンテンツの分析とメディアの組み合わせについて解説していきます。
コミュニケーションを適切に行うためには,言葉だけではなく目的や状況に応じて、相手に正しく伝えるためにポスターなどのコンテンツを制作することがあります。
書店や小売業コンビニなどでは、店舗独自で、商品などの説明を行う店内広告である、POP(Point of Purchase Advertising)が使われることがよくあります。
最近は、顧客のニーズやエリアの特徴に合わせて店舗独自にPOPなどの広告を内製するようになっています。
制作費用が削減できるだけでなく,各店舗から寄せられる要望に対して迅速にきめ
細かく対応できるようになり,効果的な広告展開を行うことができるようになっています
文部科学省情報Ⅱ教員研修用教材では内製化の流れのイメージが説明されています。
まずは、担当がヒアリングを行い店舗のニーズをラフに落とし込みます。
そして、担当率いるデザインチームに指示書で作成を指示して、社内にある
大判プリンタなどを使い販促物を内製化します。
また、機械にたよらずに手書きで味のあるPOPを作成することもあります。
WEBシステムのデザイン作成においては、短いスパンでプロジェクトが繰り返
され,企画の検討に使える時間は非常に短い場合が多いです。
そのため、効率的にプロジェクトを進行するために,開発初期から簡易な試作品であるプロトタイプ を開発し,画面のレイアウトデザインを作るデザイナーと実際にコンピュータで動くようにするエンジニアの意識の違いを埋める工夫がされています。
このように、コンテンツ制作の現場でプロトタイプを使用することで,専門家ではないプロジェクトメンバーとも具体的な問題点を共有でき,最終的な仕上がりのイメージをもとに,行うべき修正の内容と最終的に実現するべき体験を短時間で把握することができます。
企業経営において広告は販売促進のために無くてはならないものです。
たとえば、タクシーやバスなどの場合
商品イメージに応じてデザインした特別仕様のシートなどで車体を包む,ラッピング広告 (車体広告) の手法が取り入れられています。
また、社内においても、表示と通信にデジタル技術を活用して平面ディスプレイやプロジェクタなどによって映像や文字を表示する情報・広告媒体である「デジタルサイネージ(
電子看板)」が設置されていることも多くあります。
デジタルサイネージは、社内でみる小さなものから、ビルに設置される大きなものまでさまざまなものがあります。
また,単に広告を流すだけでなく,特典やクーポンの発行も行われるなど,新たな広告メディアとして活用する動きが広がっています。
広告主がターゲット顧客などに対して、効率的に広告を届けるために出稿するメディアや、露出するタイミング、露出方法などを計画することをメディアプランニングと言います。
「他の学校の生徒にも自分たちの学校の文化祭で企画を楽しんでもらい、自分たちのクラスにも来てもらう」という目標を立てたとします。
これを実現するためには,
まずは、ターゲットが文化祭があることを知る、興味を持ってもらう、詳しく調べる、
行こうと思う、学校に行く、クラスに向かう、クラスに入る、楽しむというような段階があると考えられます。
それぞれの段階ごとに適した情報が対象に届くように計画を立て、段階ごとに複数のメディアを組み合わせて使い,段階が変われば,使用するメディアの組み合わせも変える必要があります。
このメディアプランニングの中で特に重視しなければいけないのが、
「興味を持つ」という心を動かす段階と,「行こうと思う」という行動を起こす段階です。
メディアプランニングの目標は,この2つの段階を実現することでもあります。
心を動かすについて「他校の生徒」という対象の心を動かすための方法を詳しく掘り下げていきます。
ただ単に「文化祭がある」という情報より,「楽しそうな文化祭がある」という情報にする
には,文字より画像,さらに画像より映像・動画の方が効果的です。
それらを組み合わせることによって,更に大きな効果が生まれる可能性があります。
その情報が「誰からどのように伝えられるか」ということも重要になります。
例えば,街で見かけたポスターに文化祭の情報が書いてあるのと,
その人がSNSでフォローしている人が「〇〇高校の文化祭おもしろそう」とつぶやくのでは,
後者の方が、心動かされる可能性があります。
ポスターなどで不特定多数に情報を伝えるとともに,SNSで活躍している各学校の生徒に自分の学校の文化祭について語ってもらうようにお願いするなどの方法を併用することも考えるとさらに周知できる範囲はひろがります。
これに加えて,インターネット,テレビ,ラジオ,新聞など、大衆を相手としたマスメディアでの告知を活用することも重要になってきます。
SNSなどで多数の人に影響を与える個人のことをインフルエンサーといいます。
多くのフォロワーや,メッセージの再転載などで,情報を広く拡散する効果が期待できます。
このように、テレビ・新聞・ラジオ・インターネットなど複数のメディアを使って宣伝して、周知の範囲を広げ、より多く対象に情報を発信することを、「メディアミックス」といいます。
次に行動を起こすについて掘り下げてみていきましょう。
人は,興味を持っただけでは行動は起こしません。
行動を起こすためには,それなりの強い動機が必要で,そのためには,納得のできる理由を準備しなければいけません。
例えば,ポスターや新聞などの告知文に二次元バーコードをつけておいてスマートフォンですぐ調べられるようにしたり,SNSでつぶやく際に文化祭の案内のURLをつけておいたりするなど,興味を持ったら、すぐに詳細が調べられるようにしておくことで,「行動を起こす」ことにつなげることができます。
「心を動かす」段階では,短くて印象的な情報が有効です。
「行動を起こす」段階では,納得のできる理由が必要なので,Webサイト等で,文化祭の容や,学校までの経路,過去の来場者の感想など,より具体的かつ詳細な情報を提供する必要があります。
このように複数のメディアで段階を追って情報を伝えるという考え方のことを「クロスメディア」といいます。
先程の、メディアミックスとの違いは、目的に合わせて発信するメッセージがメディアごとに変わっていく点にあります。
クロスメディアでは、複数のメディアを連動させることで、それぞれのメディアの長所と短所を補いながら相乗効果を引き出すことが可能になります。
このように、メディアプランニングでは,このように段階を追って適切な情報を提供することと,対象をスムーズに次の段階に誘導することの両方を計画する必要があります。
今回のコンテンツの分析とメディアの組み合わせの単元は以上になります。
最後までご視聴ありがとうございました。
解説キーワード
POP(Point of Purchase Advertising)、プロトタイプ(試作品)、ラッピング広告 (車体広告)、デジタルサイネージ、メディアプランニング、インフルエンサー、クロスメディア、メディアミックス
【引用・参考文献一覧】
文部科学省 教員研修用教材
https://www.mext.go.jp/content/20200609-mxt_jogai01-000007843_002.pdf
出版各社 情報Ⅱ検定教科書(キーワードを抽出)
デジタルサイネージ – Wikipedia
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
