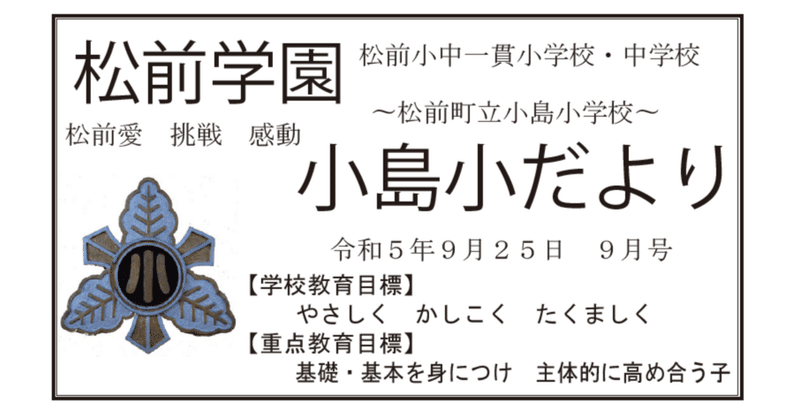
松前町立小島小学校だより【9月号】
社会情動的スキル( 非認知能力) の育成
校長 藤谷 毅
猛暑日の続いた今年の夏の暑さも一段落し、朝夕の涼しい風が秋の訪れを感じさせる季節となりました。子供たちも10 月15 日( 日) の学習発表会に向け、少しずつ練習に熱が入ってきており、大変微笑ましい光景がたくさん見られます。
さて、8 月28 日( 月) に北海道教育大学附属函館小学校長の橋本忠和先生をお招きし「SpheroBOLT( スフィロ ボルト)」を使ったプログラミング学習を行っていただきました。BOLT( ボルト) を使って前後左右に進めるプログラムを組んだりしましたが、この学習の最終目標は「子供たちの社会情動的スキル( 非認知能力) の育成」にあります。
認知能力とは、知識、計算力、思考力などのいわゆる「学力」といわれるものを指します。テストで点数がとれる頭がいいといわれる人はこういった認知能力の高い人を指すことが多かったですね。
それに対して非認知能力とはOECD の定義によりますと「目標の達成(忍耐力・自己抑制・目標への情熱)」「他者との協働 (社交性・敬意・思いやり)」「情動の制御(自尊心・楽観性・自信)」に関わるスキルなど、数値化できないものであるとしています。そしてこの能力が今後の社会を生き抜いていくために必須なスキルと言われています。上記項目を見て頂いてわかるかと思いますが、自己抑制や社交性、自尊心など学校だけでは育むことができない項目であることに気づいて頂けるかと思います。学校とご家庭が連携して少しでも上記の内容に気を配って育てて頂けるといいなと思います。どうぞご協力をよろしくお願いいたします。
地域に開かれた学校を目指して
小島小学校では、小島地区の皆様に学校を訪れてもらい、学校の様子を知っていただきたいと考えております。
そこで、学校図書館を地域に開放することを企画し準備を始めています。11月を目処に地域図書館(仮称)を開始いたします。進捗状況は、来月の学校通信でお知らせいたします。

プログラミングに挑戦
北海道教育大学附属函館小学校の先生を迎え、小島小学校の児童がプログラミングの学習に挑戦しました。今回行ったのは、自分でプログラングした命令をボール型のロボットに送り、動かすというものです。
子供たちはすぐに慣れ、自分の思う様にロボットを動かすことができていました。コンピューターやロボットを操作するという面白さに加え、自分の考えたことがしっかりと伝わりうまく動かせた時の達成感を味わうことができました。

森 林 学 習
西部森林室の方々を迎え、木に親しむ「木育」の学習をしました。ステンドグラスやコースターを作る体験学習もあり、子供たちは楽しく学んでいました。

自分の良さや将来を考えて
スクールカウンセラーの阿部千春先生を迎え、高学年を対象に、夢をもつことや自己有用感を高めることの大切さについてお話ししていただきました。
どんな言葉をどの様にかけられるとうれしいかを発表しあう場面もあり、子供たちは改めて自分自身を見つめていました。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
