
DATASaberBridge [Ordeal 0-4]
データを理解する表現の力 #DATASaberBridge [Ordeal 0-4]
※動画を見て感じたこと、考えたことをまとめていきます。
「データは数字で見たほうが正確」という誤解
明確な判断基準がある時、初めて数字に意味が出てくる。
言い換えると、文脈によって数字の意味が変わってくるということで、その文脈はストーリーテリングによって表現される。
当然、判断基準やストーリーにはそれを見出す(確定する)段階があって、その段階ではバラバラに見える数字の、それぞれの関係(大小や相関、傾向、類似…)を整理して理解することが重要になる。そこではビジュアル表現が圧倒的に優位となる。
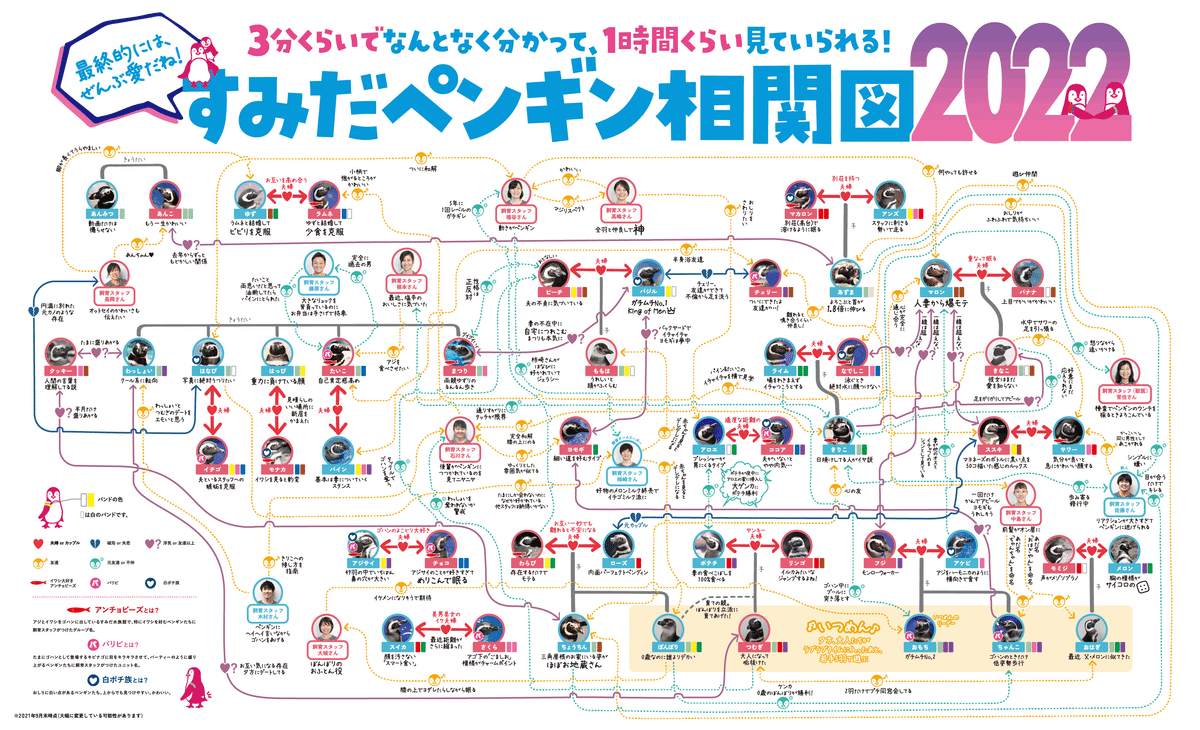
数字を恣意的に見せるということではなく、数字の理解に補助線を引くというイメージだ。
分析とは比較、視覚的に比較する技術がビジュアル表現
「分析とは何か?」
僕の答えは「分析とは比較、すなわち比べること」というものだ。分析と言われるものに共通するのは、フェアに対象同士を比べ、その違いを見ることだ。
実はみなさんが日々行っている数字を使った分析の本質は「比較」にあるのです。「比較をしない分析はない」と言っても過言ではありません。
比較をすることで数字という原石から意味を抽出するのが分析です。
分析とは比較すること。であれば、比較を正確に迅速に行うことは分析を素早く正確に行うことだ。ビジュアル表現による視覚的・直観的な比較は、数字が並んだクロス集計表で数字を見るよりも格段に速い。
ところで、『イシューからはじめよ』を読み返して気づいたのが「フェアに対象同士を比べ、その違いを見る」という点の鋭さだ。
フェアに、つまり定義を揃え、定義の理解を一致させて運用を統一しなければ比較が意味のないものとなってしまう。
17歳のころに初めてアルバイトしたコンビニでは、レジを打つ時にお客さんの性別と年齢層を示すキーを押す必要があった。いかに早くレジを打つかに情熱を燃やしていた自分からすると、やはり押しやすい位置にあるキーがあって(キーボードでいうエンターキーのようなもの)、どうしてもその客層キーを押すことが多くなっていた。客層のデータが本部に送られ、店舗の客層や商品の購入傾向の分析に使われることは教えられていたが、あまり深く考えていなかった気がする。現場での運用が勝手気ままになっていると、得られたデータをフェアに比べることはできない。
(当時10代のバイトにそうしたデータを見せてくれていたコンビニのオーナーや店長に感謝。思えば商品発注を任せてもらったのがデータを見て予測を立てた最初だった)
置いていないものは見えない
安宅さんはイシュー特定のアプローチとして視覚化を挙げている(『イシューからはじめよ』P.90)。
イシューを特定すると判断基準が明確になるし、文脈やストーリーが定まってくる。イシューが特定され、判断基準が明確になって、ようやく数字は意味を持ちはじめる。ビジュアル表現はイシュー特定に有用な技術だ。

イシューを特定する作業を進めるに当たって注意したいのが「場に置いていないものは見えない」ということだ。
つまり「場に置くデータをどれにするか選ぶ力が問われる」。
つい最近、仕事でのこと。
スタッフの稼働状況と業務量を見ていた。特定部署に絞ってスタッフの稼働状況を集計し、ひとりあたりの業務量を年月別の推移で見た。この時、実は直近で一部のスタッフが別部署の業務を行う必要があったため、所属はしているものの当該部署での業務量には影響しない状況にあったことを見落としていた。
実態を知らないまま分析を進めていたら、一人当たりの業務量が低下している(生産性が落ちている)という見立てになっていたし、それは正しくない。
場に置くデータをどれにするか、選ぶにあたっては、それらのデータがどのような「ひとの動き」によって生まれたものなのか理解することが必要だ。
現場感覚を忘れてはいけない。

この記事で引用した本やサイト
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
