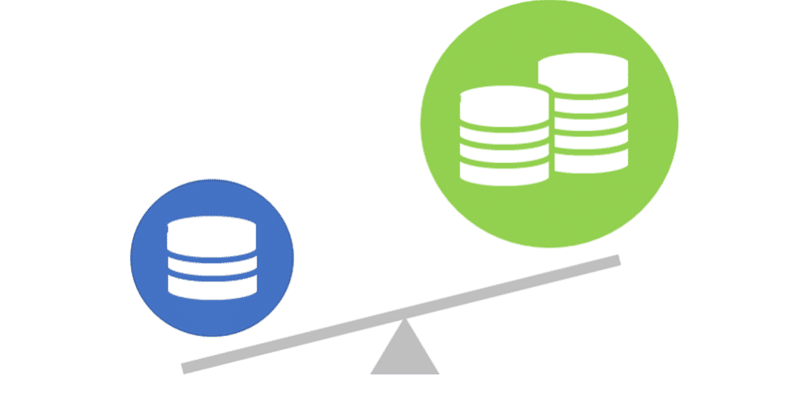
FXもう一度やってみるよ⑪ 課題と対策③ レバレッジ
今年2019年初の記事です。こんにちは。
フラッシュクラッシュで幕開けした2019年。どんな1年になりますかね。怖さ半分、ワクワク感半分といったところです。
今回のフラッシュクラッシュで大損こいた方、結構いるんではないでしょうか。私の好きなyoutuberさんもそれでロストカットされて、ヒロセ通商にスプレッド広げすぎだ!ってキレてました。
ロストカットは、要は資金の量と持っている通貨数のバランスをコントロールするしかないので、ロストカットをくらうということは、資金に対して量を持ちすぎなんです。そこを見つめなおさないと、結局FX会社に振り回されるだけです。
短期で買った負けたのトレードなら、負けの規模は損切りラインを置くことで自分でコントロールできます。なので想定外の値動きをしても、損切り注文が飛ばずに刺さりさえすれば、損失は想定範囲に収まります。しかし、長期で持ち続ける戦略においては、どんな値動きにも耐え切る必要があります。なので、資金に対しての通貨量の管理はすごく重要です。つまりはレバレッジですね。
ということで、今回はこのレバレッジについて考えます。
なお、前回までで、一回の購入資金と購入サイクル、通貨ペア、FX会社の選択など、枠組み的なことは一通り終って、今回からは実際の運用における戦略、戦術的な話に入ります。
ここからは工夫のし甲斐があるところなので、私の例を参考にしていただいて、自分なりの戦略、戦術を工夫してみてください。
勝ち負けとは別の楽しさがあると思います。
何ドル買う?
積み立てはドルじゃなくてもいいんですが、説明しやすいのでドルで。
証拠金が100万円。1ドル100円。ロング(買い)のサインが出ている。ポジションは何も持っていない。
普段ならこの状態で、何ドル買いますか?
1万ドル?10万ドル?
ここは考えるとけっこう難しいです。私の場合は積み立てとは別に、買った負けたの通常?のトレードもしているので、そっちのトレードでは、基本1ポジション1万通貨としています。それで同時にマックス10ポジションくらいまで、という制約を自分に課しています。
まあこれには正解はありませんし人それぞれでよいのですが、ただ言えることは、数量の感覚がデイトレやスイングトレードのときと同じままでは、先日のようなフラッシュクラッシュを食らってロストカットされるのがオチです。
実際、↑で触れた私の大好きなyoutuberトレーダーさんも、十分な資金でやっていた、リーマンショック級にも耐えられるくらいの証拠金維持率でやっていた、と言っていました。そのくらいの感覚でやってても、ロストカットを食らうわけです。
ということは、もうデイトレとかスイングトレードとか、そのような比較的短期間でのトレードでのレバレッジの考え方とは、まるっきり別物にする必要があるということです。
そのために必要なのは、レバレッジをリスクとして捉えることです。
レバレッジのリスク
1ドル100円のときに、仮に10万ドル買うとします。
このときのリスクを具体的に見てみます。

もしレバレッジをかけなければ、100万円で1万ドル買えます(実際には必要証拠金の分、購入できる数量は1万ドルより若干少なくなりますが、説明を簡易にするために無視します)。
それに対してその10倍の10万ドルを買うわけですから、レバレッジは10倍です。
さて、この状態で、1ドルがいくら値下がりしたら証拠金が枯渇するでしょうか。
証拠金100万円を数量の10万で割ればいいので、
100(万円) ÷ 10(万ドル) = 10(円)
10円値下がりで、証拠金が枯渇します。
この、いくら値下がりしたら証拠金が枯渇するか、というのが、レバレッジをリスクとして捉える考え方です。
レバレッジの式
ためしに5万ドルを買った場合や20万ドルを買った場合などを考えていくと見えてきますが、レバレッジ○倍とは、元の価格の○分の1の値下がりまで耐えられる、ということとイコールです。
レバレッジ10倍 = 元の価格の10分の1の値下がりまで耐えられる。
レバレッジ2倍 = 元の価格の2分の1の値下がりまで耐えられる。
式にすると、
レバレッジ = 元の価格 ÷ 許容値下幅
です。
レバレッジの適正値
式にできたので、今度はレバレッジの適正値を考えます。
式は
レバレッジ = 元の価格 ÷ 許容値下幅
なので、この「元の価格」と「許容値下幅」を決めるわけですが、あてずっぽうでは意味がないので、積み立てる通貨ペアの過去チャートを見て決めましょう。
米ドル円で考えてみます。
まず「元の価格」。
過去10年の平均価格がおよそ100円程度。なので「元の価格」は100円とします。
次に「許容値下幅」。
これは、過去の安値を決めて、元の価格との差から求めます。
10年前(2008年)の12月は、リーマンショックでだだだだだーっと相場が崩れている最中で、そのときはまだ90円くらいでしたが、その後さらに下げ続けて、2011年の11月あたりで76円を割りました。これが直近10年の最安値です。
なので、まあ区切りよく70円まで見ておけば、だいたい案パイかな、という感じです。
「許容値下幅」は、元の価格の100円から70円までの差の30円とします。
100 ÷ 30 = 3.33(小数点第3位を四捨五入)
米ドル円のレバレッジは3.33となります。
私は豪ドル円で運用しているので豪ドル円でもやってみます。
過去10年の平均価格は85円、最安値は55円なので、「元の価格」を85円、「許容値下幅」を30円(85-55)とすると、
85 ÷ 30 = 2.83(小数点第3位を四捨五入)
豪ドル円のレバレッジは2.83となります。
参考までに、ポンド円でもやってみます。
過去10年の平均価格は148円、最安値は116円なので、「元の価格」を148円、「許容値下幅」を32円(148-116)とすると、
148 ÷ 32 = 4.63(小数点第3位を四捨五入)
ポンド円のレバレッジは4.63となります。
ポンド円はちょっと高めに出ましたが、これは元の価格に対して許容値下幅が少ない(あまり値下がりしない)からです。確かに過去10年のデータから求めるとこうなりますが、4.63倍はちょっと高すぎる気がします。何故なら、ポンド円はほんとうはもっと大きくうねる可能性がある通貨ペアなので。
現在(2019年1月)は140円程度ですが、2007年では240円。現在より100円も高かったのです。過去10年の視界ではそこが見えません。ちょっと扱いが難しいと思います。
「元の価格」や「許容値下幅」に当て込む値に正解はないので、上記で求めたレバレッジじゃなければダメというものではありません。ただ、目安としては、2倍~3倍が妥当。4倍以上になると危険、という感じかなと思います。
実質レバレッジ
さて、長期積み立てではポジションはどんどん増えていきます。個々のポジションの数量も、その時々の価格によって違ってきますし、レバレッジは定期的に見直すべきものなので、レバレッジを見直すことでも数量は違ってきます。こうしてポジションがどんどん増えていったときに、全体のリスクの把握はどうすればいいでしょうか。
個々のポジションのレバレッジはあまり意味がないということは感覚的に分かると思います。
じゃあどうするか。
結論としては、1つの大きな統合されたポジションをイメージします。

1回の資金:1万円、購入サイクル:毎日、レバレッジ:2倍を1年間継続したとします。
資金は、1万円x20日x12ヶ月=240万円。
ポジション数はだいたい20日x12ヶ月=240個。
この240個のポジションを統合した1つの大きなポジションをイメージします。
図の例だと、この統合したポジションの数量は5万ドル、平均価格は100円です。つまりこれは、1ドル100円のときにまとめて5万ドルを購入したのと同じです。
この統合したポジションのサイズと証拠金から、レバレッジを求めます。
500万円(1ドル100円x5万ドル) ÷ 240万円 = 2.08
レバレッジは2.08倍です。
この、その時点の資金と統合したポジションのサイズから求めた比率を、購入時のレバレッジと区別するために、実質レバレッジと呼ぶことにします。
実質レバレッジをリスクに変換します。
「元の価格」は統合したポジションの購入平均価格である100円を当てはめます。
100円 ÷ 許容値下幅 = 2.08
許容値下幅 = 100円 ÷ 2.08 = 48.08円
つまり、このポジションの購入価格である1ドル100円から48.08円値下がりまで耐えられる、ということです。
100円から48.08円下げると51.92円。
よって、レートが51.92円になるまでは耐えられる、ということになります。
この51.92円を許容最低価格と呼ぶことにします。
この許容最低価格を常にウォッチすることが必要です。これが長期積み立てにおけるリスク管理の肝です。
先に紹介したyoutubeトレーダーさんも、証拠金維持率300%以上保っていたのに!とかじゃなくて、具体的に、レートがいくらになるまで耐えられるかをウォッチしておけば、自動損切りしないスタイル(なんとその人は買った負けたのトレードのくせに損切りを設定しない)の自分にとって、6円や7円程度の値下がりでロストカットされる状態が異常だと気付いたと思うんです。まさか瞬間的にそれほどの値下がりをするのは想定外?いやいや、2015年のスイスフランショック(興味のある方はググってみてください)みたいなのもあったわけで、十分に前例はあるわけで、普通はこんなに下がらないよ・・・というのは言い訳にもなりません。
購入レバレッジの見直し
購入レバレッジは定期的に見直すべきです。過去10年なりの相場状況をベースに求めたものですから、相場状況が変われば、適切な値も変わってきます。
また、資金に余裕が出来たり、価格がかなりの安値圏である場合などでは、一時的に購入レバレッジを上げてリスクテイクしていくのもアリです。
かといって、毎回購入の度に変える必要は無いと思います。
レバレッジ算出式の「元の価格」と「許容値下幅」がそんなに毎回ころころ見直さなきゃいけないほど変わるとは思えませんし、そもそもレバレッジは資金全体とポジション規模の関係なので、もっとどっしりと構え、長いライフサイクルで見るべきだと思います。
いまから10年ほど前の2008年の12月は、その年の9月のリーマンショックで相場が大きく崩れている状態で、ドル円はさらにそこからも下がり続けるので、ちょうど今振り返る過去10年の視界にはそのあたりの記録的な安値がすっぽり含まれます。
ですが、これから月日が経っていくと、たとえば5年後の2023年に過去10年を振り返ると、最安値はおそらく90円くらいになります。70円台という記録的な安値が視界から外れてくるわけです。
2008年というそれほど遠くない過去に70円台まで下げた。通貨ペアとしてそこまで下がる可能性を持っているということです。毎回の機械的な過去10年の振り返りの視界からその安値が外れたからといって、そのリスクが消えるわけではありません(まあこれも時間が薄めていくわけですけど)。
なので、「元の価格」も「許容値下幅」も、過去チャートを参考にした上で、最終的に自分で考えて決定すべきです。
最低でも年1、可能なら毎月見直しをすべきだと思います。
とはいえ、まあ長期積み立てではレバレッジ2倍というのが一つの基準になっているように思います。レバレッジ2倍だと、だいたい価格が半減するまで耐えられることになるので、ちょっと安全に寄りすぎで、そのレバレッジでは買える数量もいまいち少なく感じるかもしれませんが、安全重視ならレバレッジ2倍で固定するのもぜんぜんアリだと思います。レバレッジ2倍は、どの通貨ペアでもかなり安全なレベルだと思います(新興国通貨は除く)。
それでも危険だと感じるなら、いっそレバレッジ1倍で、外貨定期預金的な運用にするのもアリです(普通に銀行で外貨定期預金している人はFXに乗り換え推奨)。
まとめ
長期積み立てでは、レバレッジの意識はとても重要。
レバレッジをリスクとして表現すると、何円の値下がりまで耐えられるか。
購入レバレッジは過去チャートを長期間で眺めて算出。
最低、年1で見直す。
あとは日々、何円まで下がったらロストカットされるかを常にウォッチし、必要に応じて追加資金を投入する。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
