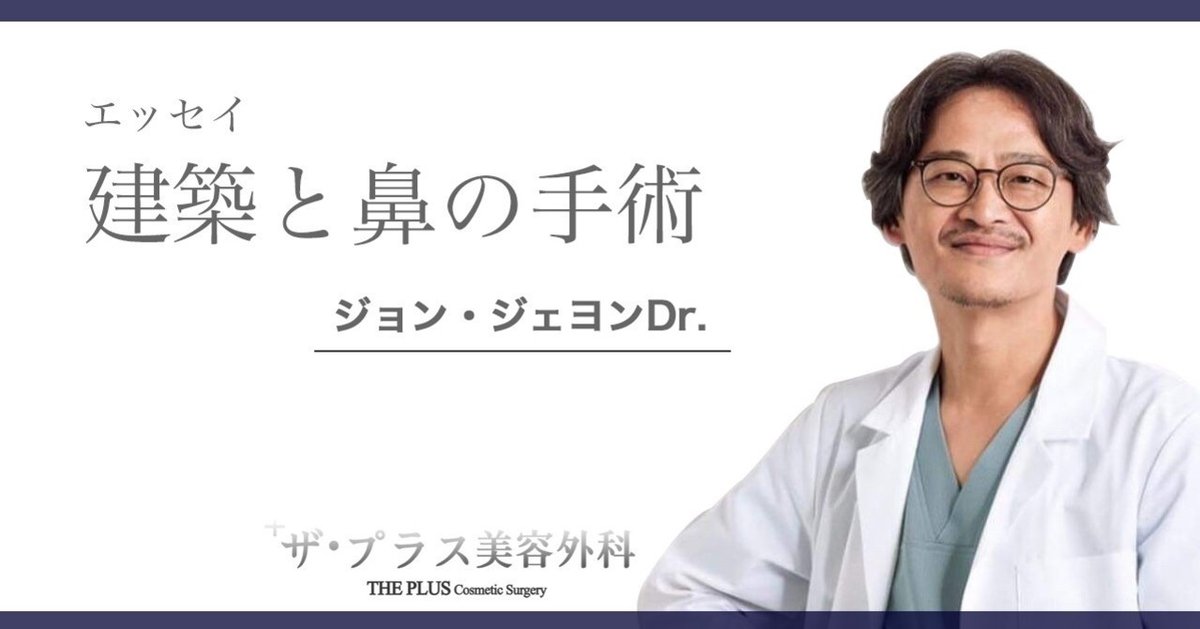
建築と鼻の手術
こんにちは。ザプラス東京広報部です。
まずは下記の動画ご覧ください。
鼻形成術後、1年が経過した方の鼻ぐねぐね動画です。
ザプラス鼻の真骨頂です。
鼻先は硬くなく、このように自由にぐねぐねしても大丈夫な鼻、
鼻中隔延長に頼らない鼻尖形成術1年後の動画です。
今回のnoteはそんなお鼻の建築に関するジョン先生のエッセイです。

建築と鼻の手術
鼻を外科的に扱う事は建築の原理にとても似ていると考え始めたのは、鼻の手術を約4年程行ってからの事であったと思う。
誰も教えてはくれなかったが、毎日手術をしながら考えたことは、頑丈な構造を築く鼻の内部の軟骨と骨組織、それを覆っている皮膚と組織、その間を通る神経と血管、そして適切な呼吸を維持するための鼻腔通路は、素晴らしい建築物のように、顔の中央で生命を維持する一つの関門のごとく働く入口のようなものだ、ということである。
このような経緯で、自ずと建築や建築家達に少しずつ関心を寄せるようになった。
2012年とある初夏、韓国と日本の形成外科医達による恒例の学術行事に招待され、日本の淡路島を訪れた事があった。
正直、日本へは初訪問だった為、東京や大阪でなかったのに少なからず失望したが、旅行ではないのを残念に思いながら出発した記憶がある。
実際、出張が目的の海外旅行は、(訪れる土地に関しての)事前準備がかなり疎かになってしまうのが常である。
下手な英語で講義をしなければならないプレッシャーの為、出発前日まで講義録を修正しながら、その初めての島に関しては、なんら気にかける事もなかった。
学会の場所は、兵庫県に属する小さな島に位置する為、関西空港から再びバスに乗り、約2時間ほど移動しなければならなかった。
神戸を通過し、かなり長い橋(世界で最も長い吊橋である明石海峡大橋という事を後で知った)を渡り、小さな島へ向かう風景は見慣れないものであったが、韓国の南海(ナㇺヘ:韓半島南部にある島)の、あるエリアに似ている気もした。
橋を渡り終えてすぐ目に入ってきた風景は、とある閑静な田舎、それ以上でもそれ以下でもなかった。
学会が開かれた大きなコンベンションセンターの建物の姿が、とても不自然に感じるほどだった。
何も無いような島の真ん中に、このような場所があるとは...。規模を見てとても驚いた。
だが、更に驚き悦ばしいことが、バスから降りて数分足らずのインフォメーションデスクで起こった。
無造作に差し込まれていた案内パンフレットからちらりと見えたホテル左手にある巨大なコンクリートの建物の正体を知って、急に鳥肌がたった。
安藤忠雄の夢の舞台である‘’夢舞台‘’。背筋がぞっとする感覚は、恐怖を抱いた時にだけ湧き上がるのではなかった。
安藤忠雄の作品を直接見れるとは思ってもみなかった私には、淡路島に泊まっていた数日間は、絶えず新しい刺激の連続だった。
とてつもなく大きく、厳ついコンクリートの建物の中に迷路のようにつながる空間と、そこを行き交うたくさんの光と空気、ひっそりとして寂しい空間にサウンドをもたらすせせらぎ、驚くほど雄大で多彩な植物で占められた内部庭園。
まるで、長く様々な方向に伸びる迷路を入念に探索するかのように、講義以外の時間は、見たり、聞いたり、感じたり、踏みしめながら、小さな島で一人過ごした記憶がある。
間違いなくこの経験は、私に大きな影響を与えた出来事だった。
ドイツの建築家ヴァルター・グロピウス(Walter Gropius 1883-1969)が提唱した“機能的図案の新しい感覚”(new sense of functional design)という概念は、“すべての鼻の手術は、機能的な鼻の手術(functional rhinoplasty)にならなければならない”という教訓をもたらしてくれる。
言い換えると、すべての鼻の手術は、頑丈な構造の安定性に基づいて行う美容的な改善のみならず、患者の鼻腔、言い換えると、すべての鼻の手術は、頑丈な構造の安定性に基づいて行う美容的な改善のみならず、患者の鼻腔呼吸に関わる症状まで考慮する機能的な鼻の手術(functional rhinoplasty) にならなければならないということである。
“機能”と“構造”の間の理解を通して、“身体の器官としての鼻”の複雑で多様な役割を把握することは、すべての鼻の手術において基本とならなければならない。
実際に全ての鼻の美容整形手術において先行すべき条件は、鼻腔呼吸通路の維持である。( maintenance of a functional nasal airway )。
もし、手術前のカウンセリングにおいて患者に鼻づまりがあれば、診断と手術計画を通して適切な生理的機能の好転を可能にする手術方法(septoplasty, internal valve reconstruction,turbinoplasty ) を加えなければならないし、必要なら手術後、症状改善のために、内科的投薬治療も併せて行わなければならない。
故に、そのためには全ての鼻の美容整形手術を行う前に、鼻についての機能的な理解が先である。
よく、術者と患者両者ともに、鼻を機能的な部分と美容的な部分に分ける傾向が見られる。
形は美容整形外科の先生へ、機能は耳鼻咽喉科の先生にお願いするという古くからの習わしのために、患者達は悩んでしまうことが多い。
私もよく「先生は機能的な部分も解決できますか」という質問を受ける。
一般的に、基礎的な鼻の美容面の手術は機能的な部分と大きな関連はないが、もう少し複雑な問題を抱えている。
私の患者達の場合は、機能と美容を別々に考える事はできない。家を建てる時に、建物の外観とインテリアを別に考える事は合理的なことであろうか。
設計をして基礎工事をする時、内部構成と動線、その他機能的な部分を考えない建築家はいないだろう。まして、
既に鼻が正常な形を失ってしまっている場合には、二つの問題がより一層混在している。まるで屋根が崩れて人が生活できないほど内部が損壊してしまっている場合のごとく、崩れた鼻が機能的に無傷なわけがない。
美容面の手術だけで、外から見える屋根だけを作り直すのでは、根本的な患者の問題を解決することはできない。
2016年、鼻の手術専門の教科書 ‘Rebuilding Nose’ を執筆しながら、このような問題についてもう少し具体的な考えを整理した経験がある。
今もしばしば私の講義では、建築と鼻との相関関係について例を挙げて説明をしている。
年を経るほどに、完全に異なる二つの分野の思いも寄らない相関関係について、確信を持ちながら手術を行っている。
参考文献
1. ヴァルター・グロピウス(西洋近代建築、ユン・ジョンソプ著、1998.4.25 ソウル大学校出版文化院)
2. 貧者の美学 (スン・ヒョサン著)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
