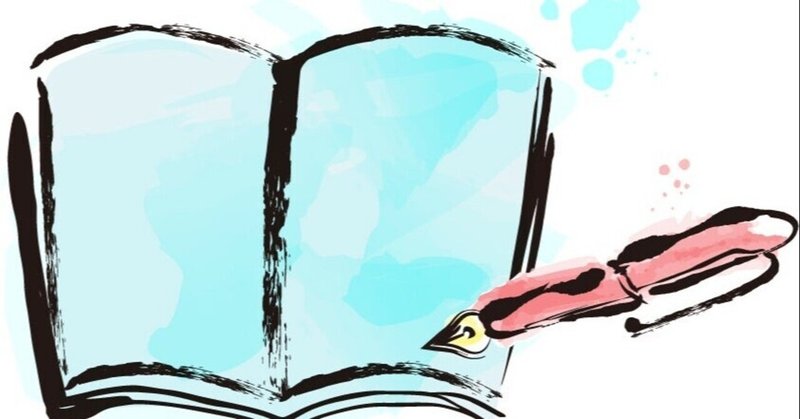
文章の書き方
〈社会人編〉
①冒頭の2~3行(時候の挨拶)は書かずに自分の伝えたい本題から書く。あ とから加える。
②主語は普段自分が使っているものを使う。あとで「私」に変える。
→仮面をかぶって文章を書くな!
〈履歴書編〉
①どのような経験をしたか
②何ができるのか
③あなたの会社に貢献したいです感を出す(具体的に)
・志望する仕事の内容に必要な能力は何かよく調べる。その中で自分がアピールできそうな点を書く。
・まずは能力について1つだけ①→②→③で書く
・能力が複数ある場合は重要度の高い順で①→②→③で書く
・まずは文字数を意識せずに書く→後で減らす
・抽象的なものは具体的に描く(優しく接した→要望に一つ一つお応えした。一生懸命頑張った→一か月に○○件訪問した)
・想像できる範囲で、自分が貢献できる点を書く(効率化を図るためにITの取り組みに貢献できます、プロジェクトがスムーズに進むよう各所との連携を行うことで貢献できます)
・漠然としててもないよりまし(お客様に笑顔になってもらうように、組織全体の効率化のために)
・文末は押しの強い表現を使う。→履歴書全体が勢いのある文章になり、意欲がしっかりと伝わる(学んだ、身に着けた→心がけている)
〈報告書編〉
・構成を決めてから清書する→効率的でわかりやすい
・本論と結論をワンフレーズで表現する(仮見出し)→「~について」は×重要な要素を盛り込む。体言止めを用いる
・序論;論じるテーマと動機を明らかにする導入部分
・本論;序論で明らかにした疑問・問題を分析する(4±1こ)
・結論;本論で明らかにした事実に基づく主張や、残された課題をまとめる。
・一行で要点を箇条書き(時系列、因果関係、重要度の高い順、全体から細部の流れで買う)→一段落とする(100から150字)
・一文は40字から多くて60字
・事例や数字を入れると具体性が生まれる
・一文一意味
・能動体で書く(主語を明示する)
・重要なエビデンスは図表やグラフで表現する
・固有名詞や数字はファクトチェックを
・推敲時参照元の情報に変更はないか確かめる
〈ビジネス編〉
①「不信・不適」どうして自分に(自社に)それが必要なのか
②「不要・不急」相手にとっての重要度・緊急度を上げるにはどうすればいいかを考える
③自分でやる場合のリスクや時間・費用を提示する→高い買い物ではないと思わせる
④実績を情報として伝える
⑤この順番を必ず守る
・リアリティーのある表現を使う(史上最少最軽量です→設置場所が半分で済みます)
・利率7%の高利率な商品です→月にゴルフにもう一回行けるだけの配当が手に入ります
・コストを大幅に削減できます→5000万円削減できるので営業部員を5人増やせます
・売りたい気持ち(自分の都合)ばかり前面に出さない。
→相手の身になって深く考えることで、有効な言葉、響くフレーズがわかるようになる。
〈note,ブログ編〉
・文章は短めに、要点は箇条書きに、重要個所は太字に
・ひらがな:漢字:カタカナ=7:2:1
・一記事一テーマ
・シリーズ化できるテーマやシリーズで
・買わない理由をすべてなくす
〈企画書編〉
・why what how を解消した内容になっているか
・一文は20字以内で
・紙一枚にまとめる
・プレゼンなしで見ただけでわかるのが理想
〈メール編〉
・内容を端的に表した件名を付け、同じ要件でのやり取りは返信(Re:)でつなげる
・要件が変わったら新規メールにして新しい件名を付ける
・メールの文末の署名には、会社の所在地や電話番号を入れておく
→なんかあった時用
・最初に要件を明示する
・切り出しにくい要件は「実はぶしつけなご相談があり、メールを書いております」などの導入部を入れる
・相手の行動を先読みして資料などを添付する
・「お手数をおかけしますが」をつかう
・返信期日の希望を書く
・遅れると困る理由を書く→今後の関係悪化も覚悟のうえで催促する
〈チャット編〉
・返信はできるだけ早くが基本
・基本は9時~18時
・指針を設定しておく(どこまで報連相するか、重要情報の共有方法、メールとの使い分け方など)
・!を添えて感謝の気持ちを伝える
・相手の欲しい言葉を書く
・具体的に伝える
・部下を叱る時はチャットよりも対面やウェブ会議ツールを使用
・幹→枝→葉の順に書く
・急なお願いの時;突然のお願いで恐縮ですが、お力を貸していただけますと幸いです。
・報告を受けたとき;ちゃんと反応する(有難うございます)
・催促するとき;進捗はいかがでしょうか。何か手違いがあったのではないかと心配しています。ご多忙のところ恐れ入りますが、ご確認いただけますと幸いです。
・注意するとき;+-+の順で書く
・気遣いの言葉をかけよう(週末はゆっくり休んでください、ミスはだれにでもあるものです。今回の教訓を今後に生かしていきましょう)
・日付や場所、固有名詞を入れる
〈人を動かす編〉
1 どん底に突き落としてから賛美する(相手をいたわる)
2 相手の心中を先取りして付け入るスキを与えない
3 頼みごとがある→相談がある
〈コピーライティング編〉
・そもそも○○とは何か→常識を疑い固定概念を捨てる
・自分の経験から「たとえば」を作る(映画、小説、漫画など自分の頭に入っているもの。普段意識に上らないようなもの)
・「つまり」を使って本質を探究する
・そのまま受け取ればネガティブなことに対して、意識的にポジティブに解釈する
・目立たせたい言葉のすぐ後ろに句読点を打つ
・言葉選びに対する執着を持つ
〈論文・事業計画書編〉
文章の型
1 結論→内容説明
2 理由→結論
3 問題提起→対立意見を踏まえて自説の展開→根拠、方法→結論
・1,2,3,のいずれかの型を用いる
・結論は抽象化を加える
・具体例を示してこそ内容が伝わる
・目に浮かぶ具体例にする(全国から人が来た→全国の車のナンバープレートがある)
・色や形を思い描けるような表現を加える
・一文は60字以内。まず言い切って、次の文でそれを補足する
反対意見を意識する
・確かに~だ。しかし○○←幅広く様々なことを考慮したうえで判断していますアピール
・理由は3つある。最後が一番説得力のあることを書く。
・さまざまな立場になって読み返す(部署の担当者、若手、ベテラン)実際に読む人だけでなく読まない人の身になって考える
〈ポイント〉
・相手に時間を使わせない
・番号付きの箇条書きにする(味気なくても相手の時間の節約につながればよい)
・手を抜くのではない。むしろ書く文章の精度は高くないといけない
〈日ごろから気を付けること〉
・スタンプや記号⁈を使わない。
→文章力は弱ってしまう。本来の日本語は疑問符や感嘆符がなくても、きちんとした表現ができる言葉である。楽な道に逃げずに
・自分の感情をしっかり伝えることが、文章力の維持強化につながる
・自分の口癖(フレーズ)を別の言葉で言い換える
→表現の幅が広がり、言葉がより豊かになる
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
