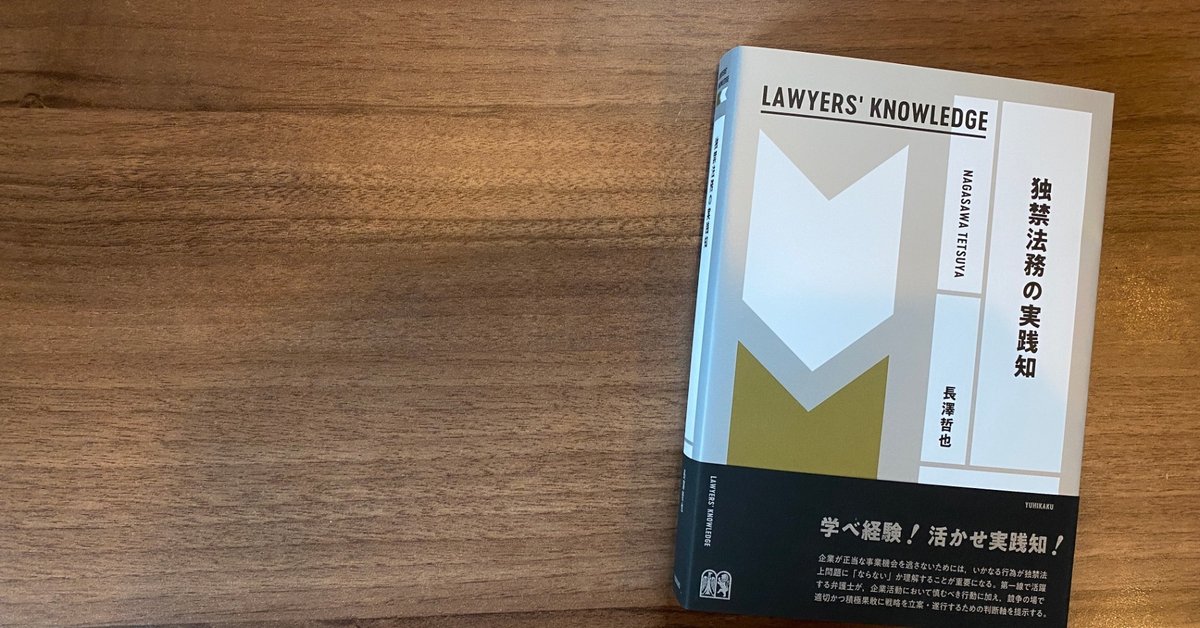
工事業者団体による作業時間短縮の取組
独占禁止法に関する相談事例集(令和元年度)の事例7です。
事案の概要
特定建機を使用する専門工事業者(甲地域所在)を会員とする団体であるX協会が、工事現場における1日あたりの特定建機の作業時間を2時間短縮するよう会員に呼び掛けるとともに、工事の発注者に対しても同様の要請を行うという取組を計画したものです。
事案の概要図は次のとおり(出典:公正取引委員会ホームページ)。
生じうる独禁法上の懸念は何か
工事業者は、工事現場での作業という役務を発注者に提供しています。工事業者が作業を提供する際の「時間」とは、メーカーが製造販売する商品の「数量」に相当するものです。
どれだけ多くの作業を提供できるかは、本来、工事業者間で自由に競争されるべき事柄の一つといえるでしょう。
そのため、工事業者が提供する作業時間を2時間短縮しようとするX協会による本件取組は、工事業者間における作業の提供競争を人為的に回避しようとするものではないかとの懸念を生じさせます。
本件取組を行おうとする目的は何か
競争者間の協調的取組が、もっぱら競争を制限することを目的とするものであり、それ以外に特段の合理的な目的が認められない場合には、そのような行為自体が通常は反競争的です。
そのため、それが実効性をもって行われたならば、競争阻害効果の有無を厳密に分析するまでもなく、独禁法違反となりやすいといえます(実践知16~17頁、41~42頁)。
X協会が本件取組を行おうとする目的は、次のとおり、長時間労働の是正にあるものとされます(2〔相談の要旨〕(2)・(3))。
労働基準法の改正により、建設業界においては、労働時間の上限規制が令和6年4月1日から適用されることから、長時間労働の是正に向けた取組を進めていくことが必要不可欠な状況にある。
X協会が会員を対象に行った調査によれば、会員が雇用している特定建機のオペレーターの年間の時間外労働時間は、規制の上限である720時間を大幅に超過している状況にあり、時間外労働時間を適正な水準まで抑制するためには、工事現場における1日当たりの特定建機の作業時間を最低でも2時間短縮する必要がある。
X協会は、このような状況を踏まえ、会員が雇用する特定建機のオペレーターの長時間労働を是正するために、本件取組を行うことを検討している。
(※原文を一部修正)
これは、X協会が会員工事業者による作業時間の2時間短縮を働きかけることは、工事業者間における作業の提供競争を阻害することを目的としたものではないことを示すものです。
そのため、本件取組は、その競争阻害効果を詳細に分析することなく独禁法違反と即断できるものではありません。
正当な目的を実現するために合理的に必要な範囲内での取組か
公正取引委員会は、本件取組の競争阻害効果の評価に先立ち、本件取組の目的の正当性とそれを実現するための手段の合理性の観点から、分析をスタートさせます。
まず、本件取組の目的について、
本件取組は、建設業界に対する労働時間の上限規制の適用を見据え、会員が雇用する特定建機のオペレーターの長時間労働の是正を図ることを目的としており、当該目的は正当なものである。
と評価しました(3〔独占禁止法上の考え方〕(2)ア(ア))。
長時間労働の是正を図るという目的は競争秩序とは直接関係のない社会公共的なものですが、独禁法においても正当化されます。
次に、本件取組が上記目的を実現するための手段として合理的に必要なものであるかどうかにつき、
特定建機の場合、工事現場での作業の前後の時間帯における事業所と工事現場の往復、点検等については、安全上の問題等から省略することができない。長時間労働の是正には特定建機のオペレーターの数の増加が必要であるが、技能労働者の減少、高齢化の進行等の建設業を取り巻く労働環境に鑑みると、当該オペレーターの雇用を増加することは困難である。このため、当該オペレーターの長時間労働を是正するためには、工事現場における作業時間を短縮するほかない。
また、工事現場における1日当たりの特定建機の作業時間を2時間短縮するという改善案は、会員が雇用する特定建機のオペレーターの労働時間の実態を踏まえ、当該労働時間が時間外労働の上限規制をどの程度超過することになるかという観点から検討されたものであり、合理的なものであると認められる。
したがって、本件取組は、正当な目的に基づいて合理的に必要とされる範囲内のものであるといえる。
とされました(3〔独占禁止法上の考え方〕(2)ア(イ)・(ウ))。
「2時間」という数字を出して作業時間の短縮を働きかけることについては、作業時間に関する競争制限と紙一重ではありますが、上記のようにその必要性を具体的に示して、手段の合理性が認められています。
もっとも、公正取引委員会は、検討の末尾において、「なお」として次のとおり付記しています(3〔独占禁止法上の考え方〕(2)オ)。
本件取組が競争を阻害することがないようにするとの観点から、本件取組を行うに際しては、X協会において、会員からの意見聴取の十分な機会が設定されるべきであるとともに、必要に応じ、会員に対する発注者や知見のある第三者等との間で意見交換や意見聴取が行われることが望ましい。
これは、手段の合理性を担保するための措置と位置付けられるでしょう。
競争阻害効果は生じるか
次に、本件取組による競争阻害性の評価に移ります。
市場支配的な状態をもたらすか
事業者団体が、ある行為によって競争自体を人為的に減少させ、競争を実質的に制限する場合には、独禁法違反となります(8条1号)。
競争の実質的制限とは、特定の事業者や事業者集団が、その意思で、ある程度自由に、価格等の条件を左右することができる状態をもたらすことをいうものと解されています。
競争が実質的に制限されるか否かの判断にあたっては、市場支配的な状態が生じることを妨げるに足りる有効な牽制力がどれだけ消滅するかが評価されます(実践知15~16頁、40~41頁)。
本件において、X協会の会員である特定建機専門工事業者は、甲地域に所在する同業者のうち5割程度を占めており、特定建機の台数ベースでは6割程度を占めています(2〔相談の要旨〕(1))。
もっとも、公正取引委員会は、本件について、競争を実質的に制限するものであるかどうかについては特に言及しませんでした。
需要者の利益を害するか
他方、事業者団体が構成事業者の機能や活動を制限する場合には、それによって上記の競争を実質的に制限するレベルに至らなくとも、需要者の利益を不当に害するものであるならば、独禁法違反とされます(8条4号、事業者団体ガイドライン〔第2の7(2)ア〕)(実践知16頁)。
公正取引委員会は、本件取組によって需要者の利益を害する可能性について、次のとおり述べました(2〔独占禁止法上の考え方〕(2)イ)。
需要者である発注者においては、本件取組によって、工期が長期化する可能性がある。
もっとも、本件取組は、正当な目的に基づく合理的なものである。また、発注者は、作業工程の見直し等の方法によって工期への影響をある程度緩和することが可能である。これらの点を踏まえると、本件取組によって発注者の利益が不当に害されるとはいえないと考えられる。
作業時間を短縮することは、需要者にとって、工期が長期化するという不利益を受けることに繋がりかねないものです。
しかし、そうした影響は発注者においてある程度緩和することが可能であることに加え、そもそも、本件取組は上記のとおり正当な目的に基づく合理的なものであることにかんがみ、需要者に生じる不利益は問題とはされませんでした。
これは、目的が正当であってそれを実現する手段として合理的に必要な取組であるならば、たとえそれによって需要者の利益を害することがあったとしても、独禁法上許容されやすいことを示す一例といえるでしょう。
差別的な取扱いがなされていないこと
また、公正取引委員会は、
本件取組は、全ての会員に対して同一の内容の呼び掛けを行うものであり、会員間で差別的な内容ではない。
と指摘しました(2〔独占禁止法上の考え方〕(2)ウ)。
仮に作業時間の短縮要請が差別的に行われるとするならば、それは、長時間労働の是正という本件取組の目的に照らして通常は合理的とはいえないでしょう。
また、仮にそのような差別的取扱いが行われるならば、そもそも、本件取組の目的自体が眉唾ものであることを示すものであるといえます(実践知38頁)。
上記の指摘は、本件取組についての目的の正当性と手段の合理性を裏付けるものであるといえるでしょう。
強制するものではないこと
さらに、公正取引委員会は、
X協会は、会員に対して、本件取組の遵守を強制することはしない。
ことを指摘します(2〔独占禁止法上の考え方〕(2)エ)。
正当な目的に基づく取組であっても、それを強制することは、目的を実現するために必要な範囲を超えるものであることが多いでしょう。
本件において、長時間労働の是正という目的に照らして、会員に対して作業時間の短縮を義務づけることまでは本当に必要ないといえるかどうかは定かではありませんが、X協会としては、本件取組を強制せずとも本件取組の目的を実現することができると考えているからこそ、「呼び掛け」に留めることとしたのでしょう。
上記の指摘は、本件取組の手段が正当な目的を実現するために必要な範囲内であることを示すものであるといえます。
以上の分析を経て、公正取引委員会は、
以上によれば、本件取組は、X協会の会員の機能又は活動を不当に制限するものではなく、独占禁止法上問題となるものではない。
との結論に至りました。
実践知!
目的が正当であってそれを実現する手段として合理的に必要な取組であるならば、たとえそれによって需要者の利益を害することがあったとしても、独禁法上許容されやすい。
このnoteは法的アドバイスを提供するものではありません。ご相談につきましてはこちらのフォームからお問合せください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

