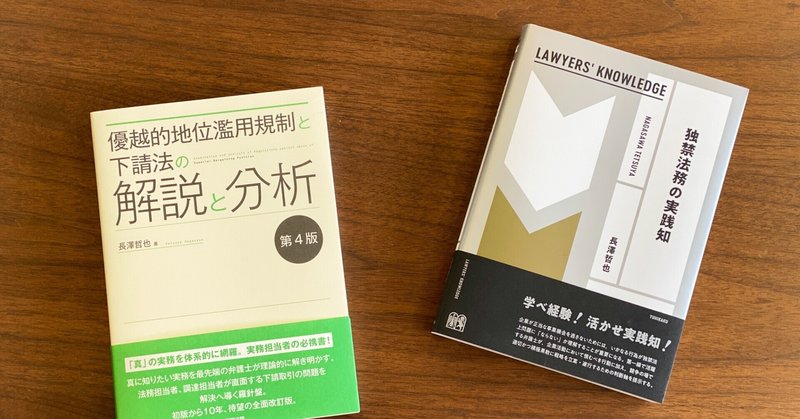
下請講習会テキストの改訂(令和3年版)
毎年11月は下請取引適正化推進月間だそうです。この時期になると下請法関連のイベントが盛んとなります。私も便乗して『優越的地位濫用規制と下請法の解説と分析』の第4版を上梓しました(こちらについてはおいおい書かせていただきます)。
それはさておき、この時期最も注目しているのが、下請法に関する公式マニュアルとでもいうべき「下請取引適正化推進講習会テキスト」(通称「講習会テキスト」)の改訂です。この度、令和3年版が公表されましたので、令和2年版からの変更点をチェックしました。
結論を言いますと、今回はめぼしい改訂はありませんでした。
以下、改訂ポイントを順にご紹介します。
代金減額に関する事例の追加(61頁)
まず、役務提供委託における下請代金の減額に関する「違反行為事例」として、以下の記述が追加されました。
㉕ 業務実績の評価結果を理由とした減額
親事業者L社は、電気通信事業者から受託する携帯電話の移動体通信サービス等に係る契約内容の説明、申込みの勧誘等の業務を下請事業者に委託しているところ、下請事業者の業務実績に対する評価結果が一定の水準に満たなかった場合、「戻入金」とする金額を下請代金の額から差し引くことにより、評価期間中の下請代金の額を減じていた。
令和3年6月23日のティーガイアに対する勧告事件を基にしたものですね。ただ、これは結構微妙な事案であったことに留意が必要です。この事案では、下請事業者の業務実績のみで下請代金の額が決まるのではなく、他の事業者の業務実績も踏まえて電気通信事業者が判定する評価結果に応じて決まるというものだったようで、下請事業者にとって下請代金の額が予測不可能なものであったことが問題視されたようです(担当官解説・公正取引851号88頁)。下請事業者の業務実績に応じて事後的に下請代金の額を確定させること自体は、減額に該当しない場合もあると思われます。
買いたたきに関するQ&Aの追加(68頁)
次に、買いたたきについて、以下のQ&Aが追加されました。
Q87: 最低賃金の引上げがあったが、従来どおりの単価で発注することは問題ないか。
A: 最低賃金の引上げにより労務費等のコストが大幅に上昇した下請事業者から単価の引上げを求められたにもかかわらず、親事業者が一方的に従来どおりに単価を据え置いて発注することは、買いたたきに該当するおそれがある(運用基準第4の5(2)ウ 164 ページ参照)。
こちらは、公正取引委員会が令和3年9月8日に公表した「最低賃金の引上げ等に伴う不当なしわ寄せ防止に向けた中小事業者等取引公正化推進アクションプラン」を反映したものですね。
割引困難手形に関する通達改定等の反映(78頁)
また、割引困難手形に関する通達「下請代金の支払手段について」が令和3年3月31日に改定され、同日、下請中小企業振興法に基づく振興基準が改正されたことを踏まえ、講習会テキストにおいても以下の太字部分が修正・追記されました。
(留意事項)下請中小企業振興法の振興基準
親事業者と下請事業者のあるべき取引の在り方を示すとともに、下請中小企業の振興を図ることを目的とする下請中小企業振興法第3条第1項に基づいて策定された振興基準においては、親事業者が下請代金を手形で支払う場合には、手形期間を60 日以内とするよう努める旨が規定されている。親事業者は、下請代金支払遅延等防止法に違反してはならないことはもちろん、下請中小企業振興法に基づく振興基準を踏まえ、手形期間を60 日以内とすることが求められている(引用省略)。
「下請代金の支払手段について」の発出
令和3年3月31 日、関係事業者団体に対し、公正取引委員会事務総長及び中小企業庁長官の連名により、下請代金の支払に係る手形等のサイトについては,おおむね3年以内(令和6年)を目途に、60 日以内とするよう要請した(引用省略)。
※ 現在まで、公正取引委員会及び中小企業庁は、業界の商慣行、金融情勢等を総合的に勘案して、ほぼ妥当と認められる手形期間(繊維業90 日・その他の業種120 日)を超える長期の手形を割引困難な手形に該当するおそれがあるとして指導してきたが、この要請に伴い、今後、おおむね3年以内(令和6年)を目途に当該期間を60 日とすることを前提として、見直しの検討を行うこととする。
下請中小企業振興法の内容に関する説明の追加(125頁以下)
講習会テキストでは、(参考)として下請中小企業振興法の内容が紹介されています。同法と同法に基づき定められる振興基準は、下請取引のベストプラクティスを定めたとでもいうべきものです。令和3年6月、同法が改正され、また、令和3年3月と7月、振興基準が改正されたことを踏まえ、講習会テキストの記述も追加されました。
下請中小企業振興法は、以下の記述(126~127頁)のとおり、下請法よりも対象となる取引の範囲が広いのが特徴です。
親事業者が自ら使用する物品や情報成果物については、下請法では、親事業者自らが業として製造・作成している場合に限り対象となるのに対し、下請振興法では、親事業者が自ら業として製造・作成しているかを問わず、親事業者が自ら使用する事業の遂行上必要となる物品の製造や情報成果物の作成も対象となる。
さらに、下請法では、他者に提供する情報成果物の作成に必要な役務である場合に、当該役務の提供を他者に委託することは対象とならないのに対し、下請振興法では、例えば映画を作成するために俳優に出演を依頼する等の役務は、役務を構成する役務として、役務提供委託の一として対象となる。
まとめ
今年の講習会テキストの主な改訂は以上のとおりです。
拙著『優越的地位濫用規制と下請法の解説と分析』の最新刊(第4版)では、令和2年度の講習会テキストを多数引用しています。令和3年度版で講習会テキストが大きく変更されたらどうしよう…と心配していましたが、幸い、内容に変更はほぼありませんでした。もっとも、Q&Aが1つ追加されたことにより、Q&A 87以降、令和2年版と比べて番号が一つずつずれることになります。また、記述が若干増えたことにより、数行分、ページ番号がずれる箇所があります。ご容赦ください。
このnoteは法的アドバイスを提供するものではありません。ご相談につきましてはこちらのフォームからお問合せください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
