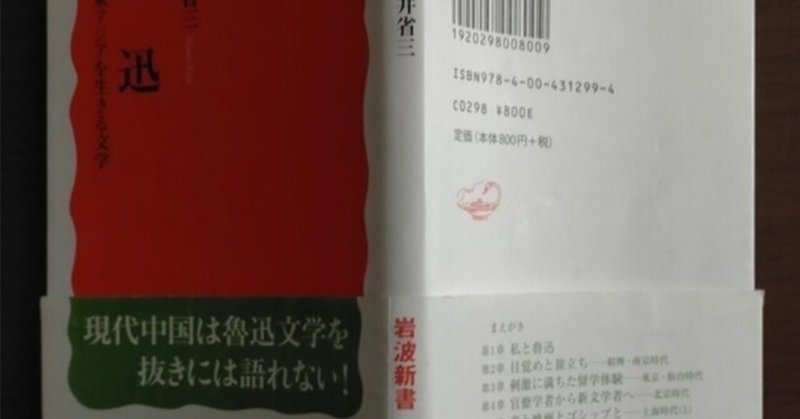
中国近代文学の父、魯迅を通して読み解く東アジア
ご訪問ありがとうございます。本日、中国文学の父と言われる魯迅を通して東アジアを読み解いていきます。
魯迅(本名周樹人)とは、「阿Q正伝」その他で、国際的に有名な中国を代表する文豪です。
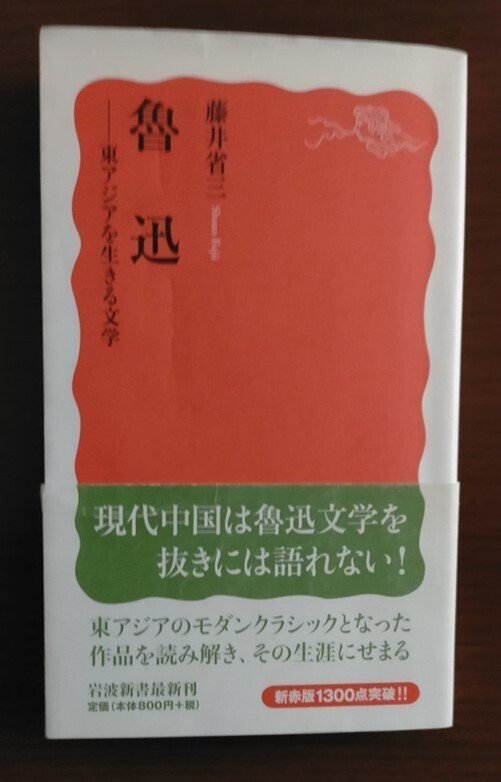
魯迅は1881年9月25日、浙江省紹興市(せっこうしょうしょうこうし)に周家の長男として生まれました。周一族は古くからの大地主でしたが、魯迅が生まれた頃には家運が衰えていました。
魯迅は11歳の時、科挙に備えていましたが、父が亡くなったため17歳の時に南京に行き、海軍の学校である江南水師学堂(こうなんすいしがくどう)に給費生として入学、その後、陸軍の学校の鉱路学堂(こうろがくどう)に入学しました。1902年、鉱路学堂を卒業した後、官費留学生として日本に留学しました。当時の清朝政府は日清戦争後ということもあり、近代化を担う人材育成のための日本留学を勧めていました。魯迅は最初、東京の弘文学院に入学しました。弘文学院は清国留学生に日本語と普通教育を授けるため新たに設けられた学校でした。この学校の普通科で2年間、日本語のほか算数や理科などの教育を受けました。
1904年9月、魯迅は仙台医学専門学校(現在の東北大学医学部)に入学しました。魯迅は同校の最初の中国人留学生でした。この年の2月には日露戦争が始まっており、市内は戦時色に染まっていたと言われています。仙台医学専門学校で、魯迅は恩師の藤野厳九郎と出会いました。藤野先生は教育者として厳しく真面目で、勉強に不熱心な学生からは敬遠されていましたが、一方で留学生である魯迅のノート添削したりして、優しさを内に秘めていたと言われています。魯迅の自伝的短編小説『藤野先生』は、日中両国の教科書に載る名作です。日清戦争後、両国関係が悪化していく中、国境を越えた師弟愛が生まれました。魯迅と藤野先生との友情についての記述が多いです。

藤野厳九郎と魯迅との師弟愛は戦後、日中両国で語り継がれています。お互いの「故郷」である芦原町(現福井県あわら市)と中国浙江省紹興市が1983年に友好市町締結が行われました。
あわら市公式チャンネル(あ!わらってネット)では、「魯迅の師、藤野先生の故郷・福井を訪ねて<中国語版>」も制作されました。Youtubeで公開されています。
今年、2022年は日中国交正常化50周年の年であり、また魯迅が清国の官費留学生として1902年4月に横浜港に上陸してから120周年でもあります。民間外交の模範ともいえる「魯迅と藤野先生との友情」の物語は、これからも語り継がれてほしいと願っています。魯迅と他の日本人との(知的)交流も多い。魯迅について、また続編を書きます。
参考文献
・魯迅と「藤野先生」:“相思互敬”の師弟愛(nippon.com 2022.02.24)
・藤井省三『魯迅:東アジアを生きる文学』岩波新書、2011年。
・泉彪之助・藤野明監修、芦原町芦原町教育委員会編「魯迅と藤野厳九郎」2003年。
・徳永重良「藤野厳九郎と魯迅をめぐって :「惜別」 その前後」宮城学院女子大学附属人文社会科学研究所編『人文社会科学論叢』24、2005年、 117-132頁。
・徳永重良「魯迅と藤野厳九郎をめぐって:日中関係の一齣」宮城学院女子大学附属人文社会科学研究所編『人文社会科学論叢』 25、 2016年、 1-18頁。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
