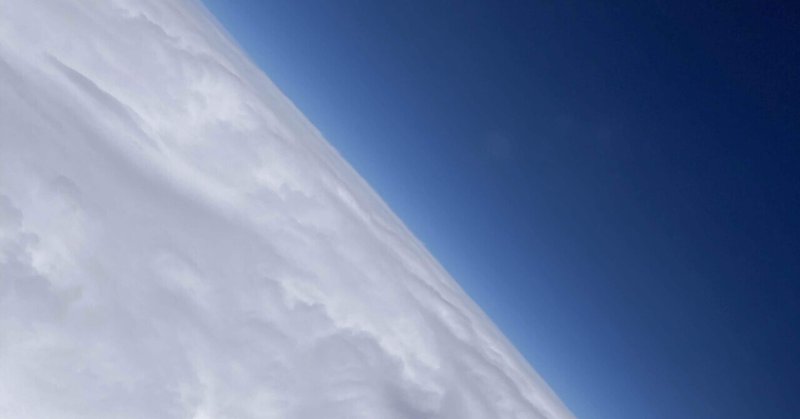
競技科学のすゝめ
プロフ;久留米大学附設高校三年生
JBO2024静岡大会銅賞/IBO2024カザフスタン大会日本代表
第13回科学の甲子園全国大会福岡県代表(筆記2位総合10位)
数理の翼伊計島セミナー/湧源
はじめに
高校一年生の一月に生物学オリンピックの存在を知り、四月からオリンピックに向けての勉強を通して、科学の甲子園を含む沢山の競技科学や、セミナーなどの活動に積極的に参加するようになりました。今回はそれらの活動を通して得たものを共有するとともに、「あれやっておけばよかったな。」や、「もっとこうすればよかったな。」と後悔していることを後輩に伝え、よりよい競技科学ライフを送ってもらうことの手助けになればと思います。
生物学オリンピック(JBO)
まずは、僕も日本代表に選んでいただいた生物学オリンピックについて書こうと思います。JBOは理論試験による予選、実技試験を含む本選を通して、生物学に関する思考力や、実験の技術を学び、身に着けていくことのできる大会です。予選は去年までは全国各地にある会場で受けていたのですが、今年の熊本大会の予選はCBT(Computer Based Testing)で行われます。本選は毎年会場が変わり、どこかの大学で行われます。僕が参加したJBO2023は静岡大学で行われました。3泊4日で行われる本選には、試験だけでなくエクスカーションや交流会がありました。また、本選が終わった後には研究室見学があり静大の研究所を見て回りました。
JBOの説明はこのくらいにして、少しだけ、僕のJBOにむけての勉強法を紹介します。JBOを受けない方や理系生物の方は結構ためになるのではないかなと思います(自分は最初は全くできなかったので)。そうでないかたは、全然飛ばして読んでいただいて構いません。
まず、予選までに使っていた教材はスクエア最新図説生物と、Newgrobal(NG)という問題集、JBOの過去問です。上述した通り4月から勉強を始めた自分はとても遅い方だったので、空いてる時間をほとんどすべて生物の勉強に使いました。まず、NGを図説を読みながら一周しました。この時はほとんど解けませんし覚えてません。その後、図説を横において、分からないところだけ見ながらもう一周NGを解きました。ここで5割近くは覚えていたと思います。ここまでは、すべてノートにしっかり書きながら解きましたが、これ以降は問題冊子の下に答えの冊子をおいて、問題ごとに答えを確認しながら頭の中で解くだけで、書くことなく解いていきました。その後図説を使わずに、間違えた問題に印をつけながら一周解きました。そして間違えた問題だけ解きまくって5周ぐらい最終的にはしたと思います。これが大体5月末には終わり、次は図説を読み込むのと並行してJBOの過去問を解いていきます。これはJBO公式のwebに上がっているので見てみて欲しいです。近い過去問から10年分ほど、2周解き、間違った問題をもう一度解きました。1年分解いて復習するのに大体3時間弱かかっていたのでこれが結構時間が掛かり、予選一週間前に終わりました。最後に解いた過去問がボーダーを切っていて、相当焦っていたのを覚えています。でも、もうやれることは無いし、とりあえずやるしかないという気持ちで頑張りました。その後は図説を一周読み、予選に挑みました。結果は約63点で(小数点以下は覚えて無いです。すいません)あと1問落としていたら落ちていたという、ぎりぎりでつうかできました。その後は図説をゆっくり一周細かいところまで読み込み、生態学入門という本を読みました。本選は7位で、総合21位でギリギリ銅賞(あと1位上がれば銀賞)でした。その後はちょっと肩の力を抜き、生態学入門をもう一度読み、JBOから頂いたキャンベル生物学、大学の生化学を読みました。問題演習としては、2つ上の日本代表の先輩方が翻訳してくださったIBO2020を解き、東大の過去問を10年分程解きました。ここまでが一年間でやったことです。
JBOを振り返って思う事は、結果にコミットしすぎて自分に過度にプレッシャーをかけてしまっていたことで、十分にJBOを楽しめなかったなと感じています。結果を出せなかったらと考え、きつい期間があったり、十分に本選のエクスカーションを楽しめなかったかなと思っています。ほかにも、試験や、試験の結果を気にしすぎて、JBOの同じ班の人に最終日までなかなか話しかけられず、交流も少なくなってしまいました。これは勝ちたい、という気持ちの表れだと思いますし、頑張ってきたことの裏付けだと思うので、しょうがない事だと思いますし、他の代表の人も、交流あんまりしなくて反省したと言っていたので、あるあるなんだと思います。が、ほんとに後悔してます。結果にコミットすることは大事ですし、ぜひ良い結果を求めて頑張って欲しいのですが、結果が悪くても落ち込みすぎないようにしましょう。本選に参加している時点で実力は担保されていますし、運もあります。このことを頭に入れながら、交流重視、楽しむこと重視で頑張って欲しいです。
まだまだ書き忘れたことがあるかもしれないですが、国際大会後にもまた書こうと思っているので、そのときに追記しようと思います。

科学の甲子園
次に科学の甲子園です。科学の甲子園は各都道府県から代表校1校が選ばれ、毎年3月につくばで理論試験や実技試験で競うと言ったもので、附設は第一回を除き12年連続で福岡県代表として出場しています。科学の甲子園は他の競技科学とは異なり、チーム戦です。筆記も六人で数学、情報、化学、物理、生物、地学を分担し解いていきます。あれ、これってなんだったっけみたいなこともチームで共有しながら解いていくのが科学の甲子園特有の良さだと思っています。僕は筆記と実技試験3に出場しました。実技試験3は気球を作って飛ばすというないようだったのですが、毎年実技試験3は事前公開競技で事前に各校で準備をして、本番に挑みます。僕は物理も副担みたいな感じだったので、理論式をつくることを主にやっていたのですが、本番ではなかなかうまくいかず、悔しい結果になってしまいました。科学の甲子園は、結構実技3次第な所があるので、みなさん、事前公開競技はしっかりやりましょう。筆記試験はちょっとやらかしもあった気がするのですが、2位になれました。総合10位をいただき、なんとか表彰されたので良かったのではないかと思ってます。科学の甲子園は結構地方格差が激しく、特に関東は激戦区です。ぜひ学校内でエリートたちを集めて予選に挑んでもらいたいと思います。
さて、科学の甲子園は今年からエクスカーションや交流会が復活しました。新型コロナウイルスの影響でなかなかできていなかったのですが、ことしからやっとできるようになり、来年もあるのではないかと思っています。僕は生物オリンピックの代表選抜試験がぴったり被ったので、参加できなかったのですが、エクスカーションも交流会もめっちゃ楽しそうでした。交流会ではいろんな学校の人としゃべれる場が設けられていて、いっしょにみんなでわいわいしながらご飯を食べていました。交流会は後ろ30分だけなんとか参加することが出来ました。なかなかそれまで他校の人と話せなかったですが最後だからと、頑張って(話しかけに行っては無いですが)積極的に?交流を楽しみました。科学の甲子園は各校最大8人で47都道府県あるので、300人以上が集まります。いろんな人がいますし、いろんな場所で交流の場があるのでどんどん話しかけに行って欲しいなと思います。話しかけに行けないと結構後悔します。
筆記試験は開会式の後に行われるので、あんまり心の準備の時間がありませんし、直前まで勉強というのもできません。しっかり準備していってください。実技試験は実技試験をやってない人たちは基本何もすることは無く、交流の時間です。楽しんでください。(僕はこの時間に全く話しかけに行けませんでした。スマホの充電はしていきましょう。)


競技科学まとめ
ここまで読んでいただいた人なら思うかもしれません。「こいつ、全然交流してないな?」と。そうです、かなりコミュ障陰キャしてます。これは、自分が結構結果を気にしちゃう方で、試験が全部終わるまで交流ムードに入れないだけです()。競技科学では試験は二の次かなと思ってます。いくら結果を残しても将来あんまり関係ないと思います。でも、交流を経て得た人間関係は本当に強いもので、去年JBO知り合った人であったり、JBOの知り合いの知り合いだったりする人がたくさんいたりします。これは、後からも続くもので、すごく貴重で重要なものです。本選出場までは頑張って欲しいですが、本選に行った暁には、肩の力を抜いて楽しも~というぐらいで楽に頑張って欲しいです。
番外編:数理の翼伊計島セミナー
いままで競技科学について書きましたが、ここからはつい先日参加させて頂いた数理の翼伊計島セミナーについて書こうと思います。これは、作文などを提出し、中高生約20人が選考され、沖縄県伊計島で4泊5日で大学の先生方の講義や、参加者間の交流、夜ゼミなどを通し科学全般の広い知識を得ることのできるものです。競技科学の人間は、自分の科目以外の科目はなかなか勉強する機会はなく、一つの科目に偏りがちだと思います。が、このセミナーではたくさんの分野から、すごい人たちが集まります。強制的にほかの分野の進んだものを勉強する機会になるため、とてもいい刺激になると思います。僕は存在自体は知っていたのですが、参加するつもりはなく応募締め切りをちらっと見てみたら沖縄であるとのことだったので、まよわず応募したらありがたいことに選んでいただいたので、今回参加する運びとなりました。なにもわからないままだったので、夜ゼミもちらっといって早めに寝ようかなぐらいのつもりでいたので、何も準備せず行ったら、めっちゃ楽しくて、あとで夜ゼミの事は書くんですけど、終始いろんな話聞いたり、話したりして楽しみました。企画もあって企画班で様々なゲームをして楽しみました。
講義について
セミナーのおもなプログラムは講義です。一人当たり約3時間の講義を聞きます。今年の伊計島セミナーは、ガン医学、理論化学、統計力学、メディアアート、数学といった講義の内容でした。自分にとって大方理解できたのはガン医学の先生の講義のみでした。他の講義は、理解できるというより理解したい講義で僕にとって、とっても意味のあるものでした。講義中は結構質問しやすい雰囲気で気になったことは随時質問して行けたので、全く分からないと言うのはなかったです。また、どの講義も全くの初学者でも有る程度理解できるように図ってくださるので、あんまり詳しくない分野でも楽しくうけられます。講義の概要は書いてOKとのことなので、書いておきます。セミナーにこれから参加しようと思っている人はぜひ参考にしてみてください。
ガン医学:がん細胞における、DNA修復のことや、がん細胞特異的な遺伝子だったり、ガン医療における最先端なお話をして頂きました。
理論化学:実験ではなく、理論で行う化学という内容で、シュレディンガー方程式のことを詳しくお話して頂けました。
統計力学:ゴムに関する物性物理の先生で、エントロピーの詳しいお話をして頂きました。物理の勉強欲があがるとても楽しい授業でした。
メディアアート:一見科学とは何も関係なさそうなアートですが、科学現象をアートにしてみたり、アートを科学を使って解明したりと、新しい見方を得られました。最後にはワークショップも行い自らメディアアートを体験してみました。
数学:同調の数理モデルに関する話で、蔵元モデルについての詳しいお話をしてもらいました。とても難しかったですがゆっくりちゃんと理解していきました。
夜ゼミについて
やはり数理の翼セミナーの醍醐味と言ったら夜ゼミです。ここではその日の講師の先生方への質問や、参加者同士の発表など、さまざまなゼミが開かれる、とても自由な空間です。スタッフの方々のお話も聴いたり、他の参加者とお話しできたりと、とても輪を広げられます。僕は研究も何もしてなかったので準備するものは無かったですが、研究をやってる方々はぜひ何かしら準備をして、積極的に自分の話をしてみてはどうかと思います。基本は10時までなのですが、最終日には朝の4時まで、白熱した()議論をやっていました。ほかにも雑談したり本当に自由な空間なので、僕みたいに寝るつもりで行くなんてことは辞めましょう。夜ゼミで聞いた話もここで書いときます。
・恒星風と言う観点からハビタブルな惑星について考える
・RSA暗号などの暗号理論について
・ゼータ関数について
・恋愛ゼミ()
などなど
ちなみに僕は生態学のお話や、分子生物学についてちょこっとお話ししました。
全体を通して
僕は将来数理生物学での運動方程式のようなものを作っていきたいと思っていて、物理学や化学における理論が実生活にそのまま応用されていたり、ちゃんと信用されたりするが、生物はそうではないのは、生物が種特異的なことが多すぎて、普遍的な理論に落とし込めないという理由だけでなく、数理生物学、理論生物学独自の理論が成立していないからではないかと思っていました。しかし、数学を全くやっていなかったり、数理生物学について勉強をしているわけでは無いので、ただの妄想でした。でも、このセミナーで数人にこの話をしてみたところ、面白い。 や 確かに。といった反応を得られました。そのため今ではかなり固く目標として確立しましたし、また、理論化学の話を聞いて、ずっとおもっていた、アミノ酸配列からタンパク質の立体構造を予測する数理モデルもつくれるのではないかと言う考えが浮かびました。と、いう風に様々な分野の方との議論は、自分の考えをより良いものにしていくとともに、新しい考えが浮かんでくる場なので、本当にいろんな方に参加して欲しいと思います。また、スタッフの方々もほんとに楽しそうで、スタッフとしても参加したいなーなんて思ってたりするぐらいです。競技科学は自分の人生のベクトルを大きく変えてくれるものですが、このセミナーはこれから将来にかけて、ちょっとずつずっと、いい影響を与え続けてくれるものだという印象です。
このセミナーではちゃんとコミュ障陰キャせずにちゃんと交流を楽しめたかなと思ってます。(どうですか?伊計島参加者)


最期に:僕が思う「科楽」について
さて、ここまで読んでいただけましたでしょうか。あんまり日本語が上手でないのと、初めてのノートなので、読みにくかったこともあるかもしれません。とりあえず最後に、ここまでかいてきてのお気持ちを書こうと思います。ここでの見出しにもなっているように、「科楽」と言う言葉が僕は大好きです。これは、僕が去年参加させて頂いた、大分サイエンスフェスティバル2023にて、テーマになっていた言葉です。僕は競技科学の人間です。なのでこの一年間科学を通して競ってきた人です。でも、それって科学の本質でしょうか?僕はそうではないと思っています。JBO内でも言われましたが、やっぱり生物を楽しむ心っていうのを常に持ち続けることが大切だと思います。僕にとっての科学って、学問を通して様々な人と議論し、その議論の中で輪を広げていく事だと思ってます。研究も一人じゃできないでしょうし、先人たちの知恵を繋ぎながら発展していっています。学問を通してのつながりが科学における重要なことだと思います。セミナーやサイエンスフェスなどにも積極的に参加することで、いろんな方と出会い、いろんな方の考えに触れ、議論し、自分の中での理解を深めていくことが出来ます。自分の好きな学問の勉強している時って楽しいですよね。新しい事を知る時って楽しいですよね。自分の世界が広がっていく感覚って楽しいですよね。そんな楽しさが、「科楽」には詰まっていると思います。これまでの競技科学ライフでの様々な人達との出会いは自分にとってすごく大切なもので、これからも続けていきたいと思う関係ばっかりです。これを読んで競技科学を始めようかなって思ってもらえた人(いるのかな?)に、素敵な出会いがある事を祈ってます。僕はこれからIBOにむけ、楽しんで自分の興味のある本を読みながら、いい思い出が作れるように自分のペースで頑張ろうと思っています(もちろんメダルは狙いながらですよ)。IBOが終わったら、国際大会も含め生物オリンピックについて書こうと思っています。
このノートを読んで何か質問があればぜひ僕のツイッター(X)のDMでもなんでも質問してくれれば答えるので、ぜひどうぞ。
ツイッター:@St03490424
7000字ほどの長い文でしたが、読んでいただきありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
