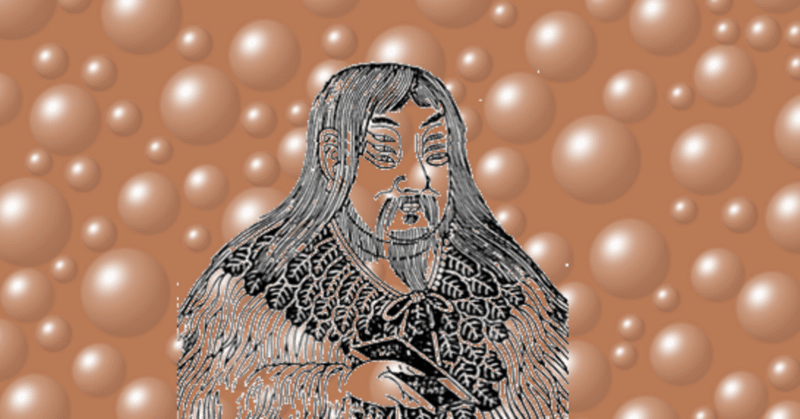
漢字の画数問題(6):漢数字
●奇妙な新ルールの広がり
漢数字の扱いも、占い師の間で見解の相違があります。昭和初期から突如広まり始めた特殊なルールが、業界内で論議されるようになったのです。
たとえば、漢数字の五や六はどちらも4画ですが、五は5画(数霊は5)、六は6画(数霊は6)と見なす流派が現れたのです。
●漢数字を数意で扱うのは、画数と数意の混同だ!
この新ルールに対し、大隈博誠氏は『姓名学大全』の中で、およそ次のように異議を唱えています。
姓名の文字に数字がある場合、例えば「九」の漢数字があれば、その字画の数え方はやはり二画が妥当である。「九」の文字がもつ意義によって、九の誘導暗示を受けるのはもちろんだが、これを九画として数える占い師は、文字の意義的側面を混同しているのであり、純然たる字画計算とはいえない。
数霊法においては、「九」の文字はあくまでも形態、つまり字画そのものを問題にしているのだから、二画に数えるべきである。
姓名を文字の意義の面から判断するときは九として、文字の数霊(字画数)の面から判断するときは二画として解釈すべきものである。
なかなか説得力のある意見に思えます。また、山口裕康氏も同様の主旨で大要、次のように指摘しています。
数字の画数について、四を四画として算出し、五を五画、六を六画、・・・ として、各々その運格を算出するときの基礎とする一派があるが、これは画数と数意を混同している。四という漢数字は、数意では「四つ」を表わすに違いないが、文字構成上の画数は五画である。
姓名のうちにある漢数字に限って、数意からその画数を計算するとなると、千、万、百、億などはいかに取り扱うべきか。
言われてみれば、理屈に合わないことがいろいろ出てきます。八千代さんという女性名がありますが、この場合の「八千代」は八千年(永遠)の意味ですから、数意は8000とするのが筋です。「八」と「千」をバラバラにして計算したのでは、数意が損なわれます。
了壱さんという男性名の「壱」も、「大字」と呼ばれる漢数字だそうです。漢数字は数意で画数計算せよというなら、壱は1画(数意が1)ではないでしょうか。
●天文学的計算が必要な名前
京介さんの「京」はどうか? ふつうなら8画ですが、漢数字の京というのもあります。京の数意は10の16乗なので、これを姓名判断するのは大変です。電卓で計算するにも桁数が足りません。
この場合の解釈としては、京介さんの「京」は都をイメージして付けたであろうから、8画に数えてよい、というのがあります。
確かに10の16乗をイメージして名前を付ける人は、滅多にいないかもしれません。ですが、そんなことは名づけ親に聞かなければ分からないでしょう。だいたい、名づけた人のイメージで漢字の画数(漢字に潜む数霊)が変わるというなら、とても字画数で姓名判断などできたものではありません。
蛇足ながら、数意で最強の名字はなんといっても京極さんでしょう。なにしろ、京(10の16乗)の次に、もっと数の大きい極が連なっているのです。極の数意は10の48乗ですから、京極さんを姓名判断するときの大変さは、京介さんの比ではありません。
●「漢数字は数意(実数)で」とする説は意外に新しい
もっとも、漢数字を数意(実数)で画数計算する流派では、このような難解な問題に対して、事前に手が打ってあります。数意(実数)を用いる漢数字は一から十まで、とするのです。
ただこのルールは、天文学的計算をしないで済むという意味では合理的ですが、姓名判断的な説得力に乏しいようです。
これが昔からの伝統的なルールなら、たとえ根拠があいまいでも、「まぁ、しょうがないか」ということにもなります。いつとはなしに根拠が忘れられたのだろうと、善意に解釈できますから。
ところが調べてみると、これは大正初期に現れた比較的新しいルールでした。そうなると、従来の方式を変えるからには、はっきりした理由を示すべきではないでしょうか。
なお、この新ルールについては、同業者の根本円通氏による痛烈な批判があるので、あわせて参照下さい。[注1-2]
=========<参考文献>=========
[*1] 『姓名学大全』(大隈博誠著、大隈博誠本舗、昭和10年)
[*2] 『名相と人生』(山口裕康著、東学社、昭和11年)
[*3] 『命名真理 姓名判断』(林充胤著、侑運堂、大正2年〔1913年〕)
[*4] 『姓名学真髄』(根本円通著、日本霊理学会、昭和4年〔1929年〕)
[注1] 漢数字を数意(実数)で画数計算する占い師
林充胤著『命名真理 姓名判断』の「文字画数の見方」 には、数字の画数について、「拾(十)以下の数は実数より見ること多し」 の注記がある。
本文中にも「数字の字画はその実数により算えるので、一は一、二は二と算えるごとく、八は二画なるも八画に算えるのである。また、右判断上、これを字画による場合がないでもないが、多くは実数によるをつねとする」とある。
こうした記述は、これ以前に書かれた姓名判断書では見つかっていない。
[注2] 「漢数字の画数は数意(実数)で」とする林氏の無節操
林氏のこの新説について、同業者の根本円通氏は『姓名学真髄』の中で、およそ次のように批判している。
林充胤氏は、『命名真理 姓名判断』に「一は1画、二は2画、・・・八は2画でも8画に数えること」と記して、東郷平八郎(8画・13画・5画・8画・10画)を姓21、名23、画数合計44としてある。
これはたぶん、従来の姓名判断書がどれも38画を最大凶としているので、〔海軍指揮官として日露戦争の勝利に貢献した国民的英雄である〕東郷元帥の姓名を38画とするわけにはいかなかったからだろう。しかし、その同じ書に、大隈重信の幼名 八太郎(2画・4画・10画)を16画としているが、八を2画と数えたことは明らかである。
私(根本円通)はこの点を疑問に思ったので、「八を8画としたり、2画としたりするのは、年齢の違い等によるのか」と林氏に問合わせた。林氏の回答は、「今は新聞・雑誌の原稿に追われて忙しいので、少し時間ができたらご返事します」とのことだった。ところが、すでに4ヶ月も過ぎたが、いまだに回答がない。おそらく、永久に回答は来ないだろう。
林氏は昭和4年1月より2月中旬にかけて、報知新聞に『財界名士の姓名判断』という記事を掲げ、三井八郎右衛門 48画、川崎八右衛門 45画、大倉喜八郎 37画、大倉喜七郎 37画・・・と記しているが、八も七も2画に数えたことは明らかである。これを東郷元帥の八を8画としたのに照らして、いかがなものか?
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
