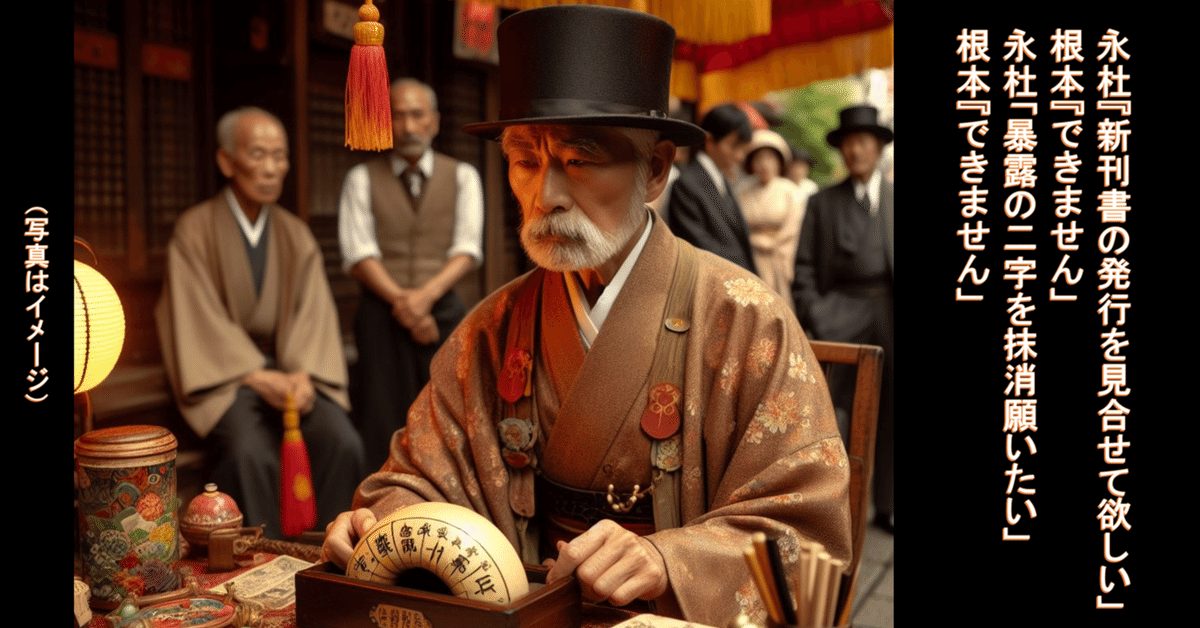
発掘!「現代の姓名判断」の起源(11)<補足>
このテーマは『発掘!「現代の姓名判断」の起源(10)』で完結する予定でしたが、急遽、追加することにしました。ネット上で次のような記事を見つけたからです。これは大きな間違いなので、見過ごすわけにもいきません。
姓名判断の理論の基礎的内容は熊﨑健翁によって広く世に広められ、熊﨑が姓名判断の源流と広く認知されているが、熊﨑は姓名判断の理論を開発したのではなく、明治時代の易者・林文嶺と言語学者・永杜鷹堂が理論化したものを大衆向けによりシンプルにしたものが熊﨑の姓名学である。
前半の「姓名判断の理論の基礎的内容は熊﨑健翁によって広く世に広められ・・・」は、まぁ許せるとしても、後半の「明治時代の易者・林文嶺と言語学者・永杜鷹堂が理論化したものを・・・」には大いに疑義が有ります。
そもそも 林文嶺、永杜鷹堂とは何者でしょうか。それが分かると、この説の疑わしさがはっきりします。
●林文嶺と永杜鷹堂の人物像
まず林文嶺ですが、明治期の「観相家」として知られている人です。「観相」とは人相術のことで、顔面に現れた血色や気色から、その人の運勢を占うのです。
現存する秘伝書(写本)はいずれも人相術であり、易についての著作は無いようです。となると、肩書きとして相応しいのは、「易者」ではなく、「観相家」でしょう。[*1] [注1]
次に永杜鷹堂(鷹一)ですが、一時期、熊﨑健翁氏の門人だった人です。上記の誤った説からは、あたかも熊﨑氏より大先輩のような印象を受けますが、事実はまったく逆で、ときには熊﨑氏の使い走りのような役目もしたくらいです。
永杜氏は同業者の根本円通氏を何度も訪問しており、その際に滑稽なやりとりがあるのですが、長文になるので注記を参照ください。[*2] [注2]
根本氏が「熊﨑式姓名判断」の暴露記事を出版すると知って慌てた熊﨑氏が、永杜氏を根本氏のところに差し向けて、出版を思い止まらせようと奮闘する場面です。
ところで、永杜氏は師匠の熊﨑氏から離反した後に『運命の哲理』を出版しますが、彼の著作はこれ1冊のようです。この中で姓名判断についても書いていますが、一読して熊﨑式をベースにしていることは明白です。[*3] [注3]

以上のことから、林文嶺、永杜鷹堂を姓名判断の元祖とする説は、まったく根拠のないものであることがわかります。
●「とんでも説」の出所
では、一体どこからこの誤情報が出てきたのでしょうか。残念ながら、この説には出典が示されていません。が、推測はできます。実は永杜氏の『運命の哲理』の中に、このような誤解を招きかねない表現があるのです。
『運命の哲理』には、永杜氏の弟子らしき人物による注記があり、その中に過剰なまでの粉飾表現が出てきます。
たとえば、「(永杜氏は)熊﨑健翁の学術顧問として待遇され・・・」とか、「「熊﨑式姓名学」の完成者たるのみならず、広く近代運命学界に貢献されたる大先達・・・」などといった記述です。[注4]
おそらく、これを読んだ誰かさんは、「ははぁ、永杜鷹堂という人は熊﨑健翁の大先輩で、姓名判断の技術指導をしたに違いない」と誤解したのでしょう。
悪意はないとしても、罪な文章ではあります。永杜氏を理想化した表現だったのかもしれませんが、「嘘」は感心しませんね。
また、林文嶺と永杜鷹堂との関係については、「(林文嶺)翁は・・・「運命の神」と称された林流の開祖にして、易・相・四柱の学に蘊奥を極め・・・(永杜氏は)林流の宗家を相続され・・・」などと注記しています。
冒頭の誤った説(「易者・林文嶺と言語学者・永杜鷹堂が理論化した ・・・」)は、事実関係が不明なこの辺の記述をもとに、憶測したのではないでしょうか。[注5]
いずれにしても、人騒がせな「とんでも説」でした。やれやれ、このテーマも今度こそ完結できそうです。
==========<参考文献>==========
[*1] 『東洋占術の本』(学習研究社、2003年)
[*2] 『姓名学大綱』(根本円通著、神国霊理学院、1932年)
[*3] 『運命の哲理』(永杜鷹堂著、清教社、1938年)
==========<注記>==========
[注1] 林文嶺の著作
『画相新編』 『画相不可思議』 『神相精微』などが知られている。
[注2] 永杜鷹堂の人物像
根本円通氏の『姓名学大綱』には、熊﨑健翁氏と永杜鷹堂氏の関係を示す詳しい記述がある。根本氏が第三者の立場で永杜氏の肩書きを「講師」と記しており、永杜氏自身も根本氏の前で熊﨑氏を「師匠」と呼んでいたことが分かる。(文中の太字)なお、漢字、かなの一部を現代表記した。
熊﨑健翁氏著『姓名の哲理』は〔熊﨑氏が主宰する〕五聖閣の講師 永杜鷹一氏が編集したもの[※]だそうで、氏は〔根本氏が主宰する〕日本霊理学会にお出でのこと、もはや五回におよび、ご自身が申されるには、「『姓名の哲理』は、〔以前に出版した〕『運命の神秘』の画数〔の誤り〕を訂正して、面目を一新したものです。何卒、ご覧下さい」と。
余はこの書を・・・来蘇堂より二日間借覧して、この批評を記すに至る。まずその経緯から簡単に述べる。
[※] このことについては、『姓名の哲理』の自序の中で、熊﨑氏自身も次のように書いている。
「・・・忙殺裏の著者をして本書の完稿を得せしむべく、これまた止暇断眠の内助を与えたる五聖閣講師 永杜鷹一君の労を付記して、ここに序と為すものであります。」
一、昭和六年十二月二十六日、
正午過ぎる五分時、五聖閣講師 永杜鷹一、および熊﨑健翁秘書 中垣喜雄の両氏が相揃って日本霊理学会にご光来、午後三時二十分お帰りになる。〔この後に、来訪の主な用件(画数の吉凶に関する議論等)と根本氏の回答が記されている〕
二、昭和六年十二月二十八日、
永杜鷹一氏、ご光来のところ、余は郵便局に行きて不在。ご足労を謝す。
三、同年十二月三十一日、
同氏ご光来、面談、午後二時より八時まで、六時間におよぶ。その大要は・・・等で、併せて、軒口にある〔根本氏の最新著書〕『姓名学大綱』の宣伝ビラを撤廃して欲しい、また〔既刊書の〕『姓名学神髄』212項にある〔熊﨑健翁氏についての〕「妖賊」云々という記事を抹消して欲しい、ということだった。・・・
〔根本氏の回答は〕『姓名学神髄』の記事を抹消することはできない。・・・妖賊の二字を訂正したからといって、あの文章〔全体〕が不明〔瞭〕になるわけではない〔だから、抹消しても無意味である、というものだった。〕
永杜氏は「師匠を妖賊といわれては、黙しては居られぬ」といい、愚妻は、「永杜さんも、もはや三回お出でになって、何のしるしもなくては困るでしょう」というので・・・妖賊の二字を他の適当なる語に改めることを誓う。〔結局、訂正後の語は「妖言」だった〕
四、昭和七年二月四日(節分当日)、
永杜氏またご光来、用談、午後二時より日没に至る。その大要は「『姓名学大綱』の発行を見合せて欲しい」ということだった。そして、「〔この書の副題に〕『熊﨑式大運神の暴露!!』とあるが、「暴露」の二字は実にひどい。・・・これは抹消願いたい。それから「大運神の霊導」を本当にわかったのでありますか」というのである。
余は答えていわく、「『姓名学大綱』の発行を見合わせることはできません。また、暴露の二字も差支えありません〔から、抹消はお断りします〕」 ・・・「大運神の霊導」については、〔『姓名学大綱』の〕本文記載の通りの、最初の原稿をお目にかけて、「これがすなわち暴露なのである」というと、永杜氏は「〔「大運神の霊導」は〕決してそんなものではない。しかるに、暴露としてこんな書を発行し、同業者を攻撃するのは、君子の取るべき態度ではない・・・」という。
余いわく、「なるほど、〔「大運神の霊導」の秘伝は非常に高額な〕三百円の伝授料なれば、あれ以上に詳細であることは勿論であろうが、その組織や用語はあんなもので、相生を吉とし、相剋を凶としておくものであろう。暴露といわれて気に入らぬならば、熊﨑氏は今後も多数の著述をなさるそうだから、その著述なり・・・機関雑誌『晃聖』なり、または著書と雑誌の両方なりへ、「大運神の霊導」の如何なるものかを示したら宜しい。・・・」
暴露という語を永杜氏は大層に嫌がって、「どうしてこんな文字を使用したか、すれっからしの新聞記者(氏ご自身が師匠なりといわるる熊﨑氏を指したか否か未詳なれども[※])でも使わない」と咎められたが、暴露〔という語の使用〕は毫も差し支えない。
[※] 熊﨑健翁氏が元新聞記者だったことに引っ掛けた皮肉である。
五、昭和七年二月九日、
永杜氏、五回目のご光来。熊﨑氏と会見して、「世間話でもして下さい」というのだそうである。(余は時に不在)〔この後、熊﨑氏の『姓名の哲理』に対する批評、というより、そこに書かれた根本氏への批判・非難に対する反論が延々と続く〕
[注3] 永杜鷹堂氏の姓名判断
永杜氏の判断法は『運命の哲理』(清教社、1938年)の「現証哲学撰名方術篇」に記されているが、熊崎式をほんの少し変えただけのもの(※)で、独創的な技法の紹介や斬新な解釈などは皆無である。なお、本書は後に『姓名の真理』(清教社、1955年)と改題して再販された。
※例えば「熊﨑式では画数合計を5種類しか使わないが、自分は7種類使う」とか、「熊﨑式の大運神では男女の区別が無いが、自分は区別する」等。
[注4] 『運命の哲理』の注記1
「永杜先生は、連山塾を主宰する傍ら、曾て(昭和六年より八年まで三箇年間)東京大森なる五聖閣主・熊﨑健翁の学術顧問として待遇され、当時同閣に関係深き華冑界の名士M海軍大佐や、Y少佐等と共に閣主を助けて、或いは内局の人事行政に、或いは門下の育英機関たる講学局の創設に、或いは出版に、或いは外部的折衝に、五聖閣機構の万般に渉って永杜先生が自己を虚しうし、以て尽瘁されたる幾多の功績は、啻に「熊﨑式姓名学」の完成者たるのみならず、広く近代運命学界に貢献されたる大先達として、後進の永久に忘ることの出来ぬ大きな足跡だったのである。・・・」
[注5] 『運命の哲理』の注記2
「永杜先生の先師が、かの有名な林文嶺翁であり・・・翁は、幕末、維新より明治の末葉期に渉って「運命の神」と称された林流(聖徳派より出でて一派を創始)の開祖にして、易・相・四柱の学に蘊奥を極め、・・・永杜先生は斯の如き英傑の学脈を継承し、かつ林流の宗家を相続された・・・」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
