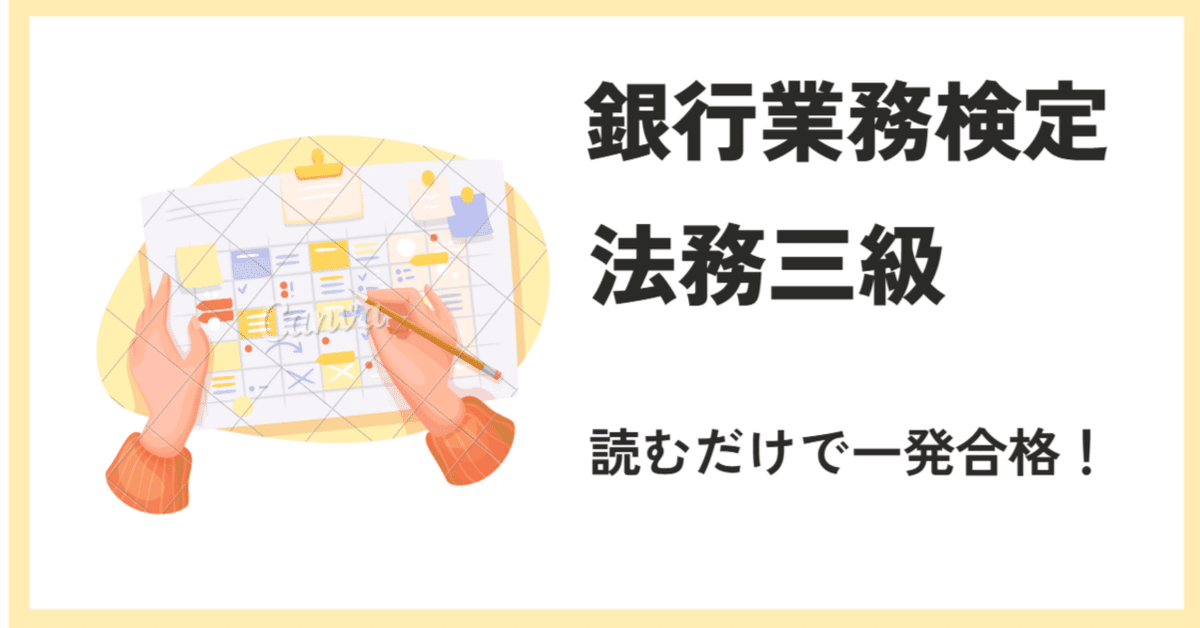
読むだけで合格?!法務三級 預金 No.2
こんにちは、今日もノートを開いてくださりありがとうございます。
さて今回は、法務三級の預金編②を執筆していきたいと思います。
今回の単元内容は、「取引時確認等」について触れていきます。
取引時確認等の項目は、出題傾向が高く、過去2021年10月の過去問から、
最新の2023年10月の試験まで、毎回の試験に出題されています。
従って、ここは絶対に落とすことができない項目になります。
まず初めに私のノートを掲載します。
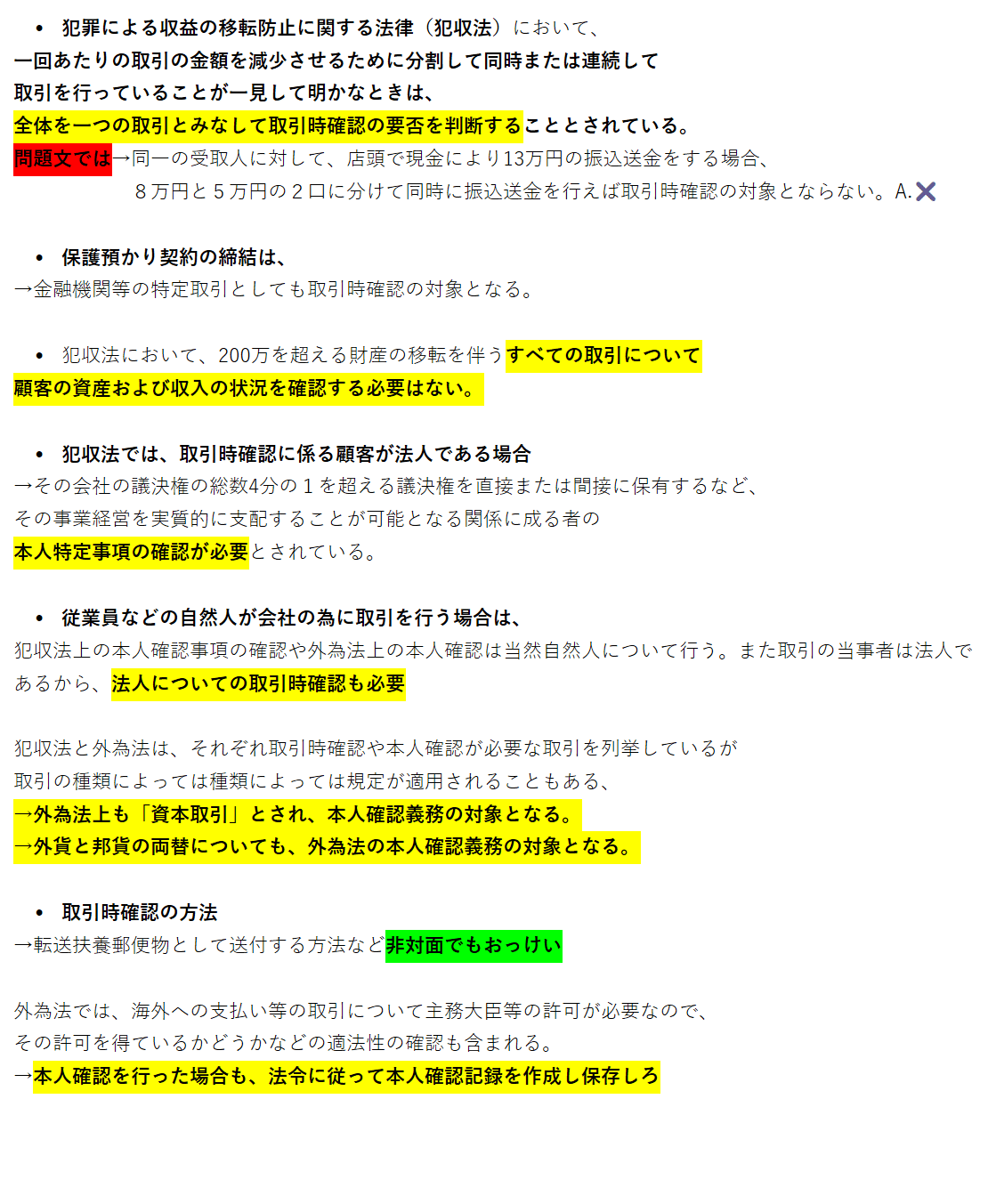
ここの取引時確認等は、主に二点を軸として問われます。
犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯収法)と
外国為替及び外国貿易法(外為法)にあたります。
正直言って、何を軸としているかは関係ありません。
あまり気にしなくて大丈夫です。
先にキーワードを列挙します。
「2口に分けて・保護預かり契約・200万越え・法人の場合・非対面」
正直、取引時確認等に関する問いは、上記のキーワードを
抑えるだけで2点獲得できます。
「2口にわけて」
過去問を解いていると、見慣れてくれるのが、
「現金により13万円の振込送金をする場合、8万円と5万円の2口に分けて
同時に振り込めば、取引時一階の対象とならない」
という上記の問題です。ちなみに、答えは、✖です。
解説すると、犯収法では、一回あたりの取引を減少させるために分割して
同時または連続して取引(問題文では振込のこと)を行っていることが
明かであれば、全体を一つの取引とみなして(=振込額は13万円とみなす)
取引時確認の要否を判断することとなされているという意味です。
保護預かり契約
そもそも犯収法において、
保護預かりを行うことを内容とする契約を結ぶことは、
金融機関とかの特定取引として取引時確認の対象となる。
まず、保護預かりとは、証券など受益可能なものを、自身で保存せず
金融機関等に保存してもらうことになる。
つまり、保護預かりを行うにあたって、必ず取引時確認は
必要となるのだ。赤の他人に、大切な証券などを
渡してはいけないからだあ!
200万越え
問題文において、以下の様に問われることが多いです。
「犯収法では、200万円を超える財産の移動を伴う取引は、
銀行は、取引の都度、必ず顧客の資産および収入の状況を確認すべき」
答えは、✖ です。
確かに、銀行側は、法令で定める額(200万円)を超える資産の移動を
伴うときは、それに加えてお客様の資産や収入の状況を確認すべきだと
犯収法においては定められているが、
「すべての取引」には資産や収入の状況を確認すべきであるとは
記載されていないのです。つまり答えは、✖になります。
この問題文は、過去5回分全てに出題されていたので、
必ず押さえておきましょう。
法人の場合
犯収法において、取引時確認に係るお客様が法人の場合、
その会社の議決権4分の1を直接、間接的に保有する者、
その会社の、実質的支配者の
本人特定事項の確認が必要とされているのだ。
要するに、その会社内でかなりの権限を保持するものに対しては
取引時確認はしてくださいね?ということです。
非対面
その文字の通り、非対面でも取引時確認を行うことが可能なんです。
付け加えると、必ず対面で取引時確認を行う必要がなく、
郵送で書類をお客様の住居に宛てて、取引時確認を行うことが可能。
一見、取引時確認は、対面のみのイメージがありますが、
対面でも非対面でもどちらでも可能なんだなあ
ぐらいの気持ちでここの点数は取れます。
以上のように、取引時確認等についての分野に触れてきましたが、
比較的に覚えてしまったら簡単なので、
何度もこのノートに振り返って、
合格を最短で勝ち取りましょう。
また次回~
