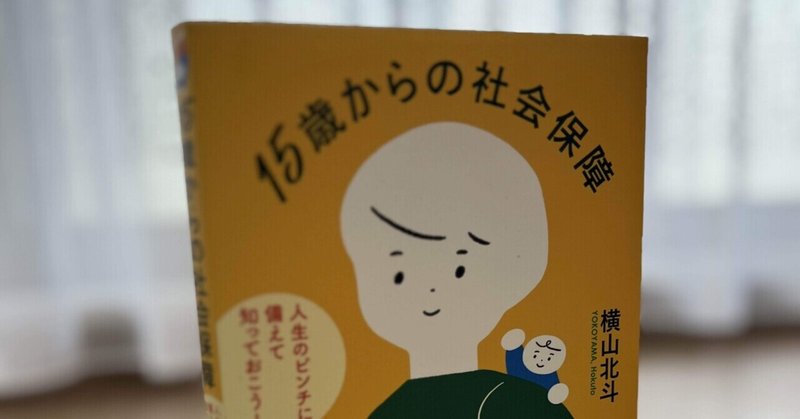
【読書メモ】15歳からの社会保障
15歳からの社会保障
本書の筆者には、2020年にSocial Change Agencyの研修プログラムを受講した際に、大変お世話になりました。
その時から、社会保障制度の申請主義、つまり、何らかの事情で生活に困り果てていても、自分で制度を調べて窓口へ行って「(自分はこれこれの条件に当てはまると思うので)利用させてください」と言わなければ一つも制度の利益を享受できない、という性質に対する問題意識を感じていました。そこへきての、『15歳からの社会保障』。もう、成人で申請主義を克服することはできないってことですか・・・というのが第一印象でした。
でも、読んでみて思うのですが、あの有名な『こども六法』同様、こどもが知っていなければならない知識は、大人にとっても知らないことが多い、ということ。
そもそも、社会保障制度はどのような役割を持っているのでしょうか? その答えは憲法にあります。(中略)
「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」は「生存権」と呼ばれ、わたしたち一人ひとりの生存権を実現するために整備されたのが社会保障制度です。
社会保障制度を利用することは、わたしたちにとっての権利なのです。
・・・そういえば、法学部生だった私は、3回生になるときに、「得意科目は憲法だけれど、憲法は私の難病患者としての生活を具体的に救ってくれない」という理由で、社会保障法演習に所属したことを思い出させる『はじめに』です。社会保障制度を、憲法上の権利と説明することが非常に重要で、ここが抜けるから「ずるい」のなんのという話に巻き込まれてしまいます。この「はじめに」の最後の1行は、15歳からぜひとも身につけておいていただきたい感覚です。学生のころと同じようなことを考えている方がいた!ということで、冒頭からテンションの上がる1冊です。
10個の物語と社会保障制度
本書は、10個の物語に沿って社会保障制度の解説が加えられています。私の本と違ってこの本がすごいのは、この10個の物語がそれぞれきちんとストーリー性のあるものとなっており、たまにマジで泣きそうになることです。話がよく出来すぎていて、社会保障制度の解説が入ってこないやつもあります。たとえば、5章はシングルファーザーが一人で子育てをするときに利用できる制度を解説する章ですが、冒頭から「突然訪れた妻の死」で始まります。妻が、歩道に乗り上げたトラックにひかれて突然亡くなってしまうんドエスが、主人公である33歳のマサトと、その長女がかわいそうでかわいそうでしかたありません。その後、いろいろな社会保障制度に助けてもらうんですが、悲しすぎて頭に入ってこない・・・
ただの社会保障制度の羅列をすると、それぞれ要件と効果をチェックするだけで極めて眠たくなってしまいます。わかります。私も、自分の本でやろうして失敗したからね! でも、そこを非常にリアリティのある10個のドキュメンタリーで十分にカバーしています。世の中はかくも生きづらいのか、という気分にさせてくれます。このストーリー性のゆえに、15歳でも読める内容となっているように思いました。
社会を変えるのはこども(教育)から
今の社会の生きづらさをなんとかしようと考えた時に、「これは子どものころから知識を身につけておいてもらわなければ」と誰しも考えるところ。だからこそ、法教育という分野が生まれたり、障害のある人とない人とが同じ場で合理的配慮を保障しながら学ぶインクルーシブ教育が重要と説かれたりします。本書も、発想としては法教育と同じ根から生じたものと感じます。私が子どものころ、学習指導要領の外でどんな教育を受けたかというと、あんまり覚えていませんが、学期末の余りの時間を使ってみんなで見た「はだしのゲン」の映画は、大人になった今でもよく覚えています。すげぇ衝撃だった。そんな感じで、中身の細かいところまで覚えていなくても、何かしら大人になるにあたって、爪痕を残すと思うのです。
他方で、市役所で多少施策的なところを担当してきた経験からすると、どの部署でもまず、「学校で教える機会を作ってほしい」と切望するものです。私の場合、最初の部署では手話教育、障害理解を学校へ依頼しました。現在の保健所に移ってからは、不登校・ひきこもりに関する啓発や、「SOSの出し方教育(自殺対策)」、精神疾患に関する教育などなどをお願いしたい、と考えています。高校生になればアルバイトするようにもなるだろうから、労働法の基礎知識は知っておいてほしいし、成人年齢が18歳に引き下げになり、ますます防御しづらくなっているので消費者教育も大事だ。子どもに知っておいてほしいことは、あとからあとから、とめどなく湧いてきます。
このように、行く先々で教育委員会へお願いしたいことがあるものですから、「こういう要望を全部受け止めて優先順位つける教育委員会は大変だろうな」と思います。そして、これらを受け取る子どもの方も、全部きちんと覚えておくことも難しいでしょう。
そんなとき、
社会保障制度を利用することは、わたしたちにとっての権利なのです。
これだけでも覚えていてくれたら、その後の人生が転落する角度をほんの少しだけずらせるかもしれません。本書は、困ったときに「ああ、あんな本があったな」と思い出した時にその子を助けてくれるでしょうし、その子のそばにいる大人に、「これくらいは知っておいて助けてやれよ」と言っているように思います。子ども向けの実務書は、実は大人のために書かれているようなものです。
申請主義を克服する
申請主義とは、生活が困窮した時にどのような制度を使えるのか自分で調べなければならないということですから、それがどれだけ酷なことか、日々実感するところです。困窮は、それだけで人の判断能力を奪います。また、自分に適した救済方法を調べるという作業は、それだけでそこそこの力を必要とします。能力的な力だけでなく、経済力も必要です。インターネットを活用するためには、まず通信環境を整え、PCでもスマホでもiPadでもなんでもいいのでデバイスを持っていなければなりません。しかし、本気で困窮すると、そういう物すら手元にないという場合もありえます。そもそも、高齢者はなかなか使いこなすことができません。
最近、内閣官房の孤独・孤立担当室から、チャットボットで行くべき相談窓口や使える制度を教えてくれるサイトを始めて「おお~」と感動しました。おもしろがって(あかんやつ)、何回かやってみました。自分の病気が指定難病であることを把握していないと難病医療費の助成にたどりつけないよ、とか、実際に到達可能な地域の窓口にはたどりつけないよ、とかところどころツッコミどころがありますが、試みとしては面白いですよね。
ただ、これも、すくなくともスマホを使いこなせるくらいの人でないと利用できません。
申請主義は克服すべきものなのですが、言うほど簡単ではなさそうです。特定の困難状況に陥ったら、自動的に社会保障制度を利用できるようにできればいいですけれど、それは特定個人が「困難状況に陥っているか否か」を常に公権力が把握していることの裏返しです。それはそれで怖い。難しい。
そうすると、考えられる申請主義の克服とは、「すべての社会保障制度に精通した超人」を養成して、住民が接触しやすいところに配備した上で、「なんか困ったらとにかくここへ行ったら何とかしてくれるから」ということだけ全国民の常識にしておくことでしょうか。
・・・それが、「断らない相談」の意図するところなんだYO、と言われてしまいそうですが。
ちょいちょい出てくる法テラス(民事法律扶助)
最後に、弁護士としてほんのり胸が痛いのが、社会保障制度として本書の中でもたびたび出てくる法テラス(民事法律扶助)の紹介。この制度がここまでの認知度を獲得したことで、確実に弁護士をはじめとする司法サービス利用のハードルが下がっています。それは、とてもいいことだと思うのです。
ただ、弁護士にとっての法テラスは、報酬額において刑事弁護における「国選弁護」とほぼ同じような感覚、・・・であることを、非法曹にどこまで伝わっているだろうか、いや、伝わっていないよな、という複雑な気持ちになるのでした。以前、職員に、「法テラス(民事法律扶助)は生活困窮者支援の制度やで」と言ったら、「え!そうなんですか!」とびっくりされ、こっちがびっくりしたことがあったなぁ。
私の本をネタにした研修の際には、口頭でできる限りお伝えしているところですが、毎回難しいなぁ。
ちなみに、今回の記事でたびたび出てくる「私の本」は以下。しつこい(笑)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
