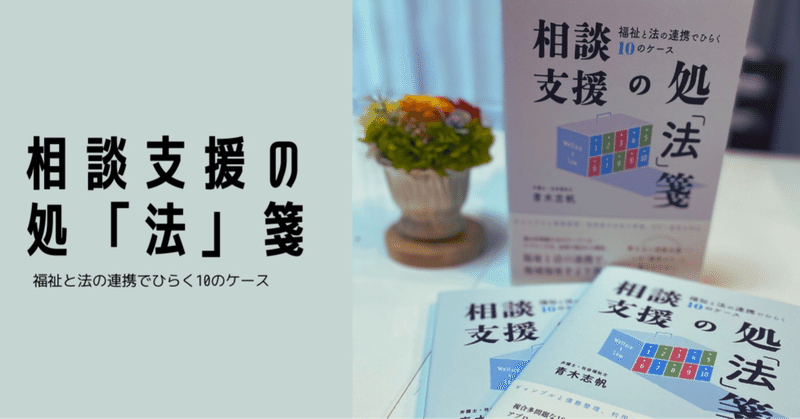
「私、民法で仕事できないんですよ、憲法で仕事するしかないんですよ」
おかげさまで
昨年、すったもんだして発行した拙著ですが、おかげさまで書店に並んでから1年を迎えました。この間、1回の重版を経て・・・そのあとどんだけ売れているのかわかりませんが、私の観測範囲におられる福祉職の方々は結構「買ったよ!」とおっしゃっていただけることに感動しております。多さ地裁の書籍売店にも、発売当初から3冊置いていただき、これも感動です。つい先日おそるおそる見にいったら1冊きちんと並んでいました! でも、初版本でした!(つまり・・・最初の3冊のうちの1冊なんでしょうね。)
ある打合せで
この本をきっかけに、研修の講師を依頼されることもあります。もちろん、本業の支障を来たさない範囲でという縛りはありますし、そもそも体調が本調子ではないということもあるので極めて稀なことではありますが。
そんな研修の打ち合わせで、「弁護士なのにいったいなんでこんなしんどいことをしているのか」と聞かれたときのことです。私としては、そんなにしんどいことをしているつもりはないんですが・・・ 業界的には「ラクしてる」と言われることもありますし。人と人との怨嗟の渦中につっこんでいく、通常の「弁護士」と比較して、どっちがどうかは人によるんでしょう。
でもたしかに、私がこれまで身を置いてきた場所にいる人々は、法律の力でなんとかなる人がめちゃくちゃ少ない気がします。年金や生活保護費の支給を受けると、その日のうちにいろいろなことに費消してしまって、期末近くになると「ご飯がない」と訴えるのはもはやデフォ。定期的にひもじくなるのだから、そうならないようにお金の管理を成年後見制度なり日常生活自立支援事業なりにアウトソーシングしてしまえば楽だろうに、財布は絶対に離したくない。死んでも離さない。
本書を「書こう!」と思ったのは社会福祉協議会でケースワークの助言者(SV)として働いていたころ。実際に執筆していたのは保健所へ異動してひきこもり相談を受けていたころ。「書こう!」と思ったころは、あの本の目次に記載しているトピックは毎日生じるルーティンでした。ところが書いているうちにだんだんあまり日常業務と関係なくなっていき、現在では「そんなこともあったなぁ」と懐かしく眺めるアルバムと化しています。
なんでかなぁ。。
「福祉」なのか「保健」なのか、という身の置き所にもよるのでしょう。
ちなみに、弁護士をしていると、「福祉」と「保健」の違いなんてさっぱりわかりませんでした。今もわかっているかどうかはかなり微妙です。
「人の人生の困りごとのうち、どっちかというと生活支援が福祉で、医療支援が保健なんじゃないの?」「でも、”生活”と”医療”なんて混然一体となっているのだから、そこを截然とわけるのってただのセクショナリズムなんじゃないの?」という、ちょう雑なくくりで眺めていました。今のところ、それが「ちょう雑なくくりだ」ということだけ理解しています。なお、保健師の皆さまからは、「福祉は”ことが起こってから介入する”けど、保健とは、”予防”だ」と教わっています。だとすれば、基本的に事後救済型の介入をとる法律学の専門家は、自分の専門性に相当のアレンジを加えないと、保健分野での有用性を発揮できない、と、いうことに、たった今、書きながら気づきました(ナマ悟り)。人の人生に対する予防法務、みたいな。なんにせよ、どこの部署に行っても、「一般的にその業界に弁護士は絶対におらん」という部署に飛んでることが多いので、行く先々で自分の有用性を研究し、開拓し、最後は部署に理解してもらわないといけないので大変です。お、そういう大変さならあるぞ(たぶん違う)。
民法ではなく憲法で仕事するやつ
さて、だいぶ脱線してしまいましたが、「財布を死んでも離さないフードバンカーたち」の話に戻ります。何が言いたかったか、というと、保健所に来て、精神疾患のある人たちの支援をしていると、後見制度を利用する場面が激減したんですよね。彼らは、客観的に金銭管理がままならなくて、期末を迎えると電気が止まり、電話が止まり、連絡が取れなくなって毎回困ると思うんですが、絶対に金銭管理は他人に任せたくない。そんな人を前に、「後見制度使おうぜ!」と説得するだけ、お互いにしんどい。
そういう現状に弁護士がいる意義を指して、打合せでぽろっと、「私、民法で仕事してないないんですよ、憲法で仕事してるんですよ」と放言したのでした。
もう、そういう人を見かけた時は、成年後見制度(=民法)が必要とされているのではなく、「愚行権(客観的に不合理な行動であってもそれを実行する権利。自己決定権の中身のひとつとして、保障されるべきかどうかがろんてんになる)」みたいな単語も頭にちらつきながら、おいおいそれはないやろ、という意思決定も尊重する(=憲法)よう助言するのが私の仕事か・・・、と思う場面があります。
成年後見制度に限らず、民法は、そのユーザーとして、「合理的な判断をし、それに基づいて行動する個人」であることが大前提となっています。契約すればそれは守らなければならないと考えるし、他人の持ち物に落書きしちゃダメだってわかってるし、収入の範囲で支出しないと生活が回習いと理解し、その枠内で生活できる、そんな人です。
ささいなところから、「守るべきルールを守る」がなかなか実践できない場合、どれだけ近所から迷惑行為を非難されても、債権者への支払いで生活が苦しくなっても、期末に電気が止まっても、正攻法でどうにもできない世界が広がっています。そんなときは、もう、本人の意思の範囲内で「一番マシな生活ができる方法」を考えるようになりました・・・ 意思決定支援、って、そういうことですよね・・・
「正攻法」の世界の規範が民法なわけですから、それを使って仕事していたところから、どれだけ不合理な行動をとる人であっても、「まぁ、そういう人もいるよね」と一旦納得できるようになるまでにはそこそこの時間がかかりました。この「まぁ、そういう人もいるよね」こそ、多様性そのものだなぁと思います。
こんなことばっかりしているので、「相談支援の処「法」箋」の「保健」バージョンを書こうとすると、きっと全然違うものになるんでしょう。あの本ですでに相当にふわっとしていますが、さらにふわっとしたものになる気がします。何より、まだ私自身が保健を理解しておらず、「これが保健分野での弁護士の仕事や!」と言えるものをつかめていません。
ひょっとしたら「要らない」・・・という結論も、ありえるんでしょう。それはそれで、つらいけど。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
