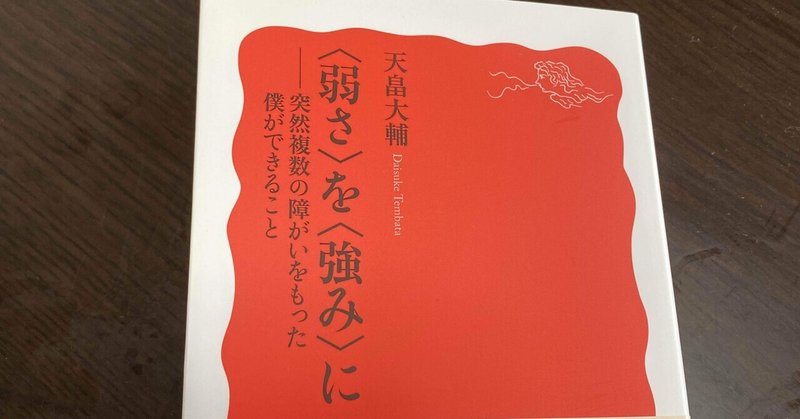
【読書メモ】〈弱さ〉を〈強み〉にー突然複数の障がいをもった僕ができること
「難病とはたらく」をテーマにしたオンラインセミナーで、天畠大輔さんが登壇されていた。
四肢は麻痺し、視力も文字を読めない程度には低下している重度身体障害のある天畠さんに対し、ヘルパーが「あかさたなはまや・・・」と並べ、途中から五十音を「ちつてと・・・」と下に降りていく。これをヘルパーが繰り返し、3~4文字そろったところで文章として表現しなおし、天畠さんに確認する。かなり迫力のあるコミュニケーション方法を取られているのに、プレゼンは、自らのヘルプ(介助)のためのヘルパー事業所の話。「難病とはたらく」とはちょっとズレている。気がしなくもない。
でも、ちょっと気になるので、この方の著書を読んでみた。
ちなみに先日取り上げた下記の記事の方と同じ方で、「先読みする通訳介助」と他己決定についてはこちらで書いている。私の思索に非常に刺激を与えてくれる人だ。どうやら同い年らしい、というのも興味が尽きない一因になっている気がする。「同い年」っていうだけでなんでこんなに特別な感情をかきたてられるんでしょうね。。今年に入って刺激的な「同い年」に出会いまくってる。がんばれ、1981年生まれ(関係ない)。
弱さからはじまる障害者運動2.0
本書からは、私が2年前に書いたこのエントリと同じような問題意識が通底しているように感じた。
2020年の障害学会で僕は京都大学の油田氏と「当事者研究」に関する共同発表を行いました。油田氏は脊髄性筋萎縮症(SMA。全身の筋力低下・筋委縮を生じる先天生活進行性の神経筋疾患)の当事者で、24時間介助を利用しながら一人暮らしをされています。そして介助者との関係性のなかで、介助者手足論の持つ「強い障害者像」規範にのれない自分の苦悩について論文を書かれていました(油田優衣「強迫的・排他的な理想としての〈強い障害者像〉」)。
僕は、自分の〈弱さ〉をさらけ出している彼女の様に「かっこいい!」と感動を覚えました。また、彼女の論文が、僕の論文の視点と似ていることにも驚きを感じました。それは自分のアイデンティティのウィークポイントを深堀にして研究対象にしていた点です。僕の場合は、「研究者」としてのアイデンティティを持ちながら、自分に著作権があるかどうかで揺らいでしまい、彼女は介助者手足論のような「強い障害者像」にアイデンティティを持ちつつ、その規範に乗れない自分の〈弱さ〉に苦しんでいました。
本書が指摘するように、従来の障害者運動は、「介助者手足論」つまり介助者は障害者がやってほしいことだけをやる。その言葉に先走ってはならず、その言葉を享けて物事を行うこと。障害者が主体なのであるから、介助者は判断を働かせてはならない、という思想に代表されるように、徹底的に障害者本人の主体性を主張することを旨としてきた。しかし、この生き様はとにかく人を選ぶ。だいたい、障害がなくたって、朝起きてから夜寝るまでのすべてを、ひとりで完璧に決定しつくせる人などどれだけいるだろうか。
Q「お昼ご飯、何食べたい~?」
A「おいしいもの~」
Q「次の夏休みどこ行きたい~?」
A「海~」
などといった会話をしたことがある人はたくさんいるはずだ。これらの回答は、問いに対してまったく意思決定していない。「なんとなくおいしいものを食べたいが、具体的に何を食べるのか、自炊するのか、テイクアウトするのか、外食するのか、そんな細かいことまで決めるのはめんどうくさい」という人のなんと多いこと。
しかし、従来の障害者運動は、そういう在り方をあんまり許さない。意思表示をするなら、文章の冒頭から「。」まで一言一句自分で言え、といわれる窮屈さ、その「主体性を表現するためだけ」に費消されてしまう時間をもっと別のことに使いたいという天畠さんの思いは至極まっとうなものに見える。でも、障害者運動の業界的には「弱い」と見られがち。私も、昔、ヘルパーの介護保障の事件を受けていた中で、こうした業界の不文律に触れることがあったけれど、「しんどそうやな~」と思っていた。
今、想像するに、かつて黎明期の障害者運動は、「ひとり暮らしすること=自立生活をすること」であり、ひとり暮らしがゴールだった。ところが、ひとり暮らしに必要不可欠なヘルパー派遣の制度が法的に整うと、次は「ひとり暮らしをして何するの?」という段階に入ってきたのだろう。だからこそ、本書も問題提起する通り、「介助つき就労」が必要になってくる。今は、障害者運動が次の段階に入ったといえる。障害のない人の社会が、重度障害者を包摂する社会を志向するのなら、障害者は、自分に与えられた時間を、コミュニケーションだけに割くわけにはいかない。だから先読みしてもらってコミュニケーションの時間をカットして、捻出された時間を社会への成果物に割きたい、と思うのは自然なことのように思う。それは「弱さ」ではなく、真のインクルーシブな社会への段階へと進むための、必要な変革のようにも思う。知らんけど。
治りたい意思は社会モデルと相反するのか
本書の中で、個人モデルにしがみついて生きるのはやめようと天畠氏が思った出来事として、2017年の検査入院があげられている。このとき、一縷の望みとして治るかもしれない治療法の可能性を探ったものの、結果として手術は難しく、成功の可能性は低い代わりに命の保障はない、と医師から言われた。それまでは体を治すためにできる努力は何でもする、と思っていたが、この出来事をきっかけとして「治らない自分」を受入れることができたと述べている。
このエピソードが、個人モデル(障害はその障害者の皮膚の内側に病気やケガといった形で存在し、それは当事者が努力したり、治療やリハビリによって治すもの、という考え方)から社会モデル(障害はその障害者の皮膚の外側にあり、当事者が感じる不便や生きづらさは、多数派である健常者向けに設計された社会の側に責任があるという考え方)への転換を果たしたという文脈で描かれている。重度障害者からの「個人モデルから社会モデルへ」という主張の根拠として、「治らない傷病を受け入れる」というエピソードが語られることが多いことから、これをそのまま難病者に紹介すると、強い反発を受けてしまい、なかなか両者は相容れない。
でも、難病に起因して重度障害になっている人は相当数いるはずで、「治りたい意思」をも包摂した社会モデルの説明は可能なはずだ、と常々思うところだったりする。
気になったこと三選
どこいった糖尿病
あらかじめ断っておくと、私の頭がおかしいことは百も承知だ。その上で、全編通じて気になって仕方がなかったのが、「この人は糖尿病ではないのか?」ということだった。
天畠さんが重度障害を負うことになったのは、14歳の時の医療事故がきっかけだった。食欲が落ち、下痢と嘔吐をくり返し、1~2か月の間に30kgも体重が減ったものの、医師には「ストレス」と言われて安定剤を処方される始末。そうこうしているうちに意識を失い、近隣のこども病院へ搬送されるものの、そこでものんきに寝かされてきた結果、3時間ほど心肺停止になってしまう。この時、脳に酸素が行かなかったため、低酸素脳症で重度身体障害が残る。そこまでなった原因が、若年性急性糖尿病。血糖値は1016㎎/dl(単位は書いていなかったけどたぶんこういうことだろう)。生きてる人の血糖値じゃねぇ。。
ところが、糖尿病のエピソードはここで終わり、その後最後まで出てこない。これって、1型糖尿病の人たちの語りに必ず出てくる「発症時エピソード」とまったく同じなのだけど、天畠さんは大丈夫だったのだろうか。1型糖尿病患者のエピソードによく出てくるのが、多飲や倦怠感、発熱、嘔吐などの症状が激化して救急搬送、その後、1型糖尿病とわかり、そのままインスリンの扱いと食事の摂り方を身につける厳しい教育入院へ突入する、というもの。ち、違うのかしら。。
そういえば、天畠さんとは関係ない話なんだけど、重度障害者の語りの中には、病気の話がすっぽり抜けていることがよくある。
かつて、重度障害者の介護支給量を保障する行政事件に関わっていたころから思っていた。24時間ヘルパーを入れないと生活できない重度障害を負う人の場合、その原因は大きく分けると脊髄損傷などの事故に起因するもの、脳性麻痺に起因するもの、そして難病に起因するものがある。難病も、一つひとつの病気は患者数が少ないものの、筋・神経難病全体ではそれなりに人数がいるため、依頼者の中にも難病の方が含まれる。いずれも「身体が動かない」という点では共通しており、介護保障を求めるにあたっての主張立証もほぼその点に尽きる。
ところが、難病の方の場合、「動かない」以外にも病気に起因するしんどさがある。痛い、眠れない、呼吸が苦しい、吐き気がする、低気圧が来ると状態が悪くなる等々である。私はこうした症状を「病苦」と整理し、「動かない」とは別次元の、病気に起因する辛さとして考えている。実際、重度障害者たちの陳述書を作る際、たとえば平日毎日作業所に通所する前提で計画を組んでいても、病気に起因する方の場合は、その病気によるしんどさのために家で寝ていたいときも頻繁にある。それは、本人の自由な語りからはあまり語られず、「ええの?毎日かようの、しんどくない?朝、目が覚めて頭が痛いとか、ない?」と聞くと結構な確率で「ある」と答えられる。そんな場合、毎日事業所へ通所することだけを前提としてギリギリでプランを組むわけにはいかない。彼らはしんどくて家で寝てるだけであっても、そばにヘルパーがいないと排泄もままならないはずなので、ちょっとよぶんめにヘルパー要らん?・・・と、思うのだけど、一緒に事件をしていた弁護士にはあまり腑に落ちてもらったことはない。
ともあれ、重度障害のある方のひとり暮らしエピソードを見ると、「介助」の論点についてはよく語られる。しかし、難病であれば大なり小なりあるであろう「療養」の側面については、すっぽり落ちてしまう人が多いことに常々不思議に思っている。ヘルパーの確保が大変すぎて、そのへんは後回しになってしまうのだろうか。それとも病苦はしんどさとしてとらえれてこなかったのだろうか。
などといったことを、本編とはいっさい関係ないのにぐるぐる考える、ダメな読者だ・・・
1型糖尿病のように慢性化しない糖尿病だったのかな。この身体で、糖尿病も罹患していたら、論文チームの前に血糖コントロールチームがないとしんどくて論文どころではなかっただろう。
障害と障がい
もう、タイトルから最後の「。」までずーっときになるのが、「障害」の標記が「障がい」になっていたことだった。社会モデルの考え方を意識的に採用している障害当事者の場合、障害は自分の身体ではなく社会の側にあると考えるので、「障害」の字を使っても問題はない、と考えるのが一般的だ。社会モデルを積極的に採用する当事者で「障がい」の表記を取っている人をあまり見たことがないので気になって気になって。通訳さんのこだわりだろうか。
がんばれ、弁護士
まだまだ支給時間数の差は大きいですが、2017年、石川県で24時間介護保障の決定事例が確認されました。現在は、行政との交渉に弁護士が協力してくれる事例も珍しくなく、「介護保障を考える弁護士と障害者の会全国ネット」という組織もあります。
・・・と、あるので、弁護士はがんばらないといかんですね・・・
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
