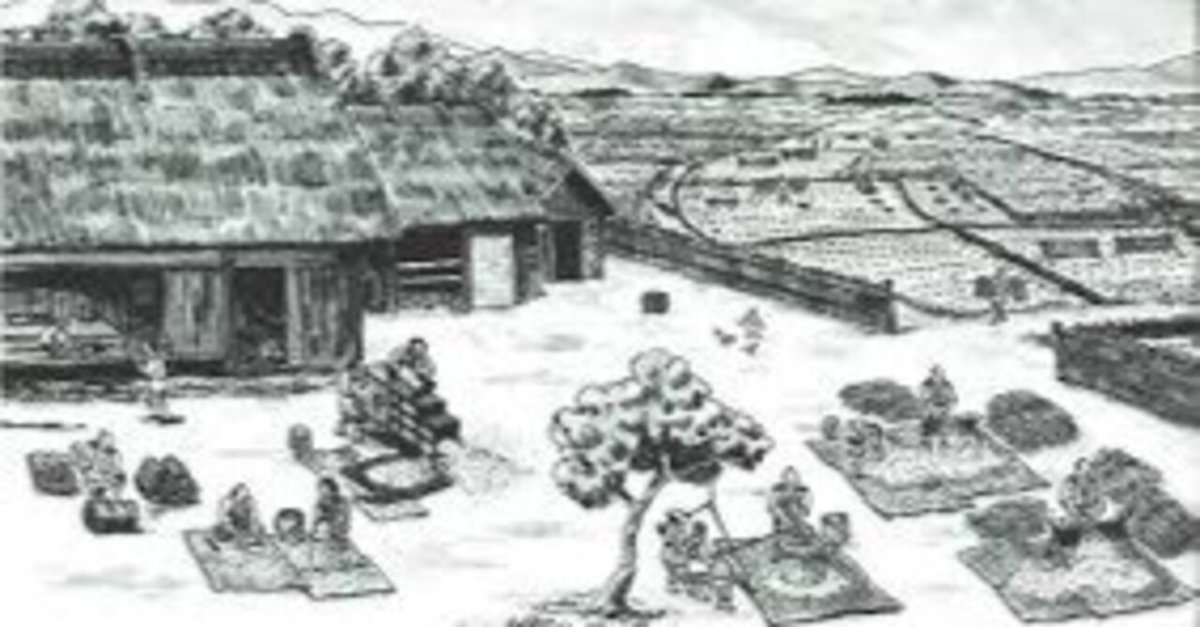
「場所の記憶」エマニュエル・トッド:江戸時代の村の記憶
エマニュエル・トッドの「我々はどこから来て、今どこにいるのか?」で場所の記憶という興味深い概念を述べている。
家族システムの相違によって、各国の特徴を説明するエマニュエル・トッドであるが、実は直系家族はもはや、ドイツであれ日本であれ、現代の居住地のほとんどの部分を構成する都市空間には存在しない。
また、モスクワも、北京も、一人の父親と既婚の息子たちが同居して一世帯を営んでいる例は多くない。
ところが、トッドはあたかも直系家族の価値観や外婚制共同体家族のそれががあるかのように話を続けている。
この恒久性の仮説をこの場所の記憶で裏付けようとしているのだ。
価値観の継承は、家族の枠内のみならず、1つのテリトリーを共有する大人たちと子供たちの間でおこなわれるという結論に到っていた。
フランス国内で頻度の高くなった移住について、H・ル・ブラーズの研究は、次のようなきわめて重要な問いを伴っていた。
これほど多くの個人が転居し、人生の大部分を人生を始めた場所とは別の場所で過ごすようになっている今日、典型的な地方文化が問題なく生き延びているのは、いったいなぜかという問いであった。
事実、フランス国内の人口流動の激しさにもかかわらず、各地で地域独特の気質が存続している。
どこを見ても、あたかもそれぞれの場所が固有の記憶を持っていて、その記憶が、もともとの家族構造や宗教的構造の消失にも、人口の入れ替わりにも、他の価値システムを出自とする人びとの転入にも、また別の人びとの外への転出にも無感覚でそうした現象から何の影響も受けずにいるようだ。
子供の「躾け」が家族の枠内で、また近隣の人びや学校によっておこなわれるという仮説を完全に捨てる必要はないにせよ、地方文化の恒久性がもっぱら個人レベルの強い規範によって確保されているという仮説はしっかりと問い直さなければならない。
もしも本当に個人が、子供時代に獲得した非常に強固な諸規範の持ち主であるならば、移住者は生涯その諸規範を守るであろうし、自分の子供にも伝えるだろうし、移住という現象は、結果的にさまざまな価値観を混ぜ合わせ、地域システムの同質性を壊し、最終的には一種の平均値を表す国民文化を創出するであろうから。
地方文化の恒久性が、もっぱら個人レベルの強い規範によって確保されていのではないという。
もしも個人レベルの強い規範があるとすると、移住者は生涯その規範を守り、移住地はさまざまな価値観が混ぜ合わされ、地域の同質性を壊すからであるからだという。
それならば、何があるというのか。
経験的に確認される現実が証拠立てるのは、移住者がおおむねかなり容易に自分たちの習慣や信念から離れること、そして、ローカルな人間同士の相互作用の中で、無意識的な模倣を通じて大きな適応能力を示すことである。
そのようにして、移住者はかなり頻繁に、子供時代に抱いていた価値観から身を引き離す。
この段階において、受け入れ社会に住む個々人が帯びているのは「強い」価値観ではなく、むしろその逆で、「弱い」価値観なのだと考えてみなければならない。
さてそこで、根本的な逆説は、弱い価値観という仮説こそが、各地域の気質の持続性を、いいかえれば「場所の記憶」という現象を説明してくれるという点にある。
家族内の濃密な継承様態という「強い」価値観もあるもあるが、
それとは別に「弱い」価値観と信念と行動様式の多種多様な世界もあるということだ。
二つのレベルの継承は、矛盾するどころか、組み合わされて、互いに強め合うことができる。
重要なのは、多くの個人が弱く有している価値観が、集団レベルではきわめて強く、頑丈で、持続的なシステムを生み出し得るということである。
たとえば、ひとつの信念が、個々の人間によって濃密に抱かれていない場合でも、あるテリトリーにおいて、長い年月、ときには果てしなく生き続けることがあり得るのだ。
「弱い個人的価値観」と「強い集団的価値観」を組み合わせる分析モデルで、場所の記憶という概念を採用すると、諸国民それぞれの気質が持続していることを理解しつつ、個人を「悪魔化」することを、つまり、各国の国民のをその国の価値観の執拗な担い手と見做すことを避けられるのだ。
個人は、自らの属するグループから離れると、たちまち別の方向へ逸れ、元々の自分の文化から遠ざかるのだ。
ただ、その速度に差があることも事実なので、それも認めよう。最後まで、リアリストでいたいものである。
この概念を使うと、かつて江戸時代の村に存在した日本人特有のメンタルが今も生きているといえるかもしれない。
小生の記事「日本人と江戸の村掟」で記載した村という共同体で営まれていた世界についてだ。
それは村の秩序が、個人の権利より優先された世界。
国家のように完結した世界で、そこでは村の寄り合いですべてが決められ、厳しい村掟によって縛られ、常に仲間の顔をみながら生活する。
閉じられた空間の中では、ときには論理より感情が優先していたかもしれない世界だ。
共同体の規範がなにより優先するというメンタルだ。
そして、それを自分なりに拡大解釈すると、
現代の恒例行事となった年2回の帰省についても当てはまる気がする。
故郷に帰省し、当地の年中行事に参加したり、故郷の仲間と会うことなどは、場所の記憶、集団としての強い価値観に触れることになる。
それは、かつての気質や規範を確認し、薄れつつあった自らの価値観がまたた再びよみがえるともいえるのだ。
したがって、これは帰省の意義、墓参りの意義がまた明確になるというものだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
