
ローリング膝栗毛(大尾)
直径三千里にも及ぶ光の渦が遠景に、ひい、ふう、みい、よお、いつ、むう、なな、やあ、八つ、巨大な円柱を形作って無茶苦茶なことになっていた。
一方、勝負は一瞬であった。
私は手に持ったね鹿スーパーを握り直し、やあっ、という掛け声とともに、ざんっ、ね鹿スーパーを横薙ぎに振り払った。
すると、ぽーん。大クス兄者の首が飛び、地面にころころと転がった。
ざっざっざっ、私は大クス兄者の首のところまで近付いて行き、
「じゃあな、大クス兄者。もう会うこともないでしょう」
そう言い残し、颯爽とその場を立ち去ろうとした。
ところがである。
言わんこっちゃない。首だけになった大クス兄者は、顔面を二倍に膨張させ、頬を河豚のように膨らませて愚図り始めた。
「待って待って待って」
「なんだよ」
「もう一回、もう一回勝負させて」
「やだよ」
「そげなー、お願いお願いお願いお願いお願いお願いお願いお願いお願いお願いお願いお願いお願いお願いお願いお願いお願いお願いお願いお願いお願いお願いお願いお願いお願いお願いお願いお願いお願いお願いお願いお願いお願いお願いお願いお願いお願いお願いお願いお願いお願いお願いお願いお願いお願いお願いお願いお願い、うわっ、なにをするっ、ふがっ、ふがっ、ふがふがっ、ふがふがっ」
懇願を続ける大クス兄者の下唇に私は超強力瞬間接着剤を塗布し、上唇とくっつけて口を封じた。
「ふがふがふがふがっ、ふがふがふがふがっ、ふがっ、ふがっ」
「許せよ、大クス兄者。悪いがあんたに構ってる暇、無んだわ。見ろよ、あの光の渦を」
「ふががっ、ふががっ」
「今回もあかんやった。俺、飛ぶわ」
私は屈んで右のソックスから一片のパケを取り出し、袋を開いて中に入っていた金色の刻印がなされた黒い固まりを口の中に放り込んだ。そして臼歯で擂り潰し、染み出た液体を嚥下した五秒後。
ばすん。
私の中の電源が落ちた。

大きな泉があった。
どどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどど。
その泉に向かって幾万、幾億の人だちが、ぽんぽんと飛び込んでゆく。
一方隣には、順番待ちの長い行列が出来ていた。
こちらの方は泉とは対照的に、一向に進む気配を見せない。
私はさらにその隣の受付のようなところへ行き、スタッフジャンパーを着た発光体に首からぶる提げたるゲストパスを提示して、黒い箱のなかへ入って行った。
なかに入る瞬間、何者かに陰嚢を舐められたような、ひやりとした冷たい感触があった。

「ふがっ、ふがっ、ふがっ、ふがっ、ふがっ、ふがっ、ふがっ、ふがっ、ふがっ、ふがっ、ふがっ、ふがっ、ふがっ、ふがっ、ふがっ、ふがっ、気合いだっ、気合いだっ、気合いだっ、気合いだっ、気合いだっ、気合いだっ、気合いだっ、気合いだっ、気合いだっ、気合いだっ、気合いだっ、気合いだっ、気合いだっ、気合いだっ、気合いだっ、気合いだああああああああああああああっ」
茹で蛸のように顔面を真っ赤に紅潮させて、頭の血管が切れて顔中血塗れになりながらも私の塗布した超強力瞬間接着剤を剥がすことに成功した大クス兄者。
しかしながら、事態は逼迫していた。
八つだった光の渦は万に数を増やし、大クス兄者は正に光の渦に飲み込まれようとしていたのである。
「おおい、体どん、体どん」
大クス兄者が呼び掛けると、首から鮮血を噴出させながら、一体その奥底でなにを考えているのか全く分からないような佇まいで坤の方角に向かって佇んでいた大クス兄者の体が、
「あい」
まるで木偶の坊のような念波を放ち、たったったったったったったったったったったったったったったったっ、大クス兄者の首の元に歩み寄った。そして大クス兄者の首をひょいと持ち上げると、ずぽっ。自分の首に大クス兄者の首をくっつけてしまった。
「重畳じゃ、体どん」
「あい」
「うむ。さて、しかしまた厄介なことになった。なあ、体どん」
「あい」
「湯デデの奴に飛ばれてしもたわ。わっはっは」
「あい」
「まあ絶対に見つけて殺すけどね」
きもっ。ストーカー根性丸出しの蛇のような笑みを浮かべながら大クス兄者は肛門に手を突き込んで、糞便のこびり付いた一片のパケを取り出し、中から私が持っていたのと同じ金色の刻印がなされた黒い固まりを取り出し、口の中に放り込んだ。
同時に光の渦が大クス兄者を飲み込んだ。
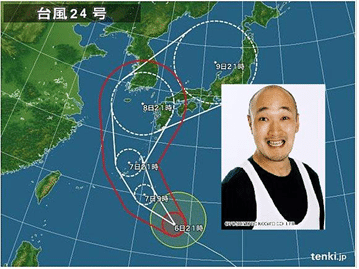
「お侍はん、お侍はん、大丈夫だっか?」
「う、うーん」
「えがったー、やっとこさ目ぇ覚ましゃよった」
一体どれくらいの年月、気を失っていたのだろう? 再び目を開いたときには、頭に角の生えた、四代目小さん生写しの鬼が、安堵した表情で私を覗きごんでいた。
ざざーん。ざざーん。
波の音が聞こえる。
私は俯せで倒れていた状態から、びん、陰茎が勃起するように起き上がった。
その様子を見て驚いた小さん、
「わっ、魂消たー。大丈夫なんでっか、お侍はん?」
「うむ。問題無い」
「えがったー。いんやあ、びっくらこいたでよ。道ば歩いでだらお侍はんが倒れではったもんで」
「そうか。それは相済まなかったね。ところで君」
「なんだふ?」
「先にから私のことを、お侍はん、お侍はん、と呼んでいるが、君、私が侍に見えるかね?」
「へ? 違うんでっか?」
「うーん、どうだろう。どうれ、一寸確認してみょう。あれっ、腰に刀を二本差して、髷を結ってる。着物のそれらしいのを着ているし、あっはっは、これは誰がどう見ても侍だ。」
「変なお侍はんだべ。矢っ張どっか悪いんじゃねえけ?」
「あっはっは、大事ない、大事ない。どこも悪くない」
「んだすか? ほいだらよかばってん。お侍はん、腹ば減っちょらんとですね?」
「腹か。おい、腹。減っているか?」
「激減りでし」
「激減りだそうだ」
「ほなったらウチば来よんさい。鱈腹御馳走しますけん。さささ、どうぞ、どうぞ、なあんも遠慮せんと、さ、さ、さ」

スプリングの利いた舶来製のソファに深く腰を沈めて、シングルバレルのバーボンウイスキーを喇叭飲みしながら、全面が硝子張りになった窓から明滅する漁火を何とはなしに眺めている。
そこへ、
「お食事はお口に合いましたでしょうか?」
自らを、洪、と名乗った小さんが、右手にピンドン、左手にシャンペングラスを二つ持って、バーカウンターからリビングに戻ってきた。
「うん、美味じゃった。美味じゃったけど」
「どうかなさいましたか?」
「洪君、君、さっきから普通に標準語話してるよね」
「ああ、これですか、いやあ、お恥ずかしい、先達ては朴訥な田舎者の振りをした方が警戒されないかと思いまして」
「そうだったのか。うーん、前にも同じようなことがあったような。いや、なんでもない、いいんだいいんだ。それよりも凄いね、駅ナカのタワーマンションの最上階に一人で住んでるなんて」
「なあに、親が参議院議員なだけですよ」
「ほう、参議院議員ですか。参議院議員は儲かりますか?」
「人生楽勝ですね」
「あっはっは、正直で宜しい。もしも少しでも謙遜するような素振りを見せたら私は君の角を引き抜いて替わりに幕の内弁当を充填するつもりでしたよ」
「おお、怖い怖い」
「ところで洪君、ここはなんという土地だい?」
「ここですか? ここは詩国といいます。雷魚が名産品です」
「雷魚か。然う言えば先の膳にも出ていたね。あれは美味じゃった」
「それは結構でございました。未だ沢山ございますが、お召し上がりになりますか?」
「いや、止しておこう」
「かしこまりました。それではこっちの方はいかがです?」
「なんだい洪君、小指なんぞ立てて」
「またまた、御惚けになって。下は六つから上は九十まで揃えてますよ」
「洪君、君は私が女を買うような低劣な人間に見えるかっ!」
「ははっ、申し訳ございません」
「十歳の現役JSでお願いします」
「ロリコンか」

ざざーん。ざざーん。
洪君が呼んでくれた十歳の現役JSと少々ござった後、私は洪君の案内で浜に来ていた。
私は洪君に言った。
「洪君。浜だね」
「そっすね」
「お、また口調が変わったね」
「えへへ」
「それよりも洪君、あれは一体全体どういうつもりなんだい?」
「あれってなんすか?」
「あれだよあれ、ほら、あすこ、沖にひと際高く屹立してる建造物」
「ああ、あれっすか? あれは、うーん、いつだったっけ、ああ、そうそう、確か一九七〇年ぐらいだったかな、岡本某っていう人間の芸術家が制作した、太陽の塔、っていう建造物っす」
「いや、それは見ればわかるんだけどね。え? てことはなに? ここってもしかして大阪?」
「は?」
「え?」
「え?」
「は?」
「あ?」
「あ?」
「あ?」
「あ?」
「あ?」
「ストップストップストップ。止めよう、不毛な問答は。洪君、君、先頃ここは詩国という土地だと言ったね」
「言ったっす」
「洪君、ここは本当は大阪という土地ではないのかい?」
「おおさか? いや、ここは詩国っす」
「OK、OK。成程、今回はそんな感じですか」
「大丈夫っすか?」
「ノープロブレム。問題ない、問題ない。ところで洪君、私はあの太陽の塔のところまで行きたいのだが、なにか手立てはあるかい?」
「クルーザーならあるっす」
「Wow! 流石参議院議員の息子だ。済まないが連れて行ってもらえないかい?」

ぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼ。
大型クルーザーのエンジンの重低音が下腹部に響いて心地好い。
「あと一分で到着するっす」
操舵室から洪君が顔を出した。
「うむ。それにしても大きいね」
「おっきっすね」
「こんなに大きかったかな? うーん、これはいくらなんでも」
「どうしました?」
「いやね、私の知る太陽の塔は、高さ七十米くらいだったと思うんだけど、単純に見積もってもこれはその十倍はあるよね」
「そうなんすか?」
「そっす」
「あ、着いたっす」
「うっす」
「あれ? あすこ見てください」
「あすこ? あっ、なにか大きく文字が彫られている」
「やっぱそっすよね」
「洪君、あすこに船を着けられるかい?」
「楽勝っす。あい、着けましたよ」
洪君が船を着けてくれて、なんと彫られていたかが判明した。
そこにはこんな短い詩が彫られてあった。
えんぜるになりたい
花になりたい
「怖っ。なんすかこれ」
「ははは。君は鬼だから知らないと思うが、これは三十歳という若さで昇天した八木重吉という人の詩じゃよ」
「ぷんすか、鬼差別だ」
「うざっ。それにしても太陽の塔に八木重吉か。益々妙なことになってきたな」
「どうするんすか?」
「うん。私はこれから太陽の塔の内部に入ろうと思う」
「え? これ、なか入れるんすか?」
「ああ。あすこを見てご覧。入口が見えるだろう」
「あ、本当だ」
「あすこまで行ったら洪君、君ともお別れだ。随分と世話になったね」
「ぐすっ、ぐすっ、そんな水臭いこと、言わないでくらはいよ」
「洪君、私の為に泣いてくれるのかい?」
「うっそー。泣いてなっいー。ほら、入口に着けたぞ。さっさと行けや」
「覚えてろよ、洪君。輪廻を越えて、必ずどつき回しにくるからな」
そう言って私は洪君とハイタッチを交わして、それから太陽の塔の内部に入っていった。入っていった。入っていった。入っていった。入っていった。入っていった。入っていった。入っていった。入っていった。入っていった。入っていった。入っていった。入っていった。入っていった。入っていった。入っていった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
