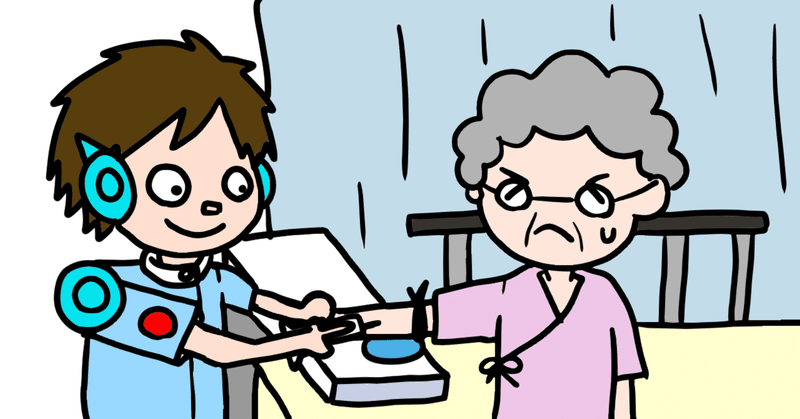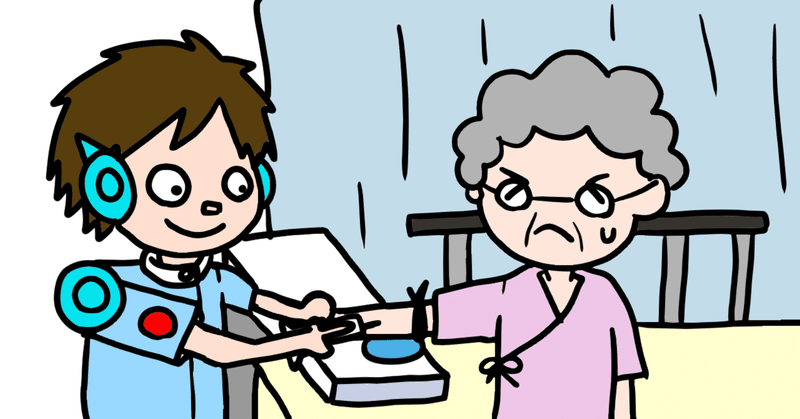「デジタル看護入門」第16回 〜在宅での栄養管理とICT〜
前回までは「呼吸器」関連の話でしたが、今回からは「栄養」関連の話をします。人工呼吸器と同様に、ひと昔前までは、点滴いわゆる「持続的静脈内注射」をしている状態で、在宅療養することは、非常に困難でした。今でも、一般の方々は、点滴や人工呼吸器を使用している状況で、自宅に帰ることができるなんて、あまりイメージができないのではないでしょうか。在宅療養における、いわゆる「点滴」による栄養管理を行う場合、少し特殊な中心静脈栄養法(Total Parenteral Nutrition:TP